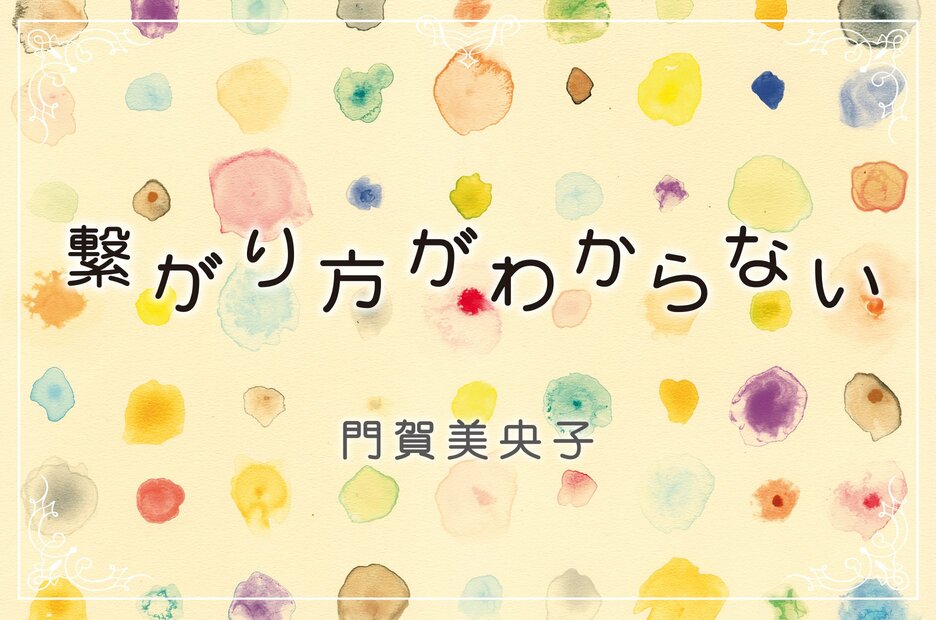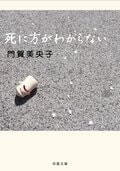一生懸命理論武装してみる
前回は大きく勢い込んで始めたわりに「特別な御縁のあった人の名前と顔ぐらいは覚えておきましょう」という、と~ってもベーシックでちっちゃな話で終わってしまった。今回も針小棒大竜頭蛇尾に終わる懸念はあるが、もう少し考えを深めていきたいのでお付き合い願いたい。
安定した「つながり」を求めるのであれば、関係の継続性が不可欠であることは言うまでもないが、ちょうどよいコミュニケーションの間隔とはどれほどのものになるのだろう。
簡潔に言えば「必要以上の連絡は避けつつ、完全な途絶も避ける」が基本になろう。そうなると時節の挨拶などを活用するのが自然になる。つまり現代では不要扱いになった年賀状や暑中/寒中見舞いが一番だ。
実は私、一昨年あたりから思うところあって一度は止めていた年賀状を復活させた。プライベートの知人かつこれまでも年賀状だけのやり取りだった方たちには再び送り始めたのである。その人になにかあった時、私にも知らせてもらえるように。
これは『死に方がわからない』の取材中に聞いた話なのだが、最近は人が他界したとして、訃報を誰に知らせればよいのかわからないケースが増えているという。昔なら各家庭にアドレス帳の一冊もあり、そこから必要な連絡先をピックアップできたが、今はスマホや携帯電話のメモリに入っているため、ロックがかかっていたらお手上げ、というわけだ。
けれども、はがきや手紙はすぐに確認できる上、内容である程度関係性の深さがわかる。つまり、遺族含めた第三者が訃報を知らせる知らせないを判断するのに最適の手がかりになるのだ。
私も一時は年賀状不要論に傾いていたが、この話に納得して再開した、というわけである。やはり最低限の消息を知りたい人は、私にだっている。
本来、コミュニケーションの間隔は相手からの反応の度合いに応じて、連絡の頻度を調整すべきところだろうが、上記のような事情からここだけは一方通行で構わないと思っている。
また、もう少し積極的に関わりたい人で、かつLINEのようにごくパーソナルで簡便な連絡手段で繋がっている相手には、その人との関係性の濃淡や好みを勘案した上で、誕生日の祝辞や季節の挨拶を送るようにしている。
というのも、人間のコミュニケーションの本質的な目的は、単なる情報交換を超えた「承認と理解の相互作用」にあると考えるようになったからだ。
誰であれ、自分を理解してくれている、あるいは承認してくれていると感じられる相手には好意を持つことだろう。
だから、まずは「私はあなたのことを忘れていません。いつもではないけれども、折りにふれて思い出すこともあるし、あなたが息災で幸せであってくれればうれしく思っています」程度のことは示し続けたいのだ。これが承認、ということだろう。
一方、「理解」はもう少し深いコミュニケーションがないと感じられない。
では、どのような場面で人はそれを感じ取るのか。
それは、音声であれ文章であれ何らかのやり取りをしている最中、背後にある文脈、感情、意図を理解しようとする姿勢と、誠実な応答があった時、ではないだろうか。
最近は「傾聴」流行りのようだが、私自身はというとテクニックとしての「傾聴」を会話上で使う人はあまり信用していない。いくたびか明らかに傾聴を意識していると思しき相手と話したことがあるが、毎度どうにも癇に障る結果に終わったからだ。わざとらしい表情と相槌、そして必殺オウム返しなどにイラッとさせられたのだろう。実際、傾聴技術の知識があれば、それをなぞっているだけの態度はタネを知っているマジックを見せられているに等しい。
一方、的確に口を挟んでくれる人には、たとえ口調や態度は雑であったとしても、胸襟を開いて話すことができる。単なる同意や否定ではなく、相手の発言の意味を深く考えた上での応答をしてくれたり、共感を示すため自分語りになりすぎない程度、あるいは相手の話を奪わない程度で自己開示してくれると話しやすいし、相互理解の機会にもなる。
普通の会話はやはり「双方向」じゃないとだめなのだ。カウンセリングじゃあるまいし。主体があくまで先方であってもお互いが理解し合い、応答し合うことで、より深いコミュニケーションが取れる。
デジタル技術が発達し、コミュニケーションの形態が多様化してどれだけ世の中が変わろうと、人間同士の本質的な理解と承認への欲求は変わらない。「共感的な理解と誠実な応答」の重要性はむしろ増しているように思うが、その起点こそ「私はあなたを認識し、折りにふれ思い返すことがあります」と示すことなのではなかろうか。
一方、頻度は高くても上っ面だけ、あるいは過剰なコミュニケーションが軋轢や分断の元になるのも忘れてはいけない。
SNSは希薄なつながりが頻繁に交わされるプラットフォームだが、そこでは常に分断と小競り合いが繰り広げられている。表面的なやりとりだけがブリザードのように吹き荒れる場なのだから、勢いそうなるのだろう。
同じ価値観を持つ人々のみとの交流が容易で、異なる意見との接触機会が減少しやすい環境だと、人は多様性への寛容さが低下し、自分の属するコミュニティーの価値観が「正しさの基準」となりやすい。すると自分の価値観が歪であっても、それに気づかないどころかますます強化されてしまう。
また、対立の可視化が空中戦を呼び、各コミュニティーが擬似陣営の様相を帯びてくると議論が感情的になりやすく、「敵か味方か」という幼稚な二項対立的思考が強まる。
さらに、自己のアイデンティティーを特定の価値観や趣味と強く結びつける傾向があると、些細な違いを「自己否定」として受け取ってしまう。
これはオフラインの場でも同じだ。いくら毎日顔を合わせようと、どれだけリアルに言葉を交わそうと、表面的なやり取りに終止していれば同じ経緯をたどる。会社や学校での小さな派閥、あれはこういうので生まれるのではないかなと思う。
こうした弊害を防ぐてっとり早い方法はたったひとつ「距離を置く」こと。過剰コミュニケーションを避けて、エコーチェンバー現象から身を守るのだ。
一週間も離れていれば、瘧が落ちたようになるだろう。なぜなら、こうした状態は必ずしも不可逆ではないからだ
悪に強きは善にも強し、ではないが、なにかのきっかけで改心できればむしろ異なる価値観との「建設的な対話」の重要性に気づき、多様性を受け入れつつ、共通点を見出せるようになるのではなかろうか。
そうなると、コミュニケーション・スキルのレベルは一段上がる。「違い」を前提とした対話の構築ができるようになるからだ。
完全な一致や同意を目指すのではなく、違いを受け入れた上での繋がりを保つのは「選択的関与」を実現するための手段に他ならない。
趣味でも興味の対象でもいい。とにかくなんらかの「共通の基盤」を発見できれば、主義主張の違いを超え、共通体験を通しての連帯感を持つことができる。
たとえば、政治的主張はまるで真逆だったとしても、大好きな明太子の話ならば延々としていられる。そんな関係があってもよいではないか。そういう些細なところから、やがて日常生活での喜びや苦労、人生における希望や不安などに共通する部分が見えてくるかもしれない。すると対立していた部分でも対話の可能性が出てくる。
もちろん、対話を明太子だけに絞ってもなんの問題もない。少なくとも、そこだけはピンポイントでお互い有益な関係性を維持できるのであれば、それはそれで立派な選択的関与だ。主義主張や価値観がすれ違い続けたとしても、少なくとも相手が虫けらには見えなくなる。
結局のところ、「理解」と「同意」は似て非なるものだ。理解できないまま同意してもいいし、理解はするけれども同意はしないという方法論も成り立つ。
同じアイスクリーム好きとして出会ったものの、先方に「私、アイスクリームには醤油をかけて食べるのが好きなの!」と言われたら、普通なら即座には理解できないだろう。しかし、「甘じょっぱい」が定番味であることを考えると、まったくおかしなわけではない。だったら「そういうのもありだね」と同意はしつつ、でも自分はしない選択が出てくる。強いられたら拒否すればいい。この拒否は分断にはならないからだ。まあ、私は一度ぐらいは試してみるタイプなのですが。だって、何でもやってみないと合うか合わないかなんてわからないもの。
とにかく、完全には重なり合わなくても一部なら共有できる「ゆるやかな紐帯」を維持すれば、柔軟な関係性を多数持ち、選択的に関与することができる。これだと、状況に応じて関わりの強度を変えられるし、一時的な距離の発生も関係性崩壊の危機にはならない。
過度な期待や義務感を伴わないが、必要な時には支え合える存在がいると、人生は楽になる。
一度ここまでのポイントをざっとまとめよう。
・常に連絡を取り合う必要はないが、重要な出来事は共有する。
・互いの生活リズムや忙しさを理解し、尊重する。
・「会わないこと」への罪悪感や不安を持たない。
・相手が助けを求めた時には可能な範囲で対応。
・しかし、自分の限界も明確に伝える。
・互いの資源(時間、労力、金銭など)の限界を理解する。
これをベースにした上で、長期的な関係維持のためには、人生の変化(転職、結婚、転居など)によって発生する関係の変化を自然なものとして受け入れることを念頭に置かなければならないが、ま、この辺りは五十代にもなっていれば誰もが経験済みなのではないかと思う。そして、どれだけ環境が変化しても根っこの信頼関係は継続することを実感として知っているはずだ。知らなければ今から知っていけばいい。
私たちは、生活様式の多様化や社会の流動性が高まった時代に人生を過ごしてきた。現在、従来の固定的な人間関係では対応できない状況が増えてきている上、世代間での価値観の差異が拡大し、「正解」とされる生き方も相対化されている。
こうした状況では、従来型の「固定的で画一的な付き合い方」よりも、状況に応じて柔軟に関係性を調整できる「ゆるやかな紐帯」の方が、より持続可能なはずだ。
ただ、「ゆるやかな紐帯」程度の関係性で、いざという時に支援を求めるのは難しくないか、という疑問も出てくる。つまり、「そこまでやるほどの間柄ではない」と判断されてしまうのではないか、ということだ。
たとえば、私が誰かに「旅行に行っている間、鍵を預けるのでペットの世話を見てほしい」と頼まれたとしよう。頼んだ方は当然私が依頼できるほど信用に足り、なおかつ受けてくれるほどには近い関係にあると思っているはずだ。一方、私のように自他の線引きがくっきりはっきりしている者の感覚では、いかに親しくとも主人不在の家に入るのはちょっと、になる。お互い親しさ自体は同レベルと認識していても、そのレベル内での許容範囲が曖昧なままだと、躊躇が生まれるわけだ。
こういう場合、事前にどの程度のことを助け合うかを話しあっておけば、余計な逡巡もなくなる。また、人のよい人ほど相手への負担を考えすぎて頼めなかったりするものだが、関係そのものが互恵性のものなのだと理解してもらえれば不安も払拭できると思う。
お互いの溝を埋めるには、まずは軽い相談から始め、相手の反応を見ながら具体的な支援要請に進むのがいいのではないだろうか。もちろん、途中で断れる選択肢を常に用意すること。また、明確な限定付きの要請にする、つまり支援の内容と期間を具体的に示したり、相手の負担を最小限に抑える工夫を提示するのも必要ではないか。また、同時に代替案も検討していることを伝えると、相手が断りやすくなる。
また、なんらかの報酬を用意するのも手だ。人間、たとえわずかな報酬でもそこに明確な取引関係が生じると心理的障壁が低くなるからだ。
そもそも、自分から積極的に行う普段の小さな支援や気遣いが、支援を求めやすい土壌を作ることになる。大きな支援の前に、小さな支援での反応を確認しておくと安心感にもつながる。
このように、支援要請のハードルを下げつつ、相手の選択の自由も保障する方法を意識的に構築することで、「ゆるやかな紐帯」でも実効性のある支援関係を築くことが可能ではないだろうか。
よし、理論は整理できた。では、次の段階に進もう。