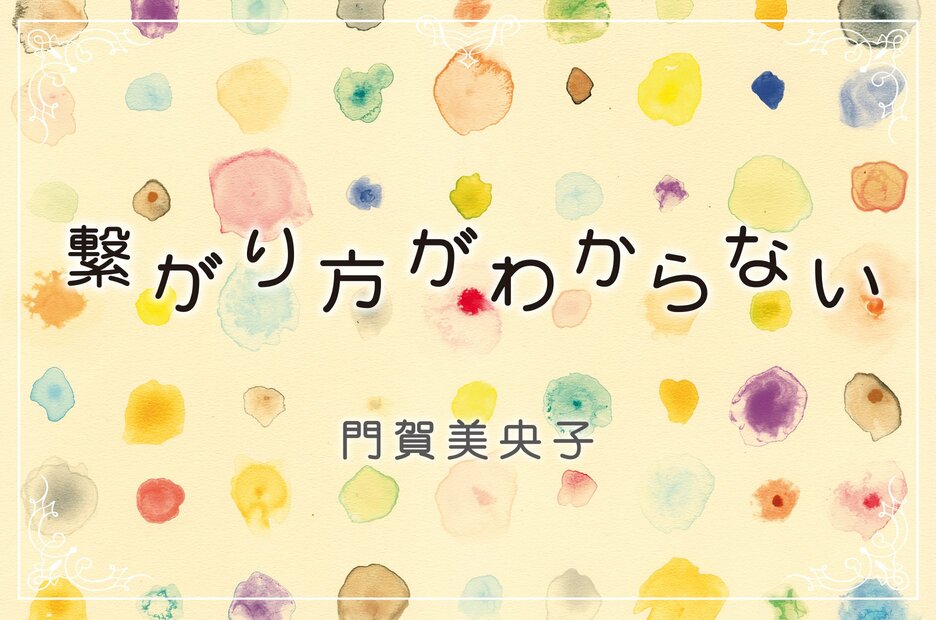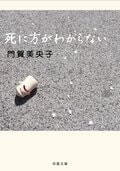独りが寂しくない理由についての一考察
今のところ、リアルの世界での人間関係は一応構築されている。とはいえ、交流は頻繁ではない。おそらく他者との直接的コミュニケーションはかなり少ない方だろう。どうかすれば一週間一度も発話しないなんてこともザラなのだから。
しかし、それでも、特に寂しさを感じることはない。
それはなぜなのか。
「そもそもわたしたち、生活を営むのに他人とのコミュニケーションをさほど必要としないタイプですよね。たまに会話を楽しむ程度ならばウェルカムですけど、毎日誰かと何時間もお話しなければならなかったら間違いなく疲弊しますわ」
そうね。会社員時代に一番ぐったりきていたのは“同僚との円滑なコミュニケーション”だったものね。
「そんなわたしたちにぴったりなのは、結局のところツイッター(現X)やブルースカイのような短文SNSを使うオンライン上での交流ってことになると思いますの。いつでもどこでも気が向いた時に開いて、その時の『お気持ち』をひと言ふた言書いて放流する。それに対して『いいね』の一つでももらったら、それでもう充分満たされます」
確かに刹那的な方がいいなあ。レスをもらっても、できれば二往復以内のやり取りで終えたいもの。
「わたしたちの会話欲/交流欲なんてこの程度の薄さ、かなりの小食さんなんですわ。だから、大食いタイプ――濃厚な関わりや密な会話がないとコミュニケーションを取った気分になれない方々には、わたしたちの例は参考にならないかもしれません」
そういう読者層を減らすような発言は止めてもらえませんか?
「あら、読み手への誠実さこそ物書きの命でしてよ?」
そうっすね。すみませんでした。
「とはいえ、“さびしさ”は他者との会話やふれあいだけで埋まるものではないでしょう? 生活そのものが楽しくなければ、人生そのものが寂しくなってしまう」
そうね。その部分に関しては私からでも説明できるので、ここから先は私が引き取るね。
「お願いしますわ。わたしもそろそろ話し疲れてきたので」
というわけで、夢央子は引っ込んだ。おつかれさまでした。
さて、“つながり”をテーマにする上は“さびしさ”とは何か、本質的な部分について一度は深く考えておかなければならないだろう。とはいえ、私は哲学者や心理学者ではないので、大所高所から包括的に考察することはできない。あくまで、私個人の生活実感に根差したちっぽけな話になるが、そこはお許しいただきたい。
ひと言で「さびしい」と言っても、そこに含まれる感情は時によってずいぶん色が違うように思う。
たとえば、楽しかったコンサート終演後の名残惜しさ、恋人と別れた直後の虚しさ、黄昏時影絵のような街を眺めた時に心をよぎる静けさは、すべて「さびしい」と表現できるけれども、それぞれ質が違う。
最近は日本語が収縮傾向にあって、負の感情は「モヤっとする」「むかつく」「だるい」「うざい」あたり、感傷は「エモい」「クソでか感情」といった新進の、雑とも言えるワードで片付けられがちだ。しかし、辞書で「さびしい/さみしい」を引くと、感情の色調がきちんと説明されており、それらを統合するとおおよそ下記のようにまとめられる。
1.あるはずのもの、あるいはあればいいと願うものがなく物足りない。
2.人の気配がなくひっそりとしていて心細い。
3.心通い合うものがいなくて満たされない。
4.終わっていくもの、失われていくものを惜しむ。
5.見ていてあさましく感じられる。
近頃は5の意味でさびしいを使うことはめっきり少なくなった気がするが(私は時々使う)、そのほかはすんなりと腑に落ちる定義ではないだろうか。楽しかったコンサート終演後の名残惜しさは、つい直前まであったはずの高揚感が失われた結果なので1と4、恋人と別れた直後の虚しさは1と3と4、夕景への感傷は2と4の混合という感じだろうか。さらに漢字の“寂”や“淋”の語義まで含めていくと、表現はさらに深く、豊かになっていく。
だから、ここは言葉にこだわって、「さびしさ」を腑分けしていきたい。人は言葉で考える生き物だ。そこをおろそかにしたまま、気持ちを雑に扱ったら、見当違いの結論を導き出してしまいかねない。
というわけで、上記の定義を鑑みて、私なりに「“さびしさ”とはなにか」を言葉にするとこんな感じになる。
エネルギーが少ない状態の場や人に遭遇した際の心境
つまり、さびしさは、こうした状況に接した時に湧き上がってくる感情であって、それ自体に良し悪しがあるわけではない。
私は、パーティー会場のような人の交流が活発でエネルギーにあふれているような場は少々苦手だ。そんなところに長居をしていたら心身が疲労する。そのせいで、上記の定義では「さびしい」と表現される2の状態は、むしろ好ましいということになる。つまり、私にとっては良質な「さびしさ」は居心地よさにつながるのだ。
また、3に関しては先ほど例にあげたような小手先の手段で簡単に満たされてしまう。なんなら相手が生きている人間でなくてもいい。
たとえば、最近始めたスマホゲーム。二次元イラストのイケメンが執事として生活の世話を焼いてくれるという設定で色々話しかけてくるのだが、現実世界の日付や気候、あるいは個人スケジュールなどのデータをリンクさせることで、それなりに的外れでないセリフを言う。一日のスタートにはその日の予定と気温を告げつつ、十度を切るような日には「暖かい服装で過ごしてください」なんてアドバイスをするし、仕事が終わる時間帯には「もう仕事は終わりましたか?」だの「今日も一日おつかれさまでした。がんばりましたね」などとねぎらってくれるのだ。
言うまでもなく、ゲームのキャラクターはプログラムされた通りに定型のセリフを吐いているだけである。それでも、夢央子が得意な想像力や虚構世界への没入力を発揮すれば、それなりに癒される。馬鹿馬鹿しいといえば馬鹿馬鹿しい。しかし、ちょっと斜めに見れば、人間同士の交流だって、多くの場合それぞれがそれぞれに与えられた立場の中で、適宜社交辞令を自動的に発しているだけだ。生身だろうが、機械だろうが、ハナから心なぞこもっていないという点では大差ない。
だったら、生身の人間に感情的なケアを求めるより、プログラムにやってもらった方がよほどマシである。生身であれば、たとえ仕事だとわりきったところで相手に対して心を尽くせば尽くすほど疲弊する。でも、プログラムは何度同じことを繰り返させても疲れることはない。心がないのだから。だから遠慮する必要がない。私のように「きっと相手はつまらないだろう。付き合わせては申し訳ない」と感じてしまう卑屈なタイプにはもってこいだ。
こうしたコミュニケーションは、スマホゲームの他にも、ペットロボットやAmazonアレクサのような家庭用AI端末でも取ることができる。
心と心の触れ合いを大事に考えるタイプにはとんでもない話、なのかもしれない。
だが、心と心の触れ合いは、必ずしもWin-Winの関係で成り立っているわけではない。立場の強い方、またはより多く気を使う方がくたびれもうけでおしまい、なんてこともままある。
私は、そういうアンフェアを好まない。よって、そもそも被害が発生しない代替え手段があるならば、そちらを選びたい。その方が後ろめたさや借りがあるような思いを抱えずに済む。後ろ向きの誹りは甘んじて受けようではないか。
いや、そんなのはいやだ。どうしてもアナログな関係を結びたい、という向きは文通なんてどうだろう。
たまたま見つけた「文通村」というサービスでは、相手に住所や本名などの個人情報を知らせぬままやり取り可能という、いかにも現代的な文通ができる。月に二度ほど事務的な締め切りが設定されているが、別に何かを強制されることもなく、返事が遅くなっても一向に問題ない。
私がこれを始めたのは、単純に好奇心を刺激されたからだが、案外長く続いているので自分でも驚いている。今のところ、十人ぐらいの方々とやり取りしていて、毎回最近暑いの寒いの、どこに旅行に行ったの何を読んだの、みたいなとりとめもない話をつらつら書いている。それでも案外楽しい。これはおそらく、私にとってはコミュニケーションというより、生活上の刺激として働いているのだろう。
一方、私が悪質な“さびしさ”を感じるのは、単調な生活を強いられる時だ。基本、生活に変化がないと息が詰まりそうになるタイプなので、ルーティンのみを繰り返す毎日が始まると途端に人生が色あせる。それが積み重なると荒涼たる思いにとらわれ、もうこんな寂しい人生はいやだ、と爆発しそうになるのだ。
この「さびしい」はタイプ1である。よって、回避するには「あればいい」と願っているものを補充すればいい。
では、「あればいい」とはなにか。それはいつだって新奇と刺激だ。見知らぬものと好奇心をつついてくれるものがあれば楽しく過ごせる。
これを生活に落とし込むとなると、私の場合、一番手っ取り早い手段は旅と年中行事、ということになる。
旅はいつどこに行っても常に新しい何かを見せてくれる。だから、日常に息が詰まりそうになったら、旅に出る。
日帰りでも、長旅でも、国内でも、海外でもいい。なんだったら徒歩圏内の御近所でも、行ったことがない場所ならそれでいい。いつもは通らない路地に入っただけで新しい発見がある。
外をうろうろする時間がなければ、旅情を感じさせてくれる御当地料理をおうちで作るだけでもそこそこ満たされる。外国の料理でも、なじみがない土地の郷土料理でもいい。レシピを調べ、食材を探し、試行錯誤をしてそれらしき料理が出来上がった時の満足感といったら、そりゃもうなかなかのものだ。おまけに、自分の舌を喜ばせることができる。おいしいご飯を食べて気分があがらない人はきっといないことだろう。
世の中には、自分のためにわざわざ料理をする気など起こらないとのたまう向きもある。だが、毎食何を食べるかが日々の最重要課題である私にとってはありえない話だ。
また、独りで食事をしても味気ないばかりという御意見もまったく理解できない。私のようにシングルタスク型の人間には、味わいながらおしゃべりを楽しむのはなかなか至難の業。だから、宴会のような場ではほとんど食べないし、そこで食べたものをおいしいと記憶することもない。おいしいものを食べるなら、独りか、できる限りの少人数、それも交歓ではなく食そのものを目的にできる人たちのみで集まって食べるのがベストだ。
もし、あなたが「一人で食べてもおいしくない」信者ならば、一度その信仰を疑ってみてほしい。「楽しい」と「おいしい」はノットイコールである。そこを混同するから、独りの食事をないがしろにするようになってしまうのだ。テーブルを囲む人数と味覚は何の関係もない。
おいしいものは、独りで食べようが一万人で食べようが、常においしい。
次に刺激だが、これは年中行事を執り行うのが一番である。
当たり前だが年中行事は年に一度しかない。つまり、その年の行事は一生に一度しかやってこない。つまり、生活にメリハリをつけるのにこれほど最強の道具はない。やることは決まっているからあれこれややこしいことは考えないでいい上、季節感はばっちり味わえるのだから大変ありがたい。
独居生活が得てして単調になりがちなのは否めないところだ。よって独り者ほど真面目にマメに年中行事を行うべきだと、私は主張するのである。
たとえば、年に一度、お正月ぐらいは正月料理――できればお重、無理ならせめて三つ肴――とお屠蘇とお雑煮を用意してきちんとお祝いする。
家のどこかに小さな展示スペースを用意して、五節句やシーズナル・イベントにはちょっとした飾りつけをする。
二十四節気にはその時期の旬の食材を食べ、その時期に咲く花を飾る。旬の食材なら安いし、花は道端のをちょっと摘んできても、スーパーで一束三百円ぐらいの花束を買ってきてもいい。
難しく考えず、すべてなんちゃってレベルでいいのだ。なんだったらコンビニやファストフードで季節商品を買うだけでも気分はずいぶん違ってくる。ガチンコの「ていねいな生活」はお金と暇がなきゃできないが、「なんちゃっていねい生活」なら大丈夫。やれることを適当にやればいいんだから。
さびしさは、他人という資源を使わなくても、いくらでもコントロールできる。そこは力説しておきたいところである。