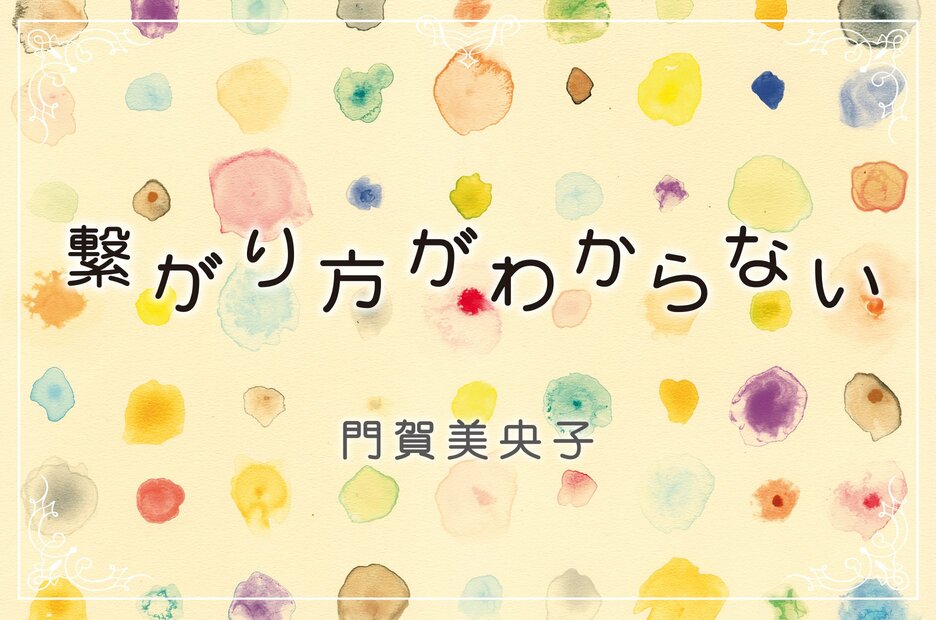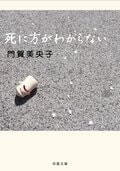ふたつとせ、本邦学者のいうことにゃ
「『孤独=豊かな独り時間は、楽しく善き人生を送るために欠かせないもの』。わたしたちモンガーズはまず、この認識からしっかり共有しましょ!」
夢子はほがらかに軽やかにそう言った。
「人はたしかに一人では生きていけない。それはあなたが前回鬱々クドクド吐露した通り。でも、ず~っと群れの中にいたら息が詰まって逃げたくなる個体もいる。何も考えずにみんなと同じように振る舞えって言われたらそれだけで病んじゃうタイプもいる。これは生まれつきの個性で、否定するものでも、できるものでもない。未婚独居のままいい年になっちゃうタイプって、だいたいはこれなんじゃないかしら? 世間一般の人より孤独耐性も孤独適合性も高いのよ。怠央子風に言えば『ぼっち上等、マジで』って感じ?」
だってね、と夢子は言葉を重ねる。
「寂しさに耐えられない人って、たいてい家族と同居のままか、結婚を目指して血道をあげてるかのどっちかでしょう?」
まあ、確かに。
「でも、わたしたちは、他者との同居や結婚せんがための婚活的な行動のわずらわしさの方がよっぽど耐え難い。それに子供のころから独りの楽しみを追求してきた結果、今やマスター……いいえジェダイ・クラスになっているし」
それは相違ない。一人っ子あるあるだが、幼い頃はよく「きょうだいがいないと寂しいわね」と同情されたものだった。しかし、そう言われてもなんとも答えようがなく、あいまいな笑みを浮かべてやり過ごすしかなかった。兄弟姉妹がいる生活がどんなだか知らないから比べようがなく、寂しいもクソもないんだけどなあと思っていたのだ。
不便なら、あった。たとえば、ボードゲームなどある程度頭数が必要な遊びができないとか、ごっこ遊びでは一人何役もこなさなければならないとか。しかしそこで感じていたのは「不便」であって「さびしさ」ではない。
一方、兄弟姉妹が多ければ多いほど生活資源や親の愛情を奪い合わなければいけないわけで、傍目ではそっちのほうがよほど大変そうだった。もちろん、兄弟姉妹が助け合い、かばい合うような場面では多少のうらやましさもあった、ような気もする。しかし、それが幼児小児ライフにおいて重大事として認識されることはなかった。
むしろ、頼れる兄弟姉妹がほしいと思うようになるのは成人後、それも親が保護者から被保護者へと変わっていく段階でのことだ。相談相手がほしいと切実に思う場面が何度もあったのだ。
とはいえ、私の場合は思うだけで切り抜けられたが、切実度がより高い人たちもいる。
2024年11月26日にネット上で公開された「『なんで私が全部?』こぼれた涙 一人娘が背負った『トリプル介護』」という記事では、長男の家に生まれた一人娘であるがゆえに祖父母や実母の介護を一人で背負うことを強要された女性が取材されていた。
その女性は、家の跡継ぎとして進学や結婚、出産などライフイベントのすべてに干渉を受けたという。しかも、夫の急死で働くシングルマザーとなったにもかかわらず、親類縁者の助けなしに子育てをしながら、祖父母や母の生活や介護をすべて一人で担わなければならなかった。塗炭の苦しみの末、家族は崩壊し、結果的に彼女は自由を得ることができたが、後味は決してよいものではなかっただろう。
こうした例は極端かもしれない。少なくとも、すでに上世代が残りわずかになっている世代の人間には起こり得ない。それでも、やはり先々を考えると彼女が味わった「誰にも頼れない」孤独は決して他人事ではない。
「その点に関してはうなずかざるを得ないけど」
夢子は口元に一本指を立てるあざといしぐさをしながら、わざとらしく首を傾げた。
「じゃあ、兄弟姉妹や夫子がいれば相談者がいない孤独から解放されると思う? 私はそう単純なものでもないと思うけどなあ。兄弟姉妹がいるせいでかえって話がややこしくなるとか、夫や子がなんの役にも立たないどころかかえって足を引っ張るなんて話、山ほど見聞きするじゃないの。家族がいるからこそ深まる孤独も苦境もあるんじゃないかしら?」
それもそうではある。身近に頼っていいはずの人間がいるにもかかわらず、実際にはまったく当てにできない方が、孤独感はより増すのかもしれない。
「その点については、阿比留久美さんの『孤独と居場所の社会学』(大和書房)を読んだ時にとっても考えたの。というのも、御本の中に『家族幻想』って言葉が出てくるのね」
内容を簡単にまとめると、現代日本の結婚は『たった一人の相手と一生添い遂げるという物語の中で、愛・性・生殖が一体化したもの』であり、『手垢にまみれた現実的な生存戦略と規範の維持装置』として機能するものとした上で、社会はそこにロマンティック・ラブという物語から生まれる幻想を付加することで現実を管理する手段として利用してきた、ということであるらしい。
「つまり、結婚して家族さえいれば安心っていう共同幻想を社会に持たせることで、国家が担うべき社会保障の一端を個人に負わせているってわけね。しかも、恋愛結婚だと、相手がどれほどのゴミクズだったとしても、最終的には破綻してしまったとしても、すべて個人責任にしてしまえるじゃない。少し前までは家族の問題に公は関与しないのが当然ってことになっていたけど、それって公が私に干渉しない配慮っていうより、個人がどうなろうが知ったこっちゃあねえってのが本音だったわけでしょ? 昭和の頃なんて、家庭内で絶対的弱者がどれほどひどい目にあっていても、警察も役所も一切助けようとしなかった。さすがに最近は公や第三者機関が介入する仕組みができ始めているけど、でもまだまだ『家族のことは家族で解決してね』っていう風潮は強いわよね。それを支えているのが『家族幻想』なわけだけど、この幻想を疑いを挟む余地もないほど強く持っている人って結構いるでしょう。ほら、よくあるじゃない? どう見ても幸せな結婚生活を送っていなさそうな人がなぜか熱心に結婚を勧めてくるパターン。わたし、前々からあれがものすごく不思議だったの。冷央子は『ありゃ結婚ゾンビだ。自分とおんなじ不幸な人間を増やしたいだけだ』なんて言うけど、わたしはもっと素朴な気持ちから相手のことを思って、勧めているんじゃないかなあって気がするの。根拠はないけどとにかく結婚しなきゃ人生は始まらない、って無批判に思い込んでいるというか、思い込まされているというか……。だから、結婚していないことを人生の一大事のように感じて、心から相手を案じているんじゃないかしら。でも、実際は結婚なんて人生のオプションのひとつに過ぎないんじゃない?」
まあ、そうだね。
「なにが幸せかなんて、人によって違うわけ。もちろん『家族がいる幸せ』は確かにあるわよ? でもおんなじぐらい家族がいるがゆえの不幸もあるし、家族がいても孤独な人だっているし。一度冷静になって『家族幻想』から離れたところで自分を見直したら、全然幸福じゃない“今”を発見してしまう人も少なくないんじゃないかな。いわゆる世間並みの生活を送れていると思い込むことで、寂しさや満ち足りない思いをごまかしているっていうか、実はそれほど幸せでない現実に気づかぬよう目と耳をふさいでいるというか」
おや、夢子さんにしては珍しく辛辣ですな。
「あら、わたしだってそれなりに思うところはありますから」
へいへい、そうですか。
「人間って、基本はめんどうなことは考えたくないわけじゃない。考えるのってカロリーを使うし。だから、世間の型に当てはまっている自分は無条件で幸福、少なくとも不幸ではないはずだってところで停止して、それ以上考えようとしない人がいるのもわかるの。そして、考えようとしないから、無邪気に結婚を勧められるんじゃないかしら」
結婚が「つながり」を作るもっとも有効な手段であることは間違いないからね。
「家族がいれば安心って思える人は、その方法を選ぶのがもっとも合理的なんじゃない? でも、“家族の絆”なんて言葉を聞いたら一目散に逃げだしたくなるわたしたちみたいな人間にはまったく向いていないわね」
そこで、ゆるいけれども、かといって赤の他人でもない生温かい関係性を求めたいわけですよね、私たちは。
「そう、身勝手な言いぐさなのは承知の上だけれど」
夢子は軽やかに笑った。
「でも、独りでいることのマイナス面も引き受けた上で、孤独の楽しみを最大限享受して生きるのが一番心地いいっていうなら、それぐらいがベストってことになるじゃない」
それに最適な距離感を模索しましょう、というのが今回のコンセプトですな。
「そう。楽しい孤独生活――楽孤生活とでも呼べばいいかしら?」
ラッコ生活か。いいんじゃない? 海獺が波間でのんびり揺蕩っているイメージが、私たちが求める生活の在り方にぴったり。
「たゆたう……私の好きな言葉です。とにかく、楽孤を目指すのに絶対陥ってはだめなのが社会的孤立。これはもう読んだ御本すべてに共通して強調されていたポイントでした。結局のところ、社会的孤立はセルフネグレクトと密接に関係していると考えていいみたい」
セルフネグレクトとは自己放任と和訳される言葉で、「通常一人の人として生活において当然行うべき行為を行わない、或いは、行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かされる状態に陥ること」を指す(内閣府が使用している定義)。いわゆる「ごみ屋敷」で生活する人が典型例だが、そこまでいかなくてもまともに身なりを整えなくなったり、他者の援助を拒否したりするのも範疇に入る。
セルフネグレクトが極まり、周囲から完全に孤立すると、最終的に孤立死がやってくる。つまり、モンガーズの誰もが忌避する「死んだ後、ぐずぐずに腐って虫に食われて、なんなら液状化した状態で見つかる」事態を招くのだ。
「セルフネグレクトって、精神状態の悪化だけでなく、認知機能に何らかの支障が出ると発生するのよね。認知機能の低下は、いわゆる老人性痴呆だけじゃなく、病気や事故がきっかけで発生する高度認知機能障害や脳疾患によっても起こります。つまり老若問わず誰もが『そうなりかねない』わけ。わたしたちだって、一歩間違えればどうなることやら」
それは確かに。モンガーズの場合、怠け競技のトップアスリートたる怠央子がいる。こいつが全体の主導権を取ろうものならもう即座にセルフネグレクトへ一直線、だろう。
「でしょ? でも、今のところ怠央子が最前線になることはないじゃない? その理由は、曲がりなりにも普通に仕事をしていて、お買い物や用足しや娯楽のために月に何度かは外出をして、たまには人前に出ることもあるっていう普通の生活を送っているからよね。でも、一見普通の生活をしていそうで、注意深く観察したらおそらくセルフネグレクト状態になっているなと感じる人もいなくって? グレーゾーンというか、転落寸前というか」
確かにいる。特に高齢男性に多い。ホームレスとまではいかないけれども、かなり薄汚れた服を平気で着ていたり、髪に櫛を通した跡が見られなかったり。異臭を漂わせることもある。時には家族がいるはずの人がそうなっていて、ちょっとゾッとする思いがしたりする。あれは果たして家族関係が崩壊しているのか、それとも妻子の言うことを聞けなくなった末なのか……。なんにせよ、見ていて痛々しい。
「その点、女性は身だしなみを整えるのが習慣化しているから、たぶんよほどじゃない限りセルフネグレクトが表面化しないと思うのよね」
国内におけるセルフネグレクトの実態は、よくわかっていない。2012年に行われた内閣府の調査によると、その時点でセルフネグレクト状態にある人は、高齢者だけで1万人前後いて、そのうちの約80パーセントがひとり暮らしだったとされている。残りの20パーセントは家族と同居していながら孤立し、自分自身に適切なケアができない状態に陥っているのだ。そこには当然、どちらも認知に問題が生じている夫婦など、家族全員がセルフネグレクト状態になっている数も含まれている。
自治体の実に9割が、こうした人々に対する対策は重要な問題として認識していて、それぞれの地域にあった対策をしている。しかし、件数を把握している自治体となると20パーセント弱にとどまっている。理由は特に明記されていないが、調査自体が難しいことは想像に難しくない。「家族幻想」が邪魔をしているのだろう。
いずれにせよ、セルフネグレクトは決してわかりやすく表面化してくれない。これが、この問題をややこしくしているのである。