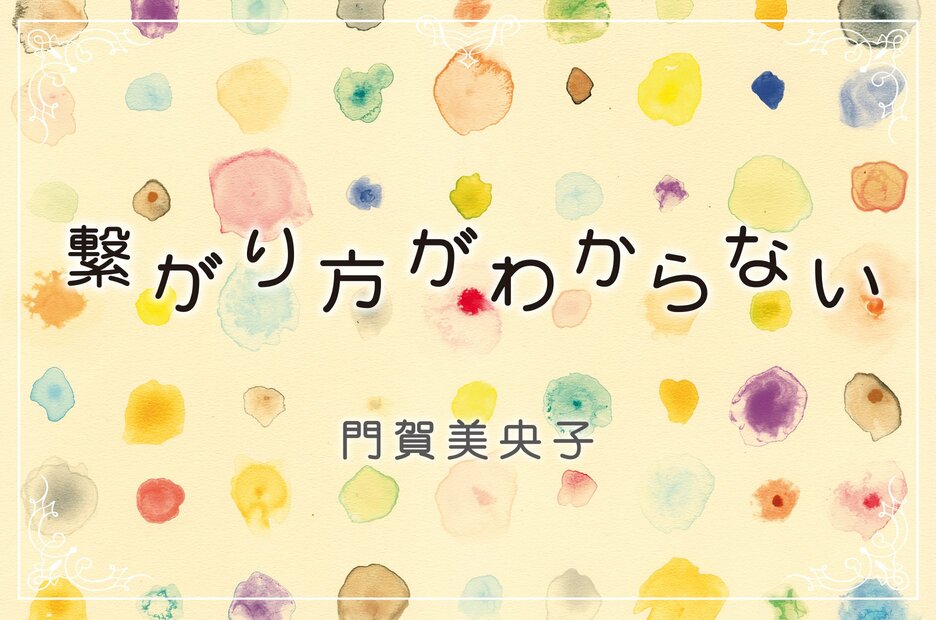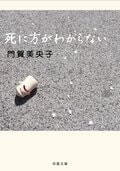夢、膨らませられる?
いの一番、これだけは何があっても実現するつもりなのは「独り者見守りネットワーク」の構築である。
まずは日々の安否確認。これは『死に方がわからない』で知り、私が現在お世話になっているNPO法人エンリッチのシステムを使えば叶う。なにせ、年間5500円(2025年4月現在)という格安のお値段で安否確認サービスを利用できるのだ。
もちろん、これはあくまでシステム利用料のみであり、実際の安否確認は人間が行わなければならないが、ここが「互助会」としての本領発揮の場となるだろう。一人が毎日安否確認の責を負わされると負担になるが、そこは当番制にすればいい。個人情報の取り扱いのマニュアルを作り、それを遵守する必要はあるが。
このシステムがさらに進めば、体調不良や緊急時に互いにサポートし合う仕組みもできるはずだ。具合が悪いときに買い物を代行したり、入院時に必要なものを届けたりと、家族のような緊急連絡先となり得る関係性を構築し、いざというときの安心感を提供する。
次にやりたいのは「スキルシェアの会」だ。それぞれが持つ特技や知識を交換し合う活動である。パソコン操作が得意な人は機器のトラブル対応を、裁縫が得意な人は衣類の修繕を、といった具合に、互いの強みを活かして助け合う。専門的な知識や経験が無駄なく循環する仕組みがあると助かるではないか。
もちろん特別なスキルがなくともできることもある。たとえば、ネット上の手続きなどは慣れない者にとってはとても複雑なものだが、経験者が寄り添えば安心できるだろう。何でも聞ける相手がいる。それだけで気持ちは安定するものだ。
また、「独り者引っ越し隊」なんかもいいかもしれない。
持ち家でも賃貸でも、心身の状態や懐具合が変われば引っ越しは必ず発生する。けれど、なかなか大仕事なのは経験者なら誰でも知っているだろう。家族がいれば自然と手伝ってもらえることも、独り者にとっては大きな負担になりがちである。重い家具の移動や、荷物の運搬など、複数人いれば効率的に進められる作業を協力して行えれば、これはたいへん助かるはずだ。
あと、独り者にはオタ活をやっている人も少なくないだろうが、「これまで溜め込んだ本やグッズの数々をどうすればいいのか」問題は必ず発生するだろう。言うまでもなくうちはすでにもう完全に発生しているわけだが、「大事なコレクションの行く末プロジェクト」みたいな感じで、万が一のときに適切に処分したり、指定の人に届けたりする仕組みを作っておけば後顧の憂いを断てる。その人の人生や思いが適切に扱われるよう、生前に話し合って取り決めておくシステムを作るのだ。
というわけで、色々とアイデアはある。なにせ自分が直面していることばかりだからニーズはあるに決まっている。これらは独り者が直面しがちな課題や不便さを解決するだけでなく、独りであっても豊かな生活を送るための工夫でもある。また、今の私には思いつかないようなことでも、三人寄れば文殊の知恵。人が増えれば、きっとよいアイデアが出てくるはずだ。
互助会の活動を通じて、独り者同士が支え合いながらも、それぞれの自立した生活スタイルを尊重し合える関係性を築けたら、それはもう大変安心できるではないか。
また、互助会を通じて得られるものは、単なる実用的な助け合いだけではないと考えている。独りで生きるという選択をした人、あるいは環境によってそうなった人が、その生き方を肯定的に捉え、豊かな人生を送るための知恵を共有できる場にもなるのではないかと期待している。
「独り者」の中には、様々な背景を持つ人がいる。生涯独身を貫いている人、離婚や死別を経験した人、家族と離れて暮らしている人など、状況は千差万別である。しかし、日常生活の中で直面する課題には共通点も多い。そうした経験を共有することで、孤立感を和らげることができるだろう。
また、独りで生きることのメリットや喜びも共有できる場にしたいと思っている。自由な時間の使い方、自分のペースで物事を進められること、静けさを楽しめることなど、独り暮らしには多くの良さがある。そうした肯定的な側面に目を向け、互いの生活を豊かにするアイデアを交換する場になればと願う。
これまで何度も指摘してきたことだが、社会は依然として、家族を持つことを基本単位として構成されている。行政サービスや社会保障制度、さらには住宅設計や商品パッケージのサイズに至るまで、多くのものが家族世帯を想定して作られている。そのため、独り者は社会システムから取り残されがちだ。
例えば、市役所や役場の手続きは平日の日中に設定されていることが多く、働いている独り者にとっては負担が大きい。家族がいれば誰かに代行してもらえることも、独りでは全て自分でこなさなければならない。また、福祉サービスなども、家族によるケアを前提としたものが多く、独り者の実情に合わないことがある。
住宅環境を見ても、賃貸物件の多くは家族向けに設計されており、独り者にとっては無駄に広かったり、逆に必要な機能が不足していたりする。食料品のパッケージも家族分を想定したサイズが多く、一人で消費するには量が多すぎて無駄になることも少なくない。
このような社会構造の中で、独り者が互いに知恵を出し合い、より快適に生きるための工夫を共有することには大きな意義があるはずだ。
今現在、ようやく社会は「独身者」の問題に目を向けつつある。
つい先日、警察庁は初めて自宅で死亡した一人暮らしの人――つまり独居死の統計を公表した。それによると、2024年の一年間で独居死した数は全国で計7万6020人。死亡数は速報値で161万8684人だったので、約5パーセントにあたる。決して少なくない数だ。
この調査も、単身世帯の増加が社会問題化したことによって行われた対策のひとつだが、問題が可視化され、対策への取り組みが広がれば、社会システム自体も多様な生き方に対応したものへと変わっていくかもしれない。
こうした動きとうまく連動すれば、会もより実り多いものに育っていくかもしれない。いや、そうしたい。
……などとなんだか大きな目標をぶち上げてきたが、もちろん、この互助会の出発点は自分のため、である。私が安心したいがゆえに発案したものだ。
だからこそ、心理的には自由な孤独を保ちながら、孤立を防ぐために誰かと繋がる、というところだけは死守したい。
あくまで自発性と任意性を大事に。
心の支え合いより実生活の支え合い。
それが可能なコミュニティーを今から育てていくことは、私の将来の安心に繋がると信じている。
老いていくことへの不安は誰もが持つものだが、独り者にとってはより切実である。体力の衰えとともに、日常生活のちょっとした作業でも困難を感じることが増えてくる。高い場所の電球を交換する、重い荷物を運ぶ、細かい字の説明書を読むなど、若いときには何でもなかったことが、年齢とともに難しくなっていく。
また、健康面での不安も大きい。病気やケガをしたとき、諸々を代行してくれる誰かがいてくれることの心強さは計り知れない。救急車を呼ぶ、病院に付き添う、退院後の生活をサポートするなど、家族がいれば自然と担ってくれることを独りでやらなければならないのはやっぱりつらい。
さらに、認知機能の低下や判断力の衰えに伴う不安もある。自分自身で適切な判断ができなくなったとき、誰が自分の代わりに意思決定をしてくれるのか。財産管理や医療行為の同意など、法的にも家族の存在が前提となっている制度は多い。そうした状況に独り者はどう対応すべきか、互いに知恵を出し合う必要がある。
ともかくも困ったときに頼れる誰かがいる安心感は、心の健康を維持する上で欠かせない。「最後まで誰にも迷惑をかけたくない」という気持ちも理解できるが、完全な孤立は心身の健康にとって良いことではない。
互助会を通じて、将来への備えを共に考え、支え合うネットワークを築いていけたらと思う。法的な備えから日常的な助け合いまで、独り者同士だからこそ理解し合える部分も多いはずだ。
そしていつの日か、たった一人でもいいから、この互助会が誰かの孤立を救うことができたら、それだけで報われるだろう。それが私にとっては、最大の御褒美である。たとえ大きな組織にならなくても、少人数でも意味のある繋がりが生まれれば十分だと思っている。
たとえ一人を救うだけであっても、その一人にとっては世界が変わるほどの意味を持つかもしれない。そう考えると、小さな一歩を踏み出す価値は十分にあると感じる。
互助会を通じて実現したいのは、単なる助け合いの仕組みだけではない。
独りで生きることの豊かさや可能性を共有できる仲間に出会えることも大きな目的である。社会的なプレッシャーや偏見に負けず、自分らしい生き方を肯定し合える場所を作りたい。別に積極的な交流はせずとも、同じような人がいると思うだけで、人間というのはどこかほっとできるものだ。
孤独を愛する者たちが孤立せずに生きていける社会の一端を担えたらという思いを抱きながら、これからも地道に活動を続けていくつもりである。
独り者が増えている現代社会において、互いに支え合うコミュニティの重要性はますます高まっていくだろう。私の始めた小さな試みが、そのきっかけの一つになればいいな。今はまだ大きく動かなくても、焦らずに続けていこうと思う。種を蒔き続ければ、いつか必ず芽は出るはずである。
たとえ反応がすぐに実を結ばなくとも、必要としている人がいればこの場を見つけられるよう、灯台のように光を灯し続けていきたい。
それが、独り者互助会の目的である。