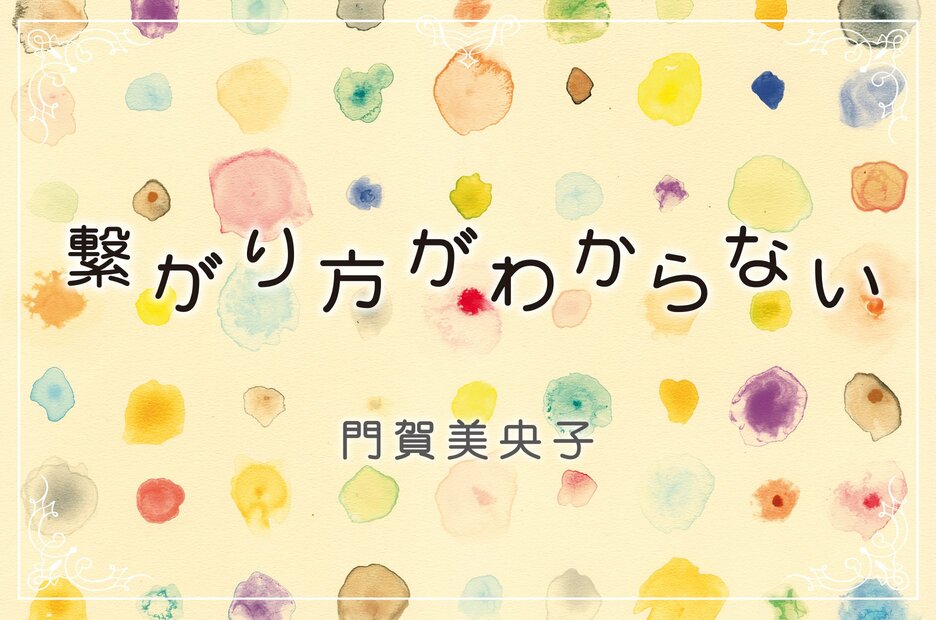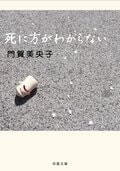結局、ネガティブ三人組を説き伏せることはできなかった。
しかし、ひとまず冷央子と悲央子はすっこんでいることには同意した。動きは止められないと観念し、高みの見物を決め込んだのかも知れない。怠央子は未だグズグズ言っているが、まあ無視しておいてもよかろう。時々丸一日ほどなにもせずに引きこもる日を作れば満足してしばらくは大人しくなるヤツだから。
とにかく、私は動かねばならぬのだ。
言うまでもなく、新たな関係性の構築など一朝一夕でできることではない。
だから腰を据えて準備せねばならない。
また、何か種を蒔いたからといって必ず芽が出るわけではない。実りを迎えられるのはさらに限られるだろう。
だからこそ、やれることはできるだけやっておくべきだ。
たったそれだけのことなのである。
しかし悲しいかな、「たったそれだけのこと」をするにもなかなか腰が上がらないのが私という人間だ。
だったら、まずはできるところから手を付けていくしかない。小さなことからコツコツと、である(このフレーズ、前作でも使った気がする。コピーライトは西川きよし氏にあることを明示しておこう)。
本連載を読んでくださっている方の多くは、きっと私と同じように「孤立は避けたいけど、どうやったらいいかわからないし、わかったところで動くのが面倒」みたいな悩みを抱えているのだろう。人生における自身の欠けを理解していても、埋める気力がわきづらいタイプだ。
少なくとも「望月の欠けたることも無しと思へば」みたいな和歌を詠めちゃうような人生を送っている人は絶対に読まないはずだ。必要がないから。
よって、同志に向けて言おう。
「月は隈なきをのみ見るものか」は、である。
我々が心の師とすべきは藤原道長ではなく吉田兼好である。あ、最近は兼好法師名義なんだっけ。
いずれにせよ、万事うまくやれる人間であればいいってものではないと己に言い聞かせつつ歩んでいくしかないのだ。
とかなんとかどうでもいいことを己に言い聞かせつつ、本当に小さなことから始めることにした。
昔やっていた活動のリスタートである。
まず手を付けるのは「三浦半島幻想文学会」の再起動だ。これは横須賀に引っ越してきてから始めたもので、名前の通り三浦半島在住者で幻想味あふれる文学を愛する人々のサークルづくりを目論んだものだった。
イベント自体は三度ほど行い、それなりに集客もできたが、当時は組織化には興味なく、単発イベント開催の母体にしただけだったので、コロナ禍のイベント開催が難しくなった時期に雲散霧消してしまった。
しかし、時折またイベントに参加したいとのお声をいただくことがある。だから、まったく需要を見込めないわけではないだろう。よって、とっかかりにするには悪くない選択だ。
ただ、以前と同じことをしてもあまり意味がない。「第二期三浦半島幻想文学会」はきちんとサークルとして機能するようもう少し工夫をこらそうと考えている。
次にやるべきはボランティア活動への参加だ。私がボランティアをする場合、スポット的にお手伝いすることが多いが、今後は継続的関与を視野に入れようと思う。
とはいえ、闇雲にやるつもりもない。
日本のボランティアは無給が大半であり、それはつまり経済的余裕がなければできない、ということである。そして、私には経済的余裕はない。
もう一つ、どんなことをするのかもよく精査しなければならない。目的はあくまで地域との繋がりを持つことであるのだから、それが叶いそうな活動に絞るべきだ。また、くれぐれも自分の特性に合わない活動には手を出さないこと。すぐに嫌になってやめたくなるに決まっているのだから。
情けない話だが、私の場合、始めたことをいかに継続させるかが常に第一課題なのだ。小学生の夏休み計画ではないが、プランニングやスタートアップはさほど難しくない。けれども長続きさせるのはかなり難しい。我ながらため息が出るばかりだが、こればかりは仕方ない。持って生まれた特性だ。
現状ひとまず決まっているのは国際交流関係のイベントでのお手伝いである。これは二~三ヶ月に一度、かつ一回が六時間程度なので携わりやすい。あとはいくつか検討中のものもある。
というわけで、二つまではなんとか道筋が見えている。
だが、最後の一手がなかなか手ごわいのだ。
正直、手をこまねいている。
実はネガティブ三人組がタッグを組んだのは、これを阻止したいがためだった。
決して仲良しというわけではない悲観と冷笑と怠惰が手を結ぶほどの計画。
それは「ひとり者互助会」的なものの設立である。
そう、私と同じように将来的な「つながり」に不安を持つ人間が徒党を組んで……もとい協働できる仕組みを作りたい。そう思っているのである。
あらまあ、これは私にしては随分と思い切ったこと!
私自身もビックリだ。
しかし、本来の目的を叶えるにはこれしかない。
というわけで、どこかのだれかにプレゼンする気分で、今どきらしい「計画趣意書」を作成してみた。
【独身者相互扶助ネットワーク(仮)構築計画趣意書】
★背景と社会的課題
現代社会において、五十代以上の独身者が直面する課題は年々深刻化しています。
厚生労働省の統計によれば、生涯未婚率は上昇の一途をたどり、今後も増加傾向が続くことが予測されています。これに伴い、家族による支援システムを持たない高齢独身者の社会的孤立が喫緊の課題になりつつあります。
特に身寄りのない、あるいは身寄りが少ない中高年独身者においては、次のようなリスクが顕在化しています。
1.病気や怪我の際の支援者不足
2.日常生活における緊急連絡先の欠如
3.認知機能低下時の意思決定代行者の不在
4.突発的事態における相談相手の不足
5.財産管理や終末期医療における意思表示の困難さ
これらの問題は、単なる孤独感という精神的側面にとどまらず、実生活における具体的かつ実用的な課題として考慮すべきものです。従来の高齢者支援システムは家族の存在を前提としているため、独身者特有のニーズに対応できていないのが現状です。
★本計画の目的と基本理念
本計画「独身者相互扶助ネットワーク構築」は、上記の社会的課題に対応するため、五十代以上の身寄りのない、あるいは身寄りが少ない独身者を対象とした実用的な相互扶助システムの構築を目指すものです。
★基本理念
1.実用性重視の相互扶助:感情的な絆や仲間意識に依存せず、実用的かつ合理的な相互支援の仕組みを確立する
2.契約に基づく明確な関係性:曖昧な友情や親密さではなく、明確な合意と責任範囲に基づく支援体制を構築する
3.相互利益の均衡:一方的な援助ではなく、参加者全員が等しく貢献し、等しく恩恵を受けるシステムを目指す
4.自律性と独立性の尊重:各参加者のプライバシーと自己決定権を最大限に尊重した上での協力体制を構築する
本計画は、「孤独の解消」や「友人作り」を目的とするものではありません。また結婚や恋愛関係の構築を促進するものでもありません。純粋に実生活上の課題を効率的に解決するための社会的インフラストラクチャーとして機能することを目指します。
★対象者
本計画の対象者は以下の条件を満たす方々です:
・原則、五十歳以上の独身者(未婚・離婚・死別を問わない)
・身寄りがない、あるいは身寄りが少ないために、万が一のことがあった場合の日常的サポートを期待できない方
・自立した生活を送っている(現時点では介護を必要としない)方
・相互扶助の理念に賛同し、自らも他者への支援意思がある方
・明確な契約関係に基づく協力体制を理解し、受け入れられる方
★具体的支援システムの構築
本計画では、以下の実用的支援システムを構築します:
1.緊急時対応ネットワーク
・医療機関等への緊急連絡先として機能するシステム
・参加者間での定期的安否確認の仕組み(デジタル技術活用)
・参加者が入院した際の必要物品の受け渡しや事務的手続きの代行
2.生活継続支援システム
・短期間の体調不良時における必要最低限の生活支援(食料品・医薬品の調達など)
・一時的に外出困難となった際の代行サービス(郵便物の投函、公共料金の支払いなど)
・各種行政手続きにおける情報提供と必要に応じた同行
3.意思決定支援システム
・任意後見契約や遺言書作成など法的準備に関する情報共有と専門家紹介
・医療・介護に関する事前指示書作成支援
・財産管理に関する相談ネットワークの構築(専門家との連携)
4.情報共有プラットフォーム
・独身者特有の法律・福祉制度に関する情報集約と提供
・各種公的支援サービスの活用方法の共有
・住まいの維持・管理に関する実用的情報の交換
★組織構造と運営方法
本計画では、感情的つながりに依存せず、かつ持続可能な組織とするために、構造を以下のように構築します。
1.ブロック制による小規模ユニット形成
居住地域ごとに数名程度の小規模ユニットを形成
各ユニット内で基本的な相互扶助機能を完結させる
複数ユニットを統括するブロックマネージャーを配置(可能であれば専門知識を持つ有償スタッフ)
2.明確な役割分担と責任範囲の設定
・各参加者の提供可能なサポート内容と範囲を事前に登録
・サポート提供時間や頻度に関する上限設定
・緊急度に応じた対応区分の明確化
3.ポイント制による貢献度の可視化
・支援提供によるポイント獲得、支援受領によるポイント消費
・ポイントバランスの定期的モニタリングと調整
・長期的な相互貢献の均衡を目指す仕組み
4.第三者機関との連携(将来的目標)
・法律・医療・福祉などの専門家との顧問契約
・地域包括支援センターや社会福祉協議会など公的機関との連携
・必要に応じた民間サービス(警備会社、家事代行など)との提携
★資金計画
本組織は互助会としての性格を持ちつつ、安定した運営を確保するため以下の資金計画を立案します:
1.会費制度:参加者からの定額会費による基本運営費の確保
2.公的助成金の活用:高齢者支援や地域福祉に関連する助成金の申請
3.有料オプションサービス:基本サービスを超える高度な支援の有料提供(検討)
★リスク管理と倫理的配慮
組織体の健全な運営のため、以下のリスク管理と倫理的配慮を徹底します。
1.境界設定の明確化
・支援可能な範囲と不可能な範囲の明示
・プライバシーに関する明確なガイドライン策定
・感情的依存の回避に関する研修実施
2.紛争解決メカニズム
・中立的な調停委員会の設置
・段階的な問題解決プロセスの確立
・必要に応じた参加者の移動や組み換え
3.安全対策
・参加者の身元確認と信頼性評価
・個人情報管理の徹底
・緊急時の専門機関との連携体制
★成功指標と評価方法
本計画の有効性を客観的に評価するため、以下の成功指標を設定します。
1.実用的支援の実績
・緊急対応の発生件数と解決率
・生活支援サービスの提供回数と満足度
・問題解決に関する具体的事例の蓄積
2.システムの持続可能性
・参加者の継続率
・ポイント収支の均衡状況
・財政的自立度の推移
★今後のロードマップ
本計画は以下のスケジュールで推進します:
1.準備期間(6ヶ月):
基本設計の詳細化
初期参加者の募集と選定
運営マニュアル整備
2.試行期間(1年):
モデルグループでのモデル事業実施
課題抽出と改善
初期評価の実施
3.展開期間(2年目以降):
会員の段階的拡大
運営体制の強化
自治体など他機関との連携拡大
★結び
「独身者相互扶助ネットワーク構築計画」は、感情的な絆や仲間意識に依拠せず、中高年独身者が直面する実生活上の課題に対する実用的解決策を提供するものです。結婚や恋愛関係の構築を促進するものではなく、あくまでも独身者が独身者として尊厳ある自立した生活を継続できるための基盤づくりが最大の目標であり、達成すべきゴールになります。
繰り返しになりますが、本計画が目指すのは、友愛や感情的結びつきによるコミュニティではありません。明確な契約と相互利益に基づく実用的な支援ネットワークです。独身者が増加し続ける現代社会において、家族に依存しない新たな社会保障の形として本計画が機能することを期待します。
私たちは互いの存在を感情的に必要とするのではなく、実用的に活用し合う関係性を構築します。これこそが、多様な生き方を選択した個人が自律性を保ちながらも社会的リスクに対応できる、成熟した市民社会の姿ではないでしょうか。
以上である。
昔どった杵柄でいかにもな計画書を作成してみたが、どうだろう。
そんなに悪くはないと思うのだが。
しかし問題は……(次回に続く)。