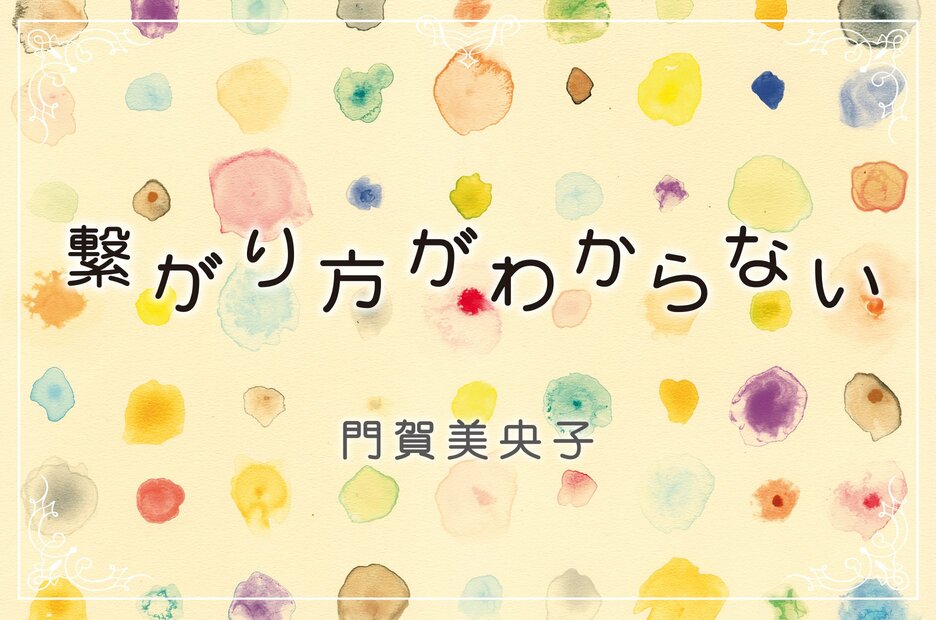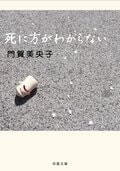第七回では“さびしさ”の本質と、人生を蝕む悪性のさびしさをはねのける方法を考えてみた。私が実践している諸々を実例に提案した行為の数々は、究極の自己満足だといえる。しかし、人生の充実は自己を満足させることでのみ成り立つ。だから、これでよいのである。
満足を積み重ねていたら、独りを寂しく思うことはない。
よって、独りが寂しい人には、感じている“さびしさ”の中身を分析してみることを提案したい。
念のため、もう一度“さびしさ”の定義を再掲しておこう。
1. あるはずのもの、あるいはあればいいと願うものがなく物足りない。
2. 人の気配がなくひっそりとしていて心細い。
3. 心通い合うものがいなくて満たされない。
4. 終わっていくもの、失われていくものを惜しむ。
5. 見ていてあさましく感じられる。
この中で、成立要件に生身の他人が必要なのは2と5のみである。そのほかは代替え手段があるし、生活を充実させることで埋まる。そこを見誤り、“さびしさ”を避けたいがためだけに無理な人間関係を続けていたらつらい結果になるのは目に見えている。
特に怖いのは、承認欲求を満たしたいがゆえに(これは1に相当するだろうか)他人を利用することだ。まず、いい結果は生まれない。どちらか、あるいは双方の心が疲弊しつくす結果になる。そんな不幸は避けた方がよいに決まっているではないか。
それにしても、人はなぜ不幸でみじめな関係でさえ独りでいるよりマシ、などと思ってしまうのか。
この理由については、おそらく、のレベルではあるのだが、第六回で夢央子が得意げに語っていた「スティグマ」が相当効いているのだろうと見当をつけている。
誰にも相手されないぼっちのかわいそうな奴と思われるぐらいなら、下っ端扱いでもいい。
ハブられるぐらいなら、パシりも辞さない。
孤高でいるより群れの奴隷であるほうがまだしもだ。
そんな、ある意味見上げた心意気の人物は、子供の頃から周囲に常にいた。私なんぞは誰かに追従したり支配されたりするのなんて真っ平ごめんだが、彼らはそちらを受け入れてでも集団を選ぶ。きっと「孤独」に強烈な恐怖を感じているのだろう。
その恐怖を助長しているのが、世にあふれる孤独忌避の風潮だ。
見渡せば、独り身であることに苦悩したり、恐怖したりする姿を描くコンテンツが、小説映画コミックなど表現形式を問わず山ほど存在している。ああいうのばかり目にしていると、自然と独りを過剰に恐れる気持ちが養われても仕方ない。
また、義務教育時代に刷り込まれる「みんないっしょが一番いい」も大きく影響しているのだろう。学校教育では個性を尊重しますとか建前をいいつつ、教師にとっては全員が同じように右向け右をしてくれるのが一番楽だ。だから群れからはぐれる者がいたら、無理にでも矯正しようとする。子供たちはそんな教師の態度から「集団での最適解」を嗅ぎとり、従順こそ生きる道と思い込んでしまう。そして、はぐれ者をいじめの対象にし始める。学校がいじめ対策に消極的なのは、実は教師自体がはぐれ者を排除したくて仕方ないからなのでは? なんて思うのはさすがに意地悪すぎるだろうか? 私はかなり本気でそう見ているのだが。
しかし、近年、ようやく独りを肯定的に描き、スティグマ除去に力を発揮しそうな作品が増えてきた。
鍋倉夫の漫画『路傍のフジイ ~偉大なる凡人からの便り~』(小学館)はその代表的なもののひとつだ。
主人公は藤井という冴えない中年男。物語は、彼を取り巻く人々の視点で藤井の挙動が観察され、藤井の生きざまを通して、視点人物それぞれが自分に欠けているもの、真に欲しているものを見出していく構造になっている。
第一話は、藤井が非正規の身分で勤めている会社の同僚で、正社員の田中という男が視点人物になっているのだが、その彼はまさに世間代表の役割を負わされているような存在だ。
休日にたまたま街中で藤井を見かけ、なぜか気になって後ろを付けて回った田中は、ある場面で藤井に向かって「なんか…人生楽しそうですね」と話しかける。すると、藤井は実によい笑みを浮かべながら「はい。楽しいです。」と何の衒いもなく答えるのだ。
その顔を見て、田中はこう思う。
楽しい、って…本気で言ってんのかよ、この人…強がり言うなよ。
金もない。
友達もいない…孤独な中年男だろ。
いや……そうやって自分に言い聞かせないとやっていられないのかもしれないな。
独り者に対する世間一般の見方が、大変端的にまとめられているではないか。
けれど、田中がどう感じようと、藤井の日常生活は充実している。上手下手関係なくやりたいことをやって、無駄な気は使わず、でも誰にでも親切にする。無理に人に好かれようとしないが、来る者は拒まずのオープンマインドも失わない。彼の辞書に退屈や倦怠といった言葉はないのだろう。
理想のおひとり様ライフだ。
この作品は、路傍の人である藤井の姿を通して、何の疑いもなく大通りの真ん中を歩く、あるいは歩いているふりをしている人たちに「その道は本当にあなたを幸せに導く道ですか?」と問うているのだと思う。
こうした「独りの楽しみ」を真正面から描くことで、ファミリー/パリピ/ヤンキー的価値観(つまり群れ至上主義)が主流の現代日本に一考を促す作品が支持を集めるようになってきたのは、大変によい傾向だ。
大きなきっかけのひとつは「孤独のグルメ」ブームだっただろう。あの作品がヒットしたおかげで、独り行動への偏見がずいぶんと軽減した。実際、一人飯に変なうしろめたさを感じなくなったと言っている人もいる。
ただ、私としては「孤独のグルメ」以上に功労賞を捧げたい作品がある。新久千映の漫画で、テレビドラマにもなった『ワカコ酒』(コアミックス)だ。
この作品は、酒飲みの舌を持って生まれたがゆえに、独りで酒を飲み歩く若い女性が、ただ純粋に酒と肴を楽しむ姿を描いている。恋愛も、友情も、仕事の悩みも、あくまで物語の添え物。メインテーマはどこまでも「ひとり酒の楽しみ」なのだ。同じく「ひとり酒の楽しみ」を描きながら家呑みに特化したテレビドラマ『晩酌の流儀』も独りの幸せに特化した、好感の持てる作品だ。
こういう、純然たる独りの悦楽をメインに据える作品は、藤井が浴びているような偏見を無力化する手段としてとっても有効だ。
孤独を分析する学術系の読み物だと、孤独を擁護しながらも、悪い面も記述しなければならないから能天気に楽孤なんてばかりも言っていられない。また、文学作品だと、心の葛藤を描こうとするせいか漫画作品ほどすっきりと「楽しみ」に振り切れないようだ。それが悪いとはいわないし、表現方法の差といってしまえばそれまでなのだが、やっぱりまずは独りの楽しみが前面に出ていて、ほんの少しの味付け程度に人生の苦みが走るぐらいが、面倒なスティグマを払拭するにはちょうどいいのではなかろうか。
もし、おひとり様現役でありながら「独りであること」になんらかのうしろめたさやみじめさ、あるいは羞恥心を感じているのであれば、ぜひこの辺りの作品を読んでみてほしい。きっと、目の前の靄が晴れるような気分になることだろう。
え? お前自身の書いているもので他人様の靄を晴らそうとは思わないのか、って? いやだなあ、思っているに決まっているじゃないですか。別に人の褌で相撲を取ろうってわけじゃありませんって。
でも、長年の思い込みっていうのはそうそう簡単に外れるものではありません。
いろんなパターンの楽しみ方を、エンターテインメント作品で追体験しながら、少しずつ認知を修正していく。それが効果的なのではないでしょうか。
そもそも、独り者は最初から自由を手にしている。これを生かさぬのは、いかにももったいない。心の底から自由を欲しているのに、“絆”とやらのせいで得られぬ人たちはごまんといるのだから。
というわけで、感情ケアに関しては下記の通り結論したい。
1. 感情ケアはまず孤独に対するスティグマを消すところから始めよう。
2. 独り者こそあらゆる手段で生活を楽しもう。そのための自由はもう手の内にある。
3. 感情ケアには必ずしも他人は必要ない。友人や恋人がいなくても、生活は楽しめる。
以上である。
さて、これでひとつは片付いたか、楽孤のためにはもう一つ課題がある。生活安全保障の確保、だ。
第六回で、夢央子は 「『自分は独りであっても孤立はしていない』と自分に証明するのが感情ケア、社会に表明するのが生活安保のためのつながり。そして、最初に欠けていきそうなのは後者。だから、外的つながりを探究するのがメインテーマになります」と言っていた。
つまり、いよいよメインテーマに入っていく、というわけである。
そういうわけなので、まずは「生活安全保障」とはなにか、について説明しておきたい。
これは、立憲民主党が2022年に参院選挙用キャッチフレーズとして生み出した言葉で、定義は「まさに、一人ひとりの『生活』の安全を保障すること」なんだそうな。内容は物価高対策、教育無償化、本義である軍事的な安全保障を一体化したもので、当時の党代表がぶち上げたものの、社会的には今一つ浸透しないまま終わった。
それから2年経った今、当時より国際情勢は混乱する一方、国内はインフレ、増税、社会保障の削減などが一層進み、生活が脅かされている感がますます強くなっている。
そんな中、恙なく楽孤したいならば、まずは身を守ることを考えなければならない。
そこで、老後生活に向けた護身術を考えるためのキーワードとして「生活安全保障」という言葉を拝借することにしたのだ。
とはいえ、概念は本書向けに微調整しなければならない。
今後、本書内で「生活安全保障」という言葉が出てきたらそれは「楽孤を成立させるための生活基盤を物理的に保障すること」と理解していただきたい。
その上で、生活安全保障の要件は公私ともに「他者」と繋がること、と見定めるのである。
よって求める「つながり」は合理性および功利性を含まなければならない。と、こう述べるとなにやらとても利己的な望みのようだし、その誹りは甘んじて受けよう。現実として利を求めないわけにはいかないからだ。
夢央子ばりに実現不可能な理想をいうなら、私はもう陶淵明の「飲酒」みたいなスローライフを送りたい。 廬を結びて人境に在り、而も車馬の喧しき無し っていう、あれである。心遠ければ 地自ら偏なりって境遇になりたいのだ。世間のワチャワチャとは離れた脱俗生活を送りたいのだ。
でも、現代社会ではそんなのよっぽどのお金持ちでもない限り無理。私の場合、宝くじでも買わなきゃ望み薄だが、そもそも宝くじを買うのがもったいないと目を吊り上げて主張するケチンボの金央子が予算権を持っている限り、実現の望み薄だ。
とにかくまずは自由業として稼げる程度に社会と関わらなければならないし、自分の身になにかあった時に頼れる何かを探しておかなければならない。
そのためには、公私ともにつながりを確保する。しかし、一方的に収奪するのは性に合わない。というか、たぶん申し訳なさが勝って無理である。そこで、相手が公的機関でない限り共存共栄、自利利他円満、Win-Winが基本理念になる。
だが、今現在、方法論はまだ見いだせていない。
よって、まずは方法論を構築するための材料探しから始めるべきであろう。
そう判断した私は動央子を召喚することにした。取材をするにはまずリサーチが必要だが、これに一番向いているのが動央子である。なにせ情報収集が何よりも好き、という性格だ。ただし、異様なまでの注意力散漫ゆえにちょっと興味が他に向くと瞬く間に脱線する。よって、私がマンツーマンで見張らなければならないところが大変な難点だ。とはいえ、そこは仕方がない。彼女もどうせモンガーズの一員。完璧とはほど遠いのである。
というわけで、動央子さん、お願いします。
「は~い! リサーチだよね、リサーチ! 楽しそう~」
前向きなのは大変よろしいかと思いますが、方針はあるの?
「理央子からの伝言。まずは人に話を聞け、だそうだよ。この辺りは本を読んでも無駄だから、って」
でも誰に聞くの?
「そこはね、わたしたちに任せるってさ」
あ~、さては逃げたな、あいつ。
「ま、いいじゃん。そもそも渉外は美央子の仕事なんだし、あなたの人脈を生かすしかないんだから」
はいはい、わかりました。では、がんばって考えてみます。でも、取材はあなたの仕事だからがんばってね。
「ま~かせて! 動央子、がんばる!」
……不安だなあ。