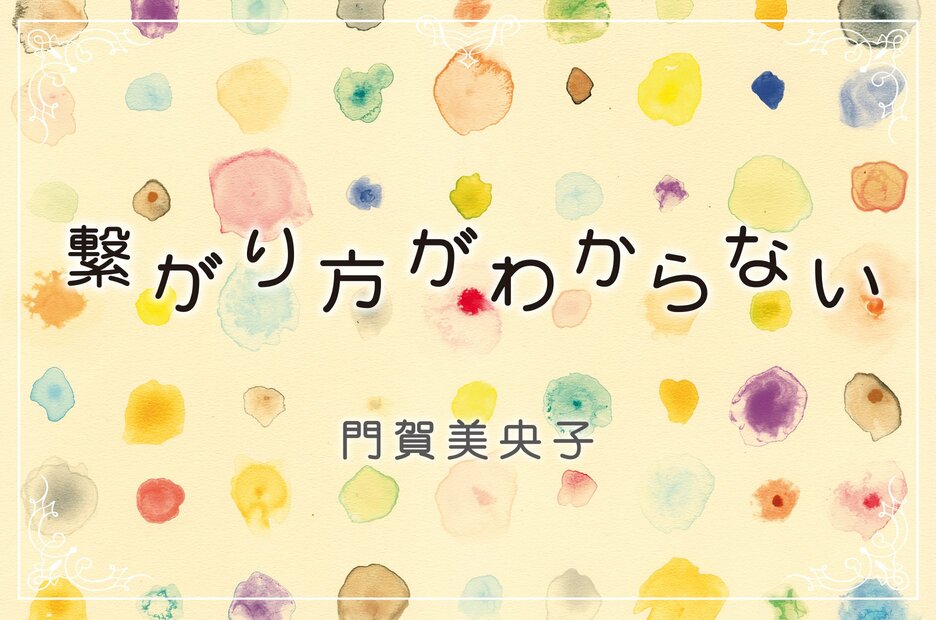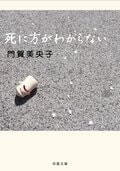孤独耐性に関する一考察
セルフネグレクトの発覚のしづらさに関して、とある医療マンガにとても参考になりそうなエピソードがあった。
富士屋カツヒト・作、川下剛史・医療原案の『19番目のカルテ 徳重晃の問診』(ゼノンコミックス)3巻第14話「守るべき“場所”」だ。
ストーリーの結末や重要なセリフにも少々触れるので、未読作品のネタバレは絶対許さないタイプは次の空白行から先、その次の空白行までの数行は読み飛ばしてもらいたい。
→ネタバレ絶許勢はここから次の矢印までスキップ。
この回では、一見完全に自立しているようだが、実はアルツハイマー型認知症を発症している老人男性が登場する。
彼は庭づくりが得意で、毎日欠かさず作業をしては自宅の前庭をいつもきれいに整えている。身なりはおしゃれで、ちょっとした会話なら受け答えにも破綻はない。人付き合いもできていて、ご近所で好感を持たれている。
しかし、昔人間ならではで、自分の困りごとを他人に相談できずにいた。家の中にはゴミがたまり始めているし、数日前の話は覚えていられなかったり、長い話をきちんと聞けなくなったりしてきている。そうした異状には本人も薄々気付いていた。しかし、「一人できちんと自立しなければ」という思いが強いため相談相手も見つけられず、症状は静かに進行していた。
認知症が明確になったのは、長く続く足のむくみと痺れの診察してもらうために病院に行ったのがきっかけだった。そこで総合診療科にかかって、ようやく認知症と診断されたのだ。
医師がその診断を下し、適切なケアを受けるように助言するシーンで、とても印象的な言葉が出てきたので、引用して紹介しておきたい。
「認知症で一番怖いのは…あなた自身が『居場所』がないと感じてしまう事ですから」
社会の中で何らかの役割を果たしている、あるいは自立できているから居場所を与えてもらえる。現代社会に生きる誰もが、こんな思い込みを強固に持っている。それが人を生きづらくさせ、問題が隠蔽される原因になっていることを端的に示す、名台詞だと思う。
→ネタバレ絶許勢はここから再開。
前提としてマンガに登場する老人はまだセルフネグレクトといえるほどの状態ではない。しかし、予備軍であることは作中の描写で示唆される。けれども、彼は社会的には孤立していなかった。また、きちんと医療を受け、医者の言葉を素直に受け入れるだけの理性は保っていた。だから手遅れになる前に必要な対策を取ることができたのだ。
このエピソードはセルフネグレクトになるのが決して特殊な人格――生まれつきだらしないとか、根っから頑固といったような人間だけではないことを物語っている。自立した好々爺でも、老いによる衰えをそのまま放置すると、悲惨な生活に陥ってしまう可能性があるのだ。
「だから、わたしだけは大丈夫、なんてことは金輪際ないわけです。まあ、わたしたちには怠央子っていう危険因子がいるから、高を括るなんてことはできませんけど。あら、そう考えるとアレもアレで役に立っているのかしら?」
それは置いといて、で、結局夢子さんは何を言いたいわけ?
「この老人のエピソードを読んで一番心に残ったのは、やっぱり人付き合いの大切さでしたの。彼は人柄がよかったから、親身になってくれるお医者さんがいました。きっと介護を受ける段階になっても、認知症の進行で性格が変わったりしない限り、すんなりと事が運ぶと予想されます。きっと、近所の方々もあたたかく見守ってくれることでしょう。翻って、わたしたちはどうかしら?」
どうかしら、と言われましても。
「まず、ご近所づきあいっていうのがないじゃない? 顔を合わせたら挨拶はするし、極々たま~に立ち話もしたりするけど、それ以上のことはないでしょう? そもそもわたしたち、ご近所さんのお名前すら覚えていませんわよね」
ギクリ。ま、まあね。
「別にご近所さんに限らず、わたしたちが人の名前を覚えられないのは今に始まった話ではないけれども、そういうの、やっぱりだめだと思うの。無関心の証じゃない? わたしたちはこれから自分のために必要なつながりを探すわけだけど、自分がまったく他人に関心を払わないくせに、自分には自分のほしい分だけ関心を払ってほしいなんて、さすがに虫が良すぎるってものではなくって? わたしたちはもう少し、他者への健全な関心を養うべきだわ。そうすることで、突破口が見えてくるのではないかしら?」
夢子の言うことはわからないでもない。だが、今回はそういう情緒的な話をしたいのではなく……。
「ほら、それよ、それ!」
突然、夢子が叫んだ。
「そこがあなたの一番悪いところ。感情を大切にしようと決心したところなんでしょ? だったら、まずは情緒的なところをきちんと整理しなさいよ!」
なんだか虎の尾を踏んでしまったらしい。
夢子は怒濤の勢いで話し始めた。逐一書いているとキリがないので、主張をするところをまとめると次のようなことになる。
後半生において、他者とのつながりが大変に大事だと気付いたのはよろしい。
よろしいが、未整理過ぎるのではないか。
今、お前が探究しようとしているのは「つながり」を基軸にした感情ケアと生活安全保障の確保であるわけだが、その二つは混ぜて考えてよいものだろうか。そもそも同時に実現できるのか。まずはそこからしっかり考えるべきだろう。
……という感じでよろしいでしょうか。
「いいと思います!」
夢子は満足気にうなずいた。
「結論から言ってしまうけれども、わたしは感情ケアと生活安保は分けて考えるべきだと思います。だって、感情ケアは必ずしもリアルのつながりばかりが手段ではないけれども、生活安保は現実のつながりがあってこそ成り立つものでしょう? もちろん、その二つが重なる領域はあるから、一挙両得の関係性を築けたらそれがベストなのだけれど、最初からあまり欲張りすぎてもなんだろうし」
だから、と夢子は言う。
まずは感情ケアの領域から考えましょう、と。
「さて、再度確認しますね。わたしは今のところ、寂しさを埋めたい、あるいは孤独を癒したいという理由で他者を求めてはいません。これは他のメンバーにも共通していることですね。もちろん、あなたも」
はい、その通りでございます。
「では、なぜわたしたちは感情面においては一人でも平気なのでしょう?」
なぜ、と言われましても……。
「いえ、ここはしっかり把握しておくべきですわ。今ここで議論していることは、読んでくださるどなたかがいる前提でしょう? 読者諸賢はきっと、テーマに興味をもってくださっていることとは思うけれども、孤独についての感じ方は人によって異なると思いますの。だからこそ、『わたしたちはどうなのか』をしっかり表明しておかないと、この先読んでいてあてが外れたと思わせることになりかねないですわ」
はあ、そうですか。では、とりあえず夢子さんの解釈を教えてもらってもよいでしょうか。
「もちろんですわ!」
なぜか胸を張る夢子。
「まず、わたしたちは基本孤独耐性が強い。そして、それは一人っ子という生まれ育ちに大きく依拠するというのは再三述べてきた通りです。そして、私の周辺にいる一人っ子を見ても、押しなべて強耐性者が目立つように思います。ですので、まずは一人っ子を第一条件にするとして、そうすると二つの問題が発生します」
問題、ですか。
「ええ、一つ目は生まれつきの生育環境が孤独耐性に大きく影響するのであれば、賑やかな環境で育った方は孤独耐性が低いのでは? という予測がなりたちます。そして、そういう方たちは孤独を『極力避けるべき負の状態』と認識しているはずです。だって、孤独を楽しめないのだから。そういう人に楽孤生活をわかってもらうのは困難を極めるでしょう。彼らは、幼い頃に一人時間の豊かさを自ら獲得していく機会を持てなかったわけですし」
夢子はそれのエキスパートだものね。楽しい一人遊びを独力でどんどん見出していったんだから。
「ええ、とっても楽しかったですわ。一人っ子ゆえにおもちゃや本はふんだんに与えてもらった方だと思いますけど、それらがなくても想像力と紙とえんぴつさえあればいくらでも遊べるってことを実地で学んでいきましたわね。そして、ここが二つ目の視点につながるのですけど、孤独耐性が生育環境で養われるものだとしたら、群れたい欲求は本能ではなく、ジェンダーのように社会的刷り込みではないか、ということ。あなたはこれまでたびたび人間は群れることで安心と幸福を感じる生き物である、と無批判に述べていましたが、その前提がおかしいかもしれないわけです」
なんだかまたえらく基本的なところからきたね。
「ええ、わたしが読んだ孤独関連の本はおしなべて孤独の良さを認めながらも、孤独に対する『スティグマ』をぬぐいきれていないのだろうなと感じるところが、なんとなく残っていましたの」
あらあら、夢子ったらまたちょっと聞きかじっただけの言葉を使っちゃって。
私の方から責任をもって説明しますと、「スティグマ」とは「社会からの排斥や差別的な扱いを受ける対象がもつ属性」を意味するそうで、「それをもつ者に対する差別や社会的に不利な扱いを惹起するだけでなく、それをもつ者自身の自己の捉え方に影響し、スティグマに基づく他者からのネガティブな評価や差別を予測することになる」んだそうです。以上、有斐閣『現代心理学辞典』より引用。
今の話の流れに適用すると、孤独好きは世間様から人間的な何かが欠けているように思われがちで、そんな色眼鏡に対して腹立ちを覚えながらも感じる必要のないうしろめたさを覚えてしまう、ってことですね。
「そうそう。わたしたちにもこうした感情がまったくない、ってわけではないでしょう?」
それは夢子の言う通りである。
「わたしは社会的偏見にさらされても特に痛痒を感じない方ですけど、わたしたち全員がそうではありませんし。特に美央子、あなたは弱いほうですわよね」
ま、確かにね。だって、私はモンガーズにおける対社会のスポークスパーソンでしょ? そうである以上、社会適合しなきゃいけないわけだけど、適合しようとすればするほど、内外のズレを意識せざるを得なくなるし、意識したら気になるのはもう仕方ないことだし。
「そう。だから『孤独はいいものです』といいつつ、それが強がりと思われないためには『自分は独りであっても、孤立はしていない』と社会と自分自身に示し続けなければいけないと感じているわけよね? 涙ぐましくもしょーもない努力ですこと」
なるほど。おっしゃることはよくわかりましたが、そろそろ何が言いたいのか、まとめに入ってもらえませんかね?
「あいかわらず理解力がありませんわね」
わざとらしくため息をつく夢子を無視して、先を促す。
「『自分は独りであっても孤立はしていない』と自分に証明するのが感情ケア、社会に表明するのが生活安全保障。そして、最初に欠けていきそうなのは後者。だから、外的つながりを探究するのがメインテーマになりますが、今のわたしたちがどうやって感情ケアを成り立たせているのか、この際そこをはっきりとさせておいた方がいいと思いますの」
ああ、わかりました。夢子さんが長年かけて編み出して完成させてきた一人遊びの心得と実践方法をここで読者に向けて御披露したいわけですね。なんだ、最初からそう言ってくれればいいのに。
「まるで自己顕示欲を満たしたいがために長々と発言してきたように取られたらなんだかとっても心外なのですが、読者に内輪喧嘩を見せるのも申し訳ないのでひとまずスルーしますわね」
あ、額に青筋立ってる。後が怖いなあ。
「さて、まずわたしが孤立を感じずに済んでいるのは、数は多くないとはいえプライベートで連絡を取ることができるリアルの友人や縁者がいるからですね。ただし、そう頻繁に連絡を取るわけではありません。オンラインで月に一度か二度、電話や実際の面会となると年に数回もあれば上等でしょう。次に、地域社会にもそれなりに顔を覚えてくれているお店が数軒あって、行くとちょっとした世間話もできるおかげで、仕事以外での会話がゼロって状況には陥らずにすんでいますわ。取材を除けば一週間以上一度も人と話をしていないなんてこともザラな毎日だから、大変貴重な機会になっています。しかも、結構レアな地域情報をゲットできたりしますし。でも、それだって月に数度が関の山。つまり、リアルで接触のある人たちとの会話なんてほとんどすることがないわけです。月単位で合算すれば、三時間に足りない程度ってところじゃないかしら」
まあ、そんなものかな。
「それでも寂しさを感じないのはなぜか。次回、その答えを申し上げることにいたしましょう」
あ、まだ引っ張るんだ。
そういうことだそうですので、読者諸賢におかれましては一週間お待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。