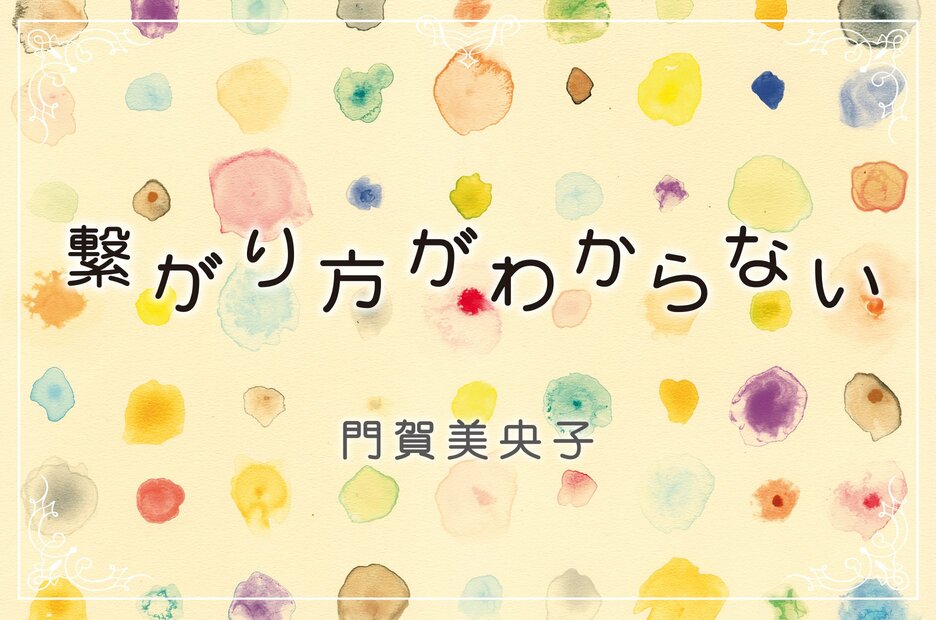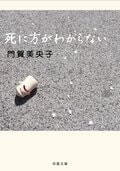風呂敷は広げ易し、然るに……
立派な(と自分では思っている)計画書はできた。だが、立派であればあるほど、実行者たるべき私が完全に尻込み状態に陥ることになった。
計画書にはやりたいと思っていることをしっかり詰め込めている。
理念も悪くないはずだ。
でも、こんなの一人で実現できるはずがない。
これが最初の尻込みポイントだ。
乗り越えるには仲間が必要になってくる。
だが、その仲間の作り方が、私にはわからない。
これが最大の尻込みポイント。
つまり初手から詰んでいる。
ネガティブ三人組が異議を突きつけてきたのもむべなるかな。
はっきり言って、己に対し身に過ぎた要求をしているのがこの計画なのだ。ほぼ起業に等しい力技が必要なわけだから。
近頃では公益性のある事業の立ち上げを〝社会的起業〟というようだ。社会的問題解決の一翼を担う仕事を民の力で、というところだろうか。私はその必要性をつくづく感じている一人である。
しかし、自分にできるとは到底思えない。
典型的な怠け者かつ人見知りである私に。
何かをやる能力がないわけではないが、有能な人に比べたら体力も気力も格段に低く、ゆえに持続力にかける。だから絶対にペースメーカーになってくれるような人が必要だ。
しかし、しつこくて恐縮だが、友人の数も多くはなく、仕事でのネットワークも限られている私には声を掛ける先がない。そんな私が「独身者相互扶助ネットワーク」の立ち上げなどできるだろうか?
組織作りといえば、カリスマ的リーダーが広い人脈を活かし、先頭きって動くのが定番だろう。地域の顔役や名士が中心となり、その求心力で人々を集めるというモデルが一般的だと思う。
しかし、その定番が使えない以上、別のアプローチを考えないといけない。
そこで、いろいろと本を読んだり調べたりした結果、「ネイバーフッドデザイン」という概念があると知った。
これは、地域社会の課題解決や活性化を目指し、住民を主体に、専門家や行政などが協働して行う活動のことで、まちづくりの総合デザイン――物理だけでなく住人の暮らしやすさやコミュニティーの持続可能性を勘案して「まちづくり」することなのだという。
ネイバーフッドデザインは住民参加型のプロセスを重視している。地域のニーズや課題を個々の声から拾っていこう、というわけだ。そして、専門家が意見を基に、具体的なプランを作成し、実現に向けて支援する。
現実的な話をすれば、このプラン作成と支援の段階をマネタイズするのだろう。公共ビジネスを掘り起こす概念といえるかもしれない。
私は、最近流行りの公共ビジネスに諸手を上げて賛同する者ではない。やはりそこは昭和の子、公益性の高い分野についてなんでもかんでもビジネス化することに抵抗感があるオールドタイプなのだ。しかしながら、持続可能性を考慮すればそれも致し方なしとも思う。運転資金はどうやっても必要だ。
私がやりたい「独身者相互扶助ネットワーク」は、50代以上の身寄りの少ない独身者が互いに支え合う仕組みだ。
つまり公益性は高い、はずである。
しかしお友達の間で細々とやっていたのでは、おそらく持続できない。
やっぱりシステム化し、属人性を排する必要がある。
そういう意味で、徹底的なシステム設計から始めるのは理に適っている。
誰がどのような支援を提供でき、それをどう記録し、どう評価するか。緊急時にはどのような連絡経路を辿るのか。こうしたことの手順書や規約を作成するか……みたいな手順設計から始めるだ。
カリスマ性のある人ならば「私についてきてください」と旗を振ればよろしかろうが、私がそれをやったところで笛吹けど踊らずになるだけだ。だから「このシステムなら安心です」と宣伝するしかない。そのためにも、システムは緻密で、抜け穴がなく、誰が見ても「これなら機能する」と思えるものでなければならない。
でも、そんなもの私に作れる?
どう考えても不安しかない。
名もない一個人が作ったシステムに、誰が参加したいと思うだろうか?
やはり、専門家の力が必要だ。たとえば、法テラスとかでこうした問題を専門とする弁護士を紹介してもらって、協力してもらうようにお願いするとか。でも、きっと無理だよなあ。相手にされないのは目に見えているし、それでもがんばって説得しようとする粘り強さが私には欠けている。劉備玄徳の爪の垢でも欲しいものだ。
それに、よしんば顧問をしてもらうとして、顧問料なんて払えるわけがない。こういうの、どうすればいいだろう? う~ん、ひとまず保留。
次に考えるべき手段は地域包括支援センターへの相談だろうか。社会福祉士が仲間にいれば心強いに決まっている。けど、当てはない。以下、前文「でも、きっと」から「欠けている」と同文である。
このように、もともと人脈がない人間にはかくも新規事業は難しい。私が怯む理由もわかってもらえるのではないかと思う。
それに、どれだけ計画は立派でも、実績がなければ誰も信じてくれないだろう。
ならば実績作りから始めるべきか。
でも、そこでもまた怯んでしまう。理由はもう説明せずともよいかと思う。
もちろん、SNSなどを使って「小さな実験に付き合ってもらえませんか?」ぐらいの気軽さで声をかけたら、誰か手を上げてくれる人はいるかもしれない。
たとえば、週に一回、互いの安否を確認するオンラインミーティング、あるいはグループチャットを主催する。こういうのを三ヶ月ぐらいお試しでやってみるのはどうだろう?
そして、この小さな実験から得られたデータと体験談を計画に反映できたら。「理論上のシステム」ではなく「実際に機能しているシステム」として、いろんな人たちに提示できるようになるかもしれない。
幸いなことに、既存のデジタルツールを組み合わせれば、これぐらいのことならすぐにでもできる。対面でのコミュニケーションが苦手な私にとって、デジタルツールは大きな助けになるだろう。直接会わなくても、システムを通じて繋がることができるのは大変魅力的である。
私が魅力的に感じるということは、同様にコミュニケーションに不安を持つ人にも魅力的かもしれない。そうして信頼関係を築いていけば、いずれ組織運営に参加する仲間をゲットできる可能性もでてくる。
ただ、ひとつだけ絶対に避けたいことがある。
それは閉鎖的なオンラインサロン化することだ。
ネット社会ではカリスマ性や人望ですらインスタント化しているが、手軽になった分、目端が利いていればマネタイズが容易になり、結果として支持者を食い物にするようなメソッドが幅を利かせている。
私にとって、こうした状況はどうにも気持ち悪い。憎んでいるとさえ言って良いかも知れない。フェアネスのない空間は、私にとっては嫌悪対象なのだ。
だから、私がやるならば絶対オープンな組織にしたい。
しかし、NPOなど法人格を持たせるのは時間もかかるし骨である。
主催者がどこの馬の骨かもしれない任意団体ならば、成功させる秘訣は「徹底した透明性」しかない。
実は、この点に関してのみ、経験がある。
二〇一一年の東日本大震災がきっかけで始まった「ふるさと怪談」イベントの事務局をやったからだ。
「ふるさと怪談」はアンソロジストの東雅夫氏が主宰で、当初は震災で被災した仙台の出版社荒蝦夷の支援を目的としていたが、荒蝦夷からの申し出により途中から「みちのく怪談プロジェクト」の活動資金として、プロジェクト終了後は「三陸文化復興プロジェクト」や「東日本大震災こども未来基金」など寄付先を変更しながら二〇一六年まで続けた。
この活動にあたっては、出演者や会場提供者などはすべて無償ボランティアを原則とし、当日集まった入場料と募金は全額寄付するというシステムを取った上、寄付額は内訳から寄付先まですべて公式サイト上で公開した。
無償ボランティアと全額寄付の方針を決めたのは東氏だったが、寄付先の全公開を提案、実施したのは私である。
それをやった理由はたった一つ。
支援を謳っている以上、完全な透明性が担保されるべきだと考えたからだ。
あの頃のことはまだ昨日のように思い出されるが、ボランティアやチャリティーが盛んに行われ、共助の精神が広がった一方、一部によからぬことを企む者がいたのも確かだった。
そういう状況下において気持ちよく活動したければ、痛くもない腹を探られるような状況を作ってはいけない。そのためには一切合財を公開するのが一番である。
この方針があったからだろうか。最初はごく私的なイベントだったが、やがて公共施設や地方自治体からも声をかけられるようになった。もちろん東氏の人望あってのことだが、運営母体としても信頼されたのだろう。
「独身者相互扶助ネットワーク」だって、透明性を持ちながら実績をつんでいけば同じ経緯をたどる可能性は低くないと思う。
全ての活動記録、会計情報、意思決定プロセスを文書化し、定期的に参加者に共有する。どんな小さな決定も、その理由と過程を明らかにする。これにより「私の個人への信頼」ではなく「システムへの信頼」を形成していく。
でも、そのためには監査する第三者および意思決定権を分散させる仕組みがないといけない。一人ではまったく説得力がないからだ。やっぱり仲間がないと無理なわけだ。
困ったものである。
いずれにせよ、こうしたことをやるならばいずれはなんらかの公的な枠組みと連携するべきなのだろう。たとえば地域の社会福祉協議会なんかを通して既存の高齢者支援事業と協働するとか。「公的なお墨付き」は、個人的な信頼性が低い創設者にとっては信頼獲得のよき手段となる。
しかし、そこまで組織を育てるにはどれだけ時間と労力が必要になることか……。
リーダーシップもカリスマ性も、人望も人脈もない一個人になにができるのか。
でも、やり始めなければ何も生まれない。
そのためには、むしろ私の「弱み」を前面に出し、徹底補完する方向で動く方が、組織化する場合の強みになるかもしれない。属人化を免れうるからである。今の時代、人間よりシステムだろう。
そして、もしこの取り組みに少しでも光が見えたら。
私と同じような人が、同じようなことを始めるきっかけになるかもしれない。たとえ「目立たない人」「苦手なことの多い人」「人間関係が得意でない人」であっても、良いシステムを設計し、専門家の知恵を借り、小さく始めて実績を積み、透明性を確保することで、社会に価値あるものを生み出すことができるというのを提示できたら。
心のネイバーフッドたちとともになにかできたら。
私も少しは人の役に立ったと胸を張れるようになるかもしれないじゃないか。
そうなったらちょっとうれしい気がする。
……いや、かなりうれしいな。
うむ。
ここまでのところ、悲も冷も邪魔してくる気配はない。怠はあいかわらずぶーたれているが。
とりあえず、やれるところからやってみますか。
あ、最後に。本当に仲間募集中です。やりたいって思った方、お気軽に御連絡くださいませ。