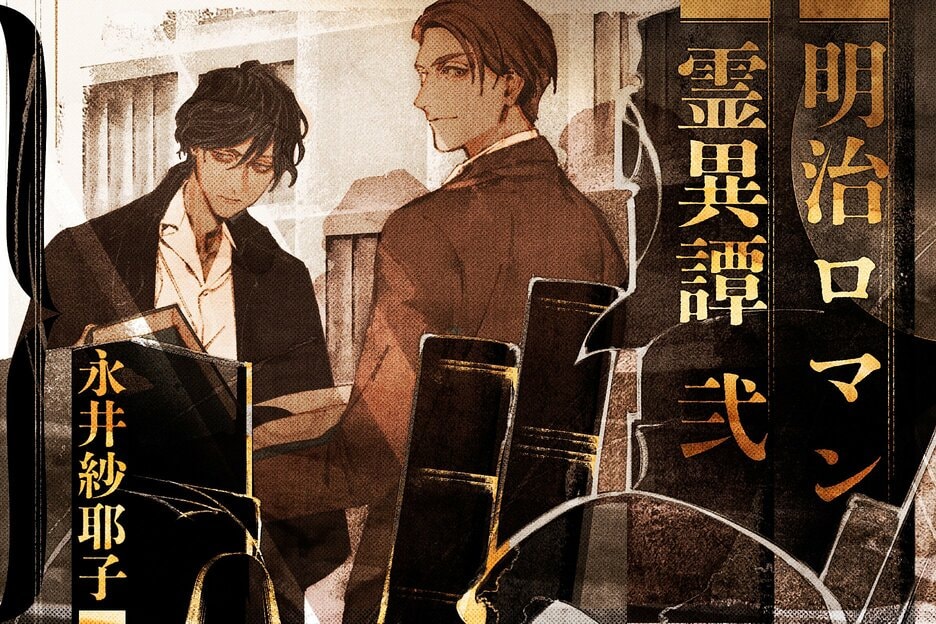第四話 センチメントな再会
*
谷中にある伯父、敬円の寺の奥には、正周の祖母である寿照尼の庵と共に、啓吾の父母と妹の住まいがある。
啓吾は山門をくぐる時にやや緊張した。
傍らには正周と共に、明るい陽射しの下で揺らめく影となっている祖父、啓照がいる。この啓照を母に会わせたら、どんな風に思うのか……と、考えていたら足が止まった。
すると、正周がトントン、と啓吾の肩を叩く。
「今、啓照僧都は隣におられるのか」
「はい、ここに……」
啓吾は己の左肩の辺りを指さした。正周は、ほうっと嘆息しつつそこを覗き込んだ。
「そうか。では私は、お祖母様のところにいるから」
「え、いいんですか。若様のことだから、またどんな風に視えるんだ、とか、僕だけではなく母にも聞くものだとばかり……」
霊となった祖父と、視える母の邂逅を見物するためについて来たのだと思っていた。すると正周は、やれやれと肩を竦める。
「君は私を、デリケシーの欠片もない人間だと思っているようだね。確かに関心はある。しかし、親しい人のセンチメントな場面に首を突っ込むのは無粋だろう」
えへんと一つ咳払いをすると、改めて啓吾の傍らにいる祖父の方へ頭を下げる。
「ごゆっくりなさって下さい」
視えていないので、少し角度はずれている。しかし、踵を返して遠ざかっていく正周の背を見送りながら、「あの人が遠慮をするとは」と可笑しくて、ほんの少し緊張が解けた。
「では、参ります」
啓吾は啓照に声を掛けてゆっくりと参道を歩いて、庭の奥へと進む。庫裏の離れとして建てられた家の引き戸を開けると、ひんやりとした土間があった。
「ただいま」
声を掛けると、奥から「はい」という声がして、母、幾がひょいと奥から顔を見せた。
「ああ啓ちゃん、お帰りなさい。先だっては表の御寺だけで帰ってしまったそうね。兄様に聞きましたよ」
破崩坊の一件の後に立ち寄った時のことらしい。あの時は、呪いを目の当たりにした後ということもあり、家族に害があってはいけないと、立ち寄らなかった。
「父さんは」
「御門跡様の御紹介で、大きな料亭の欄間を彫るお仕事を頂いて大忙し。さ、ともかくも上がりなさいな」
奥の間へ進むと、縁側からは、庫裏との間の木々が望めた。そこには仏壇が設えられており、祖母の位牌があった。啓吾は線香を立てて手を合わせ、暫しその前に座っていた。
「帰って来ると言ってくれれば、好物でも用意したのに。庭の柿くらいしかないわ」
幾は土間から声を張る。
「気にしないで。またすぐに来るから」
そう言いながら、啓吾はふと傍らを見る。
そこには確かに啓照がいるのだが、母には視えていないのだろうか。
母、幾は啓吾が幼い頃から、人ならざるものを視る人であった。時には啓吾よりも早くそれを見つけて、啓吾に視えないように目を塞ぐことさえある。だが、今のところ幾は祖父の姿が視えないようだ。
啓吾は所在なく縁側に座ると、幾は慌ただしく剥いた柿を盆にのせて運んでくる。そして啓吾の隣に並んで座った。啓吾は母の視線を追うが、啓吾の方こそ見るものの、その隣の啓照の姿はまるで目に入らないようだ。柿を食べながら、庭木を眺めてほうっと息をつく。
「啓ちゃんは、お祖母さんのことを覚えているかしら」
どういうわけか、祖父ではなく祖母の話を切り出した。
「覚えているよ」
啓吾が十一の時、亡くなった。
祖母は寛永寺の近くに生まれ育った町人の娘であった。上野の戦の時には、燃え落ちる寺を見て、悲嘆にくれたのだという。戦の後、遺体が放置された山に行き、そっと花を手向けていたところを官軍に見咎められ、逃げる途中で祖父に助けられたのだという。
怪我を負っていた祖父を家に匿ったことをきっかけに、還俗した祖父と一緒になったと聞いていた。「お前の爺様は、そりゃあもう、男前でね」と、江戸っ子の祖母は、気さくに語っていた。病床で、「あの世であの人に会えるかしら」と、呟いていたのを覚えている。
亡くなってからも、妹が風邪をこじらせた時に、枕元に座っていることもあった。母もまたそれに気付いていて、「母さん、この子のこと助けてね」などと、二人で話しているのを見ていたので、死んだということを時折、忘れるほどだった。
とはいえ、日ごろは姿を見せることなどない。
「お祖母さんがね、昨晩、夢に出て来たのよ」
母は微笑みながら、懐かしそうに言う。
「久しぶりなんじゃない。この前、出て来たのは……僕の進学の頃だったっけ」
啓吾が帝大に入るかどうか案じていた母は、事あるごとに仏壇に手を合わせていたらしく、遂に祖母は夢に出て来た。
「そう。母親は泣きごとを言わずに黙って見てなさいって怒られたわ」
江戸っ子ならではの気風のいい啖呵であったらしい。
「それで、昨夜は何だって」
「父さんを、許してやって……って」
啓吾はふと傍らの啓照を見やる。啓照は何も言わず、ただ母の顔をじっと見ている。
「困った顔をしていたっけ」
啓吾は母に倣って柿を齧る。
母の心には未だに、祖父との蟠りがあるらしい。それ故に、母の目には祖父の姿が視えないのだろうか。
「母さんは……やっぱり許していないの? お祖父さんのこと」
その言葉に、母は口をへの字に曲げて首を傾げる。
「許すも何も……一緒にいた記憶が薄くてね」
母が幼い頃から、何かと家を空けている人であった。寛永寺を離れた者、残った者、それらの世話や、寺の再建のために再び頭を剃って、托鉢に出向いていたこともある。祖母は「いっそ私と離縁して、出家なされば」と言ったこともあったらしい。
「私が子どもの時は、母さんが寂しくて泣いていたのを見たことがあってね……無論、世間的に見れば、妾や遊廓に通うわけではないのだから、まだましなのかもしれないけれど……子ども心に、どうして母さんの傍にいてくれないのかと、恨みに思ったこともあったわ。だから、母さんが許せと言うのならいいんだけど……」
祖母の為だけではなく、母の心の中にも、引っかかりがあるのは一目瞭然であった。何せ、母は、啓吾が知る限り、隠し事が出来る人ではない。
「お祖母さんの為じゃなくて、母さんの中にある蟠りは何?」
すると母は暫し黙ってから、意を決したように口を開く。
「……私、最後に父さんが出て行く時、悪態をついたのよ」
また誰かに呼ばれたからと、「行って来る」と出かけようとした祖父の背を見た瞬間、嫌な予感がした。何度も止めたのに、母の手を振り払って出て行く祖父に向かって、母は言った。
「それならいっそ縁を切って行けって……」
いつ帰って来るのかと案じることにも疲れた。もう帰って来ないと思った方がいっそ楽だとさえ思った。だから、縁を切ってくれた方がいいとさえ思ったのだ。
「父さんは困った顔して出て行ったわ。だから今まで帰って来ないのかもしれないって思ったりして……」
母の中に拭いきれない自責の念があることを知った。そして、母がそこまで言ってしまった理由の一つを、啓吾は知っている。
「お祖父さんが、僕や母さん、伯父さんの視る力のことを、疎んじていたと、思っているんでしょう」
母は、言えずにいたことを言い当てられて絶句し、驚いたように目を見開いた。戸惑う母に、啓吾は言った。
「知ってたよ。母さんが、お祖母さんと話していたのを聞いたことがあったんだ」
「違うのよ、啓ちゃん。父さんは貴方のことを可愛がっていたのよ。よく抱っこして、あやしていて……」
「分かってるよ、母さん。僕は会ったよ。お祖父さんに」
母は怪訝そうに眉を寄せた。啓吾は母に改めて向き直る。
「お祖父さんがいなくなったのは、僕らの力を疎んじていたからじゃない。むしろ、僕らを守りたいと……そう思っていたからなんだ」
「どういうこと……どうしてそんな……」
そこまで言ううちに、母の目からほろほろと涙が零れ始める。
「いやだ、私、子どもみたいに……」
そして無造作に掌で拭いながら、涙を隠すように項垂れた。啓吾は暫し黙ってその背を撫でていると、傍らにいる祖父が、そっと母の目の前にしゃがみこみ、その手を取った。
「すまなかったな、幾」
その声に、母がゆっくりと顔を上げた。
西に傾く日に照らされ、祖父の姿がゆらめく。母はじっと祖父を見つめ、いよいよ声を上げて泣いた。
母の心の中にあった蟠りが解け、ようやく祖父のことを受け入れることが出来て、姿が視えたのだろう。
啓吾は、父娘二人の時間を邪魔せぬように、そっとその場を離れた。
二人がその後、何を話したのか知らない。一時間ほど経った頃、ふと縁側を覗くと、祖父の姿は消えていた。
「お祖父さんは、逝ったの?」
啓吾が問いかけると、母が振り返った。涙で目が赤くなっていたが、表情はどこかすっきりしているように見えた。
「兄さんの所へ寄って、母さんの所へ行くそうよ」
まるでふらりと立ち寄った人の話でもするかのような口ぶりである。
「色々と話せた?」
啓吾の問いに、母は苦笑した。
「口下手な人だからね。上手くは話せなかったけど……会いに来てくれたから、それでいい……」
縁側に並んで座ると、爽やかな風が吹いて来た。今頃、寺では伯父の元を訪ねた祖父が、何を語っているのだろう。
祖父の身こそ、何処かの山中にひっそりと葬られているけれど、その心は変わることなく人々に尽くし、子を思い、遠い旅を続けて来たのだ。
「僕はお祖父さんのことは余り知らなかったけれど、お祖母さんの言う通り、なかなかの男前だな」
母は、ふふふ、と笑う。
「子どもの頃は自慢の父だったんだから。そうそう、夕飯を食べて行きなさい。もうすぐ父さんも寿々も帰って来るから」
妹の寿々は十二歳。尋常高等小学校に通っている。学校の終わりに、近くの元御武家の奥方から琴を習っているそうで、最近ではすっかり夢中になっているらしい。
「寿々にも会って行ってくれるのかしら」
寿々は啓吾とは違い、霊を視ることも声を聞くこともない。だが、母や啓吾が視ているものについて話を聞いても、驚きもせず、「ふうん」と、当たり前のことのように受け止めている。
「お祖父さん、寿々と話をしたくて、またここに寄るかもしれないよ。母さん、通詞をしてやらないと」
「いやよ。啓ちゃんがやってちょうだい」
軽口を叩きながら台所に立つ。
啓吾はふと夕焼けに染まる空を見上げた。紫がかった雲が美しい曲線を描いて伸びている。
正周の言う通り、少し「センチメント」な再会と久方ぶりの団らんのひと時を、祖父からもらったような気がした。
*
連翹寺家の書斎では、相変わらずの本の山の中で、正周が唸りながら本を捲っていた。
「何を調べているんです」
啓吾の問いに正周は、ぬっと顔を覗かせた。
「ああ、啓吾君。久しぶりの御実家はどうだったかい」
「お陰様で、色々と懐かしい話をしました」
母は、これまで語るに語れずにいたらしい、祖父との思い出話をしていた。すると、父はそれを聞きながら、
「そう言えばお舅さんは、気が利くように見えて、存外粗忽なところがあったなあ」
などと相槌を打つものだから、あんなこともこんなこともと話が止まらない。寿々はというと、はじめのうちこそ興味津々だったのだが、そのうち大きな欠伸をする始末。
夜になってから、啓吾は伯父の元を訪ねると、伯父は静かに本堂に座っていた。灯明の灯りの下で端座していたが、啓吾が顔を見せると、振り返った。その目は今しがたまで泣いていたように赤かった。
「お前が父さんを連れて来てくれたんだな。ありがとう。やはり、私が思っていた通りの父さんだった」
伯父、敬円から祖父の話を聞くのは、思えば初めてのことだった。
「あの人は、私が幼い頃から、己や己の身内と同じように、他の人のことも思いやる人だった」
貧しい家族が食いはぐれていると、家の米を握り飯にして与えてしまう。病の人がいると聞けば、「伝染するかも」と言われても、看病に行ってしまう。祖母はその都度、子らを守るために「しばし帰らないで」と家から追い出すこともあったのだが、それで気を悪くすることもなければ、懲りることもない。祖母もまたそういう祖父を受け入れていた。
その一方で、祖父が幾と敬円が「視える」ことに戸惑っていることも気付いていた。
「幾と同じように、私も父から疎まれているのではないかと思っていたこともある」
今よりも「天社禁止令」が厳しく、肩身が狭い時代。「視えぬふり」「聞こえぬふり」をするように言い聞かされていた。その頃は祖父への反発もあったが、十三の年に修行のために寺に入ってからは考え方も変わった。
「私は仏道に入り、父さんの心も分かる。あの人は無私であろうとした。ただ、それでも私やお前を含めた家族を守りたいとも思っていた。その葛藤を抱えていたのだろうと……」
京の寺に、時折、訪ねて来ることもあったが、ある時からぱたりと止んで、行方が分からなくなった。敬円は、幾度となく祖父の行方を捜すために祈祷をしたが、霊すら見つけられなかった。
「理由があると思っていたが……会えて良かったよ」
敬円は、心底安堵したように、深く吐息した。そして照れたように笑って、己の頬を掻いた。
「苦労をかけてすまなかった、母と妹のためにありがとう……と言われてね。幼い日の己が、父に褒められた時のように、何ともこそばゆく、嬉しかったな」
そうして敬円が視ている目の前で、祖母が迎えに来て、去って行ったのだという。そうして語る敬円の顔は、屈託から放たれたように晴れ晴れとしていた。
それを見た啓吾自身もまた、心が軽くなった。
「若様の言うところの、センチメントというものですか」
すると正周は、ははは、と笑った。
「昨今、あの夏目漱石も『感傷』にわざわざ『センチメント』とルビを振っていたんだ。流行り言葉に過ぎないよ」
自らの言葉でないので、そこを強調されると居心地が悪いらしい。変なところで潔癖なのが何やら滑稽だ。
「何はともあれ、ようやく、祖父を見送れた気がします」
啓吾の言葉に正周は、「それは何より」と嬉しそうに微笑んで、再び、書に視線を戻す。
こういう時、正周は何か気がかりなことがあるのだ。そして大抵の場合、この問題には啓吾も巻き込まれることになる。
いつもならば忍び足で書斎を出るところであるが、何となくとどまろうと思った。これまで避けて来た「霊異」が、自らに小さな幸せをもたらしてくれたことに、啓吾は少し気を許していた。
「何を調べているのですか」
正周はパッと顔を上げ、我が意をえたりとばかりに啓吾に向かって身を乗り出した。
「峯斎先生の話の中で、気にならなかったかい」
「……何が、ですか」
啓吾にしてみれば、気になることが多すぎて、正周が何に引っかかっているのか見えない。己のこともさることながら、凛と峯斎の縁についても、初めて聞くことばかりである。言うなれば、情報が多すぎて戸惑っているくらいだ。
「隠れ里は、何故、見つかったのだろう」
「そこですか」
隠れ里とはいえ、人が住んでいて、そこに人が辿り着くことができる以上、見つかることは何もおかしくない。
「それはほら、新政府が戸籍のために方々を調べていたからでは」
「いや、それだけではないと思う。峯斎先生も、隠れ里にいれば、妻子は安全だと信じていた。恐らく、何かしらの護りがあったのだろう」
「それこそ、不動明王の護りなのでは。凛さんが背負っているという……」
あの日も、峯斎の元を去る時、ちょうど仕事から帰って来た凛と行き会った。
以前から感じていたのだが、啓吾の目には、凛が歩いて来ると、その後ろに大きな不動明王の影が揺らめいて視える。それは恐ろしくも頼もしい、絶大な守護だ。
しかし、凛がその守りを得たのは、祖父が持って来た玉眼によるものだと聞いた。とすると、申岡の襲撃の後だ。
「申岡の襲撃の前に、隠れ里の護りは解けていたんだ」
何かを考えこみながら、ぐるぐると部屋の中を歩き回っている。正周のこの仕草にも、もう随分慣れて来た。
「その時、何があったのか……知りたいんだ」
正周が好奇心に駆られて動いている。それは啓吾にとっては日常が戻って来たようで嬉しかった。
「分かりました。付き合いますよ」
啓吾は机の上に、広がった本に栞を挟んでは片づけ、床に落ちた書付を纏める。
「あ、そうだ、あの本を取ってくれ」
正周が指を差すと、はいはい、と返事をしながら本棚に梯子を掛けて登る。「今度はそっち」「あの絵巻も」と、埃の舞う部屋の中を右往左往する。
啓吾は梯子に腰かけたまま、机について何かを没頭したように読んでいる正周を眺める。見ると、明り取りの窓から、白い雲が浮いているのが見えた。
今頃、祖父と祖母は何を語らっているのだろうか。
祖母の陽気な声を、ふと懐かしく思い出していた。