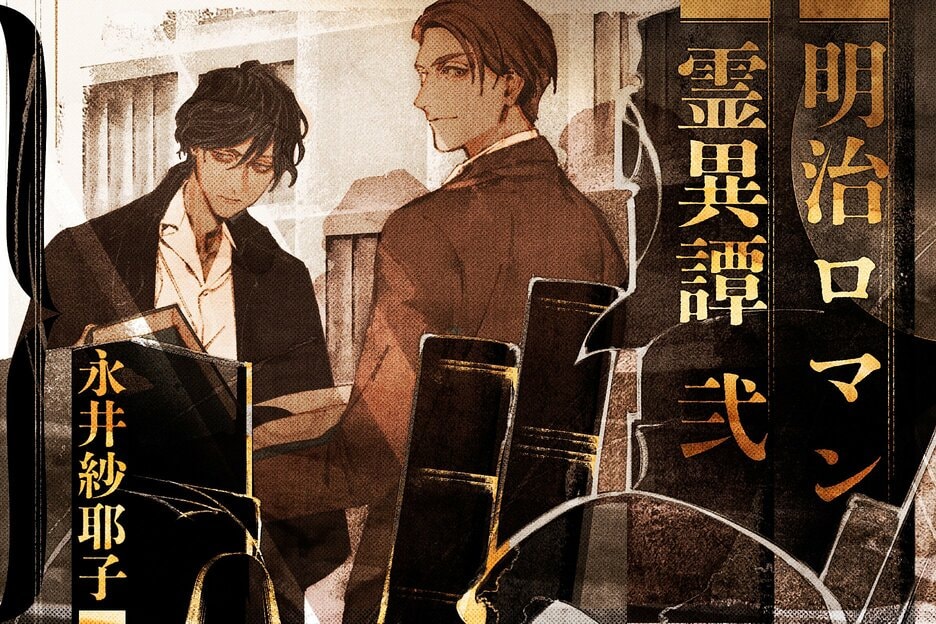第四話 センチメントな再会
その屋敷の門の前に立ち、啓吾は大きく息をつく。
芝増上寺の大門近く。ぐるりと塀に囲まれ、見越しの松が植わっている数寄屋造りの屋敷は、元は街道筋から少し入った隠れ家のような料亭であったという。今もその静かな佇まいは変わりない。
「しかし、いい設えだなあ……」
傍らで頷いている正周を見やり、啓吾はため息をついた。
「どうしてついて来たんです。これは僕の仕事ですよ」
この日、啓吾がここを訪れたのは、上条からの依頼であった。「昨今、芝の辺りによく当たる易者がいるらしい」というのだ。その易者の元には、名だたる実業家や、政治家も足しげく通っているという。しかしながら、訪ねて行けば誰でも会えるというわけでもない。「金を積んでも会えなかった」と文句を言っている者も少なくない。
「お前さん、会ってみないか。そいつが本物かどうか、見極めてくれよ」
と、アルバイトに出向いた啓吾に声を掛けた。上条は占いの類を信じていない。霊異についても、自ら体験したことがあっても尚、「気のせい」とか「夢かな」と思っているほど懐疑的な人である。ましてや実業家や政治家には斜に構えてみる新聞記者という仕事柄、それに関わる易者など、「胡散臭い」という疑念しかない。
「上条さんが会えばいいじゃないですか」
と啓吾が言うと、上条は苦笑した。
「俺は三度行った。そして、一度も会えなかった」
記者と名乗らずに行ったにもかかわらず、門前払いで会えずじまい。女中に約束を取り付けても、「お返事は追って」と言って、返事は来ない。近くで待ち伏せても会えず……。
「金はないから積めないしな」
「僕も会えないかもしれませんよ」
「お前さんなら会える気がするんだよな」
「金を求められてもありませんよ」
「なら、例の若様を連れて行けば心配あるまい」
とはいえ、財布代わりについて来いとは言えない。正周には黙って、平日の昼間に大学を休んで、一人で出かけようとしたところ、門前で正周に見つかった。「何処へ」と問われて渋々答えると、それはもう嬉しそうに、「ならば私も行こう」と、頼みもしないのについて来たのだ。
「私はね、噂の芝の易者というのは、峯斎先生ではないかと思っている」
思いがけず再会した凛は、芝の辺りにある峯斎の屋敷に世話になっていると言っていた。啓吾もそんな気がしていたのだ。こうして屋敷の前に立った時、その見込みは間違っていない気がした。存外、上条は勘が良いと思う。そして正周もまた、勘が良い。
「では、行きますか」
約束も何もしていない。突然の来訪なので会えなくて当然だ。啓吾はからりと引戸門を開けて足を踏み入れた。
「御免下さい」
玄関の前で声を掛けると、引き戸が開き、白髪で渋い木綿着物を着た老女が丁寧に頭を下げた。
「ようこそおいで下さいました。どうぞ」
名乗りもせぬうちに招き入れられる。啓吾は戸惑って正周を振り返るが、正周はまるで気にしていない。
「では、お邪魔します」
さっさと革靴を脱いで中へ入ったので、啓吾も慌てて続いた。
入ってすぐの部屋に通されると、縁側から前栽が見える。松の枝ぶりを眺めながら待つともなしにぼんやりしていると、軽い足音が聞こえて来て、縁側からひょっこりと白髪の老爺が顔を見せた。すっきりとした作務衣を纏っているのは、やはり峯斎であった。
「ちょうど良かった。お前さん方に会いたいと思っていた」
まるで二人が来ることを予め知っていたかのように、驚きもしないし、ここに来た理由を問いもしない。
「昨夜から、お前さん方の夢を見たからね。ここは凛に聞いたのか」
「いえ。昨今、噂の当たる易者を取材しろと、新聞社から命じられまして」
峯斎は、かかか、と大声で笑った。
「そうか。新聞社でアルバイトをしているとか言っていたな。ならば、大外ればかりの易者だったとでも書いておくといい。人にうろうろされて鬱陶しいからな」
啓吾はその言葉にやや安堵する。易者として「当たる」「当たらない」という表現が、この人にはどうにもそぐわない。視えているものが違うと言ったところで、記事としては意味が分からないだろう。いっそ、大外れと書く方がよほど楽だ。
正周は、ふうむ、と腕を組む。
「昨今、当家にやって来る政治家や実業家の中にも、芝の易者に会いたがっている方はいるようです。お会いにはならないのですか」「会ってどうする。何事においても、本人が動かねばどうにもならん。端から人の話を聞く気のない人や、悪縁を切る気のない人とは話しても仕方ない。そもそも易者を名乗っていたのは小銭稼ぎだ。儂は占いなぞしとらん。ただ、視えたものを伝えているだけのこと」
そして、廊下の方を見やる。
「門前に立った時、ここから覗く。それだけでその人が持っているのが欲か疑いか、分かる。切実な祈りがあれば、ここを目指して歩いている時から念が来る。そういう人とは会うけどな。煩悩塗れの輩は門の手前に札を貼ってあるので、辿り着くことも難しい」
道理で上条は門まで辿り着くものの、門前払いされたのだろう。
「……では、これで僕の用事は済んでしまったわけですが……」
啓吾としては、今回の仕事は「噂の易者は当たらない」という、ありがちな記事を書いて終わることになりそうだ。
すると正周が、ついと膝を進めた。
「実は、先生にお話ししたいことがあったのです。破崩坊という片目の見えぬ男に会ったのですが……」
「旧知だ」
正周が語る先を遮るように、峯斎は即答した。
「同郷でな。一月ほど前にも訪ねて来たが……その後は……」
峯斎は苦い顔で口を閉ざし、答えを求めるように二人を見た。啓吾は正周と顔を見合わせ、何と告げるべきか逡巡する。やがて正周がゆっくりと口を開く。
「破崩坊殿は、我らの目の前で……」
二月ほど前のこと。破崩坊は三鈷剣で自らの身を貫き、同時に申岡の家に出入りする侠客に取り憑いた。空になった破崩坊の体は、その場でどうと崩れ落ち、そのまま砂の如く消えた。
正周は目の前で起きた怪異に、流石に常の好奇心ではなく、驚きと恐れを抱いたように黙り込んでいた。啓吾もまた、人の身がこんな風に変貌するのを初めて見て、呪いの恐ろしさに震えた。
正周が語る言葉を聞いた峯斎は、静かに目を閉じた。
「やはりそうだったか。新聞で申岡の死を知った時、あやつは敵討ちを成し遂げたのだと思った。それが、呪いによって為されたのなら、それ相応の報いを受けるだろうと思っていたのだが……骸は消えたのだな」
「骸が消えるなどという怪異を、これまでにも見たことがおありですか」
正周が驚きを込めて問うと、峯斎は首を縦に振る。
「昔……旧幕の頃に一度だけ見た。ある男が呪いを成就させた時、その身が砂の如く崩れ去った。呪いは身だけではなく、魂魄を丸ごと消し去ると聞いたことがある。だがあの男は禁忌と知って尚、為さずにはいられぬほど、心の闇は深かったのだろう」
峯斎はすっと立ち上がり、後ろの違い棚に置かれた桐箱を手に取り、二人に向かって差し出した。
「呪具となったのは、これであろう」
桐箱には、あの三鈷剣が入っていた。実際に見ると短刀ほどの長さしかないが、破崩坊が持っていた時にはもっと大きく感じられた。
しかし、啓吾にとってそれ以上に気になったのは、三鈷剣の傍らにたゆたう影の如く姿を見せた老僧の霊である。今、峯斎の傍らに座ってこちらを見ている。先日、凛が「おじじ様」と呼んでいた人物だ。
「この方は、何方ですか」
啓吾が問うと、隣の正周が、え、と声を上げた。
「誰かいるのかい」
「ええ。先だって三鈷剣を凛さんに渡すように言った方です。恐らく、三鈷剣に憑いているのでしょうが……」
「この方は、お前さんとも縁がある」
峯斎の言葉に、啓吾は眉を寄せる。
見たこともない老僧と「縁がある」と言われても俄には信じがたい。そもそも峯斎の言葉をそのままに信じていいのか。啓吾は目の前に座る峯斎をじっと見つめた。
初めて会った時は、髪を振り乱した世捨て人のようであった。次に見かけた時は、小綺麗な装いで実業家の後ろに立っていた。それでも古いボロ長屋に住まい、寝そべって酒だけを飲んでいたのだ。それが先日の永富家の一件からこちら、身形も住まいも変えて、啓吾と正周が捜していた少女「凛」を養女として迎えている。
さっぱりした作務衣を纏い、綺麗な畳に端座する白髪の老爺が、果たして何者なのか。疑問が湧きおこって来た。
「この方のこともさることながら、そもそも貴方は何者なのですか」
これまでも、それとなく問いかけたことがあったが、いつものらりくらりとはぐらかされて来た。
しかし峯斎は、背筋を正して啓吾と向き合った。
「これまで、儂とそなたの間には、何かしらの因縁があると思っていた。それが何なのか、これまでよう分からんかった。しかし今、答えが見えたのだ」
「どんな因縁なのですか」
峯斎は、ううん、と唸って首を傾げる。
「さて、どこから話せば良いか……まずは、儂のことを話そうか」
峯斎は俯いて自らの手をじっと見つめてから、気まずい様子で苦笑する。
「儂は、元は幕臣でな。とはいえ、名が残るような者ではない。いわば幕府の隠密……とでも申そうか」
訥々と語り始めた。