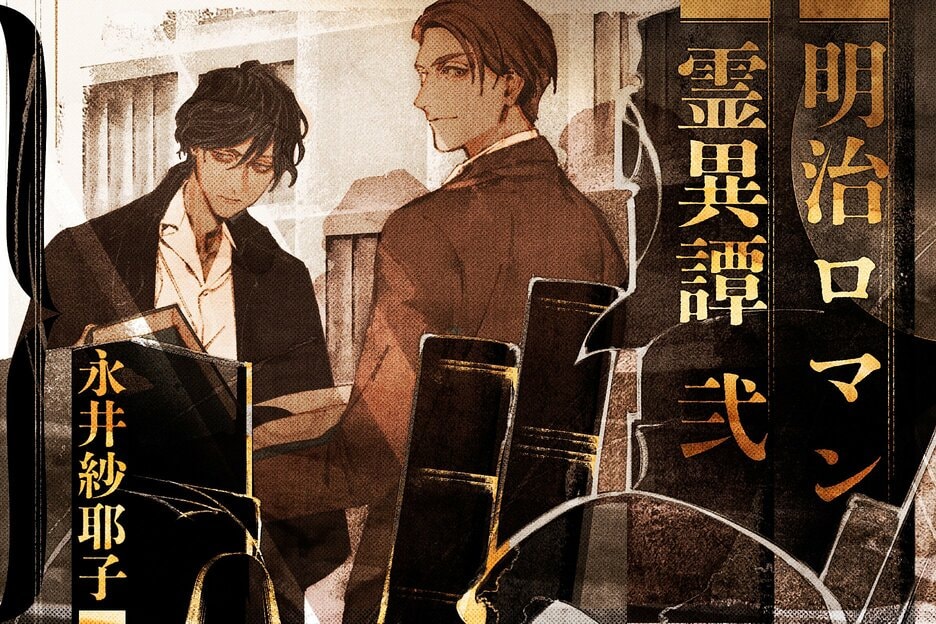第五話 絵巻アバンチュール
*
地蔵はひっそりと、寂れた裏路地の角に、草に埋もれるようにして立っていた。啓吾は地蔵に花を供えて手を合わせる。その傍らで同じく手を合わせていた正周は、耐えきれなくなったように立ち上がり、地蔵のある草の生えた一角を覗き込む。
「君はこれが、連翹宮の札を納めた地蔵堂の地蔵だと言うのかい」
「ええ、私にはそう視えました」
隠れ里と言われるところから、この東京まで、歩けばかなりの日が掛かる。当時のことを思えば、延々と続く草原を歩く。人もまばらで宿すらなく、ようやっと見つけた小さな地蔵堂だった。その場所が時代を経て江戸と呼ばれるようになり、今は東京になったようだ。
「なるほどねえ……」
感心したように腕組みをして唸る。相変わらずの好奇心で突き進んでいる正周を見ると、何故かほっとしてしまう。振り回されることに慣れ過ぎているのだ。
その分、突如として倒れ、魂の気配まで消えた姿を見た時には、心底、怖いと思った。
「何だい」
啓吾の視線に気付いて、正周が眉を寄せる。
「いやあ……目が覚めて良かったと、思ったんです」
「確かに、戻って来られて良かった。しかし、絵巻の中に入るなど、稀有な体験だったね。しかも、高貴な女性としての数日間を過ごしたようで、なかなか興味深い」
「ええ、そうでしょうとも」
姫宮として尊ばれて数日を過ごした正周とは違い、啓吾はというと、宮に命じられるままに遠路を旅して、刀を揮い、武士としての暮らしである。
「楽しいばかりでもないですがね……」
夜叉の里のことは、その凄惨な有様や漂う死臭までもが鮮明に思い出され、啓吾は眉を寄せる。
「それに、御屋敷の皆さんは心配されていたんですから。楽しかったなんて言ったら叱られますよ」
ここ数日、子爵や子爵夫人はもちろん、使用人、女中の悉くから「いかに皆が心配したのか」を懇々と聞かされた。
中でも委細を見ていた芳は、夜食を食べに来た啓吾を捕まえ、愚痴を交えて語った。
「奥様なんぞ、横浜からお帰りになって、あんな様子の若様を目にしたので、その場で泣き崩れてしまって」
しかもその傍らには、同じような状態で啓吾まで倒れている。駆け付けた医者は、「流行り病かもしれない」と大騒ぎ。
「それを御門跡様が一喝なさったんですよ。この二人は、絵巻に取り込まれた……なんておっしゃるでしょう。私たちは、御門跡様がおかしくなられたのではないかと……あら、ごめんなさい」
しかしながら、その重々しい口ぶりに圧倒され、皆、黙るしかなかったのだという。
せめても床に倒れた啓吾を、長椅子に横たえようとしたのだが、どうにも動かない。仕方なく、眠り続ける二人を、家中一同が、二日間、交代で見つめていたらしい。
「啓吾さんの御実家にも報せが行ったんですよ。そうしたらお母様が落ち着いていらして」
啓吾の母は、息子が倒れたと聞いて血相を変えて駆け付けた。しかし床に倒れた啓吾の様子に驚くこともなく頬にそっと触れた後、傍らにあった厨子の十一面観音の前で、黙って手を合わせたという。
「後は、御仏にお縋りしますと仰って……流石はお寺に御縁のある方は、信心深いというか、肝が据わっていらして、驚きましたよ」
一応、目覚めた後に母を訪ねると、母曰く、「部屋を視た時に、禍々しさがなかったし、絵巻と観音様が繋がっていたので、遠からず戻ると思って」とあっさりと言って笑っていた。
かくして、大勢の心配を掛けたので、既に家中であの一件は禁忌になっている。書斎で話をしようにも、女中たちが頻繁に覗きに来るようになった。
そこで、「少し河岸を変えて話をしよう」と、二人で連れ立って、この地蔵の所までやって来たのだ。
「しかし、連翹宮の視界から見た世界は面白かった。君が言うように霊異が視えるというのは、実に新鮮な体験だったよ」
正周がはしゃいで語るには、当初、宮の前に右京亮と夜叉が現れた時、右京亮の背後には静かな白い光に包まれた男の姿があった。一方の夜叉の背後には、さながら黒い岩のようにいかめしい黒い炎を纏う男の姿があったという。
「あのように、人の後ろに影のように霊が視えるのは初めてだったんだ。どうやら宮には、今の君と同じように視る力があったらしい」
呪術や陰陽道、密教についても知識を持っていたようだという。
「夜叉を助けるにはどうするか……と考えた時、自らの持仏を使って里そのものを隠そうとしたようなのだ」
元々、十一面観音には、「十一面観世音神咒経」なるものがあるらしい。
「どんなものなのですか」
「密教だから、それこそ病を治す祈祷として使われたり、調伏に使われたりと、色々あるが……怨敵を破り、衆生に慈悲心を生じさせるともいう。だから、その力を里に宿すことを考えた。しかもあの厨子の中には、十一面観音像と共に、地蔵尊と不動明王が納められていたから、十一面観音の霊力を、地蔵尊と不動明王に分けて、隠れ里を囲んで護ろうとしたのが、連翹宮の目論見だったのだろう」
「囲んで護る……と」
「まあ、三合の法という陰陽道の術を合わせたのだろうな。三つの点に囲まれた地は運気を上げることになる。その点である里は、囲いの内側に入るから、因縁を越えて守られると考えたのだろう。咄嗟にしてはよく考えたんじゃないかな」
絵巻の中で夜叉の姿を見た時、纏う気配や凛とした力強さは、峯斎や破崩坊、そして凛の持つ揺るがぬ力に似通っていた。
「しかし、それほどまでに護られていた里が、どうして襲われることになったんだろう」
啓吾の問いに、正周はうんと頷く。
「あの厨子が隠されていたことが原因ではないか」
そう言えば、明治初期の混乱の折に、新政府から厨子を護る為に先代の連翹寺家の当主が床下に隠したと聞いた。
「或いは、それが隠れ里を守る力を弱めたのではあるまいかと思っている。もう一つ、地蔵尊はその時どうなっていたのか……それが、この地蔵だというのかい」
正周は、改めてその小さな地蔵を裏側まで覗き込んでいる。
「先日、新聞社で古い地図を見ていたんです」
啓吾は新聞社にある古地図で見てみると、かつてこの地蔵がある場所には地蔵堂があったらしいことが分かった。
「壊されたのは、この線路を通すためだったようです」
啓吾が指さす先には、新橋から横浜へと延びる汽車の線路がある。
「というと、明治の五年頃……お祖母様の持仏が隠されたのと同じ頃だね」
一方で、神仏分離の動きによって仏像を隠すことになり、一方で文明開化の動きによって線路が通された。二つの流れがほぼ同時に起こり、太古に連翹宮が張り巡らせた結界は破られてしまった。
「恐らくそれで、隠れ里が申岡らに見つかった」
新政府にとって、旧幕と関わりのあった「稀なる宝」を隠す里として襲われることになったのだ。
啓吾はふうっとため息をつく。
「時代の狭間で起きた小さな出来事が、巡り巡ってあの里を危難に晒したのだとしたら、何とも人は無力な気がします」
しかし正周はいや、と即座に否定した。
「無力じゃないよ。確かに悲しいことはあったけれど、その中でも逞しく生きる人もいる。私は、先日の凛さんが大手町を闊歩する姿に、新しい時代の風を感じたよ」
確かに、悲劇はあった。その恨みを抱えて苦しんでいた者もいた。
だが、生き残った峯斎や凛が、新たに手を携えて暮らし始めている。それは希望でもある。啓吾は、そうですね、と答えた。
正周は大きく伸びをした。
「私はこれから峯斎先生をお訪ねするが、君はどうする」
正周は、今回の体験について話したくて仕方ないらしい。果たして峯斎が何と言うのか、啓吾も気がかりではある。しかし、この日は先約があった。
「僕は新聞社で活字拾いをしてきます。人手が足りないらしいので」
「そうか。それは残念だが、また一緒に行こう」
路地を抜けて大通りに出ると、啓吾は正周と別れ、一路、銀座の毎報社へと向かった。
今回の絵巻に入った話は、正直なところ、例の記事にはなりにくい。何せ、一般の家には絵巻も持仏もありはしない。装置が極めて前時代的なのだ。
「写真や電話とはわけが違うからな」
啓吾は独り言ちながら笑う。
しかし、装置は違うが起きていることはよく似ているのだ。
そもそも、あの『連翹宮物語』で描かれていた物語も、真相は何も不思議なことではない。時の権力者が、叛逆者を「鬼」として討伐しようとした。しかし「鬼」と呼ばれる者たちは、端から叛逆していたわけではない。突如として夷狄として襲われたことに怒り、嘆き、苦しんだ。それを護るために隠れ里を創った。
つい数年前、「鬼やらい」と称して、雉尾と申岡がやったことは、同じようなものだ。時の権力の都合によって、隠した宝を狙われ、戸籍がないから人ではない「鬼」として、いわれのない暴力に晒された。怒り、嘆き、苦しんだ破崩坊は、復讐を果たすことになった。
ここに千年余りの歳月の隔たりがあるとは思えない。
新聞社に入ると、相変わらずの忙しなさである。山のように積み重なる書類と本の隙間から、ひょいとこちらを覗いた上条が、啓吾に向かって手を振った。
「おお、遅かったな」
「はい、ちょっと立ち寄るところがあって……何を読んでいるんですか」
見ると英語の新聞のようである。
「ああ、海の向こう……米国のアトランタという土地で、白人たちが黒人を二十五人殺した事件が起こったらしい。切っ掛けは、黒人の男が白人の女を犯したという新聞記事であったとか。昨今、記者仲間の間でもこのことは話題になっているんだ。我々も、何を書くかを考えないと……無関係な人間までも命を奪う大惨事も巻き起こしかねない」
手渡された『Le Petit Journal』という新聞紙面には、白人たちが黒人に襲い掛かる様が挿絵になって描かれていた。
「同じだ……」
古今はもちろん、洋の東西を問わず、同じようなことが繰り返されている。
啓吾は英字の新聞を上条に返しながら、ふうっと深くため息をついた。
「そんな新聞に、僕が書くような霊異の話なぞを載せていいのでしょうかね」
上条は、ふむ、と腕組みをする。啓吾は思わず言葉を続けた。
「僕の書いたもので、誰かを傷つけたりとか……」
「まあ、ないとは言わないが……古今東西、人は不思議な話は好きだからね」
「まあ、そうですけど……事実かどうかと言われると、僕の主観でしかないという不安もあります」
「存外、繊細だなあ」
上条は揶揄うように笑い、そして言葉を選ぶように暫し黙り、そして自ら納得したように頷いた。
「だからかな。お前さんが拾って来た霊の話は、何と言うか、声なき声に思えたんだ」
「声なき声……ですか」
「ああ。旧幕の兵士であったり、落籍された女郎であったり、父に結婚を強いられる令嬢であったり、殺された幼い子であったり……皆、言いたくても言えない言葉を呑み込んでいた。あそこで書いていたのは、お前さんの創作だろうが、一方ではあの人たちの最期の叫びのような気がしてね」
啓吾が書いて来たのは、創作ではなく、実際に見聞きしてきたことだ。拾い上げた髑髏であり、祈る猫であり、笑う写真であり……起きたことの裏側に、時代の変化や、世の仕組みの中で懸命に生きる人がいた。
それらについて「何故、どうして」と知りたがる正周に引っ張られるうちに、自分もまた新しいことを知る。そのくり返しだったのだ。
「そうか、そうでしたね……」
「不思議なことを通して見えてくる、東京の今があると思うよ」
そこまで言うと、よっこらせという声と共に立ち上がり、啓吾の肩をトントンと叩いた。
「ま、これからも面白い話を集めて来てよ。それから、大学を出たらここに勤めるんだろう」
「……そうしたいと思っています」
「あ、そうか。お前さんは連翹寺家に引っ張られるのかな。だが、華族様の秘書や家令より、こっちの方が面白いぜ」
ははは、と笑いながら資料室へ歩いて行った。
啓吾は活字拾いに行き、黙々と文字を拾って活版に並べていく。その日に起きた何気ない事件や、政治家のこと。遠い町での市場の話を文字で並べながら、ぼんやりとこれからのことを考え始めていた。