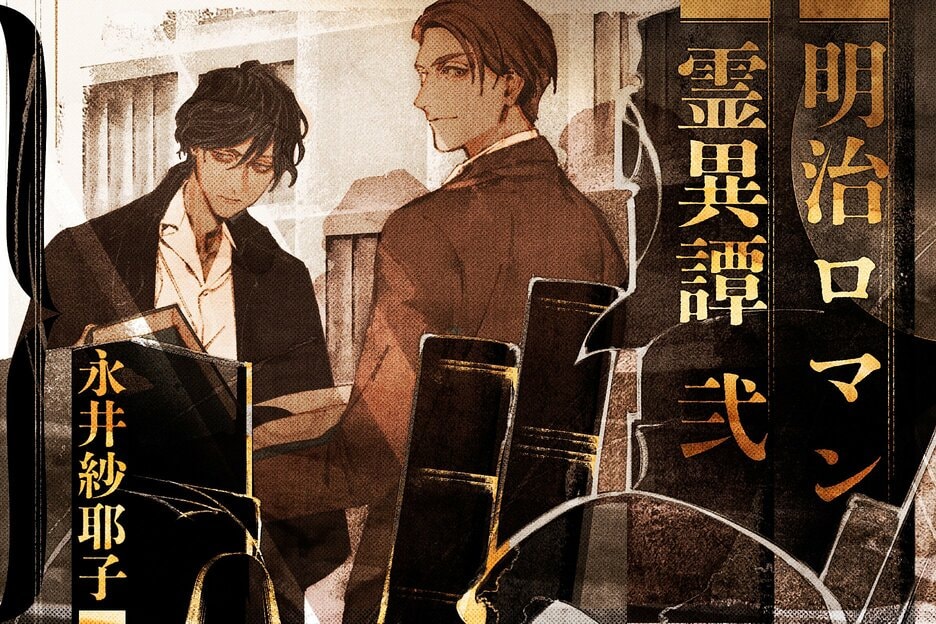第五話 絵巻アバンチュール
夕焼けが空を赤く染めている。
啓吾は大学での講義を終えて、帰途についていた。明日は休刊日で、新聞社でのアルバイトも休み……さて、これからゆっくりと読書でもしたいところである。しかし、このところ、正周は調べものに没頭している。放っておけばいいのだが、如何せん、啓吾にとっても無関係の話ではないだけに気になっていた。
調べているのは他でもない。「隠れ里」のことである。
所在やその土地の名について峯斎にも尋ねてみた。しかし峯斎は、「今となっては禍つ地の名。知らぬが良かろう」と、頑なに教えようとしない。
ただ、峯斎や凛から聞いた細切れの話を繋ぎ合わせると、少しだけ予測はできる。祖父、啓照は、幼い凛を連れて逃げる途中、中山道の外れにある小さな宿場町で、申岡らによって殺された。凛の母が隠れ里から逃れた地と宿場町はさほど遠くないので、隠れ里も「大体、この辺り」と分かる。しかし地図を見たところで、道なき道の先にある山また山の中。まさに辿り着くのも難しい場所であるからこその「隠れ里」だ。
それでも祖父の埋葬された地に行かねばならないと思っていたのだが、当の祖父自身が夢枕に立ち、「来なくて結構。仏壇に手を合わせておけ」と笑っていた。
一方の正周はというと、何かが引っかかっているらしく、史料を眺めて唸っている。遠からず行きたいと言い出すかもしれない。もしそうなれば、その時にお供をするのは自分だろうな、とも思っていた。
「行きたくはないな……」
啓吾は登山の類は余り好きではない。生まれながらに町の子で、昨今では、路面電車で移動する方がいい。
そんなことを考えながら、連翹寺家の門をくぐり、そのまま鳳雛寮に向かおうかと思ったのだが、一旦そこで足を止めた。どうせまた、顔を出すことになるのだから……と、本宅の勝手口を開ける。
「あら、啓吾さん、お帰りなさい」
のんびりした様子で女中の芳がいた。夕食の支度の前のひと時らしい。手には啓吾のアルバイト先である毎報新聞がある。
「ここの記事が好きなのよ」
と、指さしたのは、啓吾が受け持つ小ネタである。霊異にまつわる噂を書いた記事だが、政治や経済、事件事故の間のちょっとした息抜きにちょうどいいらしい。
「若様は」
「相変わらず……あ、先ほど御門跡様がいらっしゃいましたよ」
「御門跡様が、どうして」
「何やら大きな厨子を持っていらして……あれは何かしら」
御門跡様は、正周の祖母である。啓吾の伯父、敬円の寺の奥で庵を結び、静かな暮らしをしている。
正周が気になることがあったのだろう。まさか御門跡様まで巻き込んでいるとは思わなかった。
「それで御門跡様は」
「ああ、少し前にお帰りに。若様がまた調べものに熱中しだしたから、邪魔せんように、とおっしゃって」
やれやれ、自らの祖母を追い返すほどに何に夢中になっているのだろう。
啓吾は芳に「丁度良かった」と、盆に載った煎餅を書斎に届けるように言われ、長い廊下を運んでいく。廊下の先の書斎を覗くと、扉は開かれたままだ。啓吾はひょいと中を覗いて、「若」と声を掛けると、正周はくるりとこちらを振り返った。
「ああ、啓吾君。これを見てくれ」
テーブルに置かれた腰高ほどの黒い厨子は、漆塗で、扉には金の細工が施されている。開かれた厨子の中には、繊細な彫が施された十一面観音像があった。
「こちらは、何ですか」
「御門跡様にお持ちいただいたのだ。『連翹宮物語』の絵巻に描かれた十一面観音像は、正にこれではないかと思うのだ」
『連翹宮物語』という絵巻は、連翹寺家に伝わるもので、広く知られてはいない。連翹寺家の祖にあたる帝の皇女であった姫宮のもとに、鬼がやって来て、一人の武士がそれを退治するという物語である。ありがちな寓話だと思うのだが、正周はこの話に常々、関心を寄せていた。
「絵巻の何処にこの像が……」
すると正周は、くるくると絵巻を巻いて、十二単を纏った女性が手を合わせている厨子を指さした。
「ほら、ここにある」
そこに描かれているのは、目の前にある十一面観音像によく似ていた。
「確かに似ていますが……この物語は飽くまで寓話の類なのではありませんか」
啓吾が言うと、正周はいいや、と首を横に振る。
「寓話とて軽視できないよ。ドイツのシュリーマンという人は、神話に描かれた物語から、壮大なるトロイアの遺跡を発掘したそうだ。物語の中には幾分の真実が隠れているのだ」
この絵巻も連翹寺家に伝わるものだし、持仏もそうである以上、絵巻に描かれる物語も、シュリーマンの遺跡のヒントとなった神話と同じく、何か現実に起こったことを表しているのかもしれない。
「若様は例の隠れ里を探しているかと思ったんですが、今度は絵巻の解析ですか」
「いや、そうじゃない。この絵巻の鬼が逃げ込む里こそが、隠れ里であろうと思うのだ。ほら、見てくれ」
絵巻の後半には、武士によって追われた鬼が逃げ込む山が描かれている。その山には不動明王が守護するように立っていた。
「逃げた鬼を見上げる姫宮の傍らにも、この厨子がある。そこには十一面観音の両脇に別の像があるんだ。よく見てくれ」
確かに、厨子の中には十一面観音を中心に、右に不動明王、左に地蔵尊が描き込んであった。不動明王像の姿は、背後の焔の色や形も含めて、山の上に立っているものと同じだ。
「まあ、不動明王の姿そのものは何処も似たり寄ったりかと思うんですけど……」
「それだけじゃないんだ。これを見てくれ」
今度はバサバサと古地図を広げて見せる。
「千年ほど前、連翹宮領という荘園がこの辺りにあった。尤も、その後は戦乱の時代になり、太閤検地で荘園は姿を消しているが……一部、奇妙な形で寺領として残ったものがあってな」
正周が指さす先は、中山道にほど近い山寺である。その寺領は、石高もさほどにあるわけでもないことから、寺領として残されていたのだが、その後、徳川家の血を引く後水尾天皇の姫宮を介して、寺領から徳川家の管轄に入った……らしいことを矢継ぎ早に説明する。
「故に、徳川の隠し財産があるなどという噂が立つのも無理はないだろう」
「確かにそうですね」
正周は再び史料を繰りながら、首を捻る。
「あの隠れ里は連翹宮も関わる者がある気がする。とすると、あの護りが破られたことにも、当家が関わる理由があったかもしれない。詳しい経緯を知りたいのだが……」
ぶつぶつと呟きながら、部屋の中をうろうろと歩き始める。
隠れ里のことを調べているうちに、絵巻に答えを求めるようになったらしい。何処まで遡るつもりなのか……呆れつつ眺めていると、正周の手から細く光りながら伸びる糸が視えた。その糸がテーブルの上にある絵巻と厨子にも伸びているのだ。正周がぐるぐると回るうちに、次第に糸は正周の体にも絡まり始める。
啓吾の目にしか視えないから、正周が気にするはずもないのだが、啓吾は気になって仕方ない。
「若、少し落ち着きましょう。お茶でも入れて……」
啓吾は一旦、正周を座らせようとするが、正周は上の空で、ぶつぶつと呟く。
「いっそ、この中に入ってみたいくらいだ」
正周は絵巻に手を伸ばし、ぐいっと引っ張った。すると、正周の足元に伸びていた光る糸が、正周の足元にピンと伸びる。そのまま正周が再び歩き始めると、ととと、と足が絡み、その場にどうと倒れた。
視えない糸に転ぶとは珍しいこともある。
「大丈夫ですか、若。うろうろするからですよ」
啓吾は駆け寄って正周を助け起こそうとした。しかし、正周はぴくりとも動かない。慌てて体を揺すっても、まるで反応がない。
「若、どうしたんです、若」
正周の体は揺さぶられ、力なくそのままごろんと仰向けになった。顔色は悪くなく、腕は脈を打ち、微かな呼吸もある。
だが、そこに魂がない。
そんな気がした。
「大声が聞こえましたけど」
女中の芳がひょいと顔を覗かせると、床に座り込んでいる啓吾と、その傍らで倒れている正周を見つけ、慌てて駆け寄る。
「急に倒れたんだ。すぐに医者を」
切羽詰まった啓吾の声に、芳は、はい、と踵を返した。
しかしこれは医者で事足りるのだろうか。
恐らく体には何の障りもない。ただすっかりと体から魂が抜け落ちてしまったように見えるのだ。それは、いつぞや「笑う写真」に取り込まれた雉尾伯爵家の昭子嬢の姿にも似ている。啓吾はゆっくりと辺りを見回すが、部屋の中に、正周の生霊はうろついていない。
「若様が倒れられたとか」
慌ただしく姿を見せたのは、車夫の耕三である。耕三は正周と初めて出会った時、寿照尼と揉めていた車夫で、その後に連翹寺家のお抱えになった。事情を知りながら迎え入れた正周に恩義を感じており、常日頃からよく言葉を交わしていた。
「ああ、今しがた突然」
「芳さんたちから、若を御部屋に運ぶように言われまして」
そう言うと、倒れている正周をひょいと軽々抱き上げ、部屋を出て行こうとする。正周の手から伸びた糸がピンと張る。啓吾はその様子を視て、この絵巻と正周を離してはいけないように思った。とはいえ、事の次第を話しても、すぐに分かってもらえるとは思えない。
啓吾は絵巻を手際よく丸めて小脇に抱え、厨子の扉を閉めて持ち上げる。そのまま耕三の後を追って、二階にある正周の寝室へ向かった。
寝台の脇にある棚に、厨子と絵巻を並べて置くと、啓吾は丸椅子を引き寄せて寝台の傍らに座る。大きな寝台に寝かしつけられた正周は、相変わらず微動だにしない。耕三は心配そうに顔を覗き込む。
「生きて……ますよね」
「当たり前だろう」
思わず声を張る。それは啓吾自身も不安を感じているからだ。
啓吾は頭の中で忙しなく、倒れる直前の正周の様子を思い浮かべる。「絵巻の中に入りたいくらいだ」と言った直後に自らと絵巻を結ぶ糸に躓いた。
「まさか、この中に……」
啓吾は慌てて絵巻を広げ、眠る正周の足元に置いた。絵を凝視していると、部屋の戸が勢いよく開いた。
「正周さんが、倒れはったて……つい今しがたまで達者やったのに」
小柄な白髪切り髪の女性、寿照尼だ。震えながら寝台まで歩み寄り、正周の手を取る。正周は微動だにしない。
正周の父と兄は神戸に出向いており、母は横浜に知人と共に出かけていた。寿照尼の他にはなかなか駆け付けることができないらしい。生憎と医者はまだ来ない。
「御門跡様。こちらの厨子は、御門跡様がお持ち下さったのだと聞いておりますが」
啓吾の問いに、寿照尼は頷く。
「私が持って参りましたんや。正周さんが頼まはった。絵巻に描かれている観音様はあるのかと聞かはって」
「それがこれなのですね」
啓吾が言うと、寿照尼は暫し口を引き結ぶ。
「実は、この厨子はここ数年の間、行方知れずだったんや」
新政府が立ち上がってから間もなく、神仏分離令や天社禁止令など、信仰や祭祀に纏わる政令が下った。
「当家は元々、宮中の祭祀の一端を担って来た。ただ、この十一面観音を納めた祠は、宮中とは無縁の私的な祠でな。私の夫であった先々代の連翹寺家の当主が、新政府によって淫祠邪教との誹りを受けかねないと、祠を封じ、厨子を隠しましたんや」
代々、祈りを捧げられて来たこの厨子が消えたことに、当時、まだ生きていた先々代の母は卒倒するほど狼狽えたという。それというのも、先々代は入り婿であり、祠の由来を知らなかったかららしい。
「由来とは何ですか」
「それが、この絵巻にある通り。連翹宮が、鬼の逃げた山の方を向いて祠を置いて、日々、祈りを捧げることで、災いを封じたと伝わる」
確かに、かなり年季の入った仏像であることは見てとれる。小さいながらも丹精に造られており、落剥しているものの、金箔まで貼られていた。
「価値のあるものだと宮さんもご存じやったさかい、奪われては困ると考えはったらしい。しかし、その隠し場所を私と母には伝えぬまま、急な病で世を去りはって……」
以来、長らく行方が知れなかったのだが、つい先ごろ、京の屋敷の管理を任せていた分家の者から、「床下から桐箱に入った厨子が見つかった」という報せが来たという。
「そんな時に、正周さんからこの厨子について尋ねられましたんや。そこで、京から運んでもらったんやけど……」
そう言って寿照尼は、横たわる正周の頬に触れた。すやすやと眠っている顔は穏やかだが、息をしているのかどうかさえ危ぶまれるほど動かない。
「背の君が亡うなった時を思い出して……怖い」
この厨子を隠した後に急逝したという夫を思い出すらしい。
だが、啓吾が視る限り、この厨子には禍々しさの欠片もない。むしろ怖いほどに清澄だ。しかしそんな清らかなものを前にして、啓吾はずっと落ち着かない。
「……あの時はどうしたっけ」
啓吾はいつぞやの「笑う写真」のことを思い出す。生霊が物に取り込まれることを目の当たりにした。あの時は写真であったが、今回は絵巻である。物は違うが、似通ったことが起きていると考えてもいいだろう。
ならば、あの時と同じく、物理的に腕を引っ張って呼び戻してみるか……。確か、昭子嬢にとって思い入れのある薫子や正周が手ずから引いたことによって呼び戻せた。今回、もしも正周が引き寄せられた理由があるとするならば、それは連翹寺家の歴史そのものである。
「御門跡様。一度、若の腕を引っ張っていただけますか」
寿照尼は怪訝そうに眉を寄せた。
「私が、引っ張るのか」
「ええ。こう……引っ張り出すように」
寿照尼は啓吾の言う通りに、正周の腕を掴んで、ぐいっと引っ張った。しかし、正周の体は少しだけ浮き上がったものの、ぐにゃりと再び寝台に沈む。
「一人ではとても……」
確かに還暦過ぎの寿照尼の手で、二十歳そこらの青年を引っ張り上げるのは難しい。だが、物理的に引くわけではないので、たとえ持ち上げられなくても、離れた生霊が還って来るのではないかと思った。
しかし、正周は相変わらず動かない。見込み違いだったようだ。
力なく横たわる正周を見つめているうちに、このまま目覚めなかったらどうしよう、という想いがぐるぐると頭の中で渦巻く。
沈黙する啓吾を見た寿照尼は、首を傾げた。
「啓吾さんは、正周さんが何や……怪異に巻き込まれていると思うてはりますの」
「……はい」
「先も申しましたように、当家は元々、祭祀に携わりますよって、時折、そうした勘の強い人が生まれます。正周さんもそういう性質なんやろか……」
正周は視ることも聞くこともできるわけではないのに、要らぬ厄介に突っ込んでいくことも多い。いつも呆れつつも付き合ってきたが、祓う力が強いので正周はいつも無傷だ。それは当然のことだと思っていた。
「こんな時に、何の役にも立たないなんて……」
正周と違って、啓吾には視る力も聞く力も備わっている。しかし、霊異に対していつも斜に構えていた。お陰でこうした奇妙な出来事の道理も仕組みも分からない。視えるだけなのだ。正周が絵に取り込まれているというのなら、そこへ入って連れ出したいところなのだが、その術が分からない。
正周がいれば、古今東西の書物から事例を導き出し、方法を考えてくれるかもしれないのに。他にも詳しい人がいれば……。
「……峯斎先生」
啓吾は寿照尼を振り返る。
「御門跡様、いつぞやお会いになった易者の峯斎先生を覚えていらっしゃいますか」
「ああ、あの寂れた長屋にお住まいの」
「ええ。最近では、芝に屋敷を構えているのです。あの方ならば色々と分かるかもしれない。すぐに呼んで参ります」
啓吾は言うが早いか踵を返し、正周の寝台から離れて駆けだそうとした。
その時、正周の足元に広げた絵巻と、厨子の観音像の間に伸びた糸に引っかかった。
あ、しまった……と思った瞬間、啓吾はその場でどうと転んだ。実体のない糸なのだが、そういえば以前も正周とこの絵巻を結ぶ糸に躓いたことがあった。
やれやれ、と顔を上げた時、目の前にはまるで見覚えのない風景が広がっていた。
鬱蒼と茂る木々の中、見上げると月がある。立ち上がろうとした啓吾は、自らの身に甲冑を纏い、腰に太刀を佩いていることに気付いた。
あの絵巻の中に、入ったのだ。