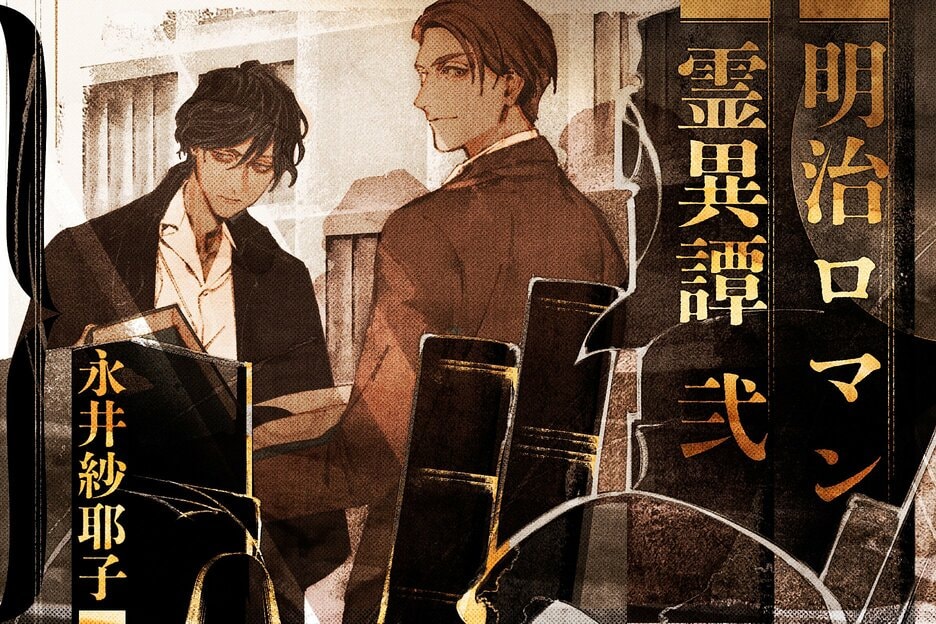第三話 ハイカラ電話
―――暗く長い廊下の先。ぼんやりと浮かび上がる女の姿があった。ゆっくりと近づいて行くと、女はこちらを振り返る。洋館の階段の下に灯る小さな明かりで見ると、女は十七、八といったところか。
「誰」
そう問うと、女は怯えたような顔でこちらを見やる。
「ここは……何処ですか」
声は掠れたように聞こえた。そもそも、屋敷の中にいながら、何処か分からないということがあるのか。困惑しつつ、どう答えるかを迷っていると、女はそのまま、すうっと姿を消した―――。
「ということがあったんですよ。どう思います、啓吾さん」
連翹寺子爵邸の台所部屋で、賄いを食べながら女中の信は、ずいと身を乗り出す。同じく賄いをご相伴に与っている書生の雲戸啓吾は、茶碗を片手に、はあ、と気のない返事をした。
テーブルには、子爵家の晩餐の残り物……とはいえ、いわしの煮つけや、ぬか漬け、それにいただき物のアサリの佃煮など、なかなか豪華な品揃えである。どれも美味しいので、啓吾は先ほどから、せっせと健啖ぶりを発揮していた。
「それは、何かの本に載っていた怪談の類ですか」
味噌汁を啜りながら問うと、
「いいえ、お由紀が視たって言うんです」
と、信は台所の隅を指さす。
由紀は信の娘で、今年で十八になる。日ごろ、子爵夫人の身の回りの世話をしつつ、行儀見習いをしており、屋敷内にある女中部屋に信と二人で暮らしていた。
「この屋敷の中で、幽霊が出たんですか」
啓吾は元々、霊を視ることができる。しかし、この屋敷の中ではついぞ視たことがない。女中たちは、啓吾が「視える」などとは知らないが、当家の次男坊である正周が、心霊研究なる怪しげな学問に傾倒していることは知っている。ついでに、啓吾もその手の話に詳しいと思われている。
「どう思う、と言われても……何処に出たんですか」
由紀は思い出すのも怖そうに眉を寄せる。
「そこの……廊下です」
台所から大広間へと向かう廊下を指さした。とはいえ廊下も長い。
「廊下のどの辺りでしょう」
信は娘に「ほら、案内して」と、急き立てる。結果、その場にいた信と由紀、それに同じく賄いを食べていた芳と啓吾は、皆で廊下に出た。
由紀は台所から廊下に出ると、その時の状況を説明し始めた。
「三日前の夜中に目が覚めて……」
信と由紀が暮らす女中部屋は、台所とは廊下を挟んだ向かい側にある。
女中部屋から出た由紀は、台所で水を飲み、再び女中部屋に戻ろうとした。すると、夜だというのに、廊下の先に人影があった。目を凝らすと下ろし髪の女である。
「奥様が何かお求めかと思ったのです」
寝間着でうろうろすることのない子爵夫人が二階の寝室から降りて来たのだ。水差しの水が切れたのか、何か異変があったのかと案じて近づいたら、夫人ではないことに気付いた。
「はじめは、私が知らぬ間に、私と年の近い女中が入ったのかと思ったんです」
「もし」と声を掛けると、女はこちらを見て驚いたように目を見開いた。そして、「ここは何処ですか」と、問うた。
「おかしなことを聞かれたけれど、寝ぼけているのかと思い、連翹寺子爵家ですよ、とお伝えしたんです。そうしたら……」
由紀は恐ろしそうに身を縮め、首を横に振る。
「え、って驚いた顔をして、そのまま女はふうっと姿を消したんです……」
信と芳もまた、互いに手を取り合って「怖い」と震えている。
啓吾は神妙な面持ちで頷きながらも、およそ怖さは感じていない。ただ、それが「何か」ということだけに関心が向いていた。
啓吾は更に廊下を歩き進み、階段の近くまで来て足を止めた。目を凝らすが、そこには誰もいない。
「今もいますか」
由紀はいいえ、と頭を横に振った。
「でも、あの時はいたんです。嘘はついていません」
涙目で訴える。啓吾もかつて幽霊の話をして、周りの人に怪訝そうに見られたことがある。「嘘ではない」と言い募る由紀の思いが分かるだけに、啓吾は何度も深く頷いた。
「もちろん、嘘をついていたなんて思いません。何せうちの若様は、心霊学なぞをやっている人ですよ。ただ、若様に話せば、却って大喜びしてしまうから……」
「私が何だって」
背後の声に、啓吾は恐る恐る振り返る。そこには好奇心を満面に浮かべた連翹寺家の高等遊民、次男坊の正周が立っていた。
「小耳に挟んだんですが、お由紀さん、屋敷の中で幽霊を見たそうですね」
目を爛々と輝かせて、由紀の顔を覗きこむ。由紀はやや身を引きつつ、はい、と小さな声で頷いた。
「その……御屋敷を悪く言っているつもりはないのですが……」
「無論。そんなことは分かっているよ。お由紀さんはお母様のお気に入りだ。何を話しても心配ないから」
そういう時、正周はとても紳士的に振舞う。由紀は正周の穏やかな口ぶりに安堵したように、ありがとうございます、と頭を下げた。
「ここに、立っていたんだね」
正周が階段の下に立つと由紀は首を傾げる。
「いえ、もう少しこちら……電話室の傍です」
階段下には、ガラスの入った扉のついた木製の電話室がある。壁に掛かる電話機で話しやすいように、少し背の高い革張りの椅子が設置されている。
「なるほど……」
正周は暫し険しい顔をして電話室を睨んでいたが、やがて何を思ったのか、書斎に向かって歩き始める。
「啓吾君、少し付き合ってくれ」
「若、僕はまだ夜食をいただいているので」
しかし正周の耳にはそんな声は届いていない。ずんずんと書斎に入って行く正周を見て、信が啓吾の背を押す。
「おにぎりを作っておくから」
啓吾は、はい、と渋々と頷いて、由紀を振り返る。
「お由紀さん、とりあえず、台所で少し塩をもらって、枕元に盛り塩でもしておくといいかもしれない」
啓吾は言い残して、正周の後に続いた。
正周は自らの書斎に入ると、本棚を見上げて唸り始める。
「お由紀さんの視た幽霊について、どう思う?」
話を聞く限り、さほど恐ろしいものには思えない。言葉が通じていて、しかもすぐに消えている。驚かそうという気もなければ、恨み言も言っていない。
「うっかり、出ちゃったんでしょうね」
「そんなことがあるのかい」
「まあ……たまに」
以前、新聞社の近くを歩いていたら、銀座の交差点の真ん中に、男がぼんやりと立っていた。はたと気付いたように辺りを見回し、こちらに向かって駆けて来たと思ったら、「俺はどうしてここに」と、問われたことがある。周りの人には見えていない様子から、霊らしい。「帰った方がいいですよ。何処に帰るか分かりますか」と啓吾が尋ねると、暫し考えてから、「はい」と答えるなり、姿が消えた。
今回、由紀の話を聞いた時に、それと似ているように思えた。
だが、霊とて見ず知らずの所に突如として現れることは稀だ。その土地や、そこにいる人などに思い入れがあってこそ、現れるはずだ。
「お由紀さんと同じ年ごろの娘ということですが、心当たりはありませんか。この家に所縁の方で……」
正周は首を傾げた。
「そういう年で亡くなった方はいたかな」
「いえ、亡くなった方だけではなく、生霊の類かもしれません」
「君や、お兄様、お義姉様、女中や書生……この家には大勢いるからな。所縁の人の中には、そういう年ごろの娘さんもいるだろう」
「まあそうですが、霊異は若様絡みのような気がして……」
すると何故か正周はほほ笑む。
「まあ、そうだろうね」
何が嬉しいのやら。啓吾はため息をつきつつ、案じてはいない。
何せ、正周は本人でも気づかぬうちに悪霊を祓ってしまう特異な体質だ。おかげで当人は視ることができないのが悔しいらしいが、視えてしまう啓吾としては、それが良い霊か悪い霊かが一目で分かるので助かる。
「啓吾君、一体、何者なのか、知りたくはないかい」
それは他でもない、正周が「知りたい」という意味である。
「残念ながら若様、私が視たのならば調べようもありますが、私は視ていないんですよ」
さも口惜しそうに顔を顰めて見せ、深々と頭を下げる。
「また何かありましたら調べますよ。とりあえず、夜食の続きを食べてきますので」
啓吾はくるりと背を向け、正周の部屋から廊下に出た。階段の下の電話室の前を通るが、誰の姿もない。
「単にお由紀さんが寝ぼけたのかもしれない」
実はそれが真相ではなかろうか、とも思う。台所部屋へ行くと、賄いの食卓は既に片づけられていて、おにぎりが二つ、竹かごの弁当箱に入っていた。
「ありがたく」
啓吾はそれを小脇に抱え、軽い足取りで勝手口に向かい、そこから鳳雛寮へと庭を横切っていく。
今日も一日、ばたばたと忙しなかった。
夜食を食べ終えて眠りについた深更のこと。
「きゃああああ」
屋敷の方から宵闇を劈くような叫び声が聞こえた。
啓吾は寝台から飛び降りて、屋敷に向かった。勝手口を叩くと、内側から信が戸を開けた。
「お騒がせを……」
他の書生たちも駆け付けており、屋敷の中の使用人はもちろん、子爵や夫人らも廊下に集まっている。そこには由紀が蹲っていた。
「また……出ました……」
由紀の目の前の空間には、相変わらず誰もいない。だが、指さす先は同じ場所。
腕組みをした正周は、暫しの沈黙の後に首を傾げる。
「どうして私の前に来ないんだ」
いや、疑問を持つべきはそこではない。
と、言いかけて黙る。
一体、何がどうして現れているのだろうか……流石に啓吾も気になり始めていた。