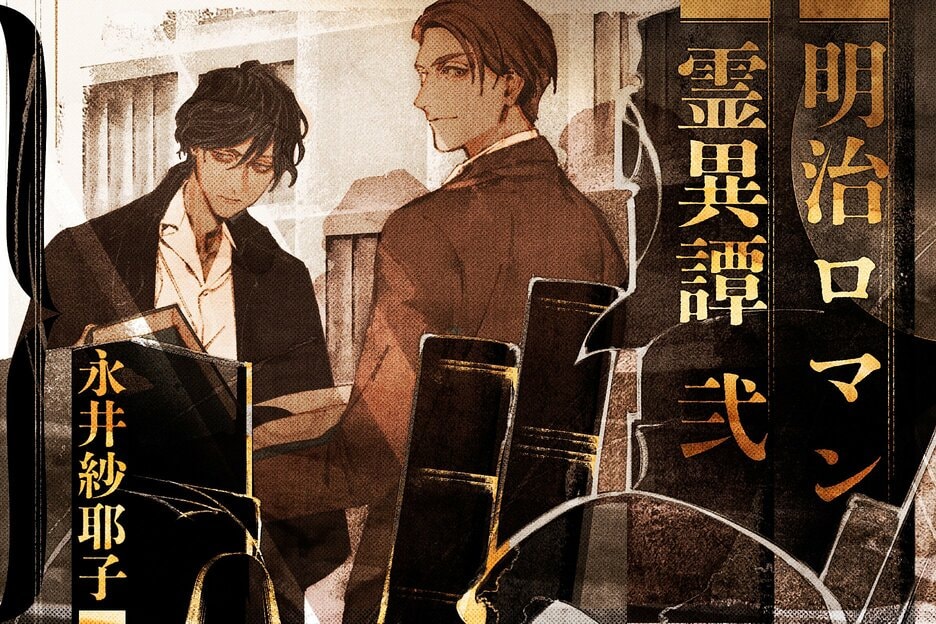第五話 絵巻アバンチュール
*
暗がりの中で目を凝らすが、そこにいるのは己だけだ。どこか山中で足を滑らせているらしい。
辺りを見回しても、正周の姿はない。
「こんなこともあるのだな……」
啓吾は今、誰かに憑いているようだ。視界は誰かに重なっているのだが、その身は思うようには動かない。
姿かたちからして恐らくは武士なのだろう。
あの絵巻に描かれている時代が、平安の末頃であろうと正周は言っていた。源平の合戦が始まるよりも少し前の頃だろうか。武士は、貴族の元に仕え、護衛の任に当たっていたと思う。
「どうした、右京亮」
声を掛けられ、啓吾は男が「右京亮」と呼ばれる身の上であることを知る。
「大事ござらん」
声と共に立ち上がる。そして滑り落ちた崖をよじ登ると、そこにいたのは松明を持った屈強な体躯の男である。差し伸べられた腕には蛇が這うような入墨があり、装いも、右京亮が纏っているのとは違う甲冑である。だが、この二人はとても親しそうである。
そこから啓吾は少し、二人の様子を俯瞰で視えるようになってきた。
絵巻の中で起きたことを眺めているようである。
右京亮は立ち上がり、大柄な男を見上げた。
「では参ろう、夜叉殿」
右京亮は男を、夜叉と呼んだ。その名が男の真の名とは思っていない。ただ、男の仲間がそう呼んでおり、男もまたそれを受け入れていた。
右京亮と夜叉が進んだ先には、石が積まれた垣がある。しかし二人はそれを乗り越えて、道なき道を松明を手にして進んでいく。やがて壮麗な屋敷が見えて来た。
屋敷の裏手に進み出た右京亮は、短く指笛を鳴らした。その音で、端近に姿を見せたのは白髪の老婆であった。
「右京亮、参ったか」
「はい。連翹宮様にお取次ぎを」
老婆は右京亮とその後ろに控える大男にあからさまに眉を寄せた。しかし、渋々中へ入り、こそこそとした声で話す。暫しの間があって衣擦れの音がした。御簾の向こうに人影が見え、微かに焚きしめられた香が漂ってくる。
「右京亮、その者が夜叉か」
右京亮は地面に膝をついたまま頭を下げる。
「さようでございます。この者は、都より離れた東の地にある山に住まう者でございます。昨年、夷狄討伐のために討伐に都より兵が遣わされ、戦となったのでございますが、元よりこの者たちに叛意などなく、静かに暮らしていきたいとのこと。私も派兵で赴きましたが、この者が直訴を申し出ました故に連れて参りました」
右京亮はそこで言葉を区切り、ぐっと口を引き結んだ。
「何と」
その声と共にばさりと御簾が撥ね除けられた。
「宮様、なりませぬ」
制する声を後目に、中から一人の若い女が姿を見せた。
松明の灯りに照らされた白皙の面差しは、まだあどけなくも見える。長い黒髪を背に流し、緋袴に薄紅の袿を纏っていた。こちらを見つめる黒い目は、灯りを映してきらきらと光っている。無礼とは知りながらも、右京亮は思わず見入り、次いで慌てて目を伏せた。
「夜叉とやら。詳しく聞かせよ」
その言葉に戸惑ったように沈黙している。右京亮は夜叉を振り返り、話すように促した。
「我らは古くから山中に住まい、傾斜に田畑を耕し、木の実や獣を食して暮らして参りました。時には山裾の民人とも食物を贈り合い、共に生きて来た……されど、都から夷狄討伐にやって来た都から近衛中将様の命でやって来た兵たちは、我らを災いを招く鬼だと襲って来たのです。それは……この地の持主である姫宮の御為であると」
姫宮は眉を寄せ、首を何度も横に振った。
「かようなことを申してはおらぬ。望んではおらぬ。近衛中将はこの身に業を負わせるつもりか」
怒りを孕んだ声を張る。長らく姫宮の護衛として、この庭にいた右京亮でさえ聞いたことのない声である。
「我らは夷狄のように女将に害意するつもりはござらん。静かに暮らしたいだけ。害意も叛意もございません。どうか、住まうことをお許し願いたく」
「我は如何にすれば良い。主上に奏上を」
すると白髪の女房が、「いえ」と止めた。
「宮様から主上に奏上するのは畏れ多いことでございます」
しかし姫宮は己の扇を強く握り、苛立ちを隠せない。そして何かを思いついたように顔を上げ、「しばし待て」と言い残して御簾内に入った。再び姿を見せた時には、その手に書を携えていた。
「これを持て」
ずいと手を差し出す。手ずから夜叉に渡そうとするのを女房が止め、女房はそれを右京亮に手渡した。右京亮は恭しくそれを捧げ持ち、背後に控えている夜叉に渡した。宮は、夜叉の手にそれが渡ったのを見て頷く。
「今一度、都の者が無体を為すことがあらば、この荘園の主たる連翹宮が、そなたらの住まうことを許したと伝えよ」
夜叉は文を広げ、暫しそれを凝視してから、深々と頭を下げた。
「有難く、御礼申し上げます」
そこで啓吾の視界は途切れ、自らの身が右京亮から離れているのを感じた。
視界は真っ白い空間にある。さながら、絵巻の中を移動しているようだ。
しかしここまでの話で少し首を傾げる。
あの物語においては、鬼は連翹宮を襲い、武士である右京亮はそれを打ち払うという話だった。だが、今、啓吾が視たのは、まつろわぬ民である夜叉が、領主である連翹宮に、住処の安堵を求めている。右京亮はその仲介を担っていた。
もしも正周の説に従うならば、連翹宮は正周の祖であり、夜叉という男が、隠れ里の祖ということになる。そしてどういうわけか啓吾はこの物語の中で右京亮に憑いている。
「そもそも、若は今、何処にいるんだ……」
その姿を捜そうにも、その身は思うままにならない。
そして再び右京亮の身に戻るのを感じた。右京亮は松明を片手に連翹宮邸の庭を歩いていると、その足元に点々と血が滴っているのが分かる。
「……これは」
松明の灯りを先へと翳すと前栽の松の木の根元に、身を庇うように蹲る人影を見つけた。
「夜叉ではないか」
夜叉はゆっくりと顔を上げる。その面差しは窶れ疲れていたが、目は爛々と光る。獣のように怒りに震え、不意にこちらに向かって刃を向けた。右京亮は慌てて太刀を抜き放ち、それを撥ね除ける。
「どうしたというのだ」
右京亮の問いに、夜叉は肩で息をする。よく見ると、その右腕は深手を負って動かず、腐って腫れていた。
「腕をどうした」
右京亮の問いに、夜叉は薄らと笑う。
「連翹宮を殺す。仇を討つ」
「待て、何を……」
「宮から命じられたと、兵が里を襲ったのだ」
文を持って里に戻った夜叉は、荘園を預かる領主と話をするより先に、宮からの命を受けたという兵が、里を襲っていた。女子どもや老人までも手に掛け、住まいも焼かれ、山火事となった。
夜叉は何とか里の者たちを更なる山奥へと逃がしたものの、夜叉もまた腕を斬られ、追っ手が掛かった。
このまま死ぬくらいならばと、夜叉は都まで取って返して来たという。
「この腕は、既に刀を握ることは出来ぬ。されど、討たれた者たちの怨念を封じてある。俺を殺せば怨霊は放たれる」
せめても一矢報いて死ぬつもりらしい。
ゆらりと立ち上がり、自らの剣を手に持ち、身を引きずるように歩きだす。このままの姿で宮邸の庭に出れば、すぐさま衛士が夜叉を討つだろう。夜叉の右腕は、脈打つたびに赤黒紫と色が変わり、蠢く生き物のようにも見えた。
前に進もうとする夜叉の前に、右京亮は立ちはだかる。
「私は、宮様が幼い頃より衛士として邸にいる。稀ではあるが、お声を掛けていただき、お話をする誉にも与った。少なくとも、姫宮様が御自ら、兵を差し向けるなどあり得ない。それは分かるだろう」
「ならば誰が」
夜叉は怒りを滾らせる。その顔は血の気を帯びて赤くなり、首筋から腕へと伸びる入墨の蛇が、鎌首をもたげて来るようにさえ見えた。対峙する右京亮も怯むほどの怒気である。それでも右京亮は踏みとどまった。
「暫し……暫し待て。このまま邸内に入れば、忽ちそなたは死ぬことになる」
先日は、右京亮が根回しをし、宮と端近で言葉を交わすことが出来た。しかし、邸の庭には常に武士が控えており、不審な者がいればすぐさま射かけられ、斬りつけられる。ましてや、太刀を手にした傷だらけの入墨の男であれば、徒党を組んで狙われるのは明白だ。
「頼む。暫し……」
夜叉は怒りを滾らせつつも、じっと右京亮を見つめる。
「分かった。されど、あの月が中天に差し掛かるまで」
夜叉の指さす先には、十六夜の月がある。未だやや東にあるその月が中天に上がるまでは半刻ほど。
右京亮は身を翻して邸へと向かう。
庭を横切り、幾つかの生垣を越える。水干の裾を払い、辺りを見回す。東側にある対屋の奥まった部屋が宮の居室だ。衛士の武士たちの目を盗み、縁から中へと身を滑らせる。こんな風に邸内に入ったのは初めてだ。
御簾の向こうに、人の気配があった。
「宮様、右京亮でございます。三月ほど前に庭先にて、夜叉なる男をお引き合わせ申しました」
すると、「ああ、あの」と、承知した様子である。
「如何した」
「宮様はあの後、夜叉の里へ兵を遣わされましたか」
「何を申すか。さようなことをするはずもない。ただ主上にお目通りが叶った際、我が荘園の中に住まう者たちが安んじて暮らせるようにお願い申し上げた」
安んじて暮らす……
「それは、宮様にとっては夜叉たちの暮らしを守ることであられたやもしれません。されど主上にとっては、夜叉たちのような者を討つことと思召されたやも……里が、領主の兵によって再び襲われたそうでございます」
「何と……」
その時、わっという叫びにも似た声が上がり、争いが始まる気配がした。バタバタという慌ただしい足音と共に、衛士の一人が姿を見せる。
「宮様、妙な風体の男が剣を手にして、裏山におりましたので、捕縛しようとしたところ手向かい、この邸内に逃げ込みました」
そう言う衛士もまた斬りつけられて傷を負っている。荒々しい足音と、雄叫びにも似た声が響き、邸全体を揺るがすようだ。
夜叉が、やって来たのだ。怒り狂い、手向かいながらここまで来たとするならば、最早、説得も出来ない。右京亮は刀を抜き、身構える。
「今、入って来た男というのは、あの夜叉か」
「恐らく。こうなりましたら、ひとまず宮様はお逃げを……」
右京亮は宮を逃がそうとするが、宮は怯えている様子はない。連れ出そうとする右京亮の差し伸べた手を後目に、くるりと壁際に置かれた厨子に向かう。厨子の戸を開けると、そこには観音像があった。ふうっと一つ息をつくと、静かに祈りを唱えている。
「宮様」
それどころではない。そう言いたいのだが、宮は動かない。やがて愈々、争う声は近づいて来た。ここまで夜叉は衛士たちを斬って来たのだろう。となると、たとえ夜叉が悪人ではないことを知っていても、刃を交えるほかに術はない。
右京亮はそう思って、太刀の柄に手を掛けた。
バサリと御簾が上がり、目を血走らせた手負いの夜叉が入って来た。顔には返り血を浴び、髪を逆立てたその有様は、絵草紙に見る鬼の姿そのままである。
右京亮が宮を後ろに庇おうとすると、宮はついとそれを避け、夜叉と正面から向き合う。
「待て。話を聞こう」
柄を握る右京亮の手を押さえる。そして、夜叉の顔を真っ直ぐに見上げた。
「我は、そなたらの暮らしが穏やかなれと願ったのだ。しかし、主上がそなたらの討伐を命じるとは……」
「詫びられたとて、失われた者は戻らない」
絞り出すような苦しい声が漏れる。その間にも、次から次へと衛士は来る。宮が夜叉の間近にいるので、衛士たちは手を出すことができずに固まっている。
すると宮は自ら立ち上がり、衛士と夜叉の間に入り、夜叉をその背に庇った。
「これは我の客人故、そなたらは下がれ」
「しかし」
「下がれ」
その声の迫力に、戸惑いながら衛士は数歩後退り、その場に膝をついた。
宮は夜叉を引き入れて御簾を降ろす。そして改めて夜叉に向き直る。
「そなたらの里がかように荒らされたのは、我の本意ではない。かようなことが二度とないようにせねば……主上の御力を借りぬ。我は我のやり方でそなたらを護る」
言うが早いか、厨子に向かい、供えられた菊花の花弁を二枚とると、文机に向かう。
「オンロケイジンバラキリク……」
真言らしきものを唱えながら、紙に梵字を書いて、花弁を包んだ。そして二つの札をそれぞれ夜叉と右京亮に預けた。
「夜叉は元の山中へ戻り、不動明王を祀りなさい。右京亮は里から南東に下り、最初に出会う地蔵菩薩像にこの札を納めよ」
意味は分からない。だが、長らく祭祀に関わり、神仏に祈りを捧げて来た宮なりの方法なのだろう。
とはいえ、このままここから逃げれば、二人共に討たれることになりかねない。それを察した夜叉は、再び刃を宮に向けた。
「奴らを遠ざける為に、御前には裏手の山まで人質になってもらう」
すると宮は抗いもせず、自らの長袴の裾を指貫にすると、袿をたくし上げた。
「いざ、参ろう」
夜叉は宮を傷んだ右腕で羽交い絞めにして左手の太刀を突き付ける。しかし、右腕に力は入っていない。宮は引きずられるふりをしながら、夜叉の腕を掴んでいる。衛士たちは色めき立つ。
「待て。そなたらは参るな。右京亮だけついて参れ」
宮の命令に、衛士たちは渋々その場に膝をつく。
邸を出て、庭を横切り、山へと続く生垣を越える。松明もない山中を上がり、大きな楠の前まで来ると、夜叉は足を止めた。
「追っ手は来ないな」
震える声で確かめる。暗がりに目が慣れて来ると、少しだけそれぞれの顔が見える。
夜叉は、かつて見たことのあるおおらかさと逞しさを備えた穏やかな顔つきになっており、血濡れた己の身を顧みて、戸惑っているようにさえ見えた。片や宮は怯えているというよりも、慙愧の念を抱いているかに見える。そして、宮は夜叉の赤黒い腕に触れる。
「最早、手遅れやもしれぬ。それでもまだ、間に合うものならば、どうか我がそなたらの一助となれるよう、祈る」
その真摯な声に嘘はない。夜叉もまた、うん、と深く頷く。
「御身を危難に晒し、申し訳ない。ただ、我らの無念、恨みも分かって頂きたい」
すると、宮は手を合わせた。
〽木も草も 天に賜るものなれば
此処ぞ吾らの栖なるべし
微かな節をつけて歌う。
何のことか分からず、夜叉と右京亮は首を傾げると、宮は顔を上げて二人を見やる。
「かつて帝は、鬼を追いやるために、歌を詠まれたそうな。
木も草も吾大君の国なれば
いずくか鬼の栖なるべき
帝の下にまつろわぬ民には、住処すら与えぬという、酷な歌だと思っていた。故に我はそなたに、今の歌を授けたい。この地は天に賜りしもの。そこに住まうのは、我もそなたも右京亮も、何も変わることはない。そなたらが討たれて良いはずもない。いずれ、時が移ろえば、そなたらもまた、共に暮らせる日が来るであろう。それまで達者でいて欲しい。どうか我の護りの中にいておくれ」
夜叉は、暫しの沈黙の後に静かに頷いた。
「右京亮も、我の頼みを聞いておくれ」
「畏まりました」
二人は改めて宮に礼をすると、暗闇の中を走り出す。
それぞれが宮から託されたものが何であったのかはよく分からないままであった。
再び、絵巻が広げられるように、場面は移ろう。
夜叉を連れて連翹宮領の山中まで行く最中、右京亮の視界は靄のようなものに覆われ、耳の奥にはずっと耳鳴りが響いているようである。やがて靄だと思っていたものが人の形をしており、耳鳴りだと思っていたものが、何者かの囁く声だと次第に気付き始めた。
これまで見えていなかったはずのものが視え、聞こえなかったはずのものが聞こえる。そのことに驚き、怯えている。
すると夜叉もまた同じように、視界に映るものを払うように歩いている。
「そなたにも視えるのか」
そう問うと、夜叉は頷いた。
「これまでも、山中の神々の気配を感じ、それらに祈りを捧げて来たが、ここまで人の形をしているのは初めてだ」
そう言う夜叉の背後には、黒い巨大な影が立ち上っている。蠢くそれは熊が両手を広げた姿のように視え、右京亮は驚き怯えた。しかし夜叉もまた、右京亮の背後に何かを視ているらしい。
「お前も白い靄のような……人のようなものを背負っている」
啓吾にとってみると、それは今の啓吾と同じ視界だ。霊が視え、声が聞こえる。それ以前の右京亮にはなかったものが視えるようになったのだ。
するとはっきりと分かることがある。
夜叉が背負っている黒い巨大な影は、いつか破崩坊が背負っていたものにも似ている。やはりこの夜叉は、隠れ里の祖に当たるのだろう。
やがて辿り着いた連翹宮領の山中には、焼け落ちた家と、荒らされた畑地。そして既に白骨になりかかっている幼い子や女、老人たちの骸……惨憺たる有様であった。拳を握りながら前を歩く夜叉の背の黒い影は、怒りと共に赤黒い焔のように揺らめいている。
「無事でお帰り」
生き残った者たちは夜叉を出迎え、同時に右京亮に敵意を向ける。
「この者は、我らを助けてくれるから」
夜叉が彼らを宥めた。
二人はそれから宮の言う通り、不動明王の札を納める場所を探し、山中の開けた原に立つ大きな楠の洞に札を納めた。
「これを……一緒に置いておいてくれ」
右京亮は、旅の道中に手遊びに小刀で彫り上げた不動明王像を渡した。
「いずれ、名のある仏師に彫らせるが、一先ずは」
夜叉は黙ってそれを受け取り、札と共に洞に納めた。すると夜叉の肩から立ち上る黒い影は、不動明王の姿へと変化を遂げていく。
その影は、先ごろ、凛が背負っていた影の姿にも似ている。祈りによって形が与えられ、荒ぶる魂を鎮めることができるのかもしれない。
右京亮はそこで夜叉と別れ、宮に言われた通り、南東へと足を運ぶ。「最初に出会う地蔵菩薩」に向かって、道なき道を、高い草を太刀で切りながら進む。やがて道の先に小さな地蔵堂があった。
地蔵堂の扉を開けた時、そこにあったのは、まだ真新しい石仏の地蔵菩薩像であった。右京亮はその地蔵菩薩像に札を納め、祈りを捧げると、一路、都を目指して歩き始めた。
向かっている先は西である。
つまり、札を納めた地蔵堂は関東……今の東京ではないか、と啓吾は気付く。そしてその地蔵菩薩像の姿は啓吾の記憶の中にもあるように思えた。
連翹宮邸に辿り着くと、衛士たちが右京亮を出迎えた。
「あの夷狄を一人で追って行かれたきり、戻られぬので、御身を案じておりました」
衛士の一人に伴われながら、その後の顛末を聞く。
「右京亮様が夜叉を追って行かれた後、我らも後を追ったのです。しかし、荘園の領主に尋ねた道を行くのですが、どういうわけか何度、向かって行っても辿り着くことができず、まるで里ごとかき消えたような有様で……」
どうやら、宮が施した術が効いたのか。里は真に「隠れ里」となったようである。
連翹宮邸の庭先まで来た右京亮は、御簾の向こうにいる宮に向かい、深々と頭を下げた。
「夜叉を里まで送り届け、仰せの通りに不動明王を祀り、某は南東へ向かい、地蔵堂に宮の御札を納めて参りました」
そう言って顔を上げると、御簾の手前に、大きな二頭の犬が、こちらを睨んでいるのが視える。
「わ、犬」
思わず声に出してしまい、次いで、「御無礼を」と頭を下げた。
すると、宮が、御簾の内でふふふ、と笑う声がした。
「どうやら、我の力がそちらに移ったようだ」
「どういうことでございましょう」
「そなたの目には今、我の前にいる狛犬が視えたのであろう」
言われてみれば確かに、神社にいる狛犬のような姿をしている。
「これは真の犬ではない。我の護りよ。他にも、人ならざるもの……幽霊、妖怪、鬼……そうしたものが視え、騒がしかろう」
言い当てられたことに戸惑いつつも、右京亮はほうっと吐息した。
「己の気が触れたのかと……」
「それは、かつて我が視ていたものよ」
宮はそっと御簾を持ち上げ、端近に寄る。
「幼い時分から視えていた。故に、内々に陰陽師たちに様々な術を教わった。祓う力、視る力、聞く力……いずれも使って来たのだが、あの者の無念を知り、助けたいと願った。それはどうやら、己の力と引き換えとなったようだ。祓う力だけが残され、視る力と聞く力は弱まった。見慣れていたものや聞こえていたものがなくなると、こんなにも心細いものかと思う」
言葉に反して宮は悲しんでいないようだ。そして、安堵したように吐息する。
「何年かかるか分からぬが、あの者たちと我らと、共に笑い合える日が来ると良い」
宮の中には、夜叉たちを「夷狄」や「鬼」と恐れる心は微塵もない。
「怖くはないのですか」
右京亮が問うと、宮は笑った。
「真の鬼とは、あのようなものではない。心を持ち、涙し、怒るのは人だ。出自や見目は関係ない。どれほど位が高くとも、見目麗しくとも、悪鬼を憑けている者は、人を殺めることに躊躇いすらなく、己以外が傷つくことに痛みすら覚えぬものよ」
そしてさらりと扇を広げて天を仰ぐ。
「この天の下、共に生きられる日が来よう」
右京亮は、はい、と頷く。
夜叉とは命を懸けたやり取りをし、共に里までの旅をし、語らった。時が違い、立場が違えば、きっと友にもなれたであろう。そう思えばこそ、宮の言葉を信じたいと思った。
ぐらりと視界が歪んだ。
啓吾が目を開けると、辺りの風景が消え失せて、白い空間に立っている。そして目の前に見覚えのある人がいた。
「若、良かった、ここに居たんですね」
声を張り上げると、正周は驚いたように振り返った。
「啓吾君じゃないか。えっと……これは夢かな」
辺りを見回しながら呟く正周に、啓吾は首を横に振る。
「恐らくは我らは絵巻の中に入り込んでいるんです」
「なるほどねえ……道理で。私はつい先ごろまで連翹宮と共にいたようだ。君によく似た右京亮という男がいたんだ」
「え……僕は右京亮に憑いていたようです」
先ほどまで、目の前にいた年若い姫宮の後ろに、正周がいたらしい。膝から崩れるような脱力感を覚えたが、そうも言っていられない。
「そんなことより、ここから出ないといけません。方法を考えないと……」
「方法と言われてもねえ。さっぱりわからないし、もう少しこちらの世界で遊びたい気もするし……」
「そんなこと言っていると、体が死にますよ。ただでさえ、若が倒れたと言って大騒ぎになっているんですから」
「というと君も倒れているのでは」
言われてみれば確かにそうだ。二人揃って仲良く死んでしまいかねない。
「ともかく、出る方法ですよ。若様の身から、御門跡様が持って来られた十一面観音像に糸が伸び、その糸が絵巻の中に描かれた観音像に繋がっていたんです。それに引っ張られて入ってしまったような……」
探りながら話すと、正周は、ポンと手を打った。
「先ほど、連翹宮の視界からは、確かに光る糸が視えていた。なるほど、君が言っていたのはこういうことかと初めて合点したよ。糸を手繰る術はね、宮様の如く真言を唱える」
「真言、ですか」
確かに、宮は右京亮と夜叉に札を手渡す時に真言を唱えていた。
すると正周は啓吾に向かって手を差し伸べた。
「とりあえず、今は糸が視えないので、手を掴んでいてくれ。いくよ……オンマカキャロニキャソワカ……」
すると啓吾の視界はぐにゃりと歪み、眩い光に包まれた。眩しさに目を細め、再びゆっくりと開くと、聞きなれた声がする。
「正周さん、正周さん」
声はすぐ傍でしている。そして啓吾は自らが床に転がっていることに気付いた。どうして床に転がされているのか分からず、身を起こす。
「啓吾さん、奥様、啓吾さんも目覚めましたよ」
声はすぐそばで聞こえた。屈みこんで啓吾を覗いているのは、女中の芳である。半身を起こして見ると、正周と開け放たれた十一面観音の厨子と、広がる絵巻のちょうど真ん中に己が倒れていたことに気付く。お陰で正周に釣られて絵巻に入ってしまったのだろう。
「ごめんなさいね、運ぼうと思ったんですけど、耕三が抱え上げても、まるで紐でもくっついているかのように動かなくて……」
部屋の隅にいる耕三が、面目ない、と肩を竦める。
「いえ、大丈夫です。ところで若は……」
ゆっくりと立ち上がり、寝台に横たわる正周を見る。正周は目を開けて半身を起こした状態で、真紀子夫人に泣きながら抱き着かれていた。
随分と長い時間が経っているように感じたが、どうやら倒れてから一昼夜ほどであったのか。窓の外では夜が白々と明け始めているところであった。
「ともかくも、若が戻れて良かったです」
啓吾が言うと、真紀子はくるりとこちらを向いた。
「啓吾さん。何があったか分からないけれど、貴方のお陰なのかもしれない。ありがとう」
手を掴み、ぶんぶんと振る。啓吾は、はあ、と苦笑すると、正周が腑に落ちない顔で首を傾げる。
「いや、むしろ戻れたのは私のお陰ですよ、お母様。啓吾君は何も……」
「お黙りなさい。貴方は大概、余計なことをして心配をかけて。役に立てとは言いませんから、余計なことをなさいますな」
なかなかな言いようではあるが、心配を拗らしているのも分かるだけに、正周も言い返す言葉もないようで、ぐっと唇を引き結ぶ。
「正周が目を覚ましたのか」
と、正周の父である子爵や兄の正幸らも駆け付けた。
啓吾は、改めて広げられたままの絵巻を見やる。その視線に気付いたらしい寿照尼が啓吾の傍に立った。
「これを、畳んだらいかん気がして……」
「ありがとうございます。多分、そうですね」
やはり自分たちは、つい先ほどまで、絵巻の中にいたらしい。
だが、視たものは、以前、正周から聞いていた物語とは少し違っていた。正周もそのことに気付いているらしく、話をしたいのだろう。ちらちらとこちらを見ている。しかし今は家族や使用人たちに囲まれ、叱られたり泣かれたりと忙しい。目を白黒させながら謝る正周を見て、啓吾は可笑しくなった。そして同時に、笑えることに安堵していた。