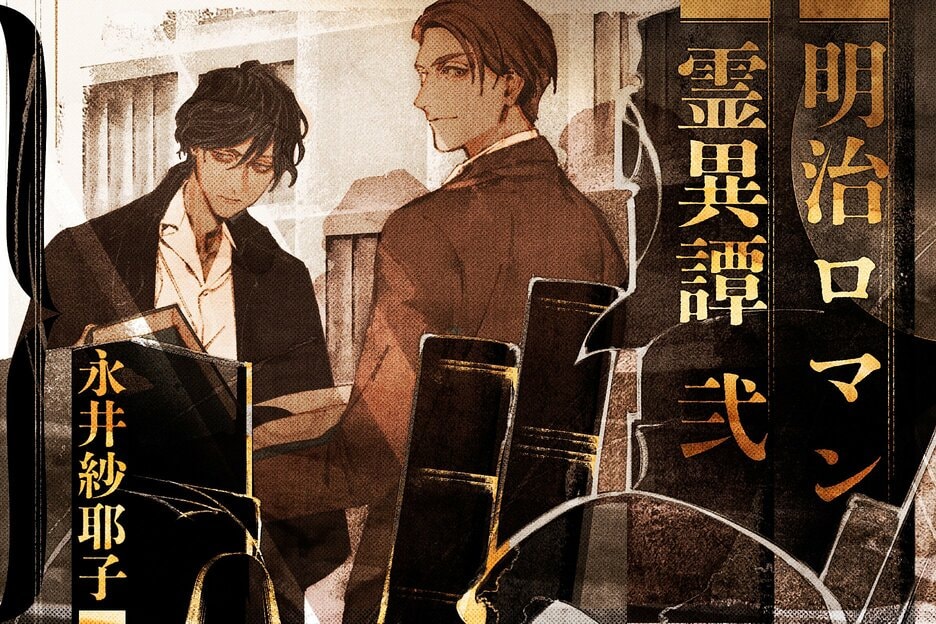第四話 センチメントな再会
*
峯斎が生まれたのは山深い里である。物心ついた時には霊が視え、声が聞こえた。そして里の者の多くが、同じような力を持っていたので、己が特異な力を持っているとは思っていなかった。
十歳になったある日、里長から呼ばれた。
「此度は、そなたに決まった」
数年に一度、里から一人、能力の高い者が江戸へ養子に出ることが決まっていた。十年前、同じ里から江戸に出た人は、大層な出世をしており、そのおかげで里は潤ったという話も聞いた。
「里の外の人々は、我らが視えるものが視えず、声も聞こえぬ。力を活かして、世のために役立てよ」
その言葉を聞いた時、峯斎は高揚した。自らの力が世の役に立つことは、子ども心に誇らしかった。
山を越えて江戸に出た峯斎は、里に縁のある武家の養子として育てられることになった。武士としての行儀作法、剣術と読書も習い、次第に面白いと感じることは増した。
ただ、江戸は里とは違い、霊の数も雑音も多い。慣れない時は、市中で悪霊を見かけて逃げ帰ったり、夜な夜な霊の声に起こされたりと、疲労困憊していた。養父となった六十歳になる老爺もまた、里の出であったので、「上手くやり過ごせ」と、自らの周りに結界を張る術を教えてくれた。「そなたの力は確かなものだ」と認めてくれており、「いずれはお上の役に立つ」と褒められた。十五で元服をすると、「これよりは、儂の後を継ぎ、天文方に仕えよ」と、役目をもらい、気が引き締まる思いであった。
幕府の天文方は、星の巡りや時、測量などのほか、異国の文書の翻訳も行う役所である。そこは遥か昔の公家の頃から星や暦を司って来た陰陽師の家の者が多くいた。峯斎は天文方の読む暦や、彼らの言葉を聞き、内々に将軍家の側用人に伝える役目を負っていた。
「そなたの真の役目は、天文方にあって天文方にあらず」
将軍家をはじめ幕閣たちは、陰陽師の言葉の真偽が分からない。故に、その真偽を確かめる為の隠密。それが峯斎に与えられた役目であった。
天文方に仕える仲間のことを裏切るようで心苦しくもあったが、「そなたにしか出来ぬ」と言われると、重責と共に嬉しくもあった。
当時、幕府は異国船の来航に加え、各藩が反旗を翻したことで、不安を抱えていた。様々な情報を精査すると共に、太古より続く陰陽師の話も聞いていた。峯斎が視る限り、天文方にいる陰陽師たちは相応に力を持っていた。星読みとしての力や知識は峯斎をはるかに凌ぎ、祈祷を行えば、その場の気の流れを変える力を持つ。峯斎もまたその末端に仕えながら、学ぶことが多かった。
天文方での日々は充実していたのだが、むしろ幕閣たちとのやり取りは苦痛であった。
「そなたにはどう見えた。あの者たちは嘘をついているのではないか」
「一体、何が起きているのだ。何か隠しているのではないか」
堂々巡りの問いに、峯斎はすっかり疲弊していた。
そんなある日、天文方の役人に呼び止められた。
「数年に一度、そなたのような者がここに遣わされてくる。さりとてこちらも視える故、そなたが幕閣たちの命により、我らを探っていることも分かる。混沌とした世情で、そなたの背負う雑念は、我ら天文方にとって好ましくない」
それならばいっそ、隠密としての役目を解いて、天文方として仕えたい。そう願っていたのだが、天文方の中には峯斎への不信があり、結局、役目を解かれることになった。
「天文方はもうよい。そなたは、霊の声が聞こえるのだとか。さすれば、大権現様の御声を我らに聞かせよ」
幕閣からの命により、今度は寺社奉行所に出入りし、徳川菩提寺の増上寺、寛永寺を日参することとなった。
気をとり直して役目を全うしようと思うのだが、しかし既に大権現たる徳川家康が世を去って、二百五十年余り。昨日今日亡くなった死霊の声を聞くのとはわけが違う。霊廟の前に座って手を合わせていても、聞こえて来るのは、市中で聞こえる怨嗟の声。一揆や打ちこわしが起こると共に、窃盗や人斬りも増えている。
「助けてくれ」「お上が悪い」「世が悪い」「隣の奴が憎い」「金がない」「米を寄越せ」
繰り返される声は、次第に峯斎の心身を蝕んでいく。
青ざめた顔で寛永寺の境内を横切って行くと、不意に強い眩暈と頭痛を覚えた。その時、すれ違った僧侶に声を掛けられた。
「もし、どうなさった」
年のころは、峯斎と同じくらい、二十代後半であろうか。
「少々、眩暈が」
僧侶はすぐさま庫裏に招き入れ、湯呑に水を入れて差し出した。
「お疲れなのでしょう。少しこちらで休まれよ」
案内をしてくれたのは、啓照という名の僧侶であった。雑念のない静かな佇まいで、峯斎はその傍らでほっと息をつくことが出来た。眩暈や頭痛も落ち着いてくる。
「このところ、日参されていますな」
峯斎は、はあ、と吐息した。
「祖霊の声を聞けと命じられております」
すると啓照はひどく驚いた様子であった。
「さような無茶を……」
「はい。流石に百年以上前の御方ともなりますと、聞こうにも聞こえませぬ。却って、市中の怨嗟の声ばかりが聞こえて……」
弱音を吐くと、啓照は怪訝そうに峯斎を見た。
「いや、話には聞いたことがありますが、その、そこもとは霊が視えたり、聞こえたりなさるのか。拙僧はそのような力はない故、俄かには信じがたいが……それはご苦労を」
いつもならば、「信じられない」と言われると腹が立つものだが、この啓照の言葉は何故かすとんと受け入れることが出来た。峯斎は、自らが視えるもの、聞こえるもの、これまでの出来事などを少し話して聞かせた。すると啓照は、ふむ、と納得できぬ様子で首を傾げた。
「己の願いが聞こえることもある。視えることもある。それは飽くまで啓示に過ぎないのではないかと、思ってしまうのだが……なるほど、そこもとの話は真に聞こえるなあ」
啓照の素直な感想は、日々、役人たちに「聞こえるはずなのに、視えるはずなのに」と問い詰められていた当時の峯斎にとって、却って肩の力が抜けた。「忝い」と礼を述べると、啓照ははて、と首を傾げていた。
以来、寛永寺を訪ねると、時折、顔を合わせることがあった。しかし相変わらず峯斎の耳に廟からの声は聞こえない。
そんなことが半年も続いたある時、市中に出た峯斎は、町の中に人が少なく、ひどく静かだと感じた。不思議に思っていたのだが、それは峯斎が視る力、聞く力を失ったからだと気付いた。
驚き、役人にその旨を伝えると、
「役立たずめが」
あしざまに言われ、峯斎は放逐されることとなった。
己がもっと絶望するかと思ったが、却って役目から解放されて心が軽くなったことに驚いた。ただ去る前に啓照にだけは礼を言おうと、寛永寺を訪れた。境内を行く啓照の姿を見つけて呼び止めた。
「どうにも目も耳も悪くなったようで、御役御免になりました。啓照様にはお世話になりました」
「それは……残念ではございますが、どうぞ、体を労わって下さい」
峯斎は、はい、と頷いて啓照を見た。目が合った瞬間、これまで視えていなかった霊の姿が、啓照の背後に視えた。
そこにいたのは、一人の仏師のような男である。それは啓照の先祖に当たるのか、或いは前世に当たるのか。だが、峯斎はその仏師が彫っている不動明王の顔に見覚えがあった。それは幼い頃から、隠れ里の御堂の中で見上げていたものと同じであったのだ。
「御坊と私とは御縁があるようです」
数百年前、幕府の開闢より以前から、一族はあの里に住んでいると聞く。その頃から伝わる像が、目の前の啓照との縁を繋いでいるのだと思った。
「貴殿の目には如何なものが視えているのか存ぜぬが、縁は縁。有難いこと」
啓照は合掌して頭を下げる。次の瞬間、峯斎の目には、啓照の背後にまた別の風景が視えてきた。
今、啓照の背後に広がっている寛永寺から火の手が上がり、多くの人々が逃げ惑う。次いで境内には骸が積み上げられ、さながら音に聞く戦場のような有様だ。その只中に啓照は茫然と立ち尽くしている。
呆気に取られて峯斎が暫し瞬くと、今度は明るく温かい場所で、赤子を抱いて微笑んでいる啓照の姿が視えた。
これは恐らく、啓照の未来だ。
「今後、御寺は大変なことになります。しかし貴方はそれを越え、明るい日々を迎えられる。故に、絶望に沈まずにいらして欲しい」
そう伝えた。すると啓照は半信半疑と言った様子で、曖昧に頷いた。
峯斎はその後、総ての役目を降りて里に帰ることとなった。自らに失望してもいたが、一方で重責から解き放たれた安堵もあった。
山深い隠れ里に帰ってみると、父祖がこの地を選んだ理由が分かる気がした。人里から離れているからこそ、人々の怨嗟の声も聞こえず、霊が迷い出ることもない。訪れるのは動物たちの霊や木霊の放つ微かな気配だけ。日々を過ごすうちに、少しずつ峯斎はかつての感覚を取り戻していった。
再び視る力、聞く力が増してくると、人々の争いと、悲しみの声が山を越えて届くようになっていた。「どうせ、何も出来はしない」という思いと、「力が戻った今ならば何か出来るかもしれない」という思いがせめぎ合っていたが、峯斎は意を決して、再び里を離れて江戸へと向かうことにした。
辿り着いた江戸で目にしたのは、燃え盛る上野の山と、逃げ惑う人々の群れだった。あの時、啓照の背後に視た戦場の景色が広がっており、無力さに打ちひしがれた。暫く、江戸市中を亡霊のように彷徨っていたのだが、ある時、かつて共に天文方にいた男に声を掛けられた。
「覚えておられるか。いつぞやそなたに、我が子が産まれることを言い当てられたことがあった」
「そんなこともありましたなあ」
懐かしい記憶が蘇る。
「すまぬが、占ってはもらえぬか」
男は元々、天文方の蕃書調所にいて、翻訳を得意としていたため、官軍が立ち上げる新政府に招かれたのだという。
「そうは申しましても……」
峯斎は、いわゆる易者ではない。しかし時折、目の前の人の周りにいる霊たちの声や、まつわる縁の糸が視えることがある。それによって彼らの行く末が微かに視えるので、伝えているに過ぎない。とはいえ、無下に断ることもできず、男をじっと見つめた。
男の周りには縁の糸が絡んでいるが、そのうちのいくつかは既に切れている。新たに結ばれているものは、すっとまっすぐある屋敷に向かって伸びていた。それが、薩長の重鎮たちが住まう屋敷であることを峯斎は知っていた。
「既に、官軍との切れぬ縁があるご様子。行く末までは存じませんが、最早、後戻りはできますまい」
男は、旧幕への忠義と、新たな役目への想いとのはざまで揺れていたらしい。しかし、男は峯斎の言葉を聞いて、「分かった」と、頷いた。すると男を取り巻く糸の何本かは、その瞬間に消えてしまった。それは恐らく、男が切れずにいた古い義理であったのかもしれない。
その様を見た峯斎は、愈々、幕府が瓦解して新たな時代が訪れるのだと分かった。隠れ里から徳川に登用されることを、この上ない誉だと思っていたが、最早それは意味を為さない。ただ、里に送る禄については考えねばならない。
一町人として生きようとする中で、途方に暮れていた。その頃、同じく役目を失い、江戸城から追い出された奥女中の一人と夫婦となった。行くあてもなかったのだが、御用商人が「旧幕にお仕えの方ならば」と、下町の長屋を融通してくれた。峯斎は物売りをして、妻は女筆指南などをしていたのだが、それだけではとても暮らしが賄えない。
そんな時、あの元天文方の男からの紹介で、「占って欲しい」という人が訪ねて来た。易者の真似事をしたところ、その人物が新興の実業家だったこともあり、大層な謝礼を受け取った。峯斎は当初、戸惑いを覚えた。「占いは売らない」と、同胞たちは言う。それは、当たる当たらぬにかかわらず金になるものの、一方では深い恨みを買うこともあるからだという。しかし、激動する時代の狭間にあって、峯斎にとって唯一の生計を立てる術でもあった。折しも、妻が娘を産んだばかり。
「背に腹は代えられぬ。しかも、こんな路地裏の長屋の小さな易者など、評判にもなるまい」
占いを生業として、長屋の戸に「易」と看板を立てた。こうして町人として生きて行こうと思っていたのだが、時代は又もうねり始めた。「天社禁止令」なるものが新政府によって発せられたのだ。
神仏分離令によって、僧侶たちが寺を追われた。そこへ、天社禁止令によって、陰陽師や易者たちが罰せられ、修験宗廃止令によって山伏たちが山を下りた。
峯斎や、里の同胞たちのような「視える」「聞こえる」者たちは、一斉に「あってはならぬ」存在へと追いやられることになった。
よく当たる易者として、ささやかな評判を集め始めていた峯斎は、文明開化の前で異端となった。
「一先ず、そなたらは逃げよ」
一人娘と妻を、隠れ里へ送ることにした。
そのまま自らも里へ戻ることも考えたが、里は山深く、作物が豊富にとれるわけではない。他から仕入れるには「金」が要る。それを稼ぐのが、里を出た者の務めであった。
「あそこは、不動明王の護りがある故、安心して暮らせる。必ず、便りを出すし、金も送るから」
幼い娘と離れることは辛かったし、妻に不慣れな暮らしをさせることは心苦しかった。それでも、東京の暮らしが落ち着くまではと送り出したのだ。そして、三月に一度は里の者に文と稼いだ金を預け、妻子の消息を聞いて土産を託す。
そうして五年余りが過ぎた頃、かつて寛永寺にいた僧、啓照殿が訪ねて来た。
啓照は還俗して、今は一町人として暮らしていた。神仏分離令で職を失くした僧たちと共に、小さな書店を営んでいた。峯斎と同じく妻を迎え、二人の子がいるという。峯斎が視た通りの明るい未来に、ほっとしていたのだが、啓照は苦い顔で頭を下げた。
「私の息子と娘は、そこもとと同じようなものが視えているらしい」
物心ついた時から、何もいない空間に向かって息子は話しかけていた。娘もまた、通りですれ違った老婆の傍らに、「男の人がいる」と言い出した。よくよく拙い子の話を聞くと、それが老婆の先だった夫であったことがあった。
「これまで峯斎殿の言い分を疑っていた。しかし、そうした者がいるということを、身をもって知った。さぞやご苦労があったことと存ずる」
啓照の真摯な言葉は、峯斎にとって胸に沁みるものがあった。
「出来れば、子らに会って欲しい」
啓照は、子らの言うことが分からぬこともあり、峯斎に教えて欲しいようだった。峯斎は幼い二人の息子と娘に会ってみると、確かに二人共に峯斎と同じように霊が視え、その声が聞こえている。
「並々ならぬ力をお持ちだ。以前であれば、寺なり、修験道なりで、修行をなさるがよろしいのだが……」
時節柄、余りそうした話を大っぴらにはできない。ましてや、啓照も峯斎も旧幕の者である。だが、廃仏毀釈の嵐が下火になり、寺が落ち着き始めた頃、啓照は長男を寺に修行にやることに決めたと聞いた。それから暫くは互いに会うこともなくなっていた。
「……さてと……ここまで話すと、少しは分かるであろう」
峯斎は一つ息をついてから、探るように啓吾の顔を見た。
啓吾は峯斎の話を聞いているうちに、脳裏に幾つかの見知った顔が浮かんでいる。膝の上に置いた手をぐっと握り、峯斎を見据えた。
「修行に出た啓照僧都の長男とは、僕の伯父、敬円のことでしょうか」
峯斎は、うむ、と深く頷いた。
傍らで話を聞いていた正周は、なるほど、と手を打った。
「では、その啓照僧都は、啓吾君のお祖父様ということか」
啓吾が母に聞いた話では、祖父は母が幼い頃から、かつての同胞である僧侶たちの元を訪ね歩き、時に施しをして回っていた。お陰で早々に本屋は潰れ、主な生計は母の裁縫の稼ぎであったらしい。時折、ひょっこりと帰って来る父親のことを、母、幾は苦々しく思っていたという。
啓吾は祖父のことは記憶にない。
祖父が行方を晦ませたのは、啓吾が三つくらいの頃のこと。母と里帰りをしていた時、「行かねばならぬところがある」と、いつものように出かけようとした。母はその時、嫌な予感がしたので、祖父のことを止めたらしい。しかし、その手を振り払うようにして出て行ったという。
「父様は元より、視える者を疎んじていらした。幼い啓吾も又、私や兄さんと同じように霊が視えると分かって、眉を寄せていらした。そして、不意に出て行かれた。私たちを捨てたのですよ」
啓吾は物心ついてから、母が祖母に向かって泣いているのを聞いた。以来、啓吾にとって祖父は、己を疎んじた人という印象が拭えなかった。
しかし祖母は「お前のお祖父様は立派な方だった。だから、大事な御役目を果たす為にいらしたのよ」と啓吾には言い聞かせていた。母の言葉と祖母の言葉、いずれを信じればいいのか分からなかった。
やがて祖母を見送った時、母は祖母の枕辺で泣きながら、「生きているなら帰って来て。死んでいるなら母様を迎えに来て」と叫んだ。しかし、啓吾の目にも、母や伯父の目にも、祖父の姿は視えなかった。遂に、母は「どうして来ないの」と怒っていたのだ。
啓吾も未だかつて祖父の霊を視たことはなかった。だから死んでおらず、ただ母や伯父、祖母を捨てた人なのだと思っていた。
「もしやその啓照という僧が、今、ここにいる……三鈷剣に憑いている方なのですか」
恐る恐る問いかけると、峯斎は、うむ、と頷いた。
「死んだ後に、この剣に囚われていたというのですか」
峯斎は、ついと座布団を降り、啓吾に向かって深く頭を垂れた。
「儂も此度、この剣を手にして初めて、啓照殿がいることに気付いた。そしてそなたと啓照殿との縁も、初めて知った。啓照殿が囚われたのも、儂のせいなのだ。申し訳ない……」
啓吾は、何を詫びられているのかすら分からず、正周を見やる。正周は啓吾の想いを汲んで身を乗り出す。
「峯斎先生、まずはお手をお上げください。この視えぬ私にもわかるように、話して頂けませんか」
峯斎は、ゆっくりと顔を上げると、自らの膝の上で両手を合わせた。
「世の中が不穏になったのは、今から二十年余り前のこと……」
明治も二十年を迎えようとしていた。
西南戦争に続き、秩父や大阪で立て続き大きな内乱が起こった。平定するために、兵力と金がかかっていた。しかも、それらの騒動の裏には、「自由民権派」の暗躍があったとか、はたまた「旧幕の生き残り」の思惑があったとか、嘘か真か分からぬ噂が漂っていた。
幸か不幸か、混乱する時代では、易者としての仕事は絶えることはなかった。露見すれば囚われかねないが、役人の中にも顧客を抱えることで、辛くも生き延びていた。
「ところで、旧幕が抱えていた御宝のことを知っているか」
付き合いのある役人から問いかけられた。そんなものの話は聞いたことがない。しかし、噂によると旧幕の書物に「稀なる宝」の在処が記されており、宝が隠されている里を見つけたのだと、手柄顔で言っている侠客崩れの男がいるという。
「かような胡乱な話、聞いたこともない」
自らも胡乱な易者になり果てていたが、その侠客崩れの話は明らかに怪しい。しかし時代の混乱の中で、そんな話でも、己の力に変えたいという欲に塗れた輩は多かった。
その筆頭であった申岡は、新政府の重鎮たちにすり寄った。その中の一人で勲功華族となっていた雉尾は「稀なる宝」に関心を示した。それをいいことに申岡は更に言い募る。
「連中は戸籍にすら名を記さぬ不穏分子。ならば、情け容赦を掛ける必要もありますまい」
そして「鬼やらい」と称して里を襲撃したのだ。
峯斎は噂を聞いていたものの、まさか己の里であるとは思いもしなかった。
「我が里には、護りがあると信じていた……それが、どういうわけか失われていることに気付いておらなんだ。そのことを知ったのは、一年半も経ってからのこと。里の同胞の一人、岩斎が、這う這うの体で逃げて来たのだ」
深夜、激しく戸を叩く音がして、慌てて出迎えると、片眼を失った岩斎がいた。
「里が襲われた」
話を聞いても、何が起きたのか分からなかった。やがて、それが申岡たちによる襲撃であり、「稀なる宝」を持つ隠れ里が自らの里であることを初めて知った。
「御妻女は、御息女を庇い、命を落とされた。御息女は何とか里から逃がしたが……」
十六になっていた娘と最後に会ったのは、二年も前に里に帰った時のこと。遠からず、嫁入りの話を考えねば……などと言っていた。妻も里での暮らしを「悪くない」と笑っていた。つい先日のことのように思い出されるのに、それらが襲われたと言われても、真のこととは信じられない。
「待て、待ってくれ」
峯斎は自らの身が震えるのを感じながら、手を合わせて里の様子を視ようとした。しかし、靄がかかったようにまるで視えない。己の視る力が、かつてほどの威力を持たないことに改めて気づく。市中で占いなんぞをして、人の欲得に塗れていたから、いざと言う時に役に立たないのだと、自らを責めた。
ともかくも怪我を負った岩斎を介抱しながら、娘の行方を捜す術を考えていた。だが、ほどなくして警察が、山中から東京に逃げた「不穏分子」を捜していることを知った。
「あいつらは、この俺を追っているんです」
「お前のことは渡さん」
「しかし、庇えば峯斎様も咎められます」
峯斎はそれでも首を横に振った。
これまで、里を出て幕府に仕えていた己を慕い、敬ってくれていた里の人々を守ることもできず、この上、岩斎をも見捨てれば、いよいよ己を許せなくなる。
「では、逃げる為の御足だけ下さい。そして、俺のことは知らぬ存ぜぬで通して下さい」
峯斎は岩斎に金を握らせて逃がした。警察が乗り込んで来たのは、その直後であった。
「不穏分子が逃げ込んだそうだな」
散々、家探しをされた上に、峯斎も捕縛された。
当時、内乱が相次いでいたこともあり、警察は拷問さえも厭わなかった。「仲間は何処だ」「お前も民権の一味か」「旧幕の者か」と問い詰められた。そもそも隠れ里の者たちを「不穏分子」と呼ぶのが間違いだ。不穏なのはむしろ、襲撃をした申岡らの方である。しかし、そんな言葉が届くはずもない。
峯斎は、岩斎が逃げる時間を稼ぐだけ稼いでから、占いの顧客の一人である政府の重鎮の名を出して、釈放された。
既に三月の歳月が経っており、暫くの間は歩くこともままならぬほど、あちこちの骨が折れていた。何とかして、逃げた娘の行方を捜したいと思うのだが、今は身動きがとれぬ。
その時ふと、啓照のことが脳裏を過った。
啓照が、寛永寺や増上寺から去った僧侶たちの元を訪ね歩いていることは、以前から聞いていた。もしや、娘がそうした寺を訪ねることがあるかもしれない。そう思い、啓照に宛てて手紙を書いた。すると啓照からは、「相分かった」という、簡素な手紙が届いた。
それから一月余りが経ち、ようやく身動きが取れるようになったところで、啓照の家を訪ねた。既に書店は潰れていて、「繕い物承り」という看板が掛かる簡素な長屋住まいであった。
妻が顔を出し、峯斎を出迎えた。
「夫は、貴方様からのお手紙を頂戴して間もなく、旅立ちました。お里が大変なことになられたと……大層、嘆いており、他人事とは思えぬと申しておりました」
峯斎の里にいた「視える」者たちは、旧幕にとって「稀なる宝」であった。しかし、新政府の一部の者にとっては、「鬼」になった。その者たちが襲撃されたと知った啓照は、自らの子らのことを思ったらしい。
「これを、貴方様に」
そう言って残された手紙には、啓照の想いが綴られていた。
「権力を欲する無法者は、指さす敵を欲しがる。それは、古今東西、変わることがないようだ。此度は峯斎殿の同胞であったが、次に鬼と呼ばれるのは、我らの子かもしれぬ。このような暴挙を見過ごしてはならぬ」
啓照の熱く真っ直ぐな想いに、峯斎は涙が零れた。「稀なる宝」を賜ったはずの人生が、巡り巡って鬼と呼ばれ、日陰を這うように生きている。しかしそのことに、怒りを覚えてくれる啓照の存在が、峯斎には頼もしかった。
峯斎もまた、身を引きずるように旅に出た。啓照の足跡を辿っていたのだが、なかなか巡り合うことができない。ようやく娘の消息を掴んだ時には、既に二年の歳月が過ぎていた。しかし、その娘は既に亡くなっていた。悲しみに打ちひしがれていたのだが、娘の終の棲家であった宿場の女将が教えてくれた。
「この方には幼い娘さんがありましてね。その子を旅の僧が連れていかれましたよ。もしもこの人の父親がここに来られたら、渡して欲しいと」
文を手渡された。
そこに書かれていた次第によれば、啓照が宿に着いた時には、娘は既に病床にあったという。共に里を逃げた同郷の男との間に子を授かったが、男の方は申岡らによって既に殺されたらしい。奴らは未だに「宝」を探してもいるが、同時にあの「鬼やらい」を見た者を片付けることにも固執している。身の危険があるので、この子を連れて逃げる……と、記されていた。
峯斎は宿場町から街道を辿って行ったが、二人の足取りは山間部の宿場町で途絶えた。
「旅の老僧は死んで、弔いは終わっていた」
聞けば、夜半に夜盗が入り、僧を殺して荷を奪って行ったという。幼子は葛籠の中に入れられて無事であったが、辺りは血の海だったらしい。
「これが、遺品です」
残されていた遺品の中に、古びた寛永寺の印のついた経典があり、啓照の名が記されていた。殺されたのは啓照であることは間違いなかった。
「何と言うことを」
己の頼みを聞き入れたばかりに、啓照は命を落とした。詫びても詫びきれない。そう思って、峯斎はその場で手を合わせた。霊を呼んで、話を聞こうと思ったのだ。しかし、祈れども祈れども、啓照の霊は姿を見せない。
峯斎はその頃、聞く力の衰えを感じていたが、視る力は未だあるはずだった。その地に留まり祈っても、精進潔斎して籠っても、まるで霊を視ることができない。
「霊ごと消し飛ぶ何かがあったのか……そう思うと、申し訳なさに居た堪れなかった」
それに、孫娘と思われる少女の行方も分からない。宿場の女は「東京の女衒が連れて行った」と言うので、何度か吉原にも足を運んだが、どれがその娘かも分からない。恐らく、啓照によって施された「護り」が強すぎたからだと、今となっては分かる。しかし当時は何もかもが恨めしく思え、生きていることが空しくなった。それでも、いつか孫娘に再会できるかもしれないという希望もあり、また、同胞たちの供養をせねばならぬという思いもあった。
「お前さん方と会ったのは、そんな最中……ぼろ長屋でふて寝したまま数年が過ぎた頃だ」
初めて啓吾と会った時、啓吾と己の間に、細い糸が見えた。それは何処か遠くを巡り巡って繋がっている縁であると思っていた。
「まさか、啓照殿の孫であったとは……」
峯斎は語り終えたところで、ほうっと深く吐息した。