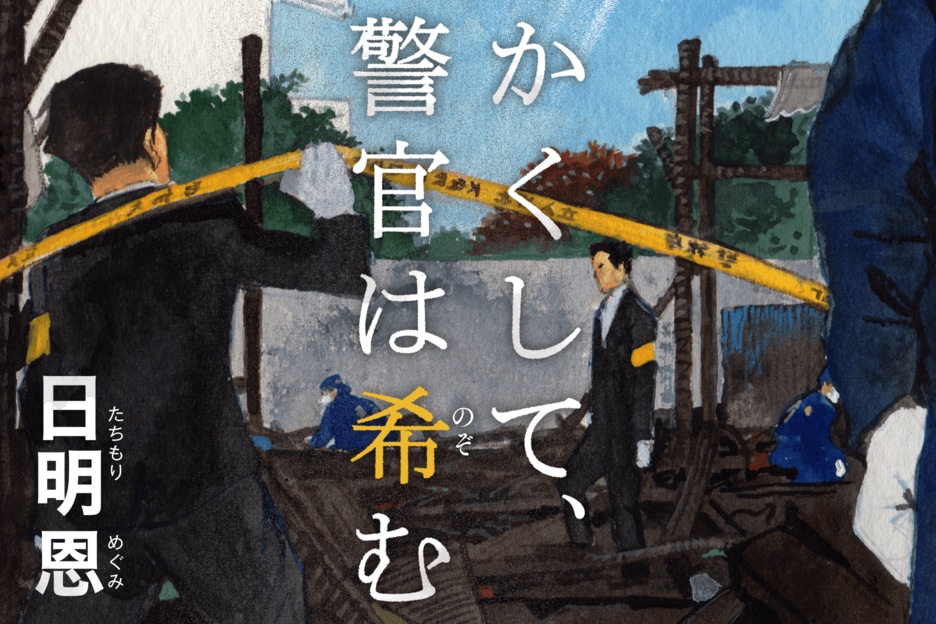「宇佐見君ではないですが、僕もやはり、すっきりしていません」
神妙な声で潮崎が言った。
「栗林も佳須美さんも、なんでこんなことになってしまったんだろうって、何度も考えているのですが、どれだけ考えても答えが出てこないんです」
潮崎は完全に食べるのを止めている。
「栗林さんを踏みとどまらせることは出来なかったのか。佳須美さんがこんなことにならずに済むには、どうしたらよかったのか」
柳原は栗林の動機を、「乱暴にまとめれば貧困からのストレスと、自分よりも良い暮らしをしている人たちへの嫉妬だ」と、言っていた。西田佳須美は家庭内の居場所のなさからの寂しさと、石原進と出会ったことで、道を踏み外してしまった。
「僕が近くにいたら、何か出来たのだろうかと、ずっと考えているんです。法を破るのは罪で悪いことだからしてはいけない。これが最適なケースもありますが、違うと思うんですよ、今回は。――強いていうのなら、そんなことしなくてもいいんじゃないの? ではないかなと思ったんです。でもそれって、現状でよしと思えばいい。それで我慢をして、悪いことはするなと言っているように思えて……」
そこで言葉を切ると、潮崎はうつむいて深く息を吐いた。頭を少し上げはしたが、視線は何もない机の上に向けたままで、また話し始める。
「足るを知る者は富むという言葉があります。これは、老子の言葉が語源の慣用句で、
人間の欲望には限りがないが、欲深くならずに分相応のところで満足することを知っていれば、精神的には豊か、つまり心が富むこととなり、幸福だ、という意味とされています。正しいと僕は思います。そうであれば、素晴らしいとも。――でも、そう思えるのは僕の現状が辛く困っていないからかもしれない」
潮崎は、閉じた膝の上で両手を握りしめていた。
「栗林は経済的に苦しい生活を送っていた。補うために働きづめになるしかなかった。まじめに身を粉にして働いて、学業も頑張っていた。そんな歯を食いしばるような生活が続く日々のなか、苦労せずに大学生活を送る学友たちや、まだ使える高価なものを平然と捨てる富んだ人たちを目の当たりにしているうちに、心が歪んでしまったんでしょう。どうして自分ばかりがと、悔しさややるせなさが募り、それが怒りに変わって衝動を抑えきれなくなって放火をした」
潮崎はそこでまた一つ、長い息を吐いた。
潮崎の語った内容は、栗林の供述調書の証言を要約したかのようだ。本来ならば、捜査本部員以外が見ることなど出来ない。だが潮崎ならば、あの手この手を使ってそれくらいは軽くこなす。しかも今回は、小津管理官から直々にメンズコンセプトカフェの洗い出しを依頼されていたのだから、とうぜんの権利として入手したに違いない。
「そんな彼に、そんなことはしなくてもいいんじゃないかな、足るを知る者は富むだよ、なんてとてもではないけれど言えません。だって、足るを知る者は富むって、言い換えれば、身分相応に満足して、それ以上は求めないようにすれば、不幸だとは思わずに済むってことじゃないですか!」
再び口を開くと一気に語り、最後は語気荒く言い放った。潮崎の顔は苦しそうに歪んでいる。
「佳須美さんもです。彼女は親にネグレクトされていて、家に居場所がなかった。そんな彼女に、それが分相応なのだから、我慢して満足すれば幸せだよ。なんて僕には言えない。絶対に無理です」
ミステリーの愛好家でとりわけ警察小説に傾倒していて、それが長じて警察官になったという変わり種が潮崎という男だ。かつて池袋署時代、捜査の最中に、小説や映画、ドラマの話を例に挙げてまるで実在していると思うほどの熱量で力説され続け、武本は辟易していた。
夢見がちではあるが、同時に警察官という職業に真摯に向き合う姿勢には一点の曇りもない。それは武本に十分に伝わっていた。
警察官は、規則に縛られながら、絶えることのない事件に向き合うだけでなく、民間人からも職務を正しく全うしているのかを問われ続ける。自由度は少なく、思う通りにはならないことの方が多い。
これまでの警察官人生の中で、担当した事件の結末に潮崎の心は何度も折れそうになっていた。だが不死鳥のように気持ちを立て直して、また現実とフィクションを混同させるようなユーモアを振りまいていた。
最近はあまり聞いてないが、それは単純に会った時間が短いのと、本庁で役付きになり、部下の手前もあって、さすがに潮崎も控えるようになったのだろうと、武本は思っていた。
――そうではないのかもしれない。
そんな考えがとつぜん武本の頭を過った。
警察官人生で、世知辛い現実にぶつかり続けているうちに、潮崎のユーモアは少しずつ削りとられてしまったのではないだろうか。
潮崎はよく喋る。話は本筋から自由勝手に飛び、また長い。これまで武本はそれを面倒だと思い、あまり相手にしないようにしてきた。
目の前の潮崎は打ちひしがれている。何か言葉をかけるべきだと武本は思った。だが、ふさわしい言葉が思い浮かばない。
それは、武本もまた西田佳須美や栗林渉が、どうしたらこんな犯罪に手を染めずに済んだのか、そう導くためにはどうしたらよかったのかの答えが出せていないからだった。
それでも、何か言わなくてはと懸命に考えて、口の中の焼きアスパラガスを飲み込んでから、「このお弁当、とても美味しいです。こんなに美味しい肉を食べるのは、初めてかもしれません。ありがとうございます」と、まだ伝えていなかった弁当の感想と感謝を伝える。
苦しそうな潮崎の表情が複雑に変化し、最後は、あははっと、声を上げて笑い出した。
なぜ笑うのかが分からず、潮崎を見つめる。
「すみません。いや、参っちゃうな。――先輩のそういうところ、僕は本当に尊敬しています」
何に参ったのか、そういうところとは何なのかが武本には分からない。訊ねようか迷っていると、「随分と遅れてしまいました。僕も食べないと」と言って、潮崎が箸でステーキを二切れまとめて口に運ぶのを見て、今は食べることに専念してもらおうと思って、やめた。
何度も咀嚼して口の中のステーキを飲み込んで、潮崎がまた口を開く。
「これ、本当に美味しいですね。お弁当ですし、それなりかと思ってしまった自分が恥ずかしいです。申し訳ございません。御見逸れしました」
弁当のステーキに向かって潮崎が一礼した。潮崎らしさを取り戻したように感じられて、武本は少し安堵する。
「まだ被害者は身元不明なんですよね」
そう言って、潮崎がグリルしたかぼちゃを箸で口に運ぶ。
「はい」と、武本は同意した。
捜査本部は、遺体の身元特定に努めた。だが焼失して人相は分からず、身体的な特徴となる医学痕もなく、所持品もない状態ではお手上げだった。
被害者の所持品の供述は石原進と山上瑛大で異なっていた。石原進は、山上瑛大が一人で所持品を処分したと証言した。だが山上瑛大は、「進が男の服を脱がしたときに、ナップザックを漁ってました。入っていたのは着替えの下着とTシャツとタオルだけで、財布には身分証明書的な物は何もなくて、千円札数枚と小銭だけでした。スマートフォンと現金だけ進が抜き取って、『処分して』って、俺に言ったんです」と具体的に話した。
自分でも所持品を確認して、身元につながる物は何一つないと判断したうえで、実際に焼却処分したのは自分だと山上瑛大は認めた。だが石原進は、自首直後の供述で、すべて山上主体で話が進み、自分は怖くて被害者の所持品にはほとんど触っていないと証言していた。山上瑛大の証言をぶつけたが、石原進はそんなことはしていない、山上瑛大の作り話だと否定した。
真偽を確認しようにも、所持品は焼却済みで残留物もない。石原進の家宅捜索を行い、スマートフォンを捜したが、こちらも空振りで見つからない。被害者の身元が分かれば、各電話会社に問い合わせることで、スマートフォンの現在地が分かるかもしれないが、身元が不明なだけに手の施しようがない。
復顔写真を見た家族や知り合いから連絡が入れば身元の特定が出来る。だから、正直にスマートフォンをどうしたのか話せと、浦島は石原進を説得しようとした。けれど、「知りません」の一点張りだ。平然とそう言い続けるのは、スマートフォンは絶対に見つからない状態にしたからだと、浦島と武本の二人は察した。
契約状態のスマートフォンは売れば金になる。だが契約している電話会社から、足はつきやすい。石原進は目先の金を捨てて、粉々に砕いて処分したに違いない。
改めて、石原進の悪事への計算高さに怖気を感じたのを武本は思い出す。弁当がまた味がしなくなっていくのを感じて、紙コップのお茶で口の中を洗い流す。
「科捜研が復顔写真を公開してから一週間経ちますが、未だに誰か分からないなんて」
かぼちゃを食べ終えて潮崎はそう言うと、続いてミニトマトを口に運んだ。しばらく咀嚼して飲み込むと、感に堪えないといった表情で「なんて美味しい。もとのミニトマト自体がすごく良い物なのはもちろんですが、グリルしたことで旨味がぎゅっと濃縮されたんじゃないでしょうか。塩加減も最高です。わずかな塩がミニトマトの甘みを引き立てている。最高です。何個でもいただきたい。でも、一つだからこそのありがたさなんだろうなぁ」と、感想を漏らした。
ミニトマト一つでこれだけの感想は自分には言えない。シンプルにすごいと武本が思っていると、潮崎が話を戻した。
「被害者は、一体、誰なんでしょうね」
広く情報を求めるために復願写真が公開されて七日が経って、数件の問い合わせが入った。だがどれも空振りに終わっている。
「山上の供述だと、もともと被害者はスマートフォン以外は、身元につながるようなものを何一つ持っていなかったことになるじゃないですか。以前はそんなことは少なかったけれど、今後は当たり前になるのでしょうね」
「そうですね」と、短く同意する。
かつては誰もが財布の中に、店などの会員証や、何かしら氏名が分かるものを入れていた。だがスマートフォンの普及とともに、紙のカードがアプリに変わるだけでなく、現金もあまり持ち歩かない時代になりつつある。
これからの証拠はスマートフォンの中にある。それさえあれば、情報のすべてが得られる可能性が高いだけに、捜査の進展は早くなる。だが今回のようにスマートフォンがない場合、捜査は簡単には進まない。
「一つだけ救いになりそうなのは、山上瑛大と佳須美さんの証言通りならば、被害者の所持金は二万数千円と小銭だったことになります。だとすると、佳須美さんの被害者に襲われて身を守ったという証言は、司法解剖の結果次第で信憑性があると判断されるんじゃないでしょうか?」
「――だといいと、私も思います」
あくまで自分の意見なので、話しても問題はないと判断した武本は同意した。
「ですよね」
嬉しそうに言った潮崎は、「いや、買春の代金ぎりぎりしか持っていなかった成人男性が、未成年の女性を買春したあげくに襲ってお金を盗ろうとしたことは、何一つ良くはないんですけれどね」と、すぐに声のトーンを落として言った。
これもまた、同じことを浦島と話し合っていた。
「――なんか、この先、どうなってくんだろうな」
会話の最後に、浦島は疲れが染みついてしまった顔で、そう嘆いた。子を持つ親の浦島には、この先の時代がどうなっていき、その中で我が子が安全に暮らしていけるのかというのは重大な課題となっていた。
かける言葉が武本にはなかった。だが、何か言おうと懸命に考えた。
そして「わかりません」と、まず答えた。
明らかに失望している浦島に、あわてて「ですが、私は警察官としてすべきことをして、人を守っていきます」と続ける。
「そうだよな、すべきことをしよう」
さきほどとは違って緩くほどけた表情で浦島にそう返されて、会話は終わった。
「――なんか、この先、どうなっていくんでしょうね?」
言葉の細部こそ違えど、浦島とまったく同じことを潮崎に言われて、武本は既視感を覚える。
考えは何一つ変わってはいない。ならば同じことを言うだけだ。口を開こうとした矢先に、「わかりません、って先輩なら言うんでしょうね」と、潮崎に先回りされて、さすがに面食らう。
「失礼ながら、先輩は考えることを得意としてらっしゃらないじゃないですか。代わりにと言うのか、その分、するべきことはする。つまり実行派です。それはお父様の教えである、後悔するという文字はあとで悔やむと書く。やらずに後悔するよりも、やって後悔した方が良いというのが礎になっていると思います。素晴らしい考えです。先輩から伺って以来、僕も人生の指針にしています」
とうとうと語っていた潮崎がいったん言葉を止めた。
「ですが、起こってしまってからでは遅いこともあります。いや、警察という職業だと、そちらの方が多いと思うんです。ですが、犯罪を抑止するのも、警察の重要な役割じゃないですか」
潮崎が必死な目で見ている。
「そのうえで、僕はこれから先、どうなっていくのかが不安なんです」
言い終えた潮崎がじっと自分を見つめている。
武本は熟考してから、口を開いた。
「わかりません」
潮崎の顔に失望が広がっていく。
「ですが、やはり私は警察官として、すべきことをして人を守っていきます」
潮崎の失望の色が濃くなっていくのを見ながら、武本は言葉を継ぐ。
「申し訳ないのですが、先のことは、やはり私には分かりません。ただ、人が困っているときに助けを求められる、助けてもらえる社会であって欲しいと願っていますし、その一端を私は担いたいです」
潮崎が目を丸くする。
「誰もが、他人はもちろん、自分も傷つけることなく生きていける。そんな未来であれば良い。そう願っています。そのためには潮崎警視の仰るように、皆で考えていかなくてはならないと思います。もちろん私もです。そして」
武本はそこで言葉を止めた。結局いつもと同じことになってしまうのを申し訳なく思いながら、言う。
「私に出来ることを、すべきことをしていきます」
潮崎はぽかんと口を開けていた。手にしていた箸がぽろりと落ちた。
「箸が」と言った武本の声を、「やっぱり、先輩は素晴らしいです!」と潮崎の大声がかき消した。
「いや、なんかもう、すみません、僕ったら。本当に恥ずかしいです」
言いながら、潮崎が勢いよく立ち上がる。
「箸を洗ってきます。すみません、食後にはどうしても、僕の淹れたお茶を飲んでいただきたいんです。申し訳ないのですが、先に食べ終えられても、待っていていただけますか?」
武本の返事を待たずに、潮崎が応接室を出て行った。取り残された武本は、弁当の残りを口に運ぶ。
食事を終えたら、日報を作成しなくてはならない。明日はまた、石原進の取調べの予定が入っている。そろそろSSBCから人身売買のバイヤーの男の情報も上がって来る頃だ。すべきことをして、事件を完全に終結させる。そしてまた新たに起こった事件の捜査をする。それが警察官である自分の職務だ。
さきほど潮崎に言ったことは、武本の本心だった。これからは、今までのように考えることを放棄せず、人が安全に正しく生きていくために警察官として考えていく。たとえ答えはでないことでも、考え続ける。それは、警察官としてこれからも人を守っていくために、不可欠なことだと気づいたのだ。
――諦めず、投げ出さず、考え続ける。
武本はそう自身に誓った。
黙々と食べていると、ノックの音が聞こえる。「どうぞ」と応えると、潮崎が室内に入って来た。どこまも礼儀を忘れない潮崎を武本はすごいと思う。
「すみません、ここから猛スピードで食べますから」
武本の残り僅かな弁当を見て、潮崎は箸でビーフガーリックライスを大きく取って口に運ぶ。もぐもぐと口を動かし、しっかり咀嚼してからごくりと飲み込み、続けてステーキを二切れ摘まみ上げた。口に運ぶかと思いきや「先輩は、動画配信のサブスクって加入されてたりします?」と、訊ねてきた。
「いいえ」と即答すると、「ですよねぇ~」と、分かっていたと言わんばかりに頷き、「僕はネットフリックス、ディズニープラス、フールー、ユーネクスト、アマゾンプライムビデオに入っているんです」と、武本も名前は聞いたことがある配信サービスを潮崎が列挙する。
加入するのは個人の自由だとは思うが、これだけあると、作品を観る時間をどう捻出しているのだろうかと武本は疑問に思う。
「それらで配信されている刑事ドラマに素晴らしいのがたくさんあるんです。翻訳本の世界的ヒットから、ヨーロッパや北欧の作品はもはやメジャーなんですけれど、南米やトルコなどの作品も侮れないんですよ。文化や地域性もあいまって、どれも実に味わい深くて面白いんです」
潮崎の話は止まらない。陽気なマシンガンのように喋り続けている。すっかり調子を取り戻したようだ。
その様子に武本は安堵する。同時に、ここから話が長くなるのは確実だとも思う。
日報はまだ書き終えていない。それでも、今日は潮崎に付き合おうと武本は決心して、弁当の最後の一口を箸で運んだ。
(了)