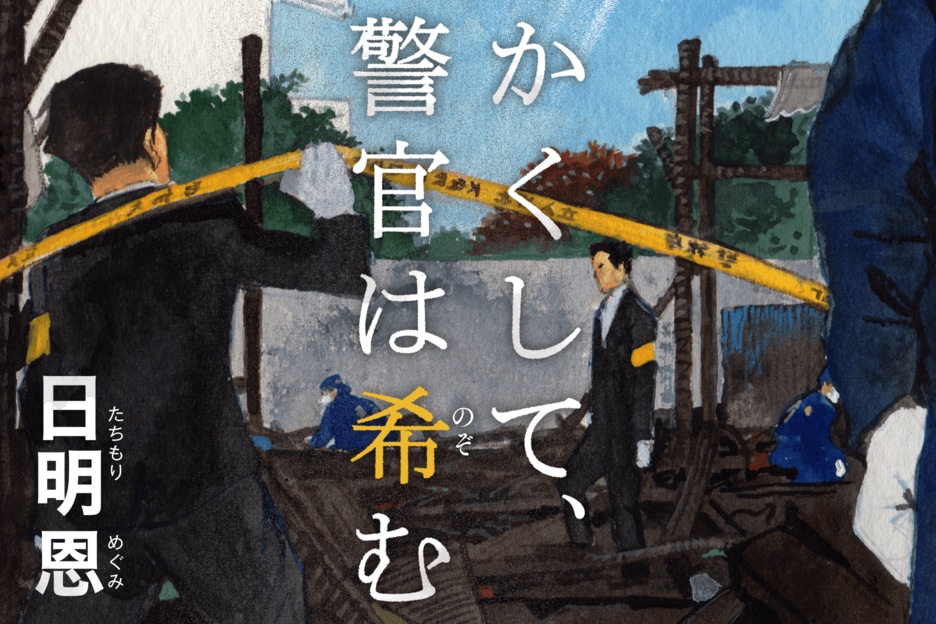23
三月十五日の午後六時を回った時刻に武本は東京メトロ桜田門駅のC1出口から地上への階段を上がっていた。警視庁の正門へ向かい、警備の制服警官に一礼して入る。日は暮れているが、吐く息はもう白くない。季節が変わったのを武本は実感する。
短いスロープを上り、自動ドアを通って建物の中に入ると、向こうから男がやってきた。火災犯捜査の柳原だ。
「よう」と手を上げて挨拶されて、「お疲れ様です」と言って、一礼を返した。
「太郎は?」
浦島の所在を訊ねられて、「直帰です」と答える。
「そりゃぁ、良かった。早く帰れるときは帰らないと」
「柳原さんもお帰りですか?」
「ああ。今日は弟と飯を食う約束があるんでな」
口の端を上げて柳原が微笑む。彼の笑顔を見るのは初めてだ。
「そっちはまだ終わってないんだってな」
三月七日に放火犯の栗林渉は今回の中落合の現場への放火だけでなく、二年前の六月の品川区、同年十二月の目黒区、昨年一月の大田区、同年九月の大田区のすべてゴミ捨て場への放火の四件も合わせて起訴となり、それで放火事件は終結を迎えた。
その時点で捜査本部の放火捜査班は解散となり、柳原たち第八強行犯捜査火災犯捜査第一係は一足先に引き上げていた。
だがまだ事件を完全に終結できていなかった。殺人の実行犯の西田佳須美は殺人罪で、山上瑛大は死体遺棄と児童買春周旋と児童買春等目的人身売買罪での起訴は確定していた。だが石原進の罪状はまだ確定しきれていなかった。山上瑛大の録音音声の存在によって、石原進は児童買春周旋と児童買春等目的人身売買を指示したと罪を認めた。だが人身売買のバイヤーの情報を提供することとなり、その取調べはまだ始まったばかりだった。なので、武本たちは縮小された捜査本部で、まだ捜査を続行している。
「長引きそうか?」
「SSBCの被疑者特定待ちです」
西田佳須美を海外で売るために、石原進はダークウェブで見つけた本名不明のルークと名乗る男と二月八日午後三時に新宿三丁目のコーヒーショップで一度だけ会っていた。本部捜査員たちは店内と店周辺の防犯カメラ映像を集め、SSBCの捜査員たちが今、男の特定を急いでいる。
「今更だが、SSBCには頭が上がらないよ」
しみじみと柳原が言う。
「以前は係内で映像を集めて、それをひたすら見続けて被疑者を捜していたからどうしても時間が掛かった。でも今はSSBCが一手に引き受けてやってくれている。今回も栗林を短時間で特定してくれたお蔭で逮捕することが出来た」
「こちらもです」
山上瑛大、石原進、西田佳須美の三名が乗っていた車を見つけ出し、持ち主が小林奈美子だと判明したことで、当日運転していたのが山上瑛大の可能性が高いと分かった。そこから石原進につながり、捜査の最中に、石原進と山上瑛大の両名の自首に伴う供述で、殺人の実行犯の西田佳須美の逮捕となった。
「それにしても、なんとも言い難い事件――そっちはまだ終わっていないのに、すまん」
途中で気づいた柳原が謝罪して、先を続ける。
「こっちは、証拠を突きつけたらすんなり白状した。動機も、乱暴にまとめれば貧困からのストレスと、自分よりも良い暮らしをしている人たちへの嫉妬だ」
捜査本部での会議で、放火事件の終結発表があり、そこで事件の全容が明かされた。栗林渉が学費のために過度なアルバイトをし続けたのも、すべては経済的な困窮からだった。そのストレスから、羨望と嫉妬が憎しみに変わってしまい、持っている者たちのいらない物ならば燃やしてもかまわないだろうという間違った考えに行きつき、実行してしまっていたのだ。
「同情すべき点はあるが、やはりやったことは許されないし、許せない」
放火犯への怒りから現職に至る柳原の言葉だけに、武本には重く聞こえた。
「だがな」
表情を曇らせた柳原が苦々しい声で話し出す。
「自供の翌日の午後の取調べに入る前に、留置係官から申し送りがあったんだ。直前に両親との面会があって、栗林がかなり動揺しているって」
栗林は逮捕後、両親に連絡を入れていなかった。
被疑者は逮捕後、留置直前に指定した一ヵ所のみ、相手の氏名と電話番号を告げれば、担当官から連絡してもらえることになっている。担当官がそう説明して訊ねると、栗林渉は「ありません」と答えた。だが、逮捕の翌日、警察が証拠収集のために栗林の実家に向かった。息子の逮捕を知らされた両親は、その日の午後に面会に訪れた。
「息子が入って来るなり、父親が『なんでこんなことを!』って、怒鳴りつけた。けれどそのあと泣きながら謝ったんだそうだ。『自分たちが不甲斐なかったから、お前には苦労ばかりかけてしまった。お前がいつも辛そうなのは気づいていた。でも、いつも大丈夫だと言っていたから、分かっていても甘えてしまっていた。すまなかった』って。栗林は床に崩れて声を上げて号泣した。その後の取調べで、真っ赤に目を泣き腫らした栗林から、その面会のときの話を詳しく聞いた」
広くない接見室でアクリル板を挟んで、面会に来た両親と、被疑者として身柄を拘束された息子が泣いている。以前新宿署の留置管理課に在籍していた武本は、留置係官として何度も面会には立ち会った。なので、何度もよく似た状況を体験していた。
「ひたすら謝り続ける栗林に、父親が『謝るのは俺たちじゃない。被害に遭った人たちに謝りなさい』、母親は『正直にすべてを話して、罪を償いなさい』と、言ったんだって。――ちゃんとしたご両親なんだよ。なのに、なんでこんなことになっちまったんだか」
柳原の声には、栗林の両親に対する同情が感じられる。
「栗林が踏み止まれなかったのは、あくまで本人の責任だ。すでに成人しているんだしな。でも、両親は一生、自分たちのせいだって責任を感じ続けるんだろうな」
息子が放火に手を染めた原因は、経済的な困窮で、その責任は息子を養う立場の自分たちにあると両親が感じているのかと思うと、武本の心も痛む。
「しかもマスコミのせいで、大変なことになっちまったし」
栗林の逮捕後、マスコミは栗林の両親に取材しようと押しかけた。「申し訳ございません」を繰り返すだけの両親に飽きると、今度は栗林のアルバイト先のサウナ施設や通っていた大学、高校、中学校まで遡って同級生から栗林の話を聞こうとした。中学時代は実家の店の手伝いで、高校以降はアルバイトに明け暮れて、栗林は親しい友人がほとんどいなかったこともあって、出てきたのは「いつも仕事に追われていて、人付き合いはほぼなかった」程度だった。
だがマスコミが報じたことで、虚偽も含めて様々な情報が飛び交った。かつて両親が経営していた店について、「不味かった、潰れてとうぜん」と悪口を流す者もいた。さらには犯罪者の親なのだから同罪だとばかりに、両親に対する誹謗中傷を書き込む者もいた。
「あまりに酷いんで、訴えることを勧めたんだ。けれど、大丈夫ですって断られた。まぁ、そんなことをしたら、ますます火に油をそそぎかねないしな」
被疑者の家族にそこまでの提案をする警察官は少ない。栗林の両親を慮れる柳原に、武本は懐の深さを感じる。
「今更だが、なんで踏み止まれなかったんだろうな。あんなことをしでかす前に、誰かが何かできたんじゃないかって」
言い終えた柳原の表情は辛そうだ。
放火犯を捕まえるために刑事になったと、柳原は言っていた。本人の口から聞かされたその過去は壮絶で、弟が現職の消防官なのもあり、放火犯に怒りを燃やす理由も納得できた。だが柳原は、ただ放火犯を憎み、断罪を望むだけの男ではなかった。事件の背景をきちんと考慮したうえで、犯人の両親のことも案じている。自分ごときが言うのはおこがましいが、柳原は良い刑事だと武本は思った。
「まぁ、たらればでしかないんだけどな。――でも、そっちの石原って奴は、あれはいったいなんなんだ?」
柳原が話を変えた。
「病的な嘘つきなんだろう? なのに裁判で弁護士が精神鑑定を依頼してきたって、太郎から聞いたぞ」
刑事責任能力――法律や道徳的に許される行為かどうかを判断し、その判断に沿って自分の行動を統制できる能力の有無で被疑者の刑罰は変わる。被疑者に刑事責任能力があれば、自身の犯罪の責任を負う能力を持っているということから刑罰を科すことになる。だが、被疑者が刑事責任能力を全く持たない心神喪失者や、刑事責任能力が著しく低下した心神耗弱者の場合は無罪や不起訴、あるいは刑罰の減免といった処分がなされる。
精神鑑定の結果、人格障害、神経症性障害、発達障害、統合失調症や気分障害などに該当したとしても、病気自体が罪を免れる理由にはならない。精神障害があることが理由に無罪になるのではなく、精神障害に起因して、事件当時に刑事責任能力がないと認定されるのだ。
罪を軽くするために、石原が弁護士に精神鑑定を提案したに違いない。だが、これに関しては被疑者の権利なので、こちらにはどうしようもない。警察にできるのは、石原の鑑定結果は罪を軽減するための虚偽でしかないことを証明できる証拠を検事に提出するだけだ。
「鑑定結果に備えて、虚偽だと立証する証拠集めを始めています」
武本の応えに「それしかないよな」と、柳原が同意して、「じゃぁ、そろそろ行くわ。お先に」と、手を上げて挨拶し歩き出した。
改めて武本が「お疲れさまでした」と一礼して頭を上げたとき、柳原が立ち止まって振り返った。
「言うまでもないとは思うが、一応言っておく。――いるぞ」
そう言って、柳原が上を指してから、向き直って庁舎から出て行った。柳原の仕草が何を表しているのかは考えるまでもなかった。
◇
捜査一課のフロアに到着し、そのまま部屋に入る。いつもならば入室とほぼ同時に聞こえる潮崎の声はなかった。さきほど柳原は潮崎がいることを示唆していたが、いないのであれば仕事に集中できる。
自分の席に着き、さっそく机の上のパソコンを立ち上げて日報を作成し始める。武本の入庁当時、書類はすべて手書きで、書き間違えたら修正液で白く塗り、乾くのを待ってからまた書き直さなくてはならなかった。時間も手間も要するので、大変な作業だった。二〇〇〇年以降、パソコンの普及が進み、書類作業は手書きから入力へとシフトした。それまでほとんど使用した経験がなかったために、キーボード操作に慣れるまで苦労した。だが警察は書類作業が多いだけに、じきに慣れ、今ではそれなりの速さで作業が出来るようになった。
順調に作業は進み、溜めてしまった一昨日の分を終え、昨日の分に取りかかる。この調子ならば、すべてを終わるのにさほど時間はかからなそうだ、と思ったそのとき、気配を感じた武本がちらりとそちらに目を向けると、五列離れた本人の席から立ちあがった潮崎がいた。両手で箱状の物を持った状態で、微妙に左右に揺れながらこちらを見つめている。
目が合ったので武本が目礼をすると、潮崎は嬉しそうに微笑んで、こちらに向かって来る。やはり来るのか、と思いながら、武本は日報を少しでも進めようと作業に戻った。
「お疲れ様です~」
すぐ近くまで来てから小声で言われて、武本は「お疲れ様です」と返した。
「夕ご飯はまだですよね? よろしければ、いかがですか?」
言いながら、潮崎が両手で抱えた風呂敷包みを差し出す。近くで見るとかなりの大きさだ。
「実は、残業をしている同僚たちの労をねぎらうために、お持ち帰り用でご家族の分も合わせてお弁当を手配したのですが、僕としたことが数を間違えてしまって、数個余ってしまったんです。宇佐見君がまだフロアに残っていたので、何なら二つ持って帰ってはとお勧めしたのですが、『ありがたく頂戴します。ですが、一つで結構です』と、遠慮されてしまって」
宇佐見独特の言い回しを真似て潮崎が言う。
「それで先ほど柳原さんにもお声がけしたのですが、今日は会食のご予定があると、こちらも振られてしまいまして」
柳原にも弁当を渡そうとした。だからあの忠告だったのかと武本は納得した。
「ご自身で召し上がっては?」
「僕の分はあるんです。他はお声がけした皆さんに引き取っていただきました。ですが、どうしても一つ、余ってしまいまして」
「持ち帰られては?」
「持ち帰ったところで、母に没収されて、おそらく廃棄されてしまうでしょう。それはあまりにもったいないです。何より、フードロスの観点からもよろしくないじゃないですか。どうか助けると思って、召し上がって下さい」
早口でそうまくしたてると、潮崎は弁当を高く掲げて頭を下げた。
年齢も職歴も武本より下だが、役職は潮崎の方が上だ。さすがにもう断れないと判断した武本は、「それでは、お言葉に甘えてありがたくいただきます。ありがとうございます」と応えて、弁当を受け取った。
受け取った弁当は、武本がいつも食べているコンビニエンスストアなどで売っている物と比べて、縦横ともに一・五倍くらい大きく、厚みも倍だ。資料とノートパソコンを広げた自分の机の上には置き場がなかった。かといって、不在とはいえ、隣の浦島や平井の机の上に置くのは、食べ物なだけに気が引ける。仕方なく膝の上に置く。まだ温かい弁当の熱が腿に伝わってくるのと同時に、肉の良い香りが鼻をくすぐった。武本の腹が音を立てて鳴った。
「空腹では、作業効率も上がりません。温かいうちにいただきましょう。応接室が空いてますので、そちらで。僕、お茶を淹れてきます」
言うなり、潮崎は武本の膝の上の弁当を手に取って、早足で応接室に向かって歩いて行ってしまった。
本来ならば、役職が下の自分がお茶を準備するべきだ。だが、歴史ある茶道家元の子息である潮崎は、お茶にはこだわりがあり、自分用に煎茶や抹茶を専用の湯飲みで愛飲している。自分にできるのは、給湯室の自動給茶機のお茶を紙コップで出すのみだ。潮崎が飲む分はともかく、自分の分は自分でと思い、武本は席を立ち、給湯室へと向かう。
無人の給湯室に入り、自分用にお茶を汲んでいると、潮崎が駆け込んで来た。給茶機の前で紙コップにお茶が溜まるのを待っている武本の姿を見るなり、「あ!」と潮崎が声を上げる。
「私の分はこちらで」
お茶の入った紙コップを取り出しながら断りを入れた武本に「久しぶりに先輩にお茶を淹れたかったのになぁ」と、潮崎がため息混じりに言って、紙コップを取ってセットした。自分に合わせて潮崎も給茶機のお茶を飲むらしい。申し訳なくなって、「警視は、いつものようになさって下さい」と勧めたが、「お待たせしたくないというか、僕もお腹が空いちゃって。食後は僕に淹れさせてください」と言って、潮崎は給茶機のボタンを押した。
(つづく)