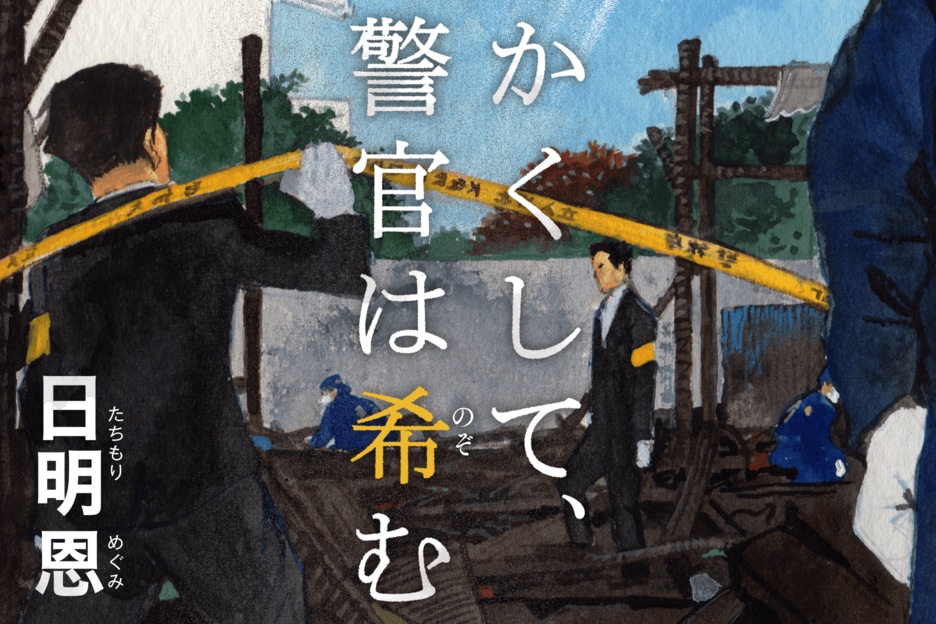17
朝の六時過ぎに逮捕された渉は、戸塚署に連行された。留置の手続きを終えて、取り調べが始まったのは午前九時過ぎのことだった。
「二月二十日午前九時七分。取り調べを開始します」
机を挟んで目の前に座ってそう言ったのは、自宅に来た刑事だった。
「私は警視庁捜査一課火災犯捜査の柳原将志」
逮捕された罪状は放火だ。そして今、取り調べを担当しているのも放火専門の刑事だ。殺人ではないことに、少しだけ渉はほっとしていた。
続けて氏名、年齢、現住所、所属大学名、と次々に確認されて、それらすべてに「はい」と答えた。
「二月五日午前三時四十分頃、東京都新宿区中落合×丁目×番地、村上義信所有の住宅の敷地内、建物の玄関わきに、破損した携帯充電器とアロマオイルをしみこませたタオルで作った放火のための仕掛けを投げ込んだ。――間違いないな?」
そう柳原に訊かれて、渉は返事に詰まった。
逮捕された時点で、渉はすべて自供すると決めていた。逮捕令状が出ての逮捕だ。警察は自分が放火犯だと確信があるのだ。ならば、やっていないと白を切ったところで、いたずらに時間がかかるだけだ。放火をした以上、懲役刑は免れない。だとしたら、少しでも早く社会に戻るためには、すべてを正直に話した方が得策だと考えたからだ。
放火したのは事実だし、場所もおそらく間違いない。けれど正確な住所や家の持ち主は知らない。
「はい」と認めてから「ただ、住所や家の所有者は知りません」と、続けて答えた。
空き家への放火の罪は認めた。問題は、過去の放火についても話すかどうかだった。警察が気づいていないのなら、言わずにいれば罪が軽くなる。だが、気づいているのならば、自分から話した方が少しは罪が軽くなるかもしれない。
今回の逮捕は空き家への放火だから、非現住建造物等放火罪で二年以上の懲役だ。だがそれまでに仕掛けを投げ込んだのは全部で九回、そのうちニュースで出火したと分かっているのは四回ある。四ヵ所ともごみ捨て場なので、建造物等以外放火罪で一年以上十年以下の懲役になる。初めて放火をして以降、何度も調べたから放火の刑罰は頭の中に入っていた。
空き家への放火に、四回分の放火の刑罰が加算されたら、懲役は全部で何年になるのだろう? それを考えると、全身が震え出しそうだ。
警察が気づいていないのなら加算はされない。すでに知っているのなら、自供した方が社会に戻るのが早くなる。もしかしたら心証が良くなることで刑期が短くなる可能性もあるかもしれない。
そこまで考えて渉の頭に違う考えが浮かんできた。
――出所が数年早くなったところで、だからなんだと言うのだ?
放火という前科が付いたあとの人生に、何の展望も浮かんではこなかった。
何かしらの職に就くことは出来るかもしれない。でも、診療放射線技師と同等の収入を得られることはないだろう。
「住所と所有者は知らない――。では、事件当日の犯行に至るまでを話してくれ」
柳原は渉の答えを復唱すると、少し間を空けてから訊ねる。
「バルト――上野にあるサウナ店のアルバイトが深夜十二時で終わって……」
話し始めて渉は気づいた。
正直に話すのなら、放火の仕掛けは事前に準備していたこと、場所は事前に知っていて防犯カメラを避けて歩いて行ったのを話すことになる。どちらも計画的な犯行となり、初犯だと思っては貰えないに違いない。何か切り抜ける方法はないかと必死に考える。
――破損した充電器もアロマオイルもタオルも、実際にゴミ捨て場から拾った物だ。ならば道中で拾った、でいけるのでは?
でも拾ったと言ったら、場所を聞かれる。どこにゴミ捨て場があったかなんて知らない。追及されたら嘘はすぐにバレる。
それ以前に、帰宅ルートからはかけ離れたところにある空き家に放火したのが問題だ。
――試験勉強で追い詰められてあてもなく散歩をした、とかだろうか。
でも、警察は防犯カメラの映像で自分を特定した。ならば防犯カメラを避けて歩いていたのはすでに知っている。
――完全に詰んだ。
打つ手はないと悟って、言葉に詰まった渉の耳に声が降ってくる。
「栗林、正直にすべて話せ」
自分を見つめる柳原の目は鋭く、すべてを知っているぞと言わんばかりだ。それでもまだ渉は迷っていた。
「この現場が空き家なのは知っていたのか?」
すぐには答えられなかった。知っていたと言えば、計画的な犯行になってしまう。
「結果としてあの家は空き家だった。だがお前がそれを知っていたのか、知らなかったのかで量刑は大きく変わってくる」
柳原の言葉に、足下まで血の気が引いて行った。
――空き家だと知らずに放火したのなら現住建造物等放火罪となり、死刑または無期もしくは五年以上の懲役だ。
心臓が激しく脈打ちだし、こめかみに痛みを感じる。すべてを正直に話さなければと思って口を開くが声が出てこない。
「もう一度聞く。空き家だと知っていたのか?」
柳原に念押しするように訊ねられて、なんとか「はい」とだけ答える。その声はかすれていた。
「そうか。では、事件当日の犯行に至るまでを最初から話してくれ」
空き家だと知っていたと認めてしまった。これで計画的な犯行となった。余罪の追及をされたら、いずれはすべてを認めることになるのだろう。
――今度こそ、本当に終わった。
進学は定められた学費の中で選択をした。そうするしかなかった。志望校の志望学部に入学は出来たが、そこからはアルバイトに明け暮れ、楽しそうな同級生たちをうらやむしかなかった。そんな日々がようやく終わりを告げようとしていた。卒論は提出済みだ。診療放射線技師の国試も手ごたえは十分だった。結果発表は三月二十一日、一か月後だった。試験の結果発表をもって、四月からはすでに内定を得ている神奈川県の整形外科クリニック勤務になるはずだった。だが、その未来予想図は完全に消え失せた。
自業自得でしかないのは分かっている。けれど頭の中を占めていたのは自分の運のなさへの落胆だった。
親の商売が上手くいかなくなってアルバイトに明け暮れるようになったことや、自転車配送のアルバイトの事故での怪我のどちらも、どうして自分だけがと周囲をうらやみ、世を恨んだ。
その憂さ晴らしから、二年生の六月から三年生の九月まで、全部で九回放火した。そのうち火事になったのは四回だ。だが二年半以上の間、ただの一度も警察の手が及んだことはなかった。おそらくだが場所がごみ置き場だったことで、警察もさほど根を詰めて捜査に当たっていなかったのだろう。だが今回は住宅だった。本当に火事になるとは、しかも家の中から男の遺体が出てくるだなんて、想像できるはずもない。
殺人事件だから本格的な捜査が行われた。だから自分の身元も特定された。そうに違いない。火事にならなかったら、ただの殺人事件の捜査だった。それならば、自分は捕まらなかったはずだ。
そこまで考えて渉は気づいた。
――火事になっていなければ、遺体はまだ見つかっていなかったのでは?
殺人事件があったのを世に知らしめたのは自分だったと悟った渉は、自分の運のなさに絶望した。
「栗林」
柳原に名を呼ばれて、渉は意識を戻した。そして、「あの日はバルト――上野にあるサウナ店のアルバイトが深夜十二時で終わって」と、もう一度、最初から事件当日のことを話し始めた。
(つづく)