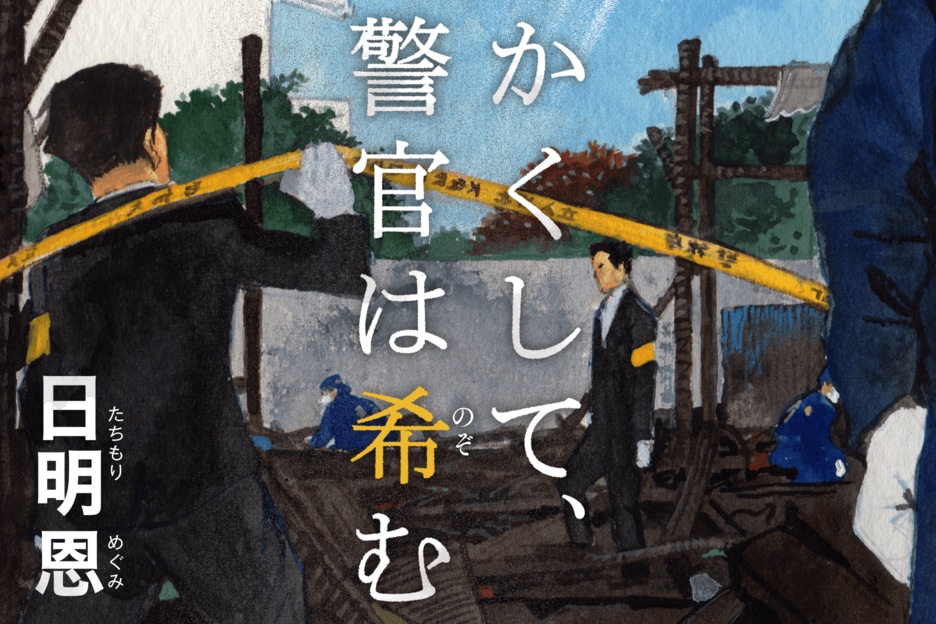「接客時間と内容を金で買う。ことにこの手の接客業がそういうものなのは知っている。どれだけ金を客が使ったとしても、違法な商売でない限りは、あくまで客の自己責任だ。――だけど」
そこまで言って浦島は顔を顰めて口をつぐんだ。小さく唸ってから、「これを言い出すと、結局、それぞれ個人とか家庭の問題になっちまうから難しいんだけどな」と、苦々しげに吐き出して、また話し出した。
「接待をしていないメンコンは、一般的な飲食店と同じくくりになる。言い換えるのなら、ケーキ屋やラーメン屋やレストランとかの飲食店に客が通うのと一緒だ」
浦島の言う通りだと武本も思う。
店で出している品が美味しいからと、毎日食べに通うことになんら問題はない。金を使いすぎて経済的に困窮するとか、健康を損う者もいるかもしれないが、どちらも自己管理の問題だ。
「金で何かを買うといえば、飲食物だけじゃなく、アイドルやゲームや漫画やアニメに入れ込む、いわゆる推し活も同じことだろう。未成年が推し活に高額をつぎ込むトラブルは、今では珍しい話じゃない。でも商売に違法性がなければ自己責任だし、それぞれの家庭の問題ってことになる。うちも息子が二人いるから、人ごとじゃない」
浦島は小学六年生と四年生の二人の男児の父親だ。捜査本部が出来て四日目の二月九日に、浦島の長男が志望中学校に合格したという朗報を聞いた。
「去年、長男の優斗がスマホゲームに課金したいと言い出して、家族会議になったんだ。
俺たち夫婦の子育てで、妻に言われて絶対にしないと決めた約束事があってな。頭ごなしに否定はしない。一通り言い分を聞く。否定する場合は、子供が納得できるまで説明する。子供相手なだけに時間がかかって大変だけれど、これは絶対に破らないと妻と約束している」
浦島の妻は高校からの同級生で、今は薬剤師をしていると聞いている。その提案からも、改めて彼女の聡明さが伝わってきた。
「優斗が言うには、親しい友人がみんな参加していて、アイテム持ちの友達にいつも頼ってばかりなのが悪いと思うし、このままだと居心地が悪い。だから小遣いから払うので課金したいと言うんだ。納得は出来た。一方的に与える側や貰う側になったら、友達付き合いは続かなくなるからな」
金銭は人間関係を構成する重要な要素の一つだ。同等の経済状態や価値観がないと、交友関係を維持するのは難しく、ときに犯罪の原因にもなりうることを、武本も熟知していた。
「小遣いをどう使うかは優斗に任せている。理論上で言えば、全額課金に使うのも自由だ。俺は、使い切ったとしても援助はしないとしたうえで許可しようと考えていた。だが妻は上限額を決めようと提案してきた」
エレベーターの到着音が鳴った。ドアが開き終えるのを待たずに外に出る浦島に、武本も続く。迷うことなく次の店に足を進めながら浦島が話し続ける。
「使い切ってしまって、でも本当にどうしてもお金が必要なときもある。それで援助するという前例を作りたくない。それに、たとえゲームでもお金で解決することに慣れることは良いと思えない。金で買ったアイテムでゲーム内で強くなるというのは、友達の間で立場が上になるのと一緒に思える。お金で人間関係がどうにかできるなんて思い違いは絶対にさせたくない。――ぐうの音も出なかったよ」
そう言って、武本を見る浦島は少し恥ずかしそうな表情を浮かべていた。
「結局、上限を決めて許可を出した。もちろん優斗には全部話してだ。何がすごいって、妻は優斗にこう言ったんだ。『同じようにお金を使うことはできない。使える範囲でしか一緒にゲームはできないけれど、それでもいいか聞いてみなさい。どう答えるかでその子たちがどんな人なのかが分かるとママは思うわ』って」
同じようにお金が使えないのなら遊ばないと言うのか、あるいはそれでもいいと言うのか。確かに、答えでその友人たちの人間性が浮き彫りになる。
「素晴らしい奥様ですね」
感嘆して言った武本に「ああ、俺にはもったいないほどの良い妻だよ」と、浦島が堂々と肯定した。
謙遜は美徳とされている。だが、家族の良さを認めて卑下しない浦島を実に好ましい男だと武本は思う。
「納得した優斗は、友達に聞いてみたんだ。『この額までしか使えないけれど、それでもいい?』って。みんな『構わないよ』って言ってくれたそうだ。中には、『プレッシャーかけちゃってたのならゴメン。実は自分も金欠なのに無理してた』って言ってきた子もいたんだ。優斗は今も上限額内で友達とゲームを楽しんでいる」
「友達もいい子たちでよかったですね」
類は友を呼ぶだと思って武本は言う。
「ああ、みんないい子たちだ。中学は別々になってしまうけれど、それこそゲームを通じてこれからもずっと交流が続くといいなと俺は思っている」
時間や物理的な接点が減ると交友関係の維持は難しくなる。幼稚園や小学校の同級生と武本は没交渉になっていた。だがネット環境が整い、生活の中で当たり前となった今、自分の子供時代とは大きく異なる部分があるのだろうなと武本は思う。
「うちの話になっちまったが、言いたいのは、何にどれだけ金を使うかは、最終的には自己責任だけれど、未成年に関しては、やはり保護者が把握して指導するべきだ思っているってことだ」
曲がり角に差し掛かり、歩くスピードを落とさずに浦島が曲がる。
「メンコンには未成年の客が少なからずいる。おそらくだが、ほとんどの家族が娘が店に通っているのを知らないと思う。四つ目のビル、あれか」
二つ目のビルの前に差し掛かり、目指す店が入っているビルを確認してから浦島が続ける。
「誰だって秘密の一つや二つ、持っていたいもんだ。ことに子供は親に隠し事をする。俺だってそうだった。でも、上手くやっていたつもりが、結局うちの親は全部知っていた。まぁ、点数の低いテストを隠すとか、濡れ場のある映画を観に行ったとか、女の子と二人だけで出かけたとかで、どれも法に触れるようなことではなかったんだが。大学に入って、彼女――妻を両親に紹介しようとして、両親に休日の予定を聞いたら、妻の名前も初めてのデートがいつだったかも、全部知っていた。そこから他の話になったんだが、とにかく隠していたことは全部バレていたと分かった。知っていたのになんで一度も何も言わなかったんだって訊いたんだ。そしたら、別に悪いことはしていないのだし、特別に言うこともなかったからだって、笑って答えたんだ」
「同じです」
思わず武本は答えていた。武本と父親はともにあまり話好きではない。母の存命時は、母親が中心になって会話があったが、没後は必要最低限の挨拶や連絡事項的な会話しか交わしていない。けれど、武本が悩んでいれば、「どうした?」「何かあるのなら話を聞くぞ」と、常に声をかけてくれた。なぜ悩んでいると分かったのだろうと訊ねると、「俺はお前の父親だ。態度や顔を見れば、それくらい気づく」と、平然と答えた。
子供の頃から表情が乏しく、何を考えているのか分からないと武本は言われ続けていた。だが、父親はわずかな変化でも見逃さずに気づいていた。
「そうか。ずっと見守ってくれていたんだな、俺たちの親は」
浦島は微笑んで話し続ける。
「親になった今なら分かる。子供に興味を持って見守りつづけているからこそ、気づけるんだって。それが愛情だし、親としての責任だと俺は思っている」
浦島が言わんとすることが武本にも見えてきた。
「親に興味を持たれていない。だから彼女たちは店に通っているということですか?」
「親だけとは言い切れないとは思う。友達とか、彼氏に振られたとかもあるだろう。ただ、一番近い存在のはずの親から興味を持って貰えなかった子たちからしたら、金さえ払えば、キャストが相手をしてくれるメンコンは居心地の良い場となる」
目当ての商用ビルに到着して、中に入った浦島が案内板の前で立ち止まった。
「クリスタルプリンス、地下一階」
声に出して店を確認してからちらりとエレベーターを見て、一階に止まっていると気づいて下りるボタンを押す。すぐにドアが開き、中に入りながら浦島がまた話し出した。
「しかも、金を使えば使うほど特別扱いして貰える。他の客との競争もあるだろう。そうなると歯止めが利かなくなる子もいるはずだ。ホストクラブでは売掛制度もあって、高額の代金支払いによる事件がいくつも起こって社会問題にもなった。それで売掛制度を禁止すると発表した店もあるが、全店舗が廃止したわけじゃない。ましてメンコンは未成年に飲酒させたとかの違法店が話題になった。法には触れていないとしても、問題はいくらでもありそうだ」
エレベーターが止まり、到着音が聞こえる。開き始めたドアを前に「すまん、なんか語っちまった」と浦島は詫びた。子供がいる親の立場の浦島は自分よりもこの状況を重く受け止めているのだろうと武本は思う。
「さあ、キャスト捜しだ」
エレベーターから降りながら言う浦島の声は真剣だった。武本は「はい」と応えてそのあとに続いた。
(つづく)