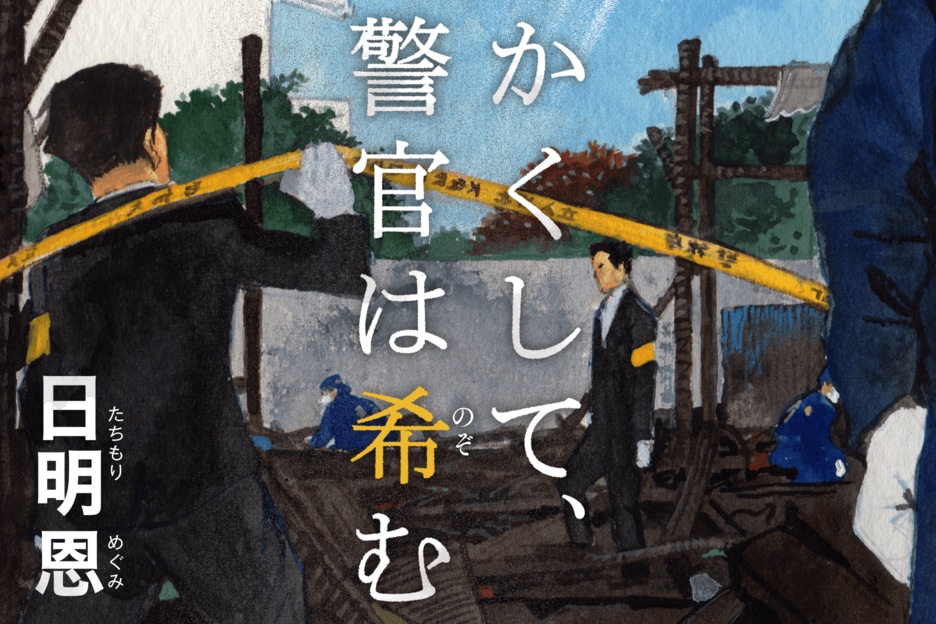近田コーポレーションの自社ビルに着き、受付で事情を説明し、近田歩に面会できたのは午前九時半だった。
「石原進について話を聞きたいそうで」
応接室でテーブルを挟んで向かい合ったのは清潔感のある短髪の中肉中背の青年だった。スーツ姿だったが、まだ着られている感が強い。
「詐欺とかですか?」
近田歩はずばりと罪状を出して訊ねた。
「いえ、違います。事件の被疑者の居場所を知っている可能性が高い人物なので、所在を捜しています」
「そうですか。あんなことがあって、それ以降は不登校で、僕も無視してたし、卒業後も没交渉なので、まったく知りません。お役に立てなくてすみません」
浦島の説明に応えた近田歩は、軽く頭を下げた。
「ここに来る前に、進さんのお母さんの泉さんに話を伺ってきました。それで、申し訳ないのですが、高校三年生の二学期に石原進さんに万引きをそそのかされた件をお聞きしてもよろしいですか?」
丁寧に訊ねた浦島に、「それ、事実は違うんですよ」と、近田歩は断りを入れてから説明し始めた。
「万引きをそそのかされたのは僕じゃなくて、やぐちん――矢口信行君だったんです」
本名に言い直して、歩は続ける。
「矢口君は小柄でおとなしくて、よく言うといじられキャラ、悪く言うといじめの標的になりそうな子で。石原と矢口君の二人ともシングル家庭だったこともあって、意気投合して最初は仲が良かったんです。でもあの日、たまたま店に居合わせて、見ちゃったんです。矢口君が万引きしたのを」
矢口を追いかけた近田歩は、店を出たところでようやく呼び止めることが出来た。「今返せば許して貰えるかもしれない。一緒に謝るから、返しに行こう」と説得した。だが矢口は「だって、こうしないと進に」と、泣き出したのだという。
事情を訊くと、「万引きしてこないと、仲良くしてやらないって言われている。何度もしていて、もうやめたいと言ったら、万引きしているのを親や学校、クラスメイトにバラすって脅された。だから、一年から今までずっとやり続けている。もう、どうしたらいいのかわからない」と、矢口は泣きながら答えた。話しているうちに店員が近づいて来るのに気づいて、とっさに「それ渡して」と、矢口から盗んだ商品を受け取り、自ら「すみません。ごめんなさい」と謝りながら、店員に商品を返した。
もちろん、それで話が済むわけはなく、二人はバックヤードに連れていかれ、双方の保護者が呼ばれることになった。保護者が来るまでの間に、近田歩はすべてを正直に話すように矢口を説得した。同席していた店員は、防犯カメラで万引きをしたのは矢口で、近田歩はまったく関係ないと確認したこともあり、賛同し、警察沙汰にはしないからと約束してくれた上で、矢口に保護者に正直にすべてを打ち明けることを勧めてくれた。
「だから、そそのかされていたのは僕じゃなくて矢口君なんです。でも、石原君の家に乗り込んだのは、矢口君の親ではなくてうちの親で」
店に呼び出されて状況を把握した近田の父親は激怒し、その足で石原の母親の勤務先を訪れた。奇しくも近田コーポレーションの所有する不動産屋に勤務していたのだ。
「親父はお母さんを解雇しました。それもあって、そそのかされたのは僕だってお母さんは思い違いしているのかもしれません」
その後の再就職もままならなかっただけに、そう記憶が改ざんされてしまったのかもしれない。
「石原は優しくしてくれそうとか、弱い立場の人を操るのに長けた奴でした。家が貧乏で、母親に暴力を振るわれていると聞かされた女の子たちは、文房具を皮切りに、お弁当を作ってあげたり、中には服をあげている子もいました。何しろ、ルックスは良かったから、アイツ。正直、面白くはなかったですよ。でも、問題がないのならとやかく言うことじゃないと思ってスルーしてたんです。でも矢口君のはスルーできなかった」
近田歩は正面の浦島の目を見て話す。そのまなざしから、彼の正義感の強さが伝わってきた。
「石原のお母さんに会ったあと、親父から聞きました」
激怒する近田歩の父親に、母親は平謝りに謝った。児童虐待をしていると聞いたと突きつけると、母親は「そんなことは絶対にしていない」と、泣き崩れた。そしてこれまでの息子の悪事と、どれだけ理解させようと努力しても同じことを繰り返すのだと訴えたそうだ。
「どちらが正しいのかは、僕には分かりません。でもどちらにせよ、進が嘘を吐き続けて、人の物を盗み続けるのなら、距離を取るだけです。もっとも、その一件がバレたあとは石原はほとんど登校してません。卒業式も来なかった。そのあとは完全に没交渉なので、今どこで何をしているのか、まったく知りません。お役に立てなくてすみません」
そう言うと、近田歩は再び頭を下げた。
最後に矢口信行の連絡先を訊ねると、「矢口は今、北海道なんですよ」と、歩が即答した。
「あの一件で仲良くなって。北海道大学の獣医学部に合格して今は大学院生です。発表した論文が学会誌に載るくらい将来有望な研究者です。もう大手食品会社の研究所の内定も貰っているんですよ」
嬉しそうに言いながら、近田歩は矢口の連絡先を教えるだけでなく、その場で連絡を取ってくれた。授業前だという矢口からは、改めて電話をする約束を取りつけることが出来た。
「もう一つ、伺いたいことが」と、断りを入れてから、浦島が「山上瑛大という人物をご存じですか?」と訊ねる。
「山上瑛大?――いや、聞いたことがないですね」
時間を掛けて記憶を辿ってから分からないと答えた近田歩は「石原の被害に遭った人ですか?」と、逆に質問してきた。
「いえ、私たちは山上を捜していて、石原さんが行方を知っている可能性が高いので、それで彼を捜しています」
浦島の答えに「そうだったんですか」と、近田歩は納得した。
最後にお礼を言って辞去しようとする浦島と武本に、歩は「石原が何か事件にかかわっているのならば、たとえ一見して無罪だとしても、疑って掛かった方がいいと思います」と言って、二人を送り出した。
石原の実家が経済的に恵まれていないのは事実だった。だが、それ以前に進の倫理観には問題があると、母親と同級生の近田の証言で知りえていた。加えて店の同僚たちと、かつては石原の常連客で、今はソープランドに在籍している豊本泰恵からの証言も加わると、石原の言葉は信憑性は薄いと疑って掛かりたくなる。
「男を運び出すために桃子さんに男の体格を訊きました」
石原の声に、武本は気持ちを引き締めなおす。
「僕より少し太っているけれど、背丈は同じくらいだと聞きました。入る大きさのスーツケースを山上さんが持っていたので、それを使うことになりました。でもそこで、部屋に入った人数と出た人数を同じにしないとダメなのでは? と思って。そう言ったら、山上さんが、僕をスーツケースに入れて部屋に行く。男をスーツケースに入れて、僕が男の服を着て男のふりをして桃子さんと山上さんと一緒に部屋を出る。それなら部屋に入った人数と出た人数が同じだと言われて」
すらすらとまでは言わないが、言葉を途切れさせることはない。
事前に弁護士の指導の下で供述を準備してきたとしても、あまりに自然な喋り方だった。
「上手くいくとは思えませんでした。でもそのときは、とにかく桃子さんを助けたい、それに自分も守りたいとしか頭になくて」
苦いものを吐き出したかのような言い方に聞こえはしたが、やはりどこか信憑性が感じられない。頭にしみこんでしまった先入観を武本は振り払って、入力作業に集中する。
「新宿区百人町二丁目の駐車場で合流して、桃子さんのいるホテル・サウスアイランドに行きました。事前に決めたとおりにして、また駐車場に戻って、中落合に向かいました」
ホテル内での行為の詳細は話さずに石原が続ける。浦島はそこを追及しない。今はいったんすべてを石原に喋らせるべきとしたのだろう。
「新目白通りの駐車場に入って、山上さんがスーツケースを持って桃子さんと一緒に車から降りました。戻ってきたらすぐに出発したいからと、僕は車で待つことになりました。何分かして、二人が戻って来たので駐車場を出ました。運転は僕でした。山上さんの指示に従って細い路地をぐるぐる回って、途中で僕は降りました。南長崎三丁目の公園の近くです。証拠を残さないように移動は徒歩で、防犯カメラに写らないようにしろと言われていたので、そこからは細い路地を選んで歩いて住んでいるマンションに戻りました」
石原の供述を信じるのならば、現時点では山上と石原二人の罪は遺体遺棄のみだ。
「歩いている間も家に戻ってからも、このままで済むはずがない。自首するべきだ。しなくちゃだめだって、ずっと考えてました」
苦悩と反省が入り混じった言葉を吐き続ける石原を遮るように、「桃子さんの居場所をご存じですか?」と、浦島がずばりと切り込んだ。
石原がびくりと身をすくませた。すぐには答えず、視線を左右に揺らしていたが、やがて口を開いた。
「――新大久保のホテルグレイ、三○一号室です」
武本は椅子から立ち上がって取調室を出ると、その足で捜査本部に向かった。
(つづく)