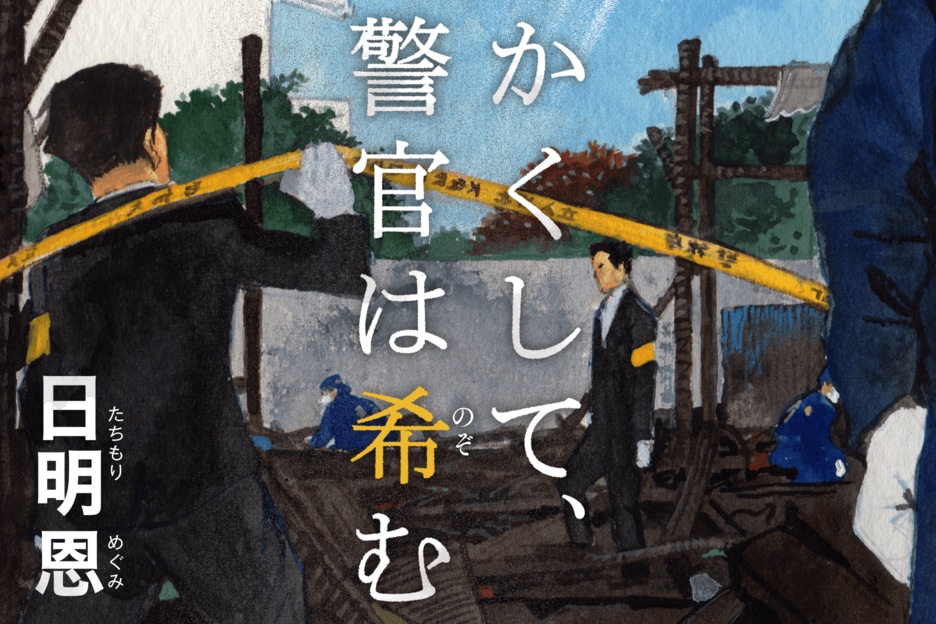昨日、浦島とともに山上と石原の出身地のある静岡市葵区で一日かけて聞き込みを行った。石原の存命の肉親は母親の石原泉だけだった。朝九時前にアパートを訪ねて、所属と氏名を名乗ると、ドアを開けて出てきたのは茶色く染めた髪が色あせて金髪に見える中年の女性だった。
「東京の警察が何?」
酒焼けらしい、しわがれ声で不機嫌そうに石原泉が訊ねた。寝起きなのか、服装は首の伸びたスウェットの上下で化粧もしていない。
「息子の進のことで話を聞きたい」と伝えると、「高校卒業後に出て行ってそれっきりで、どこにいるか知らないわよ」と即答された。唯一の肉親なのだし、連絡先くらいは知っているのではと食い下がったが、「携帯番号替えたみたいで、掛けても繋がらないのよ。まったく、恩知らずったらないわ。それで、何かしたの? 何をしてようが、あたしは知らないわよ。もう二十歳過ぎてんだし、なんだろうと本人でどうにかして頂戴」と吐き捨てられた。
進は被疑者ではなく、被疑者の山上瑛大の行方を知っている可能性があるから捜していると伝えたが、そもそも石原泉は山上瑛大のことを知らなかった。母親が知らない友人関係ならば、友人から話を聞くしかない。進の友人関係を訊ねた。
「進は友達ゼロだったわよ。わかんなくもないわ。ずる賢かったから。最初のうちは上手くいくのよ。あの子、見た目は良いから。でも、みんな離れてった。――ま、とうぜんよね。友達の物は借りパク上等、奢らせ続けるは、あげく万引きしろってそそのかすわだもの。そりゃ、みんな離れるわよ。向こうの親にどれだけあたしが頭を下げたことか」
「失礼ながら、注意は」
「したわよ!」
浦島の言葉を石原泉の怒鳴り声が遮った。
「妊娠九か月目、もう産むしかない状態になって、結婚の約束をしていたあの子の父親はとつぜん出て行ってそれっきり消息不明で。両親の反対を押し切っての交際の妊娠だったから、出産しても両親は何一つ協力してくれなかった。あたしは一人であの子を育てた。仕事と育児で生活はぎりぎりで、だから時間や愛情をたっぷりかけたとはあたしも言わない。それでも、物の善悪は教えてきた。なのに、幼稚園に入った頃から、買い与えてない物を家の中で見るようになった。借りたとか貰ったとか言われたけれど、そのままにしておけないから、名前がある物は、その子の家に一緒に返しに行った。そして言い聞かせた。人の物を借りたら返す。返さなければ、それは盗ったのと一緒だ。泥棒はしてはならないって!」
甦った記憶が爆発したかのように、石原泉は一気にまくしたてる。
「でも、駄目だった。そのときはしおらしく謝って反省するけれど、また繰り返すの。そのうちに、マジックで消してあったり、何かで削って名前が分からない状態の物になった。どうしたのって聞いたら、なんて答えたと思う? ゴミ捨て場で拾った、よ。どれも捨てられているような物じゃないことくらい、あたしにも分かったわよ」
石原泉の目には涙が盛り上がっている。
「しゃあしゃあと嘘を吐き続けるあの子をどうしていいのか、もうあたしには分からなかった。――もう、お手上げだったのよ!」
石原泉の頬の上を涙が滑り落ちていく。
「家を出た時、あの子、ウチの中の現金や、ちょっとでもお金になりそうな物は根こそぎ持って行ったのよ。頭にきたわよ。情けないったら、ありゃしない!」
そう言い切った石原泉は肩で息をしていた。
荒い息を整えてから「でも、正直ほっとした。いつかは何かもっと大きなことをしでかすに決まってるって、分かっていたから。出て行ってくれた助かったって思った。――酷い母親よね、あたし」と、吐き捨てると、石原泉は口をつぐんだ。
掛ける言葉を迷っているらしく浦島は口を開かない。そこで武本は話の中で気になっていたことを訊ねる。
「さきほど進さんが友人に万引きをそそのかしたと仰っていましたが、進さん本人が警察の厄介になったことは?」
話に聞いた進の悪事は、どれも警察沙汰にはなっていない。借りた物を返さない、人にたかる、そのどちらも友人間であり、告訴されなければ罪にはならない。唯一、明確に窃盗罪にあたるのが万引きだが、それも実行したのは友人で、進ではない。万引きをそそのかしたのなら、自身も経験がある可能性は高い。だが石原泉の口から警察沙汰になったとは出てきていない。
「一度もないわ。自分は手を汚さずに人にだけやらせたんだか、していたけれど、上手く立ち回って一度も捕まらずに済んだのか。どっちだろうと、どうだっていいわ。あたしには関係ないから。――もういい? 何を訊かれても、これ以上、話すことはないから」
そう言い捨てた石原泉の表情には、息子の進を守ろうと何かを隠している様子はまったくなかった。最後に、進が万引きをそそのかした相手の氏名を尋ねると、「近田歩。高校の同級生」と、即答した。
「忘れたくても無理よ。近田の家はこのあたりの地主で、そこいら中に親戚がいてね。それであたしは仕事はクビ。再就職もままならなくて。どうにか雇ってもらえたのが隣町のスナック。今もそこで働いてる。もう、いいでしょ!」
本当に進のことがどうでもいいのならば、知る人のいない新天地に引っ越すはずだ。だが石原泉は同じアパートに住み続けている。それは、やはり心のどこかで進からの連絡を待っているからなのだろうと武本は思う。
これ以上時間を割いても、何も得られはしないと判断した浦島と武本の二人は、進から連絡が入ったら教えて欲しいと告げて、石原泉に連絡先を渡してアパートを辞去した。
次に話を聞くと予定していたのは、進の高校時代の同級生たちだったが、近田歩が最優先となった。捜査本部に近田歩の現住所や勤務先等を調べてくれと連絡を入れた。すぐに調査結果が届き、勤務先である近田コーポレーションに向かう。
石原泉が言っていたように近田家は地元では多くの土地を持ち、不動産や飲食店などを手広く営んでいた。歩は近田家の次男で昨年大学を卒業し、今は家業のひとつである飲食店部門の事務職に就いていた。
(つづく)