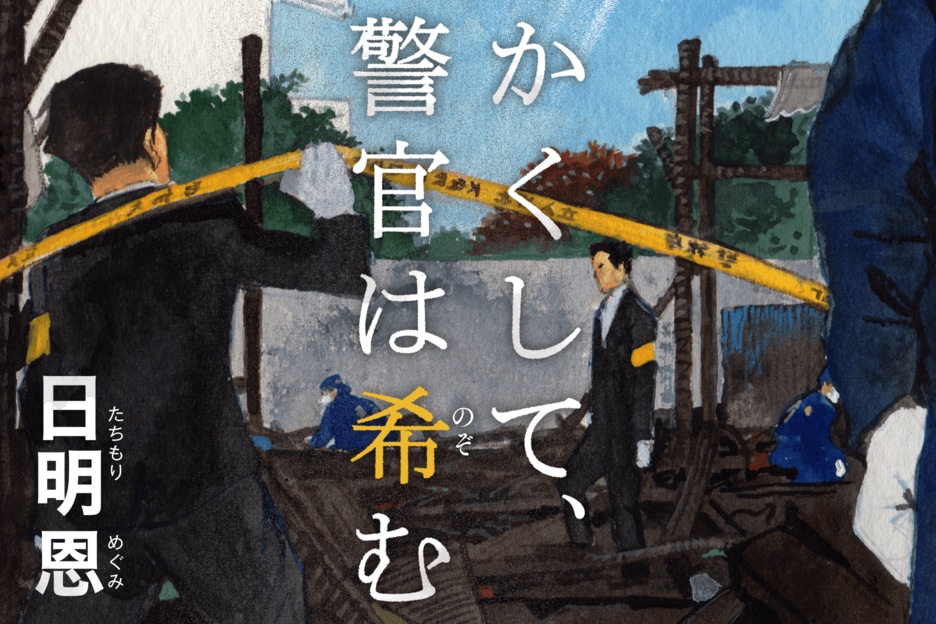14(承前)
頭を下げたまま上げようとしない石原に、「お話を伺わせてください」と浦島が声を掛けた。石原はゆっくりと姿勢を戻す。頭はうなだれたままだ。そして一つ小さく息を吐いてから、話し始めた。
「一月十二日の午後十一時七分に、僕の勤めているメンズコンセプトカフェのお客さんの桃子さんからLINE通話の着信がありました」
武本はLINE着信、日時と時刻、桃子という名前をパソコンに打ち込んだ。書記作業とはいえ、速記者のように一言一句漏れなく正しく打ち込んではいない。取り調べにはリズムがある。聞き取れずに、もう一度言い直させるなどして、被疑者や自供者、取調官の話の腰を折ってはならない。細心の注意を払って、ポイントとなる時刻、場所、人名、言動などを落とさないように記録し、取り調べ終了後、改めて文章化する。
「桃子という名前は、本人が名乗っているのでそう呼んでいますが、本名は知りません」
桃子という名前のうしろに本名不明と武本は付け足す。
「桃子さんは僕を気に入って通ってくださっていたお客様の一人です。店ではお客様と直接やりとりをすることは禁じられています。でも、売り上げを上げるためには、やはりどうしてもそうせざるを得なくて。僕だけでなく他のキャストも何人もそうしています」
石原が店の規則を破って客と直接交渉をしているという話は、石原について話を聞いた他のキャストたちから何度も出てきた。怒りをあらわにする者もいたが、どことなく歯切れの悪い者も数名いた。おそらく彼らも規則を破っているのだろう。
「桃子さんも直接連絡を取っていたお客様の一人です。本名もですが、年齢も聞いたことはありません。でも、たぶん二十歳にはなっていないと思います。それで、桃子さんはかなりデリケートな子で。他のお客様よりも頻繁に連絡がありましたし、それに応えないとその……」
言い淀んだ石原が、救いを求めるように浦島を上目遣いで見る。
「やっかいな客ですか?」
「いえ、そこまででは。ただ、人よりもちょっとセンシティブな子なんです」
桃子が面倒な客だと匂わせておきながら、取調官がやっかいな客と言うと、そこまでひどくないと否定した石原に、武本は引っ掛かった。
「そんな桃子さんから遅い時間に着信があったので、何かあったのかなと思いはしましたが、申し訳ないのですが、それがとうぜんだと思ってほしくなかったので折り返しはしませんでした。そうしたら、十一時十四分にまた掛かってきて、さすがに無視できなくて出ました。桃子さんは興奮していて、最初のうちは何を言っているのか、まったく分かりませんでした。とりあえず落ち着くまで話を聞こうとしているうちに彼女も落ち着いてきて」
石原はそこで言葉を切ると、こくりと一つ唾を飲み込んだ。
「正確に覚えてはないのですが」と、前置きしてから話し出す。
「一緒にホテルに入った男性に殺されかけて、逃げようとして蹴ったら、男が頭を机にぶつけて動かなくなった。部屋を出る前に声を掛けたけれど返事がない。足を軽く蹴ったら男が倒れた。後頭部が切れて血が出ていて、息もしていない。どうしていいのか分からない、お願い助けて。――と、泣きながらそう言われたんです」
――その男が現場から見つかった遺体だ。
供述内容は核心に近づいている。武本はポイントを落とさないように注意して入力し続ける。
「驚いて、いったん電話を切りました。正直、どうしたらいいのか、僕には分からなくて」
驚いた、どうしたらいいのか分からない。そう語る石原の声から、不安が伝わってきた。そこに芝居がかった過剰さはない。けれど、どこか落ち着いてもいる。
――華美ではない清潔感のある服装に、しおらしい態度。そのどちらもが弁護士の指導ありきの可能性は高い。
弁護士は、事前に供述する内容を聞き取るか、場合によっては文章にして提出させ、それを添削して、準備したはずだ。石原はそれを覚えて供述している。だから分単位まで日時が正確なのに違いない。
そもそも、弁護士に相談したうえでの自首というのが、やはり武本は引っ掛かっていた。
ただ年々、弁護士同伴の自首が増えているのは事実だ。情報化社会になった今、罪を犯した者が捕まったらどうなるのか、少しでも罪を軽くするためにはどうしたらいいのかなど、簡単にネットで検索できるようになった。弁護士事務所も仕事を得ようと、各事務所が競うようにホームページを立ち上げ、大々的に広告を打っている。それだけに利用するのは、もはやとうぜんのことなのかもしれないと、武本は思い直す。
「警察に通報する。そうすべきでした。でも、僕はパニックになってしまって、瑛大さ、山上瑛大さんにLINE電話をしました。同郷で親しくして貰っている先輩で、桃子さんのことも知っていたので」
いつもの呼び方から、フルネームに言い直して、石原が続ける。
「立ちんぼの客に殺されかけて、身を守っただけなのに殺人罪になるなんて、可哀そうすぎる。桃子が立ちんぼをしていたのは、お前の店の支払い、つまりはお前のためだ。なのに見放すのか? そう瑛大さんに言われました」
上目遣いで浦島を見る石原の顔は、少し歪んでいる。後悔と救いを求める感情が入り混じっているように見えもする。
「お客様のお金の出どころは探らない。そうじゃないとあの仕事はやっていけません。仕事は他にいくらでもあるのは分かっています。ですが、高卒の僕でも短時間でそれなりのお金を稼げる仕事はそう多くはありません。ホストの方が稼げるかもとは思いましたが、お客様に無理をさせる度合いが酷いと聞いて、とても僕には無理だと思って、それでメンズコンセプトカフェにしたんです。――でも、実際は同じようなものでした」
自嘲気味に石原はそう言った。
「桃子さんは頻繁に来て高額を支払ってくださるお客様でした。薄々は分かっていたんです。未成年の桃子さんがあれだけお金を準備できるのは、パパ活とかをしているのだろうなって。でも、接客し続けました。そのせいで、こんなことになってしまった。――助けてあげたいと思ったんです」
石原が口をつぐんで、机に視線を落とした。
供述の流れを止めないためだろう。「それで」とだけ、浦島が促すと、一つ息を吐いて石原が続ける。
「ホテルから桃子さんを逃がしても、いずれは警察に捕まってしまう。どうしよう、どうすれば? って、二人で話しているうちに、死体さえなければ、事件がなかったことになるのにって、思わず言ってしまったんです。そしたら山上さんが、ホスト時代のお客様から、空き家のまま放置している家が中落合にあると聞いている、そこならばとうぶんは見つからないはずだって。車はある。死体はスーツケースに入れて運び出せばいい、と。僕は何も言えませんでした。上手くいくはずなんてないと思ったからです。そうしたら、山上さんが言ったんです。桃子が捕まったら、とうぜん警察にお前に貢ぐために金が必要だったって話す。それだけじゃない。お前が店の規則を破って客と連絡を取っていたこともバレるぞって」
視線を上げた石原はすがるようなまなざしだった。
「そうなったら店はクビになる。一度悪評が流れたら、雇ってくれる店はありません。それだけじゃない。ニュースが拡散されてデジタルタトゥーになってしまったら、他の仕事でも雇ってもらえなくなるかもしれない。僕は実家が貧しくて、それが嫌で家を出ました。これからも生きるためにお金は稼がなくちゃならない。それで……」
石原の声が小さくなって消えた。
浦島の肩がわずかに動いたのを武本は見逃さなかった。石原は今は机に視線を落としているが、そうせずにいたとしても、気づかないほどのわずかな動きだった。
(つづく)