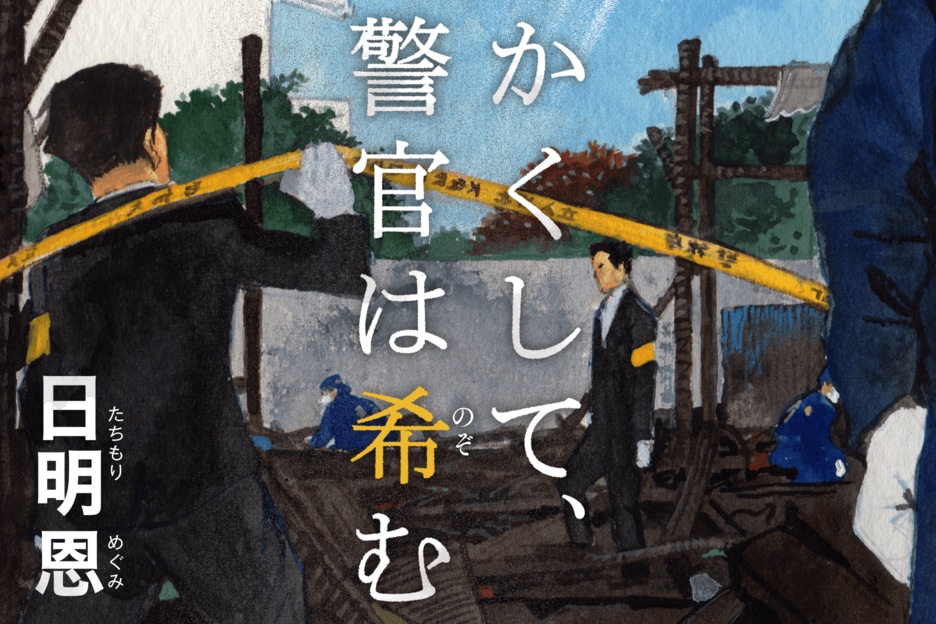「最近のテイクアウト事情って、びっくりするほどバリエーションがあるんですよ。お弁当も選ぶのを決めかねるほどの種類があって。僕の所属する係はベテランの先輩から若手の後輩まで年齢層が広く、三分の一は女性なんです。だから皆さんに満足いだたけるメニューを選ぶとなると難しくて。そうなると、ついおかずの種類の多い松花堂弁当を選んでしまうんですよ。それならば苦手でないおかずもあるだろうと思って。でも、いつも同じではつまらないので、今回はこちらにしてみました」
訊ねられてもいない弁当の選択理由を潮崎はぺらぺらと早口でまくしたてながら、武本の分に続いて自分の弁当の風呂敷をほどいて、机の上に並べた。
「それでは、御開帳です。まずはこちらから。じゃーん!」
効果音をつけて一つ目の弁当箱の蓋を取る潮崎に武本も倣う。八つに区切られた仕切りの中に、彩りよく総菜が詰まっていた。
「こちらは八寸ですね、小松菜と油揚げのお浸しと、わかめとタコの酢の物、玉子焼き、焼き物は鰆の西京漬けですね。おお、玉こんにゃくとは珍しい。それと牛肉と筍のしぐれ煮ですか。ちょっと野菜が少なかったかも。で、こちらが、じゃーん!」
潮崎は続けて二つ目の弁当箱をまた効果音付きで開けた。
「牛フィレ肉のステーキで、ご飯はビーフガーリックライスです。あっ、こっちにグリル野菜が。アスパラと黄色のパプリカにジャガイモ、それとミニトマト。ミニトマトって生でも十分に美味しいですが、グリルは一味加わってまた美味しいんですよ。僕、大好きなんです。では、いただきまーす!」
両手を合わせて食事の挨拶をすると、潮崎は箸袋から箸を出してさっそく食べ始める。
潮崎が準備したのだから、高級な弁当だろうと武本は予想していた。だが目の前の弁当は予想をはるかに上回っていた。武本が日頃、コンビニエンスストアで買って食べている弁当の比ではない。
初めて潮崎と同じ所属になった池袋署時代、潮崎は一人暮らしの武本の食生活を案じて、頼んでもいないのに親に頼んで準備させたおむすびと簡単なおかずの朝食を差し入れてくれた。もちろん武本は断った。そんな必要はないし、何より潮崎の家族に負担をかけるのは心苦しいからだ。だが、「僕は朝食を食べてきたのでお腹いっぱいでもう食べられません。お昼は仕事によっては署に戻って食べられるかわかりません。夜になったら、さすがに傷んでしまいます。今、先輩に食べていただけないと、廃棄することになってしまいます。それは、お米農家さん、海苔を採ってくださった漁師さん、加工して海苔をつくられた加工業者さん、中の具の鮭を取ってくださった漁師さん、卸して下さった業者さん、梅を育てて梅干を作って下さった農家さん、塩を生成して下さった業者さん、それらを販売して下さったお店の方すべてに申し訳が立ちません」と、まくしたてられた。
潮崎の言うことはもっともだった。確かにもったいないし、申し訳ない。武本はありがたく差し入れを受け取ることにした。だが、今回の弁当はその比ではない。
さすがに躊躇して、武本は箸を手に取ることが出来ない。
「前回は、さすがにやりすぎでした」
申し訳なさそうに潮崎が言う。
武本の異動後に久々の再会だというのもあり、潮崎の昼食の誘いに乗った前回、大変なことになったのを思い出す。潮崎は、庁内に寿司屋の板前を出張させたのだ。包丁入りのアタッシェケースを持った板前が刑事部の応接室で寿司を握ったあの昼食は、今でも部内で語り草になっている。
「でも今回は、僕の係の皆さんも同じお弁当をご家族の分も持ち帰っていただいています。ですからどうぞご遠慮なく。せっかくのお肉が冷めてしまいます。それでは牛を育てて下さった……」
「いただきます」
延々と続くであろう弁当の食材の生産者や卸業者、流通業者、料理した店に対しての申し訳なさへの語りを武本は遮り、弁当を食べ始める。一箸でお浸しをすべてつまみ、口に運ぶの見た潮崎が「よく噛んで食べて」と言ったが、かまわず飲み込んだ。
「まったく、変わってないなぁ。変わらないのが先輩の良いところだと思ってはいますが、こればかりは変えていただかないと。警察官、それも刑事は特に食事に時間をかけていられない職業なのは、僕も体験しているので分かっています。ですが、やはりよく噛まないと健康リスクが高くなってしまいます。時間の余裕があるときくらいは、意識してしっかり噛んで召し上がっていただきたいです」
潮崎が説教している間に、武本は酢の物と玉子焼きを食べ終えていた。それを見た潮崎が「――まぁ、今も日報作成の途中ですものね」と、複雑な表情を浮かべて自分を納得させる。
武本は続いて玉こんにゃくを口に入れる。
「こんにゃくはよく噛んでください! 喉に詰まったら大変です!」
切羽詰まった声と表情の潮崎に気圧されて、さすがに言われた通りに意識して咀嚼していると、「本当にお疲れさまです」と、潮崎が切り出した。
事件の話を潮崎がするのはいつものことなので、驚きはしない。
事件の被疑者は全員逮捕済みで、西田佳須美、山上瑛大の二名は罪状確定のうえで送検済みだ。残る石原進は、罪状は確定済みだが、人身売買のバイヤーの捜査に協力中でまだ取調べが継続されている。
捜査中はもちろん、終結しても事件の話は出来ない。それは潮崎も承知している。だから引き際を心得えたうえで持論を展開する。武本がするべきは、あくまで答えず、憶測は否定し、問題だと思えば止めることだ。今までと同じ心構えで臨むだけだ。
「どの事件捜査も大変なのは分かっています。ですが、今回は特にお疲れなのでは?」
武本も疲労を感じていた。両肩は常に重く、首を倒すと骨が重い音を立てて鳴る日々が続いている。だが、同意したら潮崎のことだ、大事にして何かしら大掛かりな手配をしかねない。口の中の玉こんにゃくを飲み込んでから、「いえ」と短く答える。
「そうは仰いますが、浦島さんのお疲れ具合いを見れば、先輩も同じように疲れてらっしゃるのだと思います」
二月二十日に石原進、山上瑛大の両名が自首して、翌日の二十一日から午前中は戸塚警察署で石原進を、午後は東京湾岸警察署で西田佳須美を取り調べる日々は、三月一日に西田佳須美を完全に送検し終えるまで続いた。
戸塚警察署から東京湾岸署までは、最寄りのJR高田馬場駅から山手線で新橋駅に向かい、新交通ゆりかもめに乗り換えて東京国際クルーズターミナル駅で下車するルートが運航の乱れが少なく安定していたので利用していたが、駅までの歩きや乗り換えも含めると一時間は超える。自己保身のために平然と作り話をしつづける石原進と、頑として石原には罪はないと言い張り、すべての罪を背負おうとする西田佳須美の取調べを並行して行うだけで浦島と武本は知力も体力も消耗していた。
ことに子を持つ親である浦島には、今回の事件は考えさせられるところが多く、辛かったのだろう。帰りのゆりかもめの車窓にぼんやりと目を向けている浦島の顔は、しばしば老け込んで見えた。
「佳須美さん、妹さんが面会に来てくれてよかったですよね」
苗字ではなく名前で西田佳須美の名を潮崎が呼ぶ。
「もしも妹さんと会ってなかったらと思うと……」
言葉を止めた潮崎が目をつむり、耐えられないと言うように痛ましい顔で首を左右に振る。芝居がかった仕草をするのが潮崎だ。だが、武本にもその気持ちは分かった。
石原進が罪を認めて自供した内容は、その日の午後の取調べで浦島から西田佳須美に伝えた。
これまで石原進を守るために罪をすべて背負おうとしていただけに、この事実を告げるのは辛かったし、聞いた後の西田佳須美がどれだけ傷つき悲しむかを想像すると不安でもあった。それでも、石原進の事件への関与に対する供述が、それまでと変わることを願って伝えるしかない。
取調室の西田佳須美の態度はこれまでと違っていた。前日までは椅子の背もたれに背を預けて足を投げ出して座っていたのだが、今日は少し背筋を伸ばしていて、足も椅子の下に揃えている。前日の妹の桃子との面会内容は留置係官の報告書で把握していた。妹との面会は西田佳須美に良い心境の変化をもたらしているようだ。だが石原進の自供内容は、西田佳須の心を粉々に打ち砕いてしまう恐れがあった。
それだけに、浦島は出来るだけ感情をこめないように淡々と話した。
山上瑛大から聞いた空き家の話を覚えていた石原進は、空き家が処分されるまでは遺体は見つからないと踏み、『桃子』で金を稼げると画策した。『桃子』を海外で売ると決めていて、その約束もすでに取り付けていた――。
西田佳須美が言葉を失った。顔色も青ざめている。そのまま、まったく口を開こうとしない。
事実が受け入れられずに拒絶して黙秘をしていると捉えた浦島は、「山上瑛大の録音音声がある。これは一月二十日、午後三時三十六分の録音だ」と説明してから、準備してきた音声を再生した。
『今日はどう?』
流れ始めた山上に話し掛ける石原進の声を聞いて、西田佳須美が顔を上げた。久しぶりに声を聞いたからだろう、今まで見たことのない蕩けた表情になっていた。
『朝から切れ目なく客がついてる』
山上瑛大の答えに続いて、『ルックスは下の中だから、大した稼ぎにならないし、何よりあいつ、面倒くさいんだよ。機嫌取るのもううんざりだ』と、石原進の声が取調室内に流れる。
西田佳須美の目が大きく見開かれた。
『売ればまとまった金になるし厄介払いも出来るから一石二鳥だ。今、ツテに当たっている』
見開かれた目に涙が盛り上がり、すぐに大粒の涙が零れ始めた。その涙を拭おうともせず、微動だにしない。
再生を止めた浦島は「二月十日、午後一時二十三分」と言って、次の再生をする。
『話が決まった。パスポートがいる。明日、実家に取りに行かせよう。ついて行って見張ってよ』
浦島が再生を止めた。室内から音が消える。
西田佳須美が右手を上げ、乱暴にぐいっと涙を拭ったのを見て、武本はティッシュを渡そうと立ち上がりかける。そのとき、「――立ちんぼをしろって言われたことはない。でも、他の太客がそういうことをしてるみたいなんだよ、って言われた。それで立ちんぼを始めた」と、西田佳須美が話し出した。
武本はそのまま席に腰を下ろして、今の発言を供述書に打ち込む。
「遺体を空き家に運んだあと、三人の逃走資金が必要だって言われて、ホテルの部屋にこもって瑛大が取ってきた客の相手をし続けた。それから、いつかは忘れたけれど、パスポートを持ってる? って、翼に訊かれた。必要? って訊き返したら、桃子を残して逃げるなんて絶対に出来ない。そのためにどうしてももっとお金が必要なんだって言われた」
怒りに任せるでもなく、絶望して嗚咽するでもなく、淡々と西田佳須美が供述を続ける。
だが、目からは涙が流れ続けていた。供述を打ち込みながら、ティッシュを渡すべきだろうかと武本が悩んでいると、浦島がちらりと視線を寄越して、すぐに戻した。今は流れを遮るべきではないということだと理解して、供述書に専念する。
「二月十二日に一緒に実家に行く約束をしてた。でも店の後輩の具合が悪いって、ドタキャンされた」
すでに押収した西田佳須美のスマートフォンから、その日のやりとりは把握しているが、浦島は止めずに、話を続けさせる。
「そのあと数日して、実家から持ち出したブランドのバッグやアクセサリーを売ってお金に換えたし、それにお客もかなり取っていたし、勝手に動画を撮影した客から取った慰謝料も合わせれば四百万くらいになってたはずで」
勝手に撮影した男から慰謝料を取ったという初めて聞く話が出てきた。
「もう行けるだろうって思って訊いたら、メキシコのカンクンに行こうって言われた。日本人と会う率が低いし、仕事もあるからって。でも飛行機代やその先の生活費を考えるとまだお金が足りない、全部で五百万円は必要だって言われた。あと百万円、一週間頑張れば貯まるから任せてって言った。そしたら、警察が捜査を進めているから時間がない。だから、撮影許可にして、客も一度に二人とか、それ以上にするって」
石原進の非道さに、怒りがこみあげ、キーボードを打つ武本の指に思わず力が入った。
その音に驚いたのだろう、西田佳須美がこちらを見た。とうぜん供述は止まってしまった。
西田佳須美の声が止んで、室内の音が消えた。話し出すのを待つか、あるいは浦島に上手く促して貰うしかない。流れを止めてしまった失態を武本が反省していると、西田佳須美が再び口を開いた。
「――マジ、あたしって馬鹿だわ」
脱力した声でそう言うと、西田佳須美が続ける。
「メンカフェのキャストだもの、客のことはお金としか思ってないんだろうなって、本当は気づいてた。でも、可愛い、素敵だとかの分かりやすい上っ面のセールストークだけじゃなくて、そのままで十分可愛いって、あたしのしてることとか考えていることを全部正しいって認めてくれたのは、翼だけだった」
西田佳須美の両親の事情聴取もしている。父親もだが、ことに母親の口は重かった。それまで補導歴もなく、学校からの証言でも問題行動を起こしていない長女が、昨年の七月初旬に家出をしたのに今まで捜さないどころか、連絡すらしていなかったのだ。これには、言い訳のしようもないのだろう。
母親は、親としての義務を放棄したことへの反省は口にしていた。だがときおり、難しい子で、何を考えているのか分からないとか、親子でも、やはり気が合わないものは合わないなどと、自分だけに責任があるのではなく、長女にもあるのだとほのめかした。
今回の事件を通して、浦島が取調べで声を荒らげて、怒りをあらわにしたのは、西田佳須美の両親への事情聴取の時だけだった。
「あんたたちは未成年の子を見放したんだ。親の義務を果たしていない奴が、被害者面をするな!」
浦島の怒号に、父親は身を小さくして謝罪した。母親も同じようにしていたが、うつむいた横顔の口元は不服そうに歪んでいたのを武本は見逃さなかった。
西田佳須美がしたことは犯罪で、許されはしない。すべて本人が選択して今に至った。だが、こうなってしまった理由は、多分に両親にあったのだと武本は思った。
頭にあのときの母親の醜い横顔が甦り、消し去るためにぶるっと頭を振る。
「あんなクズに貢ぐために立ちんぼして、それで人を殺しちゃって。なのに、あいつに相談したなんて。ホテルの部屋からほとんど出ずに、休みもほとんどなく、客としまくった。それに家の物まで持ち出して売って。そのお金を全部渡してたなんて。――ほんっと馬鹿。どうしようもない馬鹿だわ」
脱力した声でそう言うと、姿勢を正した。
「でも、あの男の人を殺したのはあたしです。ごめんなさい。本当にごめんなさい。罪はきちんと償います」
言い終えた西田佳須美が、深々と頭を下げる。
急激な変化に、浦島が「大丈夫かい?」と優しく訊ねる。
「自分でしたことの責任を取ります」
そう気丈に答えると、「あたしも自分にならなきゃ。――妹みたいに」と、小さく呟いた。
妹の桃子が西田佳須美の心の支えになってくれたからこその変化だろう。浦島と武本の二人は妹の桃子に感謝した。
「妹さん、三日にあげず面会に来てくれているんですってね」
その後も妹の西田桃子は、姉の佳須美の面会に頻繁に訪れている。そのたびに佳須美は態度を改めて、深く反省を示すようになっていった。
「しかし、まさか桃子さんが、音音だったとは。驚いちゃいましたよ、あの曲を作曲した当時、十五歳だなんて」
被疑者の面会内容の詳細まで潮崎は知っていた。それが潮崎という男なのはもう分かっていたが、さすがにどうなのだと思って、じっと見る。
「いや、素晴らしいです。まさに天才……」
視線に気づいた潮崎はそこで言葉を止めて、ばつが悪そうな顔で玉子焼きを口に運んだ。武本も弁当をまた食べ始める。しばらくは無言で二人とも弁当を食べていた。
潮崎が手配しただけあって、ステーキは美味しかった。美食家とは言えない食生活をしている武本にも、これは高級な肉だと分かる。
「お気に召されたようで、嬉しいです」
不思議に思って潮崎を見ると、「先輩は美味しいと思われた時、少しだけ口の端が上がるんです。今、上がっていたのでステーキを美味しいと思ってくださったんだな、と思って」
嬉しそうに潮崎が微笑んでいる。
「でも出来れば、美味しいと思われた時は、もう少し伝わるように表して下さった方がよろしいかと。前回お呼びした板前さん、自信を喪失なさってたんですよ。『マズイと思われてはなかったかもしれないが、美味しいと感じているとも思えなかった』、って」
周囲の注目を浴びた仰々しい昼食だっただけに、少しでも早く終えようと喋らずに完食したが、板前が握ってくれた寿司は驚くほど美味しかった。なので、「ご馳走様でした。とても美味しかったです。ありがとうございました」と、きちんと忘れずにお礼を伝えた。だがそんな風に思わせてしまったのなら申し訳ないことをした、と武本は思う。
「顔の構造上、先輩は表情がないというか、死んでいるも同然なんです。他の人では気づけないほどですが、僕は分かっています。ちゃんと美味しいと思われてます。なんなら、今までで最高に喜んでいます、と伝えておきましたけれど」
誤解を解いてくれたことには感謝するが、前半は酷い失言だ。だが注意をしたら、また面倒くさいことになるので、武本は黙って箸を進める。
「ああ、しまった!」
箸を置き、掌でぴしゃりと潮崎が額を叩いた。
「肝心なことがあとになってしまいました。今回の主犯というのか、一番罪の重い極悪人の石原を落としたのは先輩だと、浦島さんから伺いました。やっぱり、先輩はすごいです」
こちらを見つめて潮崎が興奮した声で言う。
「それは違います。取調べを担当したのは浦島さんです」
「いえいえ、浦島さんが言ってました。石原が落ちたのは、先輩が『今、罪を認めるのと、証拠が出てから認めるのと、どちらが得なのか、お前ならば分かるはずだ』と言ったからだと」
否定した武本にすぐさま潮崎が言い返した。
浦島に悪気はなかったのだろう。だが、潮崎に話したことには不満を覚える。きちんと否定しなければ肯定したとされ、この先ずっと潮崎は自分を持ち上げ続けるだけでなく、話を吹聴しかねない。それは阻止しなくてはならない。
「あれは、宇佐見君がいつも言っている、数で考える人間には、数を示せば理解するというのの受け売りです。真の立役者は宇佐見君です」
取調べ後、武本の一言が効いたと褒めてくれただけでなく、お蔭で落とすことが出来たと浦島に感謝されたときと同じことを言い返した。
「そう浦島さんにおっしゃったとも、聞きました。それで、さきほど宇佐見君に知らせに行ったんです。そうしたら」
紙コップを手に取り、一口ごくりとお茶を飲み終えてから、潮崎が続ける。
「『僕だけの発想ではありません。同じように考えている人はいくらでもいます』って。だとしても、少しは喜んだり、誇らしく思っても良くありませんか?」
宇佐見らしい返事だと武本は思う。
「それはそれとして、宇佐見君も石原を追い詰めた立役者の一人じゃないですか。事件解決が嬉しいだろうと思って、感想を聞いたんです。ところが」
宇佐見はもちろん事件解決を喜んでいた。だがその口ぶりは、どこか苦々しかった。理由を尋ねた潮崎に、宇佐見はこう返したそうだ。
本当に賢い犯人は、法を熟知して抜け道を見つけだして、証拠となる数字が世に出たところで問題にならないように扱います。どころか、発覚すらしないように犯罪を行います。それに比べたら、脱税で言えば石原はただの馬鹿です。その場しのぎで数字に嘘をつかせようとした。僕に言わせれば珍しくなく、よくいる馬鹿です。ただ、今回の事件で脱税はあくまで氷山の一角、どころかおまけみたいなものです。事件全体を通して考えると、石原は相当頭の回る悪党です。なのに脱税という愚かなミスをしている。事件の犯人は全員逮捕されて捜査は終結しました。ですが、未だに僕の中で石原という男の人物像が定まらない。それがどうにも気持ちが悪いんです。しかもこれは、この先どれだけ考えても正解にはたどり着けないでしょう。僕は、そういうのが一番苦手なんです――。
例の如く抑揚のない早口で憤りをまくしたて終えると、「お弁当をありがとうございます。それでは、お先に失礼します」と言って、潮崎を残して宇佐見は退庁したのだという。
「お弁当を両手で持って早足で歩く宇佐見君は、まさに茶運び人形でした」
何かに感激したような口ぶりの潮崎をよそに、武本は弁当を食べ進める。
人物像が定まらない、石原進を宇佐見はそう評した。それは武本も同じだった。
石原進は自分の利益と自己保身のためならば、いくらでも嘘を吐く。しかも証拠は何一つ残さない。幼少期に友人から借りた物を貰ったと言い張ったり、記名を削り取ってゴミ捨て場から拾ったのだと釈明したり、中学では金の貸し借り、高校では恐喝へと発展した。
だが、どれも相手がおかしいと判断して、正すべく行動すれば阻止できたはずだ。高校の同級生の近田歩のように。
そこで武本は間違いに気づいた。近田歩は石原進から直接の被害を受けていない。脅迫されて万引きさせられていたのは矢口信行だ。それに、クラスメイトの飯島千佳、布川理恵、蒲原良子は石原に立ち向かった。だが証拠がないのを良いことに、逆に悪評を流布されて三人は窮地に追い込まれた。
石原進は獲物を選んでいるのだ。孤立していて、人として隙や、どこか弱さのある相手を見つけて近づき、信頼を得る。そして弱みを握り、支配する。
今回も同じだ。両親から相手にされずに孤独だった西田佳須美は格好の獲物だったのだ。
石原のことを考えていたら、食べ物の味がしなくなったような気がする。せっかくのステーキ弁当に申し訳ないと思い、気持ちを弁当に集中させる。
「宇佐見君の言葉に、改めて考えたんです。――もしも栗林渉が放火していなかったら。放火しても、火事になっていなかったら、と」
武本と浦島の二人も、同じ考えに至っていた。
栗林渉があの空き家に放火して火災になっていなかったら、こんなに早く遺体は発見されていなかった。遺体が発見されていなければ、西田佳須美は海外で人身売買されていた。いずれ空き家は処分され、遺体は見つかっただろう。だが年単位で時を経ていたら、周囲の防犯カメラの映像も犯行時のものは消去されて残っていなかった。そうなっていたら、石原進と山上瑛大の逮捕は難しかっただろう。何より、西田佳須美の身の安全の保障はなかった。
石原進の目論見通りならば、西田佳須美を売った金を手にし、逮捕されることもなくメンズコンセプトカフェのキャストを続けて、何人もの女性を食い物にしていたに違いない。
宇佐見の言うように、石原進は頭の切れる悪党だ。だが、誤算が生じた。それが栗林渉だ。
「そう考えると、放火という絶対に許されない犯罪に手を染めてしまった栗林には感謝したい気持ちも湧いてきたりして。――絶対にダメなんですけれどね」
潮崎の心情は武本にも理解できた。
実は、浦島と武本の間でまったく同じ内容の会話を交わしていたのだ。だがこれは潮崎に言うべきではないと考えて、武本は無言で弁当を食べ続ける。
「それにしても、山上はよく録音してましたよね。あれがなかったらと思うと、こちらもぞっとします」
大仰に身を震わせて潮崎が言うのを聞いて、これも潮崎の言う通りだと武本は思った。
山上瑛大もまた、石原進の誤算だった。
いいカモだと思い、石原進は山上瑛大に近づいた。地元にいた頃は、確かにそうだったのだろう。だが二年先に上京して新宿でホストをしている間に山上瑛大は世間慣れして、昔とは変わっていたのだ。
桃子を軟禁して売春させはじめてから、証拠が残るやりとりはすべて自分がしていると気づいた山上瑛大は、違和感を覚えて、録音し始めたのだという。
想定していなかった二つの誤算によって、警察は石原進の罪を暴くことが出来た。だが、それは放火という重罪と、石原進の共犯者の山上瑛大の自己保身のお陰だ。その事実が、武本の胸に今も重くのしかかっていた。
(つづく)