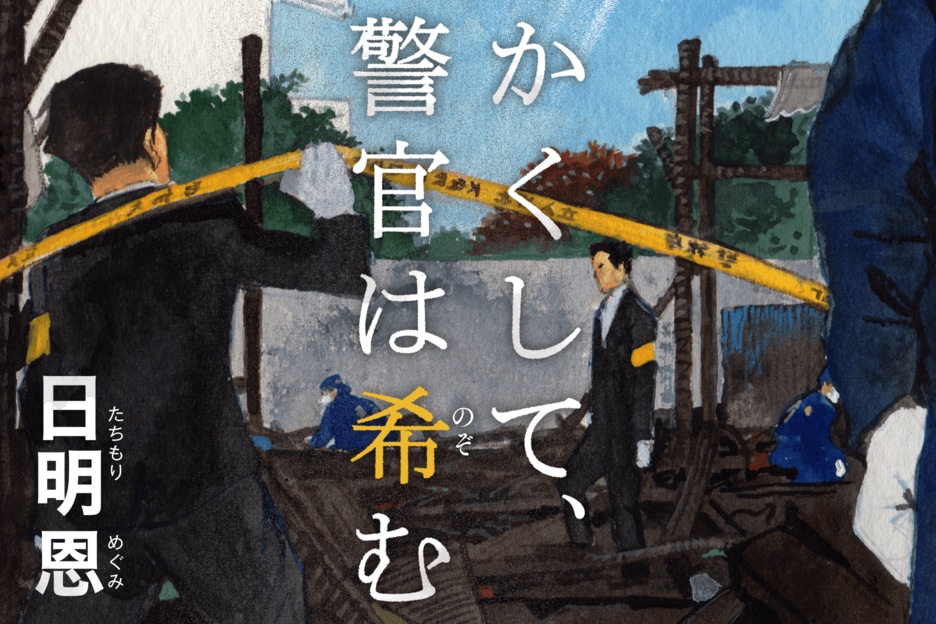22
それまでと態度を一変させた石原を見た武本は、これからだと気を引き締めて、「シクった」という石原の発言を供述書に打ち込んだ。
ファイルから山上瑛大の供述書を取り出して机の上に広げながら浦島が続ける。
「山上瑛大とお前の出会いは九年前、山上が高校二年生、お前が中学三年生の六月のことだ。山上がスーパーマーケットで男性化粧品を万引きして店外に出たところ、あとからお前が追いかけてきた。山上はマズい、脅されると思ったが、違った。お前は山上に自分が万引きしてきた菓子を見せて、『あの店、チョロイよね』と言った。意気投合したお前たちは連絡先を交換し、それ以降、定期的に会うようになった」
浦島は供述書に目を落としていない。取調べに入る前に読み込んで内容を記憶したのだ。
「飲食店で過ごしたりもしたが、会った時は必ず万引きや置き引きをしていた。多いときは週に一度、少ないときでも月に一度は犯行を重ねていて、それは山上が高校を卒業して上京するまで続いた」
淡々と山上瑛大と石原進の関係性を浦島が挙げていくと、石原が動いた。これまで取調べの間ずっと、椅子の背もたれに背はつけず、常に少し前傾姿勢で、両脚は開かず揃えていた。だが今は、背もたれに身を預け、脚も開いている。
「山上の上京後はSNS上のみでの関係で、やり取りの頻度も低くなった。だが六年前の十月三日以降、お前からの連絡は急激に増えた。内容は、母親に男が出来た。そいつに暴力を振るわれている。家を出たい」
石原の同級生の近田歩の証言では、石原に脅されて万引きをしていた矢口信行をかばって、二人揃って店に捕まったのが十月一日のことだった。翌日以降、石原はほとんど登校しておらず、山上に窮状を訴え始めた。
「お前の母親の石原泉に確認を取った。その当時、交際相手はいなかった」
石原が身を起こした。閉じた膝の上に両手を置き、前屈みでうつむいたまま「あの人の言うことを信じるんですね」と、呟いた。
「嘘だと?」
「母親のことを悪く言いたくはないんですけれど、あの人は男性がいないとダメな人で。しかも、男を見る目がまったくない」
悲しそうな声で言いながら、石原進が顔を上げた。途方に暮れたような表情を浮かべている。
石原進の母親・石原泉は息子が遺体遺棄で逮捕勾留されたと知って動揺した。電話口の浦島の話を聞こうとせず、自分は何をどうしたらいいのかだけをひたすら訊いてきた。浦島は根気強く、石原進は弁護士を伴って自首し、そののちの逮捕だということ、勾留中に必要な服や物は弁護士や知人が面会に来て渡しているので、現時点では何も問題ないと説明した。
息子が窮していないと理解した石原泉がようやく落ち着いたので、浦島は改めて石原進が山上瑛大に送った六年前のLINEの内容の事実確認を行った。
質問された石原泉は絶句していた。しばらくしてもたらされた答えは、「そんな事実はない」だった。それだけでなく、進の中学時代には交際していた男性がいたが、進が相手の財布から複数回お金を抜き取ったことが発覚して関係が終わったことを明かした。通話の最後に石原泉が疲れ果てた声で漏らしたのは、「私にはもう、あの子のことが分からない」だった。
石原進の人物像を掘り下げるべく、出身地で中学高校の同級生に追加調査を行っていた捜査本部員が、泉が当時交際していた男に話を訊ねに行き、事実だと確認が取れた。
「二月二十日の午前八時半過ぎに、俺たちはお前の母親に会って話を聞いてきた。中学時代から、母親に暴力を振るわれていると同級生に言っていたそうだな。だが、そんな事実はないと彼女は証言している」
「――そう言うでしょうね」
石原が小さくため息を吐いて、先を続ける。
「通院していないので、証明のしようもありませんけれど。体を殴られたり蹴られたりしていました。人に気づかれたら、マズいことになると分かっていたんです」
悲しげな表情ですらすらと言う石原を見て、武本は大したものだと思った。
客観的な証拠がない以上、被害者側と加害者側どちらの言い分も立証は難しい。だから石原と母親の証言は、いつまで経っても平行線で交わることはなく、落としどころもない。
だが浦島と武本は、すでに直接、母親の石原泉と同級生の近田歩から証言を得ている。さらに捜査本部員の追加調査報告も届いている。それらから、石原進の言葉の信憑性は薄いと判断していた。
「母親の話を聞いたあとに、お前の高校の同級生の近田歩さんと面会した」
近田歩の名を聞いた石原進の眉がぴくりと動いた。
「矢口信行さんとも電話で話した」
石原の顔から悲しげな表情が消えていく。
「他の捜査員がお前と中学二年のときにクラスメイトだった飯島千佳さん、高校一年のときのクラスメイトだった布川理恵さん、二年時のクラスメイトの蒲原良子さんからも証言を得ている」
母子家庭で経済的な余裕がなく、食べる物、衣服、文房具等で困っている。母親からも暴力を受けている――。
石原進の言葉を信じた彼女たちは、お弁当や文具や洋服をあげたりしていた。けれどそれを一年後には止めていた。さらに今も石原と交流が続いている者は誰一人いない。そうなった理由は三人とも同じだった。
三人とも石原にお金を貸していた。最初は小銭だったのが千円単位になった。その頃は返済されていたこともあり、数万円の借金を申し込まれても、また返して貰えると思って貸した。だが、返済はなかった。返して欲しいと言っても、のらりくらりと誤魔化されつづけるだけでなく、さらに金を貸してくれと頼まれた。さすがにこれ以上はお金は貸せない。貸すにしても、まず借金を返して欲しい。返してくれないのならば、大人に相談すると強い態度を示したとたん、一方的に熱を上げられて付きまとわれて困っていると周囲に吹聴したというのだ。
三人とも石原の言っていることは嘘だと反論しようとした。だが、お金を貸したときは全部口約束で、しかも現金を手渡ししていた。SNSでのやり取りもなく、とうぜん借用書もない。それもあって、借金を踏み倒されたことの立証は出来なかった。
「ずるいのは、私がお弁当やお菓子や文房具をあげていたことはきちんと認めるんです。そのうえで、『勘違いさせてしまった僕が悪いのだけれど』と前置きして、『でも、それで恋人だと思われるのは』って……」
話を聞かせてくれた中学時代のクラスメイトの飯島千佳は、この話が広がった結果、なぜか自分が悪いとされてしまった。周囲から白い目を向けられ、揶揄されたり冷たい態度を取られて学校生活が辛くなり不登校になってしまったのだと辛そうな声で証言した。高校時代のクラスメイトの布川理恵、蒲原良子の証言も、似たり寄ったりだった。
今回、石原について話を聞きたいと訊ねると、返ってきた第一声は三人とも、「詐欺ですか?」だった。口を揃えたかのように、まったく一緒だったと現地に赴いた捜査員たちは言っていた。そしてこれは、浦島と武本の二人が面会した近田歩も同じだった。
「飯島千佳さん、布川理恵さん、蒲原良子さんの三名はお前に金を貸して踏み倒されたと証言している。矢口信行さんは、お前に脅されて万引きをさせられていたと言っている。相手とのやり取りを残さないのは、この頃からだったんだな」
淡々と告げる浦島を、石原が見つめている。その顔からは何の表情も読み取れない。石原の目がわずかに動いた。
「千佳ちゃんや理恵ちゃん、良子ちゃんは、僕に優しくしてくれていました。当時の僕は本当に暮らしに困っていたので、貰える物はありがたく貰っていたんです。彼女たちの優しさに甘えて、何でも貰ってしまっていた僕が悪かったんです。そのせいで彼女たちに勘違いさせてしまった」
申し訳なさそうに石原が言う。それは飯島千佳から得た証言とまったく同じ態度だった。
「やぐちんは、僕の大事な友達でした。でも、一人で勝手に万引きをして捕まったのに、急にあんなことを言い出して。――ショックでした。さらにショックだったのは、やぐちんのした作り話を真に受けた近田君がその話を言いふらしたことです。近田君は良く言うスクールカーストの上位にいて、何しろ地元の権力者の息子でしたから。だから皆それを信じてしまった。そんな状態ではとてもではないけれど、登校なんて出来なくて」
肩を落とし、項垂れて切々と語る石原の姿は哀れに映る。
「でも、それだけじゃすまなかった。僕の母親は当時、近田君の父親の系列会社に勤めていたんです。でもこの一件で母はクビにされました。それから母から僕への仕打ちは以前の比じゃなく酷くなった。――もう地元には僕の居場所はなかった。だから上京したんです」
悲しそうに自分こそが被害者だと石原は訴える。その内容を武本はひたすら調書に打ち込んでいく。
これまで武本は何人もの被疑者の取調べを経験してきた。取調べの最初から罪を認めてすべてを話す被疑者は多くない。現行犯の緊急逮捕者ですら黙秘する者もいる。そんな被疑者たちは、取調べの中で証拠を列挙されて言い逃れは無理だと悟ると態度を変える。
ただ、それにも二つある。一つは、少しでも罪を軽くするために、素直にすべてを正直に話す。もう一つは罪を軽くするためにまでは同じだが、その犯行は不可抗力だったのだと強調する。
石原は明らかに後者のタイプだ。だが悔しいが、過去の借金や脅迫行為に関しては証拠がない。
武本は石原の作り話をひたすら調書に記録し続ける。仕事だと分かっていても、ストレスを感じていた。だが、直接石原と向かい合う浦島は、自分どころではないだろうと思いなおして、気を引き締める。
「飯島千佳さん、布川理恵さん、蒲原良子さん、矢口信行さんの四名については、お前から受けた被害を立証する証拠は何もない。お前が母親から暴力を受けていたというのと一緒だ。だから残念だが、これらについてはお前を罪に問うことは出来ない」
苦々しい声で話していた浦島が、そこで一度言葉を止めた。再び口を開くと、「だが、今回は山上瑛大の録音がある」と、今度は張りのある声で断言する。
石原の瞳が小さく速く左右に動き出す。それがぴたりと止まり、うつむいた。少しして首を垂れたまま、「――冗談です」と呟いた。
勢いよく石原が頭を上げた。すがるような目で浦島を見上げて、口を開く。
「冗談だったんです。正直、桃子さんをどうしていいのかもう分からなくなっていました。彼女を助けたいと思って、だから死体遺棄をしてしまった。でも、やっぱり怖くなって、それで桃子さんがどこかに行ってくれればと思い始めていたんです。でも桃子さんは自分だけでなく、瑛大さんや僕の逃走資金を稼ぐと言って――。そんなこと、僕は頼んでいません。勝手に桃子さんがしていただけです」
悲痛な声で助けを求めるように石原が言う。
それをただ聞き、記録を取り続ける武本の胸の奥から怒りがこみあげた。キーボードを叩く指に力が入ってしまい、大きな音が出る。石原の視線がこちらに向いたのに気づいて心を落ち着けようと、武本はいったんキーボードから指を離した。
石原が浦島に視線を戻して訴えを続ける。
「僕はもう、桃子さんと離れたかったんです」
「海外で人身売買しようと言うのと、どう繋がるんだ? 離れたいのならお前が立ち去ればいい」
思わず武本は言ってしまっていた。浦島の邪魔をしたのは分かっていた。だが止められなかった。石原が目を見開いてこちらを見ている。
「それは……」
石原はそこで一度言葉を切ると、目を閉じた。再び開かれたときには、今度は武本に救いを求める目つきに変わっていた。
「その通りです。僕が離れればよかった。でも、これまで築きあげた生活を簡単に捨てる勇気がなかったんです。甘えでしかないのは分かっています。でも、そのときは自分のことしか考えられなかったんです」
しおらしく後悔の念を表明する。
許容できる非は認め、反省を示す。これが石原のパターンだ。だがそれは真の罪を逃れるための嘘でしかない。石原の保身能力の高さに武本の背に怖気が走る。
「売ればまとまった金になるし、厄介払いも出来るから一石二鳥だ。今、ツテにあたっている」
浦島が感情のない声で告げた。石原が山上瑛大に発した言葉だ。身を乗り出して石原が言い訳する。
「追い詰められてたんです。どうしていいのか分からなくなって、もう、誰でもいいからどうにかしてくれって、それしか考えられなくなっていた。そんなときに、ネットニュースか何かでそういう事件があったのを思い出して。――それに」
言葉を切った石原の目に涙が盛り上がる。ぽろりと涙の粒が頬に零れ落ちるのと同時に、また話し出した。
「平然と桃子さんに客を取らせている瑛大さんが怖くなったんです。ここで僕が逃げ出したら、何かされるかもしれない。それでつい、嘘を吐いてしまったんです。ああいうことを言えば、一目置くから僕には手出ししないだろうと思って。僕が馬鹿でした」
最後は消え入るような小さい声で言うと、石原は口をつぐんだ。
これまでの取調べの質疑応答では、証拠がないだけに石原の言い分も聞かねばならないと考えざるを得なかった。だが、今回は録音という証拠がある。さすがに言い抜けるのは無理だろうと武本は思っていた。だが石原は、あくまでもシラを切るつもりらしい。
――これで言い抜けられると本当に思っているのだろうか?
武本には平然と嘘を吐き続ける石原が理解できなかった。
こみあげ続ける怒りに、理解できない薄気味の悪さが加わって、息が詰まったような錯覚を覚える。
「思ってたより馬鹿じゃなかったんだ。シクった、と言ったよな」
これまでになく鋭い浦島の声に、石原の視線が戻る。一瞬詰まったが、すぐに「まさか本気にして録音するとは思ってなかったんです。それで僕が疑われて、つい腹が立って言ってしまったんです」と言い返すと、頬を伝う涙を指で拭った。
石原は呼吸をするように嘘を吐き続けている。
知らずにまた力が入っているのに気づいて、武本は石原に見えないようにして、握っている両手を開く。
「お前のスマホからシグナルの利用痕跡が出た」
冷静な声に戻した浦島の声が聞こえる。
逮捕の際、証拠として押収した石原進のスマートフォンはすぐさまSSBCが分析捜査を行った。その結果が今朝の捜査会議で発表されたのだ。
「シグナルなら証拠は残らない。そう思っていたんだろう? だが、大間違いだ」
SSBCの捜査員による説明を武本は思い出す。
近年、急増している闇バイトによる犯罪の多くで、シグナルと呼ばれるアメリカの通信アプリが多用されている。シグナルはアメリカのSignal FoundationというNPOが運営しているオープンソースメッセンジャーアプリとして二〇一四年の七月にリリースされた。最たる特徴は、使用者同士――エンドツーエンドの暗号化によって、シグナルの運営サイドを含む他の誰もメッセージや通話を盗み読めないようにしてあり、通信内容とユーザーのプライバシーの保護が最優先されていることにある。さらにメッセージも設定した時間が経過すると消せる。その秘匿性は犯罪者にとって便利な存在として、急激に利用され出した――。
「証拠は完全に消えてはいない。アプリを利用すればスマホに紐づけされる。メッセージは消えても、スマホにGPSなどの情報は残っている」
頬に指を当てたままの石原が眉を曇らす。
「そうした断片データをつなぎ合わせれば、死体遺棄当日の一月十三日から、お前が山上瑛大に『話が決まった。パスポートがいる。明日、実家に取りに行かせよう。ついて行って見張ってよ』と言った二月十日までの間、お前がどこに、いついたか特定できる」
石原の眉間の皺が深まる。
「今、お前が立ち寄った場所周囲の防犯カメラの映像を集めている。そこからお前がどこで誰と会ったのかを見つけ出す。相手が分かれば、次は相手を防犯カメラ映像で追って、どこに住んでいる誰なのかを特定する。時間はかかるだろう」
そこで身を乗り出した浦島が「だが、絶対に突き止める」と断言する。
確たる証拠がない以上、このまま石原進の取調べを進めても、ああ言えばこう言う状態のやりとりが続くに違いない。その中で、以前の供述と違う部分を指摘して、石原に非を認めさせるしか、今のところ方法がない。
石原の勾留は所得税法違反の再逮捕でここから最長二十日間の延長となった。その間にSSBCが証拠を見つけ出すのを待つしかない。見つからなければ、石原は死体遺棄と所得税法違反の二つの罪のみで裁かれることになる。
これまでの捜査ですでにSSBCの能力は十分に発揮されている。だが、ここから二十八日間の石原の行動確認に加えて、会った相手の特定まで含めると、二十日間という時間が十分だとは武本には言い切れなかった。
――時間との勝負か。
石原が膝に手を下ろした。瞳が左右に速くきょときょとと動いている。このあとどう立ち回れば一番損をしないのかを考えているに違いない。
それを見ている武本の頭に、とつぜん小柄な宇佐見の顔が浮かんだ。
会計士の資格を持つ財務捜査官の宇佐見は、物事を数字で考える。それが宇佐見のポリシーだ。
利益のために罪を犯した相手ならば、捕まって生じる損失を突きつければ自分の愚かさを痛感するはず。数で考える人間には、数を示せば理解する――。
宇佐見の言葉が甦ったと同時に、武本は口を開いていた。
「証拠が出れば、お前はすでに認めている死体遺棄の罪と、発覚した所得税法違反に加えて、人身売買罪が加わる。営利目的での売買で一年から十年、さらに海外で売買の計画を企てたから二年以上の懲役が加算されることになる」
人身売買罪では、営利目的、または性奴隷、結婚、身体に危害を与える目的で人身を購入(または売却)した者は一年から十年以下の懲役、国外へ人を売買した者は、二年以上の有期懲役に科されるとされている。
振り向いた浦島と視線が合う。余計なことをしてしまったと申し訳なく思って口をつぐもうとすると、浦島が小さく頷いた。了承を得た武本は、先を続ける。
「今、罪を認めるのと、証拠が出てから認めるのと、どちらが得なのか、お前ならば分かるはずだ」
目の動きを止めた石原が、じっとこちらを見つめていた。口元に力が込められているのが見て取れる。
「一つ言い忘れていた」
姿勢を戻した浦島が切り出す。
「お前の客だった豊本泰恵さんが、お前を結婚詐欺で訴えると言っている」
石原の言葉を信じてソープランドで働いてお金を渡していた豊本泰恵に結婚詐欺で石原進を訴えることを勧めたのは浦島だった。豊本泰恵は一も二もなくすぐにその話に乗った。
「金の受け渡しは現金だったし、結婚の約束をした明確な証拠もない。だが豊本泰恵さんは、何時いくらお前に金を渡したかの記録を取っていた。それに、お前が豊本泰恵さんの親に会いに行く約束をしたのに、当日ドタキャンしたやりとりも残っている。この二つで訴えることは可能と判断した。受理次第、結婚詐欺でお前を逮捕する」
石原の目がまた動き出した。この男のことだ。告訴されても証拠不十分で起訴には至らないと踏んでいるに違いない。
「起訴できるかは俺にも分からない」
浦島の言葉に、石原の目の動きが止まり、口元の緊張が少し解けた。
「だが、お前を結婚詐欺で訴えるのは豊本泰恵さんだけではない。小林由美子さん、大島貴代さんもだ」
さすがに驚いたらしく、石原の口がわずかに開いた。
捜査員たちは、石原の常連客で店に来なくなった女性たちを、店の他のキャストや客たちから話を聞いて捜し、現在そのうちの二名を特定することが出来た。二人ともデリバリーヘルスで働いていて、大島貴代は立ちんぼとパパ活の掛け持ちまでしていた。
石原進の逮捕に伴い捜査をしていることを告げ、豊本泰恵が結婚詐欺で訴えることを伝えると、二人とも自分も訴えると言ったという。
「その二件でも逮捕は出来るだろう。逮捕すれば、一件で二十日間、三件だから六十日間勾留が延びる」
石原が口を閉じた。奥歯を噛み締めている。
「お前の過去を探れば、余罪はいくつも出てきそうだ。勾留はさらに長くなるだろうな」
SSBCの捜査員たちが証拠を見つけ出す時間は十分にあると浦島が匂わせる。だが石原進はまだ迷っているらしい。奥歯を噛み締めたまま、口を開こうとしない。
追い詰めるのは今だ。そう思った武本は口を開いた。
「火災現場の遺体発見が二月五日、防犯カメラの映像から山上瑛大を特定したのは二月十七日。山上とつるんでいるメンズコンセプトカフェのキャストがいるという情報を得て、聞き込みに回って、お前を特定したのは二月十八日。かかったのは十三日だ」
武本を見る石原の顔は、山上が録音していたと浦島が告げた時と同じで憎しみに満ちていた。
「もう一度言う。今、罪を認めるのと、証拠が出てから認めるのと、どちらが得なのか、お前ならば分かるはずだ」
とつぜん石原が机の上に両肘を突いて、両手で頭を抱えた。続けて、「ぁあっ!」と唸り声をあげると、ひとしきり髪を激しく掻きむしってから、両手を机に叩きつけた。ダンっ! と、激しい音が鳴る。
乱れた髪の石原は大きく溜息を吐いてから、口を開いた。
「人身売買のバイヤーの情報を話したら、捜査協力したってことになりますよね?」
そう訊ねる石原進は、これまで見せたことのない狡猾な表情をしていた。
(つづく)