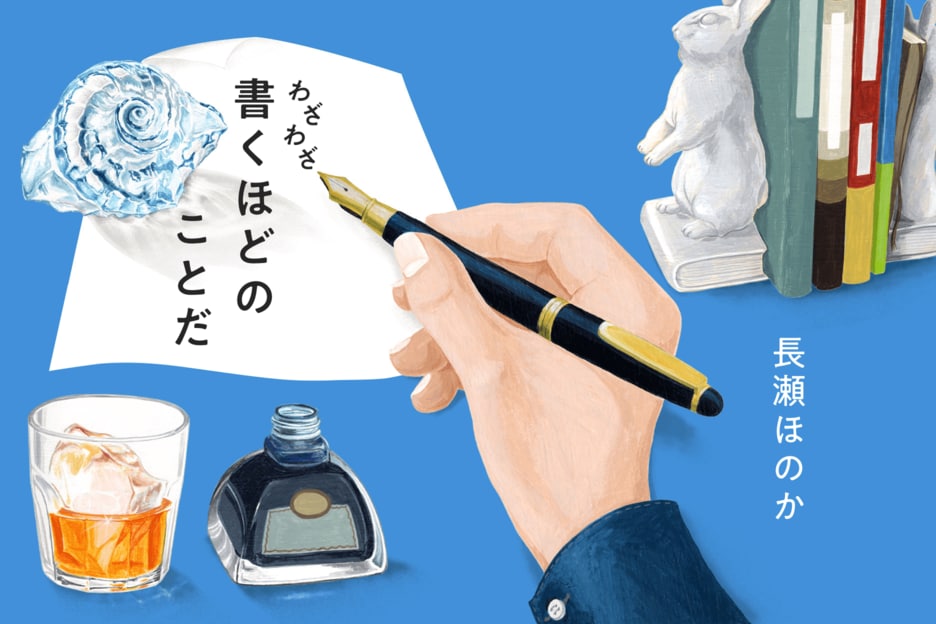初孫
1988年11月6日、早朝。両家初孫として鳴物入りでこの世に生を受けた。
初孫が家族に与える影響は絶大である。私の誕生によって親は初めて親となり、祖父母は初めて祖父母となった。どれほどのお祭り騒ぎであったか、覚えていないのが悔やまれる。皆に囲まれ愛でられる赤子の自分を想像すると何とも誇らしく、「我こそは初孫であるぞ」と威張り散らしたい気分になる。過去の栄光に縋るという意味ではその最たるものであろう。
私の誕生は実にもったいぶったものであった。母曰く、予定日から二週間経っても腹に居座り続け、医者から「明日生まれなければ促進剤ですね」と通達された途端、慌てて出てきたという。怠け者のくせにプライドだけは高い。そんな私の性質が如実に表れた初登場シーンである。
三年後には双子の弟たちが生まれ、そのドタバタによって私はおむつの卒業を平均より大幅に猶予されたが、いよいよ卒業させようと母がその旨を私に告げたところ、訓練せずとも即日トイレで用を足すようになったという。とっくに準備はできていたのに、面倒がって素知らぬ振りでおむつに放出し続けていたに違いない。「ついに年貢の納め時か」としぶしぶトイレへ向かう幼児の背中が目に浮かぶ。
この生まれながらの怠け者気質によって、私の執筆活動は著しく出遅れた。何を隠そう、私は高校生の頃にはすでに己の文才によって将来何かしら成し遂げてみせようという野望を胸に秘めていたのである。しかし、秘めに秘め続けること15年、実際に執筆をはじめた時にはすでに三十を越えていた。
発端は、小学校の図書室で読んだ児童文学である。小学生が作家デビューを目指す話で、詳細は忘れてしまったが、主人公の少女と編集者のあるやりとりが今も脳に刷り込まれている。
その内容は、レストランのウェイトレスがテーブルを回る姿について、「あなたならどう書く?」と問われた主人公が、「蝶が花から花へ飛び回るように」と描写し、編集者から「あなたらしい表現だわ!」と絶賛される、というものであった。
これを読んだ私は、「へえ、そんなもんでいいのか」と思った。確かに作文は得意な方だったが、そんな洒落た比喩を使ったことなどない。しかし、書こうとおもえばいくらでも書けると思った。図書室に通って何度もそのくだりを読み返し、そのたび鼻息を荒くした。厄介なものが芽生えた。根拠のない自信である。
人並みに陽気な子どもだったが、目立つのが苦手だった。授業中当てられるとスポットライトを浴びるが如く緊張し、うまく答えられないと涙が出て惨めな思いをすることもしばしばであった。
だから、作文はわざと少し下手に書いた。万が一何らかの賞に選ばれ、朝礼で読まされるようなことになってはたまったものではない。皆が使いそうなありふれた言い回しを用いた上で、最大限上手く書く。それがちょうどいい作文にするコツだ。恥ずかしがり屋というにはだいぶ感じの悪いエピソードである。
目立ちたくはないが、一目置かれたかった。その都合のいい願望は、今も昔も変わらない。
高校時代、綿矢りさの『蹴りたい背中』を読んだ。普段は立ち読みだけして帰るゲオの古本コーナーで、1ページ読んですぐにレジへ持って行った。今まで読んだ何より面白いと思った。
本格的に書きたい気持ちに火がついた私は、大学入試に本腰を入れた。どこでもいいから大学に入りさえすれば、在学中にいくらでも文章を書く時間が取れるだろうと考えた。だから学部にもあまり拘らず、地元の教育大学の推薦入試を受けた。
特段成績が良かったわけではないので、合格できたのは自己推薦文のおかげだと思っている。我ながら会心の出来で、教員を志す若人の熱い思いがそこにはあった。書いているうちにちょっと教師になりたくなったほどである。添削してくれた現代文の先生も、「今まで読んだ自己推薦文史上最高傑作」とハリウッド映画の宣伝さながらド派手に褒めてくれたので、私はいよいよ調子に乗った。
面接では、皆勤だったことも追い風になった。普段学生たちの遅刻や欠席にうんざりしているのであろう教授たちが、高校三年間無遅刻無欠席という私の記録に目の色を変えたのがわかった。「風邪ひかないの?」と嬉しそうに冷やかされたので、さも健康優良児とばかりに「ハイ!」と元気よく返事をしてみせた。
そうして合格した私が入学後、遅刻・欠席常習犯の絵に描いたような堕落した大学生に成り下がったのだから、申し訳ないが教授たちの目は節穴であったと言わざるを得ない。
大学は自由で時間に余裕もあったが、私は持ち前の怠け者っぷりを遺憾無く発揮し、テストやレポートはいつもギリギリで、それらを綱渡りでこなしながら、バイトをしたり、酒を飲んだり、恋人と付き合ったり別れたりしているうちに、日々はあっという間に過ぎていった。
周りの友人たちが将来について悩んだり、勉強や就活のことで焦りはじめたりしても、私は動じなかった。今後の人生がどうなろうとも、たとえ何もかもが行き当たりばったりだったとしても、物書きとして結果を出せばすべての辻褄が合うと思っていた。夢見ることは素晴らしいとされるが、夢見る「だけ」でここまで強気で生きてこられた例もなかなか珍しかろう。
謎の自信に溢れ、何を成したわけでもないのに偉そうな私の態度は、考え込むタイプの友人からはある種の達観として崇められた。その半分は優しさであると知りながらも、私は満更でもない顔で、酒を飲みながらべらべらと持論を述べたりした。
あらゆることを完璧にこなそうとして疲れ切ってしまった友人に、私はこんなことを言った。
「あちこちの畑を同時に耕そうとするからじゃん。順番に耕すとか、規模を小さくするとか、誰かに任せるとかしなよ」
そう言う私はたった一つの畑もろくに耕かさないまま、大学四年間を終えた。
大学は自由すぎて張り合いがなかった。働き始めれば自然と生活リズムが整い、執筆にも身が入るに違いない。私は就職後の自分に熱い期待を寄せた。しかし、当然の如く目論見は外れ、働き始めてより一層、怠惰に磨きがかかった。仕事の後の一杯を覚えてしまったのである。
一人暮らしの狭い部屋に無理やり執筆スペースを設けたが、デスクとノートパソコンはいつも埃を被っていた。デスクは焦げ茶で、ノートパソコンは黒。それを見るたび、暗い色は埃が目立つから、もっと明るい色にすればよかった、などと思った。
明日こそ生まれ変わろう。そう決意して、早く生まれ変わるためにすぐに寝た。そんな毎日を性懲りも無く繰り返す。自分に嫌気が差した。しかし、宿題のページ数を夏休みの残り日数で割るように、私は何度でも仕切り直し、蘇った。そして、書かない。怠け者界の不死鳥とは私のことである。
20代の終わり頃、夫と出会った。他人の功績にケチをつけることで自分の不甲斐なさから目を逸らすという情けない悪癖が定着していた私だったが、努力を重ねて古生物学者となり、日々研究に勤しむ夫に対しては、ひたすら素直に尊敬の念を抱いた。
そんな夫が新聞でコラムを連載することになった。内容は古生物のことでも、それ以外の日常のことでも何でもいいらしい。原稿に意見が欲しいと言われたので、あれこれ口を出すと喜ばれた。「良くなりすぎて、俺の文章でなくなってしまう」などと言われることもあり、すっかり有頂天になった。
私が危うく満足しそうになったところで、夫は言った。
「ほのかさんも何か書いてみたらいいのに」
私は書きたかったのではなく、書かされたかったのかもしれない。誰かに読みたいと言われる必要があった。でも、それは誰でもよかったわけではない。過去に出会ったどんな人の顔を思い浮かべてみても、私が夫以外の人の言うことを聞くとは到底思えないのだ。
埃を被ったノートパソコンを開き、私はやっとスタート地点に立った。
noteで書きはじめて一年ほど経った頃、酒を飲んで天皇陛下に拝謁した件を書いた記事がちょっとした成り行きでバズった。それはもう、この世の果てまで拡散されるのではないかと思うほどの勢いだった。通知欄で皆が私の文章の話をしていた。嬉しかった。あまりに嬉しかったので、各方面に言いふらした。
畑を耕しすぎていた友人が言った。
「ほのちゃんはやればできるのに、なんでやらないんだろうってずっと思ってた!」
このまま稼げるようになるかもしれない。期待を胸にウハウハ気分で過ごしていたが、執筆依頼が次々舞い込むような景気のいいことにはならなかった。そりゃそうである。ただ大酒飲んで天皇陛下に手を振っただけの奴に、一体誰が何を書いてほしいと言うのか。
それから数年、私はエッセイを書き続けた。怠け癖は相変わらずだったが、それを何とか奮い立たせて、どうにかこうにか書いていた。その間にも、同じようにウェブ上で文章を書いていた人たちが次々と本を出した。2023年の創作大賞では中間選考に2作品残ったが、最終結果は落選だった。
ある時、夫と居酒屋で飲んでいたら、ふとした拍子に蓋が開いてしまった。見て見ぬふりで仕舞い込んでいた感情が、涙腺からぼとぼと溢れ出してきた。
認めざるを得ないほどに、私は悔しがっていた。
「そのうちほのかさんのターンがくるよ」
夫は励ましてくれたが、私はビールを呷って「もうエッセイなんかやめてやる」と自暴自棄なこと言った。
やめてやる、なんて言ってはみたが、そんなのは全部出し切った人間が言うことである。どう考えても、私はまだ出し切っていない。
夫のことを書くことにした。夫のことを通して、自分のことをちゃんと書こうと思った。私はまだ、剥き身でエッセイを書いていなかった。
夫の言う通り、私のターンはやってきた。その年の創作大賞で、めでたく受賞を果たしたのである。図書室で根拠のない自信に鼻息を荒くしていた小学生の自分に、やっと根拠をあげられた。
私がぐうたらやっている間に、長瀬家には次世代の初孫(甥っ子)が誕生した。両親は祖父母となり、祖父母は曽祖父母となって、家族内における私の地位と影響力は弱まるばかりである。
実家に帰ったとき、私の髪がグラデーションカラーになっていることを誰も指摘しなかったのにはさすがに痺れた。皆、グラデーションカラーよりおむつのおしっこサインに夢中である。やはり初孫が家族に与える影響は絶大だ。
画用紙に線の一本でも引けばベタ褒めされる存在に対抗するには、本の一冊でも書くしかあるまい。
(つづく)