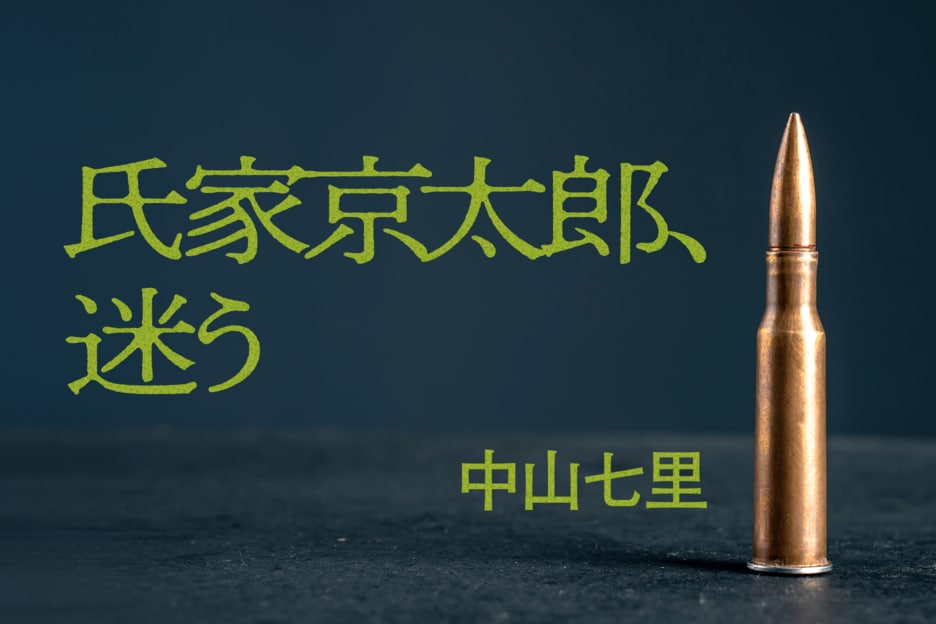3
幡野は報告書が読めても空気が読めないらしい。周囲の雰囲気に気づかない様子で言葉を続ける。
「発射された弾丸には例外なく線条痕が刻まれています。所謂、弾丸の指紋です。線条痕さえ追っていけば、必ず犯人は逮捕できます」
黙って聞いている宮藤は不機嫌さを隠そうともしない。刑事にしてみれば線条痕の説明など釈迦に説法のようなものだ。最初の顔合わせで線条痕に言及する幡野はいささか無神経と言わざるを得ない。
線条痕は銃身内部に刻まれたライフリングに削られながら射出されることで生じる。大手メーカーは銃身内部に型となるマンドレル(心棒)を通し、外側から叩いて圧縮してライフリングを刻む手法を採っている。
ライフリングを刻めば必ず銃身内に切除痕(ツールマーク)が残る。この切除痕は大量生産品であっても、製造時の刃の形状や圧力差、使用頻度による摩耗、そして腐蝕や焼損などによって一本一本が異なる点が銃の指紋と称される所以だ。銃を用いるような強行犯を相手にしている捜査一課の刑事にとっては基本中の基本でもある。わざわざ説明される桐島班の面々には鼻白む思いだろう。
「幡野先生」
宮藤は挑発気味に疑義を差し挟む。
「わたしたちは先生ほど科学捜査に精通している訳じゃありません。しかし線条痕が人間の指紋と同様という言説には少し引っ掛かりを覚えますね」
「ほう、何故でしょうか」
「たとえば銃国家のアメリカじゃあ、簡単に銃身が手に入るので交換も容易い。メリーランド州などでは公判を維持できないという理由で、線条痕を証拠物件として採用するのを廃止していると聞きます」
「ああ、メリーランド州などの裁判で線条痕が問題にされないのは、確かにその通りです。しかし、それはあくまでアメリカの話であって、日本のように銃規制が厳しい国では複数の銃を所持する行為自体がレアケースです。逆に言えば、レアケースだから犯人の特定が容易になるのではありませんか」
狩猟免許を持っている者でも所持している銃は全て登録されている。いくら銃身を交換したとしても結局は足がつくという理屈だ。また、狩猟者登録をしている者に該当者が現れない場合、容疑者は不法に銃を複数入手できる反社会的勢力の関係者に絞られる。幡野の意見は概ね間違ってはいない。
だが話し方と場所を間違えている。
幡野が言葉を切った瞬間を見計らい、葛城が歩み寄った。
「桐島班の葛城公彦です。どうぞよろしく」
「あ、ああ。こちらこそよろしく」
「早速ですが幡野さん。今の線条痕の件で詳しいお話を伺いたいのですが、お時間よろしいでしょうか」
「構いませんよ。皆さんの疑問にお答えするのもわたしの役目と認識していますので」
葛城が幡野を誘って刑事部屋を出ようとする際、宮藤は早く行けというように片手を払ってみせる。この場はお前に任せたという意思表示でもある。
幡野のような異分子の扱いは自分の仕事と相場が決まっている。葛城も特段嫌がりもせず引き受けているので、ますます子守り役を押し付けられるという寸法だ。
フロア隅の別室に移動すると、葛城は正面に幡野を座らせた。
「それで葛城さんは、どの辺りの詳細を聞きたいのですか」
「線条痕の異同識別についてです。先ほどのお話で線条痕が銃の特定に最適であると仰いましたよね」
「はい。この点に関しては断言してもいいと思っています」
「わたしも同感です。ただ、確率の問題が引っ掛かっています。指紋の場合、個人の特定が容易なのは僕でも分かります。特徴点抽出法、でしたか。指紋に現れる十二カ所の特徴点を比較することで識別すると、その十二カ所全てが一致する確率は一兆分の一にしかならない。従って同じ指紋を持つ人間は存在しない」
「素晴らしい」
幡野は目を見張って称賛の視線を投げて寄越す。さっき会ったばかりだが、とても相手を揶揄しての態度には見えない。
「現場の刑事さんで、そうした基本を押さえている人は多くないのですよ」
「どうもありがとうございます。指紋の異同確率が一兆分の一だから特定が容易というのは、とても納得できるんです。でも世界中に流通している銃を集めたところで人口に匹敵する訳じゃありません」
「ああ、なるほど」
全てを聞き終わる前に幡野はこくこくと頷いてみせる。おそらく一を聞いて十を知るタイプの男なのだろう。彼が一知半解でないのを祈りたくなった。
「確かに指紋鑑定に比較すると、線条痕のそれは確度が低いと思われがちですね。よおく分かります。何故なら分母の小ささも然ることながら、発射弾丸の異同識別は比較顕微鏡を用いた目視検査がもっぱらだからです」
「目視検査では専門的な技術や知識が不可欠だから、熟練の技術者以外では心許ないという人もいますね」
「そうそう、そうなんですよ」
幡野は我が意を得たりとばかりに顔を綻ばせる。まるで子どものような反応だと、葛城は少し微笑ましく思う。葛城にもオタクめいた知人が数人いるが、彼らは自分の感覚が相手と共有できたと知るとひどく喜ぶようなのだ。きっと幡野にもそうした気質があるのだろう。
「比較顕微鏡による鑑定では二つの発射弾丸を同時に観察して類似している線条痕の特徴を抽出します。この方法では目視に頼らざるを得ないので、どうしても観察者の技術や経験値によって効率に差が生じてしまうんですよ。そこで科捜研では鑑定作業の効率化と定量化を可能とする開発が進んでいるのです」
幡野は上着のポケットからペンとメモ帳を取り出し、早口で喋りながら机の上で数式を書き始めた。
「つまり弾軸方向に連続する線条痕を強調するために、二次微分と位相限定を比較検討することにしたのです。ここで言う位相限定というのはN1×N2画素の画像f(n1, n2)が与えられた時、二次元画像信号の離散空間インデックス(整数)をn1=-M1,…, M1及びn2=-M2, … , M2とします。ただしM1及びM2は正の整数で、N1=2M1+1及びN2=2M2+1。画像f(n1, n2)の二次元離散フーリエ変換を次式に示すと次の通りになります」
『F(k1, k2)=Σf(n1, n2)n1, n2WN1k1n1 WN2k2n2』
高校時分、数学のテストが悪い訳ではなかったが、幡野の説明も数式もまるで理解できない。ただしいくつかの印象的な単語から、言わんとする内容には凡その見当がつく。
「つまり線条痕を画像として見やすくするための技術なんですね」
「その通りです。画像を精細にするために二次微分はヒストグラムを均等化、位相限定は階調を十倍にして表示する訳です」
幡野はひどく嬉しそうに頷いてみせる。
「この技術を応用して画像解析すれば、昨日科捜研に入ったばかりの新人でも、容易に線条痕の異同識別が可能になります。もう捜査一課も、この道何十年のベテランに頼らなくても済むようになります。いや、葛城さんくらいの理解力があれば、捜査員自らが線条痕の異同識別が可能になるでしょう。それはつまり作業の効率化にも結びつくはずです」
葛城は慌てて声を抑えるような手振りを示す。効率化と言えば聞こえはいいが、要するに鑑識係の人員を削減できると公言しているに等しい。当の鑑識課が聞いたら、いったいどんな顔をすることやら。
「葛城さんは業務の効率化に反対なんですか」
「決してそんなことは考えていませんが、業務にも効率化すべきものとそうでないものがあるんじゃないでしょうか」
「果たして区別する必要なんてありますかね」
幡野は小首を傾げる。
「効率化が進めば、それだけマンパワーに余裕が出てくる。時間的にも資金的にも余裕が出てくれば、捜査に集中できるじゃありませんか」
幡野の話には一部肯定できる箇所もある。捜査一課は常時人手不足であり、ひと頃よりは労働環境が改善されたとは言え、凶悪犯はこちらの都合など考慮してくれないので深夜の出動や超過勤務はほぼ常態となっている。まだ若い葛城や宮藤はともかく、定年間近のベテラン捜査員は愚痴交じりに疲労を訴えるのが口癖という有様だ。
「幡野さんの意見は理に適ったものだと思います」
「そうでしょう、そうでしょう」
「しかし理に適う話が全面的に正しいのでしょうか」
「どういう意味ですか」
「捜査一課に配属されて数年経ちましたが、この仕事は効率化だけで片付くようなものとは思えないんです」
葛城は慎重に言葉を選ぶ。自身の知見を卑下するつもりは毛頭ないが、幡野の機嫌を損ねる訳にもいかない。
「幡野さんは観察者の技術や経験値によって効率に差が生じてしまうことを憂いているようですが、だからと言って個人の技術や経験値を現場から除外するのは違うような気がするのです」
「しかしね、葛城さん。各部署にベテランや名刑事と謳われる捜査員が揃っていれば結構ですが、全国の警察署にそれを期待するのはどだい無理な話でしょう。一例を挙げれば、福井県警の検挙率は八割を超えているのに大阪府警では三割にも届いていない。無論、人口比率の問題もありますが、捜査員個別の能力に差があるのも事実です。ならば個人差を可能な限り縮小させ全体的な能力を嵩上げしていけば、県警間の差異も極小化するはずでしょう。今の状況が続けば、殺人犯が検挙率の悪い県警の管轄地に死体を運んで逮捕を逃れるなんてジョークが現実になってしまう。能力の偏在というのは、結局組織の弱体化を招いてしまうのですよ」
線条痕に関する数式を説明していた時の浮かれ具合とは打って変わり、幡野は俄に白けた顔つきになる。
「仰る意味は分かりますが、後進への教育や知見の継承という意味でも秀でた能力は必要だと思います」
「うーん、古い。その若さで葛城さんの職業意識は半世紀もズレています。それでは、まるで徒弟制度じゃありませんか」
「実際、僕も先輩から学ぶことが少なくありませんからね」
「ではトレーナー役となる先輩の能力が低かったらどうするんですか。徒弟制度の下では弟子は師を凌ぐ能力を発揮するのが困難になる。捜査能力を高める機会はますます失われてしまいますよ」
幡野はゆるゆると首を横に振る。現状の警察機構にすっかり失望しているという顔だった。
「技術革新とは言ってみれば能力の平準化なんですよ。古色蒼然とした徒弟制度やパワハラ紛いの教育を続けていれば若い芽を摘んでしまう。葛城さんのように柔軟な思考を持つ捜査員が長らえているのは、おそらく稀有な例ですよ。普く捜査員は科学捜査に対する深い理解と効率的な捜査能力を身につけなければ、多発する犯罪に対応できなくなる」
「しかし犯罪者の側にとんでもない知能犯が出現した場合、平準化した捜査員ばかりでは太刀打ちできないのではありませんか」
(つづく)