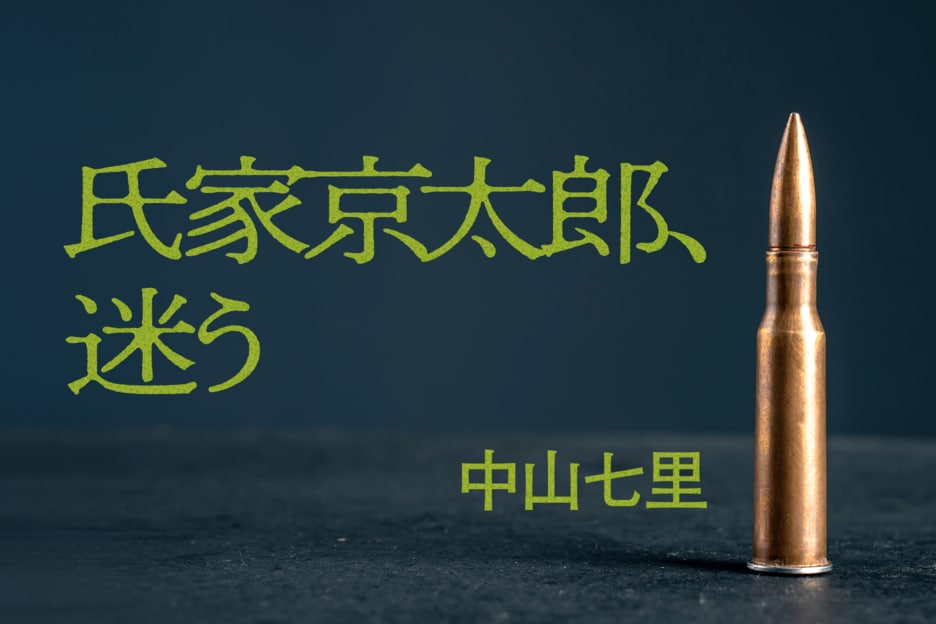3
葛城が立ち去った後、氏家は「さて」と呟いて思案に耽る。
線条痕の鑑定依頼はそれほど多くない。ほとんどが犯罪絡みであるため、鑑識課や科捜研の案件になってしまうからだ。鑑定センターに持ち込まれた例と言えば、獲物を仕留めた銃弾が誰の銃から発射されたかを特定する依頼だった。
とは言えノウハウがない訳ではない。葛城にも告げたが、二次微分画像の生成もとっくの昔に導入している。鑑識の世界は日進月歩であり、海外の学術書に目を通しているとそれこそ月単位で新技術が開発されている。幸い資金力に恵まれているので気に入った新技術はすぐに取り入れるようにしている。何も散財している訳ではなく、鑑定技術を更新することでクオリティと評判を上げているに過ぎない。
氏家が戸惑いを覚えるのは、話に出ていた土屋と幡野の確執だった。ともに評判を聞き、それぞれに敬意を抱いている。更に縁のある者がセンターの職員として働いている。鑑定センターが線条痕について分析するのは、二人のうちどちらかの見解を否定することになりはしないか。
悩んでいても仕方がない。氏家は縁の深い者たちから話を聞くことにした。ラボに足を運んで相倉尚彦と飯沼周司に声を掛けた。
「二人とも、ちょっといいかな」
二人を自分の部屋に招き入れ、捜査一課から依頼された用件を伝える。先に反応したのは相倉だった。
「作業効率の考え方は、なるほど幡野さんらしいですね。僕が科捜研にいた時分からテーマに掲げていましたからね」
「ちょうど僕が抜けた後かな」
「そうです。氏家所長が辞めた後の年度に、予算が縮小されたんですよ。お蔭で新規採用の枠が狭まるわ、導入予定の機材を見送る羽目になるわで大変だったんですから」
まるで氏家が抜けたせいで予算が削られたような言い方にも聞こえる。ひと言返したくなったが、よくよく考えてみれば辞める時も辞めた後も等々力管理官からは文句の言われっぱなしだ。事によると氏家本人に自覚がないだけで、管理官以下科捜研の連中は自分を相当恨んでいるのかもしれない。
「次代の所長を嘱望されていた人が去り、代わりに入った新人一名は右も左も分からない。頼りとする機材は型落ちばかり。作業効率は落ちる一方で、一課から苦情めいた言葉も浴びせられました」
「それは大変だったね」
「また、そういう他人事みたいに。その時、現状を打開しようと旗を振ったのが幡野さんでした。新人が一日も早く戦力になるようにローテーションを組み直したり、機材に手を加えて素人目にも分かりやすくしたり、それはもう八面六臂の活躍で」
「でも、空回り気味だったな」
過熱し始めた相倉に冷や水をかけるように、飯沼が呟く。
「鑑定作業の効率化というのは確かに間違ってなかったけど、所長や管理官に何の相談もなく押し進めるものだから、内外から批判食らったじゃないか。ローテーション替えちゃったら鑑定に必要な担当が強制的に休みになっちゃうし、機材を自己流で改造するのはいいけれど、お蔭で故障しやすくなっちゃうし、結局は行って来いで作業効率もあまり向上しなかった」
「いや、それはそうかもしれないけどさ。少しでも現状をよくしようと具体的に行動したのは幡野さんだけだったじゃないか」
「今更こんなことを言うのは後出しじゃんけんみたいだけど、あの時に必要だったのは一にも二にも予算調達だったと思う。だから真剣に科捜研の窮状を憂うのだったら、所長や管理官に訴えて予算を分捕る策を練るべきだった」
「ホントに後出しじゃんけんだな。だって幡野さんは」
「そう。交渉術がなかった。と言うよりコミュニケーション能力が絶望的だった。だから上司に直訴するより、研究所内のシステムや機材を弄る方を選んだ」
「自分の得意分野を生かして何が悪いんだよ」
「悪いとは言ってないけど非効率なんだよ。それこそ焼け石に水ってヤツだ。言っちゃあ悪いが、やってる感を出すために小手先の仕事をしただけだよ」
「お前、幡野さん評が辛辣過ぎやしないか」
「いや、相倉の人物評が少し過大なんだと思う。相倉は幡野さんに恩義があるから」
「やめろよ」
相倉が顔色を変えたので、さすがに飯沼も控えた。ただし今のやり取りで、幡野が科捜研でどういう立場にいるかが類推できる。つまりは専門家に多く見られる「木を見て森を見ない」タイプに捉えられているのだろう。
「まだ幡野さんは線条痕について分かりやすく明示している分、理解してもらおうという意識がある。だけど土屋さんときた日には、ほとんど職人の勘みたいなもので喋っているようじゃないか。それこそコミュニケーション能力に問題があるんじゃないのか」
「土屋さんが職人ってのは否定しないけど、その専門性には敬意を払うべきだ。専門的過ぎるから説明しても素人には全然易しくない。易しくないからコミュニケーション能力が乏しいと勘違いされているだけだ」
今度は飯沼が土屋の弁護に躍起になっている。
「あの人は大したもんだぞ。ただ鑑識のベテランというんじゃなくて、生きた分析器みたいなものだ。肉眼で〇・〇一ミリを測れる人間なんてそうそういない」
「そんなもの、デジタルノギスがあれば事足りるじゃない。そういうのがオーバースペックって言うんだよ」
「ものの喩えだ。肉眼で〇・〇一ミリを測れるのなら、どんな微細な遺留品も見逃さないという意味だ。それに目だけじゃなく知見もある。ウィンチェスター銃に限ってもM1866からM1895までひと通り鑑定してきた鑑識係なんて土屋さんくらいのものだ」
ああそうか、と相倉は合点がいったという顔をする。
「飯沼は飯沼で、科捜研時代に土屋さんに世話になったんだよな。そりゃあ贔屓の引き倒しにもなる」
「別に贔屓もしていないし引き倒しもしていない。あの人に対する正当な評価だし、鑑識課の全員が土屋さんを信頼している」
「そりゃあ身内だから、信頼してないなんて口が裂けても言えないでしょ」
これ以上角突き合わせていたら口論になりそうだと、氏家は判断した。
「まだ依頼を受けると決めた訳じゃないから、そんなに熱くならないでよ。相倉くんは仕事に戻ってくれていいよ」
相倉は何やら言い足りなそうだったが、一度だけ振り返ってから部屋を出ていった。
「所長、わたしは」
「飯沼くんからは、もう少し土屋さんの話が聞きたくてね。僕は幡野くんを多少知っているけど、土屋さんに関しては人伝に人となりを知っているだけだ」
「僕の口から聞いても人伝ですよ」
「今のやり取りを聞いていると、単に鑑識係と科捜研研究員の間柄とも思えなくてね」
「わたしが科捜研に採用された半年後に氏家所長が辞めてしまいました」
「うん、ちゃんと憶えているよ。結構さっぱりしたお別れだった」
「有能な人材はどんどんウチが引っこ抜くからって、所長が宣言したからじゃないですか。最後の挨拶がヘッドハンティング宣言で、どう湿っぽくしろというんですか」
「そうだったっけ」
「引退試合のセレモニーで『明日から敵チームの監督です、よろしく』って高笑いするようなものですよ」
まさか、そんなにふざけた態度だったとは思わないが、敢えて反論はしなかった。
「次期所長と目されていた人が抜けて大変だったのは、さっき相倉が言っていた通りですよ。それまでは分からないことは氏家所長に聞けば、すぐに答えが返ってきたし、所長も人に教えるのが上手かったじゃないですか。そういう人に突然辞められるとですね、いきなり灯台を見失った船乗りみたいな気分だったんです。まあ、船乗りになったことはないんですけどね」
「それは申し訳なかった」
「ある時、捜査一課から筆跡鑑定の依頼を受けたんです。筆跡もコンピューターで鑑定できるんですけど、最終的には人が判断するじゃないですか。ところが物件を持ち込んだ一課は明らかに真筆であってほしい素振りをしているんです」
よくある話なので氏家は頷いてみせる。捜査一課が科捜研に案件を持ち込む際は、容疑者が浮上した上での依頼が少なくない。自ずと証拠物件が容疑者を逮捕できる根拠になればという思いが滲み出る。
「真筆かどうかは微妙なラインだったんです。でも一課は真筆だというお墨付きを欲しがっている。本当に悩んだんですよ。そうしたら土屋さんがふらっと科捜研にやってきて言うんですよ。『確信が持てないなら、報告書にはちゃんとそう書け』って。鑑識係は捜査一課の一部だから、容疑者を追い詰めるために結論を急がされる場合もある。だけど独立機関の科捜研は中立公正な結論を出すべきだ。そう助言してくれたんです。お蔭ですごく楽になりました」
飯沼は感に堪えないような声を絞り出す。普段は豪放な態度の飯沼には珍しい感情の吐露だった。
「土屋さん自身、結論を急がされて後悔した経験があったのかもしれないね」
「それからも悩んだ時には色々相談に乗ってもらいました。郷里が同じ水戸だというのも手伝って親しくなりました。立場も所属も違うのに。土屋さんの教えがなかったら、わたしは大勢に流されて、グレーをクロと言いかねないような研究員になっていたかもしれません。土屋さんは恩人なんですよ」
優柔不断さなど欠片もないような飯沼の人格形成には、土屋の影響があったのか。話してみるものだと思う。今回のことがなければ、なかなか聞ける内容ではない。
それで決めた。
「今回の依頼、受けてみようと思う。ウチの出した鑑定結果が土屋説に傾くのか幡野説に傾くのかは分からないけど、放っておいても捜査は停滞するだろうし」
飯沼は神妙に頷いてみせる。
「土屋さんは、3Dプリンターを使用することで容疑者は反社会的勢力の関係者という限定から外れるという説でしたよね」
「うん。最近の3DプリンターはABS樹脂やエポキシ樹脂のみならず金属まで素材にしてしまえるからね。ウィンチェスターの銃身部分くらいなら苦もなく成型してしまえる。可能性は決して小さくない」
氏家は葛城から渡された銃弾の拡大写真を取り出す。
「無論、正規の工程を経て製造された銃と比較すれば耐久性も低いだろうし、連射すればするほど銃身に歪みが生じて命中率も低くなる。だが3Dプリンターで大量生産が可能なら、一発発射するごとに銃を交換してしまえば問題ない。捜査機関には厄介な時代になったものだよ」
飯沼は同意していいのか逡巡しているようだった。
(つづく)