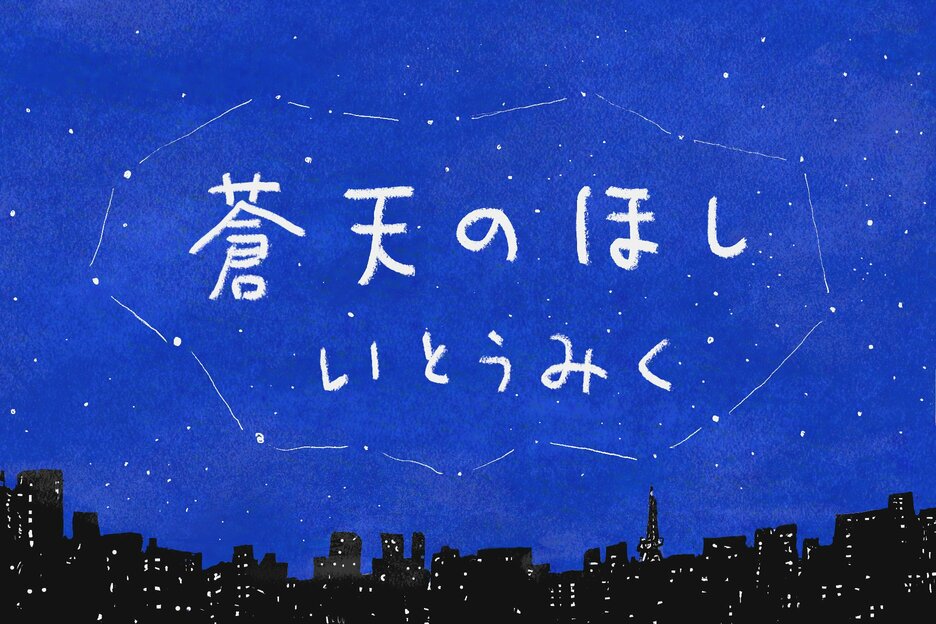数日後――
眠っている子どもたちの様子を見守りながら、薄暗い保育室で『豆庵』の葛餅を食べていると、インターフォンが鳴った。素早く保育士の坂寄千温が子機に手を伸ばした。
「はい。あ、お帰りなさい。いま開けます」と、立ち上がりながら門を解錠する坂寄に、「だれのお迎えっすか?」と、斗羽が葛餅を口にしながらもごもご言った。
「空君」
「今日、早いっすね」
壁掛け時計の針は、まだ十時を少し過ぎたところをさしている。坂寄が玄関へ向かうと、「空君連れてきます」と、斗羽も腰をあげた。
「ちょっと待って」と鈴音が言うと、
ん? と斗羽が振り返った。
「空君を起こすの、ちょっと待ってもらえる?」
「いいっすけど」と首をひねる斗羽に、鈴音はそれ以上は言わず廊下へ出た。
「お帰りなさい」
玄関先で坂寄と話しているお父さんに鈴音が声をかけると、「どうも」とお父さんは頭を下げた。
「あの、今日、館山へ行ってきました」
「館山って千葉の? 出張だったんですね」
と返す坂寄に、「空君のおばあちゃんのご自宅が館山でしたね」と、鈴音が口をはさむ。坂寄は「あっ」と口を動かした。
空君のことは、保育士たちには共有している。園児の家庭に関する問題は、個人情報保護などの観点から考えると周知の範囲は難しいところではあるが、空君親子の場合は、職員が全員で支えていく必要があると判断した。
「もしお時間が大丈夫でしたら、お茶でもいかがですか」と、鈴音が事務室を示すと、坂寄も「空君、よく眠っているので大丈夫ですよ」と、頷いた。
「……ありがとうございます」
いえ、と坂寄は笑みを浮かべて保育室へ戻って行った。
「冷たいお茶がいいですか? あったかい方がいいかしら」
「いえ、おかまいなく」
「わたしも一息入れたかったので、お付き合いいただけると嬉しいんですけど」
「では、あたたかいほうで」
了解です、と鈴音はお父さんにソファーを勧めて、コンロにヤカンを置いた。
窓の外からマツムシやコオロギの鳴き声が聞こえてくる。
「秋を感じますね」
鈴音が言うと、お父さんはふっと笑った。
「大学で上京したとき、東京でも虫の音が聞こえるんだって驚きました」
「どちらのご出身ですか?」
「山梨です」
「いいところですね」
「まあ、そうですね。山に囲まれてなにもないようなところでしたけれど」
鈴音はコンロの火を消して、急須にお湯をそそいだ。
「私はずっと東京だったので自然の中での暮らしに憧れがあるんです」
「東京の人はよくそう言いますよね。実際に暮らしたら不便なことが多くてうんざりすると思いますけど」
かもしれません、と鈴音は苦笑して、お父さんの前に湯気のあがる湯呑を置いた。
ありがとうございます、とお父さんは熱そうに湯呑の口と底を指先で持って、一口すすった。
「館山へは、空君のことで?」
抽象的な言い方をしてしまったけれど、お父さんは「はい」と頷いた。
「直接会って話をしたほうがいいと思って」
そうですか、と鈴音が言うと、お父さんはテーブルの上に湯呑を置き、それから顔をあげた。
「空が、あんなことを考えていたとは思ってもいなかったんです。義母との電話を聞いていたことにも気づいていませんでした。ひと言もわたしには言わなかったんで」
鈴音はわずかに口角を上げて見せた。
「不安にさせて、本当に空にはかわいそうなことをしました」
お父さんはすっと鈴音から視線をそらして、三か月程前に義父母から空君を引き取りたいという申し出があったのだと話を続けた。
「最初はそんなことはありえない、妻とも空を幸せにすると約束をしているのだと断りました。でもその後も何度も義母から話がありました。空に幸せになってほしいのは自分たちも同じだと」
膝の上で組んでいたお父さんの指先に力が入っているのが、鈴音の目にも見て取れた。
「言われたんです。空の幸せを思うなら冷静に判断してほしいと。何度も懇願されました。妻が亡くなったあとも義母がうちに泊まりこんで数か月間、空を見てくれました。そのときの私の様子からも、義母は私には任せられないと思ったのかもしれません。もちろん、私にはそんなことは言いませんが。でも、たしかに私が空と過ごせる時間は一日のうち数時間です。眠っている時間をのぞけば、二時間、いや、一時間程度です。これから小学校、中学校と成長していくにつれて、なおさら家族がそばにいるということは必要なんじゃないかと。空は義父母にも懐いています。空を手放さないのは私のエゴなのではないかと思うようになりました。そんな揺れを空は感じていたのかもしれません」
保育室から赤ん坊の泣き声が聞こえて、お父さんは廊下に顔を向けた。
「〇歳児の拓士君です。最近夜泣きが始まって、いまぐらいの時間にぐずりだすんです」
「そうなんですか」
「大丈夫ですよ。しばらく抱っこをしたり、外の風にあたったりしていると眠りますから」
「……空にもあったんですかね」
ん? と鈴音が首をひねるとお父さんは「覚えていないんです」と、ぼそりと言った。
「子育ては妻に任せきりで……。朝は出勤のぎりぎりまで寝ていたし、帰ったらもう深夜ですから二人とも眠っているのが常でした。休みの日に、『空を見ているから出かけてくれば』なんて妻に言ったりもしましたが、正直なところ、妻はそうはしないだろうってわかっていたんです。育児なんてまるでわかっていないおれに、空を任せることなんてしないだろうって」
お父さんは自嘲するように薄く笑った。
「本当は、義父母に任せた方が空は幸せかもしれません。それでも空を手放す決心はつかなかったんです」
鈴音は静かに頷いた。
「この間の日曜のようなことだって、今後もないとは言い切れません。もう少しゆるい部署への異動もいずれ考えなければとも思います。でもいまは」
「まだ迷ってらっしゃるんですか?」
鈴音の問いに、お父さんはかぶりを振った。
「空にとっての幸せを考えたら、手放したほうがいい。日曜のあの日、そう思って空を迎えにここへ来ました。でも……空の気持ちを知って、情けなかったです。たった三歳の子どもに、そんなに辛い思いをさせていたことにも気づかなかったなんて。父親失格です。ぜんぜん親としてやれていない。だけど、空が『おとーといっしょがいい』って言ってくれて、ぜんぶ吹っ切れました。空と生きていく。空が大人になって自分の意思で離れていくまで一緒に暮らしていきます。空のためじゃありません。空とおれのために。義父母にもそう話してきました」
お父さんは息をついて、冷めかけたほうじ茶を一気に飲み干した。
よかった、と無意識にことばがこぼれると、お父さんは小さく頷いた。
「空君、あれからとっても落ち着いています。お父さんが日曜に言ったことばで安心したんだと思います」
「そうですか」
「お父さん、周りを頼ってくださいね。迷惑をかけるなんて遠慮しないでください。迷惑はうんとかけていいんです」
お父さんは、不意をつかれたような顔で鈴音を見た。
「迷惑はかけていいんです」
鈴音はもう一度繰り返した。
「お互いに迷惑をかけあえる社会って、案外居心地がいいと思うんです。もちろんわたしたちもいますからね。たくさん迷惑かけてください」
お父さんは顔をくしゃっとして笑みをこぼした。
ベッドの中でふと目が覚めた。あくびをしながら枕元に置いてあるスマホで時間を確認するとまだ午前五時半だった。トイレへ行ってベッドに戻ったけれど、目が冴えてしまった。
麦茶をグラスに入れて、物干し台へ出た。
昼間は汗ばむくらいだけれど、朝夕は風が冷たく感じる。もう秋はそこまで来ているのだと空を見上げた。
昔、夜眠れないと言うと、祖母はよく物干し台に連れ出してくれた。小さなベンチに二人並んで腰かけて、ほとんど星の見えない空を見上げたり、虫の音に耳を傾けたり、ときには昔話をしてくれることもあった。鈴音に聞こえるか聞こえないかくらいの声で、囁くように語る祖母の声に耳を澄ませていると、いつの間にか祖母にもたれて眠っていた。
祖母とは高校二年の冬、母親が再婚をしたあとに再会した。それまで母親は、かたくなに祖母の住所を教えなかったけれど、再婚したことで気持ちが変わったのだろう。「いまも住んでいるかは知らないよ」と言って、祖母の住所を書いたメモを母は手渡した。
覚えてくれているだろうか。突然行って迷惑ではないだろうか。いまも本当にこの住所にいるだろうか。
祖母との思い出は断片的にいくつもあったけれど、祖母の顔もはっきりとは覚えていなかった。
恐る恐る訪ねていった鈴音の姿を見た瞬間、祖母は迷いなく「鈴音」と名前を呼んでくれた。
それから、祖母が亡くなるまでの五年間をこの家で祖母と暮らした。祖母の遺言で鈴音がこの家を相続し、十年前、一階を改装して夜間保育園を開いた。
顔をあげると、空が徐々に曙色に染まっていく。夜の濃い空に光っていた小さな星は、もう見えない。
社会の空気はいま、どのような環境にある子どもでも保育を受ける権利を認める、という流れに変化している。けれど、夜間保育はいまだ偏見をもたれている。夜まで子どもを預けるなんて子どもの成長によろしくない、働き方がおかしいと、声高に夜間保育は非難されることもある。食卓は家族で囲み、会話を楽しみ、家族団らんで過ごし、一緒に眠る。そうした環境が、子どもの情緒を豊かにする。
言っていることはわかる。理想もわかる。
理想は希望でもあると思う。
けれど、明るい場所からは見えないこともあるのではないだろうか。まるで蒼天の星のように。
夜に親がいない環境に置かれている子どもたちが現実にいる。現実にいま困っている子どもや親がそこにいる。彼らから目を背けること、見ようとしないことは切り捨てるということなのではないだろうか。
誰かが支えることで親子の暮らしを守ることができるのであれば、その努力はするべきだ。
向かいの家から犬の鳴き声が聞こえた。かしゃんと門が閉まる音がする。
「行ってきます」「行ってらっしゃい」の声が聞こえる。学校だろうか、仕事だろうか。ずいぶん早いなと思いながら、笑みがこぼれた。
「行ってきます」と出かけて行く人には、「おかえりなさい」と待っていてくれる人がいる。「行ってらっしゃい」と送り出す人には、「ただいま」と帰ってきてくれる人がいる。
帰って行く場所があり、待っていてくれる人がいる。
当たり前のことかもしれないけれど、これ以上幸せなことはないのではないか、と鈴音は思う。
子どもの頃、鈴音にそれを与えてくれたのは母親ではなかった。けれど……。
親であっても、祖父母でも親戚でも、あるいは血のつながりはなくとも、子どもは自分が愛されていること、守られていること、信用できる大人の存在を感じることができれば、幸せになれる。
自分を尊い存在だと、信じることができる。
鈴音は空を仰ぎ、目には見えない小さな星に目を凝らした。
(了)