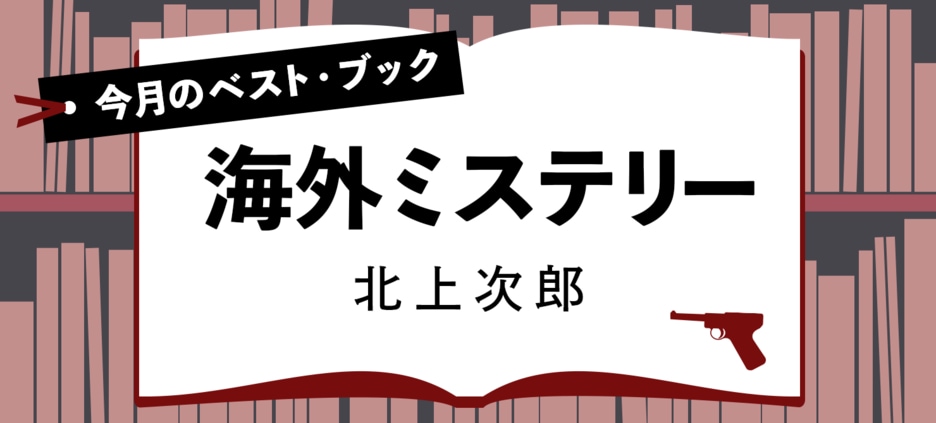今月のベスト・ブック
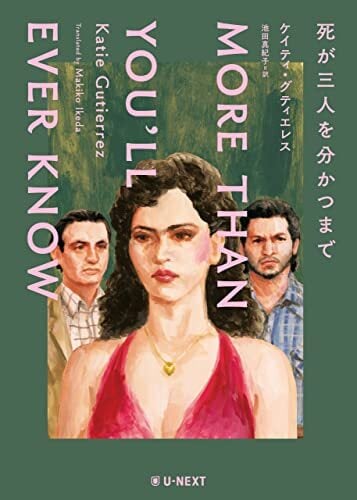
装画=高橋将貴
『死が三人を分かつまで』
ケイティ・グティエレス 著
池田真紀子 訳
U-NEXT
定価 2,200円(税込)
誤解されないように最初に書いておくが、マーク・グリーニー『暗殺者の回想』(伏見威蕃訳/ハヤカワ文庫)はやっぱり面白い。では、何が面白いのか。若き日のコート・ジェントリーの姿が描かれるからだ。「グレイマン・シリーズ」は今回が第12作だが、若きコート・ジェントリーが描かれるのは初めてではなかったか。そしてこれが、とてつもなく興味深いのである。
25歳のコート・ジェントリーは、すでに暗号名ヴァイオレイターの非公式偽装工作員として知られていたが、突如としてCIAの特殊部隊への編入を求められ、つまりチームプレイを要求されるのである。こうなると、どうなるか。個人としては有能でも、チームの一員としては機能しないのである。
だから特殊部隊の他の面々がコート・ジェントリーを認めずに対立することになる。そのときのコート・ジェントリーの態度に留意したい。彼はこう言うのだ。
「おれはあんたたちのチームにはいりたくない。ここに5分いただけで、あんたらが思いあがった馬鹿野郎だとわかった。おれは──辞めない──それだけだ」
これほど露骨に感情をぶつけるコート・ジェントリーは珍しい。ようするに、自分の感情の爆発を抑えられないほど、まだ若かったということだ。
興味深いのは、このあとの展開である。最初は対立していても、やがてコート・ジェントリーの実力にみんなが気づき、力を合わせていく──との展開になるのがこういう場合の常套だが、『暗殺者の回想』の場合、そうはならない。なぜか。
こういう一文がある。
「25歳のジェントリーはもともと、ひとと交流すると気詰まりがする。だが、今回のストレスは、限度をはるかに超えていた」
つまり、コート・ジェントリーが個人プレイを好むのは、暗殺者という職業的特性ではなく、性格的な問題だというのだ。そうか、そういうことか。コート・ジェントリーに友達がほとんどいないこともこの文脈で理解されるし、シリーズ第2作『暗殺者の正義』がいまだ忘れられないのも、そういうことだ。ネタばらしになるのでこれは詳しく書けないが。今回は恋人ゾーヤが不在だが、そのことよりも友達がいないことが気になる。唐突ながら、ジェイムズ・ボンドにも友達がいなかったことを思い出す。あれもやっぱり、ひとと交流すると気詰まりになるという性格的な問題だったのだろうか。ヒーローがいつも孤独であるのはそういうことなのだろうか。
今回、若きコート・ジェントリーの姿が描かれるのは、12年前に死んだはずの男が生きていて、それを調べるという結構のためである。そのために、12年前と現在を交互に描いていく。この先が書き辛い。
これまで私は、マーク・グリーニーのこのシリーズをずっと絶賛してきた。冒険小説の神が21世紀に降臨した、とまで書いた。これは現代の奇跡である、と書いた。
しかし、今回はどうか。最初に書いたように、グリーニーはやっぱり面白い。特に今回は、若き日のコート・ジェントリーの姿が描かれるので、大変に興味深い。後半のたたみかけるアクションも素晴らしい。だから、ちょっとしたことには目をつぶり、今回も絶賛しておけばいい。
だが私は、このシリーズをこよなく愛しているので、少しでも違和感を感じるものを絶賛することはできない。違和感とは何か。
いつもの躍動感に少し欠けないか。冒頭から激しいアクションをたたみかけ、あっという間に物語に引きずり込む迫力に、少し欠けていないか。12年前に死んだはずの男が生きていた、という今回の発端のネタも、よく読むとたいしたネタではないし、この男にも魅力がない。前作『暗殺者の献身』の仇役の凄さにはとても匹敵できない。
おお、書きはじめるとどんどん欠点を指摘しそうで、イヤだ。あまりグリーニーの欠点など指摘したくない。たぶんこれは、ちょっとした気の迷いだ。どんな天才にもこのくらいの寄り道はある。それに、他の作家の作品と比べれば、遥かに面白いのだ。しかしグリーニーの作品に普通の○印は付けたくないので、今回は無印にしておく。
今月の推薦作は、ケイティ・グティエレス『死が三人を分かつまで』(池田真紀子訳/U-NEXT)。これはヘンな小説だ。急いで書いておくが、「ヘン」というのは私の場合、褒め言葉である。30年以上前の殺人事件を犯罪実話ライターのキャシーが調査する話で、その事件の中心にいるのは、2人の男と重婚したヒロイン、ローレ。1人の夫がもう1人の夫を殺した事件なのだが、すべての原因となったローレはずっと沈黙を続けている。そのヒロインに取材できれば、新しい犯罪ノンフィクションが書けるはずだとキャシーは考えるのである。
ここまでならよくある話だが、キャシーの側にもいろいろあって(これが本書の読みどころなので、その詳細はここに書かないでおく)、これが圧倒的に読ませて飽きさせない。そして、読んでいくとどちらのヒロインが主人公なのか、実際に起きたのは何なのか、わからなくなるのもヘン。これがデビュー作ということで、この作家がどこへ向かうのか皆目見当もつかないが、今月の○印。