柳宗悦 1889 - 1961 享年72
名もなき器に、美を見た──
柳宗悦と民藝という逆襲
無名の職人によってつくられた日用の雑器の中に、美を見出した柳宗悦。
彼が提唱した「民藝」は、権威ある美術から
見過ごされてきたものへの眼差しだった。
美とは何かを根源から問い、日本の美意識に大きな転換をもたらした
思想家の探求の軌跡を辿る。
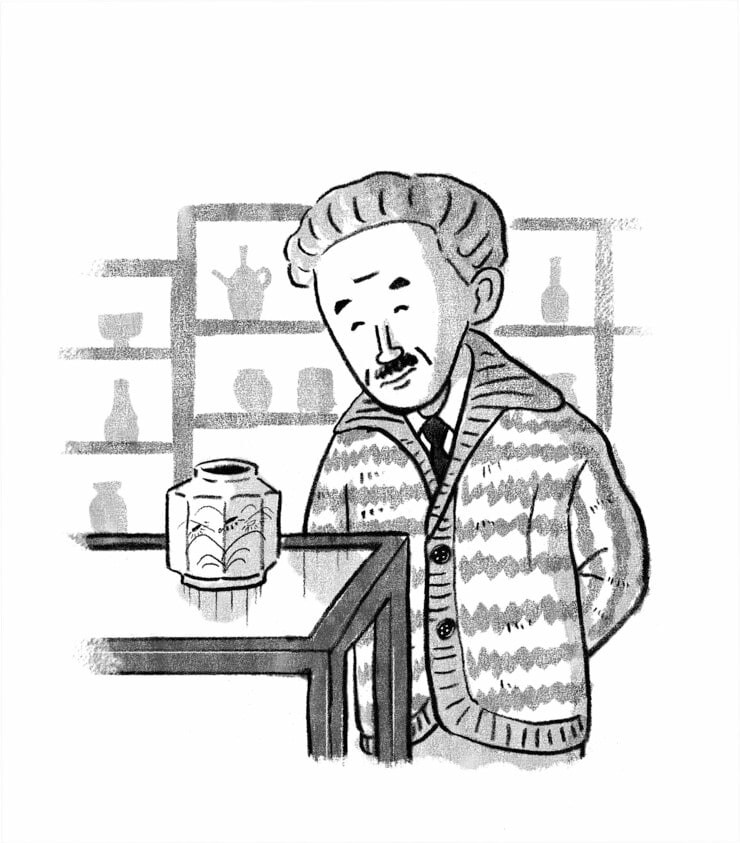
1889年、柳宗悦は東京市麻布区市兵衛町(現・港区六本木3丁目)に、海軍少尉・和算家であった父・楢悦と母・勝子(柔道家・嘉納治五郎の実姉)の三男として誕生した。
学習院初等科・中等科を経て、高等科に進んだ柳は、当時英語教師として学内にいた鈴木大拙から指導を受けている。やがて、仏教哲学者として世界的に知られるようになる大拙だが、この時点で柳が思想的な影響を受けたという記録はない。ただ、後年、二人は「無心」という境地を思索の柱とするようになり、終生にわたり深い交流を育んでいく。無心とは、自己や知識を手放し、物事と静かに向き合う心の在り方である。この若き日の出会いも、柳の内面にひとつの静かな余韻を残していたのかもしれない。
21歳
雑誌『白樺』創刊、ロダンの衝撃
1910年、柳は学習院出身者の志賀直哉、武者小路実篤らと文芸・美術誌『白樺』を創刊する。誌上では文学を通じて人間の内面を見つめ直すと同時に、西洋の近代美術も積極的に取り上げた。同年、「ロダン号」を発行した折には、ロダン本人から白樺同人に作品3点が寄贈され、その初来日のロダン彫刻を横浜港に引き取りに行ったのが柳だった。それまで日本には仏像彫刻は存在したが、西洋的な「彫刻」という概念はなく、ロダンの作品を実見した柳は、「そのときの想いは全く筆には書けません」と述べるほどの衝撃を受けている。
24歳
指針となる言葉を得て、無銘の美と出会う
1913年、東京帝国大学哲学科を卒業した柳は、翌年に声楽家の中島兼子と結婚し、千葉県我孫子へ転居する。白樺派をはじめ、多数の表現者が集ったこの地を、柳は「コロニー」と呼び、さまざまな出会いが刺激となり、創造の源泉ともいえる場となった。
この頃、柳はイギリスの詩人で画家のウィリアム・ブレイクの思想に傾倒し、日本初の本格的研究書を出版する。「見る眼は知る心よりも勝る」というブレイクの言葉は、柳の精神に深く刻まれ、それが単なる詩句を超えた〝指針〟として機能しはじめる。理屈や知識によらず、物をそのまま観て、そこに宿る本質を感じ取る──それこそが「直観」であり、この言葉が、のちに民藝という思想を生む眼差しの起点となった。
そしてある日、韓国で小学校教師をしていた浅川伯教が、朝鮮陶磁器を手土産に、柳邸にロダンの彫刻を見に訪れた。その無銘の器物に美しさを感じた時、柳の中で何かが静かに揺らいだ。名や由緒に頼らずとも、美は確かに存在し得るのではないか。その気づきが、柳の眼に新たな方向性を与えたともいえる。以後、柳は幾度も朝鮮を訪れ、朝鮮工芸に触れる中で、その背後にある人々の暮らしや風土への愛着も深めていくようになった。
35歳
木喰発見、京都へ転居、「民藝」誕生
無銘の朝鮮の器物との出会いを契機に、〝名にとらわれぬ美〟への関心を深めていった柳は、1924年、朝鮮陶磁器を蒐集する知人宅で、木喰上人の仏像を偶然目にする。今でこそ、江戸時代に諸国を行脚し、民衆のために仏を刻み続けた円空と並び称される木喰だが、当時はまったくの無名で、芸術的価値を見出す者はいなかった。だが柳は、素朴で荒削りながら微笑をたたえる像に、即座に心を奪われる。この邂逅を通じて、柳は日本各地を巡って木喰仏の調査を進めるようになり、土地ごとに息づく民衆的な工芸の存在と、その広がりを実感していくことになる。
関東大震災を機に、同年京都へと移り住んだ柳は、我孫子時代に交流があった濱田庄司と再び交わる。濱田は1920年からイギリスでバーナード・リーチらと作陶を学び、震災後に帰国し、現在は友人である陶芸家・河井寛次郎の邸宅に寄寓していた。こうして3人は京都において親しく交わり、木喰仏やスリップウェア(ヨーロッパでつくられた古い時代の陶器)、京都の朝市で入手した「下手物」と呼ばれる民衆の雑噐などを前に、「美とは何か」を語り合う日々を重ねていく。以来、互いの信頼と対話は続き、美の本質を巡る探求を生涯にわたって共有し続けることになる。
そうした中で柳は、無名の職人が生み出した生活の道具の中に美を見出し、それを「民藝(民衆的工藝)」と名づけた。1925年のことである。それは、既存の美の序列に意義を唱える沈黙の革命だった。
47歳
「日本民藝館」開館、初代館長に就任する
1933年、柳は京都から東京へ戻り、その翌年に民藝運動の活動母体となる日本民藝協会を設立。さらに、1936年には東京・駒場に日本民藝館を開館する。日本民藝館は、日々の暮らしに根ざした美の存在を社会に問いかける場として設計され、蒐集・保存・研究・展覧会といった活動を通じて、民藝を広めるための拠点となった。
70歳
柳が示す美への姿勢とは
戦後も著作や講演を通じて民藝思想を広め続けた柳は、晩年、自らの信念を短句集『心偈』にこう記した。
「見テ 知リソ 知リテ ナ見ソ」
まず見て、それから知れ。知ってから見るな──知識や先入観によって視野が曇る前に、まっさらな眼で対象と向き合えというこの言葉には、柳の美への姿勢すべてが凝縮されている。肩書や由来ではなく、目の前にあるものの本質を見つめること。それは、美は誰かに教わるものではなく、自らの眼で見出すものだという確信であり、「直観の眼」こそが、柳が辿り着いた美の核心だった。
