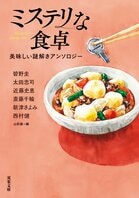「うちは実家が千葉のダリア農家でさ、そこの花を中心に仕入れてるんだ。今はハウス栽培もできるから、日本全国にダリアの生産者がいる。だから、一年中いろんな品種を揃えられるんだ。その全部に名前がついてるんだよ」
「そうなんですね。咲き方もいろいろあるみたいで、すごく興味深いです」
もっとダリアのことが知りたい。名前も覚えたい。そんな欲求が湧いてきた。
太輝を見つめていた陸が動き、ショーケースの真ん中に手をかけてガラスの引き戸を開けた。真っ赤な『宇宙』を一輪だけ取り、水気を取って太輝に差し出す。
「せっかく来てもらったんだ。プレゼントするよ」
「いいんですか?」
「もちろん。あとで和馬にラッピングさせるから」
「了解っす!」
美形だけどお調子者っぽい和馬が、おどけて敬礼をする。
太輝は、陸から手渡された深紅のダリアにしばし見惚れた。
薔薇の花のように艶やかだが、薔薇のような強い香りはしない。きっちりと規則的に並ぶ花弁と相まって、どこか人工的な感じもするけど、摘まれる前は大地に根を生やしていた生物だ。茎を切られて朽ちる前の今もなお、凜と咲き誇っていることに、畏怖の念すら覚えてしまう。
「花ビラが規則的に並んでるから、見てると真ん中の花芯に吸い込まれそうな気持ちになるんですよね、ダリアの花って」
思わずつぶやくと、陸が「そうなんだよ」とうれしそうに相槌を打った。
「雪の結晶や葉脈の模様のような〝フラクタル〟と呼ばれる自然の幾何学模様は、人間の前頭葉に何らかの刺激を与えるらしい。ゾワゾワと落ち着かなくさせたり、逆に安らぎを与えたりね。ダリアの花弁のつき方も幾何学的だから、同じような効果があるのかもしれない」
学者のごとく饒舌な陸。ダリアのことならなんでも答えてくれそうだ。
「うちのオーナーはね、ダリアだけじゃなくて占いなんかにも詳しいんだ。お客さんに花占いをしてあげることもあるんだよ。よく当たるって評判なんだ」
得意げに和馬が鼻を膨らませる。
花占いもするオシャレなダリア専門店か。さぞかし人気なんだろうな。
正直なところ、店の花瓶に整然と並ぶダリアよりも、福島の農家で土に生えていたダリアのほうが自分の好みには合っている。だけど、ダリアの専門店なんて本当に珍しい。今まで知らなかった情報も、ここにいたら入手できるかもしれない。できることなら働かせてほしいのだが……。
物思いにふけっていたら、「で、太輝くん」と陸に呼ばれた。
「バイト、いつから入れる?」
「雇ってもらえるんですか?」
「うん。前の子が急に辞めちゃって、早く人手が欲しいんだ。君、ダリアに縁がありそうだし、真面目そうでちょっと影のあるところが女性客にウケそうだしね」
「あの、どんな仕事をすればいいんでしょう?」
「花の手入れや掃除、接客、あと配達。肉体労働も多いけどすぐ慣れるよ。なるべく早く来てもらえたら助かる。一応、履歴書は持ってきてね。本当に引っ越す気があるなら和馬が世話してくれるよ。和馬も君と同い年だ。気軽に相談するといい」
「ういっす」と、和馬が右親指を突き出す。
「オレ、こっから徒歩十五分のコーポに住んでんだけど、そのコーポ、うちの母親が家主なんだ。空き部屋あるから紹介する。ボロいけど安くて住みやすいよ」
「はあ……」
不思議なほどサクサクと話が進んでいく。だけど、何かがうまくいくときは、点と点がスムーズに結ばれていくように繋がるものだと、誰かが言っていた。この流れに身を任せたら、順風満帆とは絶対に言えない自分の人生にも、変化が訪れるかもしれない。
「じゃあ、来月からお願いします」
太輝は、陸と和馬に深々とお辞儀をしたのだった。
店を出る直前に、「魔女」と呼ばれていた少女が持っていた丸いダリアが、ショーケースの中にあるのを見つけた。花瓶に『シルクハット〈フォーマル・デコラティブ咲き〉』とある。滑らかなシルク生地で作られたような、直径八センチほどの愛らしい純白のダリアだ。
あの子も、この店でダリアを買ってるのかもしれないな。
猫のように光ったハシバミ色の瞳が、どうしても脳裏から離れなかった。