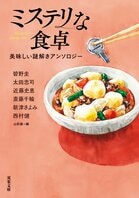*
奇妙な少女に後ろ髪を引かれながらも、気持ちを改めて目的地へと向かう。
その日、太輝が訪れていたのは、世田谷区の多々木町だった。
多々木町は、瀟洒な邸宅やマンションが立ち並ぶ住宅地でありながら、東京二十三区では珍しい渓谷がある街。渓谷の真ん中を流れる小川の周辺には、湧水の発生場が数カ所あり、ケヤキやコナラといった樹木や幾種もの湿性植物を育みながら、緑豊かな湿地帯を形成している。
そんな多々木町の商店街に、ダリア専門店『THE DAHLIA』がある。
初めて店を見たときは、洒落たバーかと思った。
ガラス張りの店内はステンレスのバーカウンターで仕切られ、その奥の巨大な水槽のようなショーケースに、ダリアが品種ごとにディスプレイされていたからだ。カウンターの前にはスツールが四脚ほど置いてあり、そこに座るとバーテンダーがカクテルを出してくれそうな雰囲気さえ醸し出している。
入り口の左右横に設置された、花器やアレンジメントが飾られたガラス棚や、磨き上げられた白い大理石の床も、スタイリッシュという形容詞がよく似合う。
入りたいんだけど、オシャレすぎて入り辛いんだよな……。
ガラスに映った痩せて無造作な髪型の男が、やけに貧相に見える。いつものクセで、着古したパーカーの袖口をクンクンと犬のように嗅いでしまった。昨日、洗濯して日干ししたばかりなのに。
しばらく躊躇していたのだが、ガラスに貼られた「アルバイト募集中・要運転免許」の貼り紙に背中を押され、思い切って自動ドアから中に足を踏み入れた。アロマのような人工的な香りが押し寄せて、落ち着かない気分になる。
「いらっしゃいませー」
濃いグレーのTシャツにブラックジーンズ、銀色で店名の入ったグレーのエプロンをつけた青年が、愛嬌のある笑顔で迎えてくれた。目にかかるくらいにセットされたブラウンの髪には、金色のメッシュが細かく入っている。大きな黒目がちの瞳。緩やかに弧を描く口元からは白い歯が覗いている。
雑誌モデルのように都会的な青年。自分とはかけ離れすぎていて苦手だ。別の人がいるときに出直したほうがいいかもしれない。
踵を返そうとした太輝を、「ちょっと待って」と青年が引き止めた。
「もしかして、バイト募集の貼り紙、見てくれました?」
「あ、はい。でも……」
またにします、と言おうとしたのだが、その言葉は彼の甲高い大声に遮られた。
「陸さん! バイト希望さんが来てくれたっすよ! ねえ、陸さん!」
「……なあ、いつも言ってるだろう。和馬は声がデカいんだよ」
カウンターの奥から長身でガタイのいい男性がヌッと出てきた。腰をかがめて何かの作業をしていたようだ。和馬と呼ばれた男子と同じグレーのTシャツにエプロン姿で、顔は薄っすらと日焼けをしている。短髪でやや厳つい顔つきだけど、目元の皺がやさしそうな人だった。
「こんにちは。オーナーの戸塚陸です。こっちは唯一の社員で岩野和馬。えーっと、お名前と年齢を訊いてもいいかな?」
「鏡太輝、二十歳です」
「太輝くんね。履歴書はある?」
「いえ、表の貼り紙を見ただけなので」
「そう。車の免許は持ってる?」
「はい。大型を」
「大型免許ってことは、トラックでも運転してたのかい?」
「そうです。廃棄物を運ぶ仕事をしてました」
産業廃棄物ドライバーだった頃は、常にゴミの臭いに悩まされていた。特に酷かったのが、汚泥や廃油の回収時だ。全身をくまなく洗っても、しばらく臭いが取れないのである。そのせいで、いまだに身体や衣服の臭いを気にするクセが直らない。
「廃棄物の処理か。尊い仕事をしてたんだね。気に入ったよ」
陸が柔らかく微笑む。パイプオルガンのように重厚な低音ボイスが、すっと耳に入ってくる。前職を褒められたのは初めてで、どうリアクションしたらいいのかわからないけど、肩の緊張が少しずつ解れてきた。
「それで、今どこに住んでるんだい?」
「神奈川県の川崎です。でも、ここら辺に引っ越したいなと思ってて……」
「へぇー、なんでなんで? あ、立ってないでここに座りなよ」
人懐こそうな和馬がスツールを勧めてくれたので、なるべく浅く腰をかける。
「……あの、渓谷があるからです。緑の多い街に住みたくなったというか。……それに、ダリアの花にも思い入れがあって、専門店なんて珍しいから来てみたんです。そしたらバイト募集中みたいだったので、つい入ってしまったんですけど……」
とつとつと話しながら、ガラスのショーケースにディスプレイされたダリアに視線を向けた。鏡になった壁を背景に、大小さまざまな形のダリアたちが、円柱形のステンレス花瓶に生けられている。その中に、昔、弟と墓標にした大きくてまん丸い深紅のダリアも交ざっていた。『宇宙〈フォーマル・デコラティブ咲き〉』と書かれたプレートが花瓶に貼ってある。
「あの大きな赤いダリア、宇宙って名前なんですね。知らなかったです」
「日本産では一番巨大なダリア。最大で直径三十センチを超えるんだ」
穏やかな表情で陸が言う。聞く者の心を落ち着かせる、ゆったりとした話し方だ。太輝の口も自然に開いていく。
「実家の近くにダリア畑があって、子どもの頃、よく売れない花をもらってたんですよ。その中にこれもあったなって、思い出しました。結構いい値段がするんだなあ……って、すみません」
余計なことを言ってしまったが、陸は目元の皺をさらに深くした。