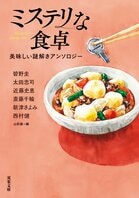*
太輝が「彼女」と出会ったのは、桜が香る季節の夕刻だった。
とある街の桜並木を歩いていたら、前方の角からふいに現れたのだ。
「ねえ、お母さん。魔女がいるよ」
横を母親と歩いていた幼い少年が、彼女のほうを指差す。
「こら、大声で言わないの。聞こえちゃうでしょ」
「でもさ、魔女を見たら呪われるんだって。なんか怖いよ……」
「そんなことあるわけないでしょう。ほら、あっちに行くよ」
母親が少年の手を引いて、横断歩道を横切っていく。
魔女、と呼ばれていたのは、全身黒ずくめの少女だった。
漆黒のフード付きロングワンピースに黒いブーツ。大きなフードで顔の半分を隠し、まだ幼さの残る口元を固く結んでいる。フードの下から腰までありそうな栗色の髪を垂らして、うつむきながらトボトボと歩いている。まるで、喪にでも服しているかのように寂し気に。
彼女は、ワンピースの長い袖から覗く華奢な右手で、ゴルフボールのように丸くて白いダリアの花束を抱えていた。左手には水の入ったビニール袋が握られている。ビニール袋に目を凝らすと、紅色の小魚が一匹だけ、腹を上にしてぽっかりと浮かんでいる。──あれは金魚の死骸だ。
心臓が止まりそうになった。
ダリアの花と生物の死骸。福島にいた頃に弟とやっていた『お墓ごっこ』を、否が応でも思い起こしてしまう。
しかも彼女は、小声で歌を口ずさんでいた。
「唄を忘れたカナリヤは 後ろの山に棄てましょうか──」
小学校の音楽で習った童謡の『かなりや』だ。続きがあるはずだが、そのフレーズだけ繰り返している。ピアノの高音のような澄んだ歌声だけど、どうにも不吉で視線が外せない。
──まさか、どこかの山に金魚の死骸を埋めようとしているのか? ダリアを墓標にして。いや、田舎の子どもじゃあるまいし、そんな奇特な人いないよな。だけど、本当に魔女みたいに不気味な女の子だ。フードの下の素顔が気になるけど、覗き込むわけにはいかないしな……。
などと考えていたら、ふいに春風が吹き上がり、彼女のフードがふわりと脱げた。
ロングヘアが後方になびき、切り揃えられた前髪と目元があらわになる。
大きく開かれた二重の瞳。ふっくらとした涙袋。黒目ではない。ヘーゼルナッツのような茶色がかったハシバミ色だ。睫毛が驚くほど長い。ツンと上を向いた鼻と、小さく尖った顎。人形かと思うほど整った顔立ち。あわててフードを被り直そうとした右手の長い爪には、真っ黒なネイルが塗られている。
太輝は、一瞬だけ視線を合わせてしまった。
街灯の光を受けて、彼女の両目が猫のように金色に輝く。
「魔女」という言葉がまた浮かび、背筋がゾワッとした。
彼女は純白の花束と金魚の死骸を抱え、黒いフードを被ったまま通り過ぎていく。『かなりや』のワンフレーズを繰り返しさえずりながら。
一体、どこに何をしに行こうとしてるんだろう……?
すれ違ったあとも、その場に立ち止まって少女の背中を見つめてしまった。
夕闇に桜の花ビラが舞う中、黒い後ろ姿が遠く小さくなっていくまで。