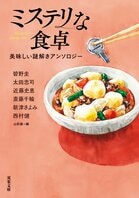ヨーロッパが原産のダリアには、『天竺牡丹』という和名があるらしい。
天竺牡丹。まるで天上の神々に選ばれた花のような呼び方だ。
この場に飾るのにふさわしい、厳かな響きの和名を持つ花。舟形の長い花ビラで幾重にも覆われた、直径二十センチほどもある巨大な深紅のダリア。
──やっぱキレイだな、と改めて思う。見慣れた花なのに、墓標として土に挿した途端、まったく別の神聖な花のように見えてくる。
しばらくダリアの墓標を眺めたあと、弟と並んで手を合わせた。
どうか安らかに眠ってください──と、心から祈りながら。
*
鏡太輝の故郷には、クジラが泳ぐ森があった。
一千万年もの遥か昔、その辺りの大地は海中に沈んでいたという。それが長い年月をかけて隆起した結果、現在のような山地になったそうだ。だから、貝を始めとする太古の海の生物は、今も化石となって山に埋まっている。
巨大クジラの骨の化石が発掘されたのは、今から二十年ほど前のこと。以来、地元ではここらの森林を『クジラの森』と呼んでいる。雨の降ったあとにその辺りに来ると、潮の香りが漂うこともあった。きっと、海中だった頃の名残だろう。
単なる気のせいかもしれないけど。
ダリアなどの観賞用植物や、米や野菜が主な生産物の、福島県にある長閑な街。茨城県との県境からほど近いその地で、太輝の両親は小さな温泉旅館を営んでいた。二階に和風の客室があり、一階に食堂や温泉浴場を設えた、民宿に毛が生えたような旅館だ。太輝たち家族の住居は敷地内の離れにあった。
朴訥だが丁寧な父のもてなしと、地産の食材で母が作る素朴な夕食、知られざる秘湯と呼ばれた効能豊かな温泉は、殊のほか評判を集めていたようだった。リピーター客も多く、太輝を見かけて声をかけてくれた人も数知れない。
両親が多忙だったため、幼少時はいつも弟と共に遊び回っていた。
弟、とは言っても、二卵性双生児なので誕生日は同じだ。ただ、自分のほうが先に母親の体内から出てきたにすぎない。
顔立ちも体格もあまり似ていなかったが、太輝にとって弟は半身のような存在だった。彼が笑えば自分も笑顔になり、泣けば同時に悲しくなる。互いの痛みすら感じ合うほど、心が通じ合っていた。──などと、あの頃は純粋に信じていた。
弟と同じベッドで並んで眠り、隣同士の机で学校の宿題をやり、他愛もないことで笑い合う。家のリビングに古びた木製のピアノがあって、結婚前はピアノ講師をしていた母親から習った曲を、ふたりで奏でたりもした。
室内でピアノを弾くのも楽しかったけど、外で遊ぶほうが圧倒的に多かった。
澄んだ小川でザリガニを釣ったり、クジラの森で昆虫採集をしたり、ボーイスカウトで習ったロープ結びでハンモックを作ったり。
中でも夢中になったのが、『お墓ごっこ』だ。
自然の宝庫であるこの辺りでは、小さな生物の死骸をよく見かける。昆虫や爬虫類、ハトやカラスなどの鳥類。ときには狐や狸など、野生動物も見つけた。野生動物は、車に轢かれていたことが多かったと記憶している。
魂が抜けてしまった亡骸をビニールで包み、クジラの森へと運ぶ。
死骸を土に埋めたら、そこに花を挿して『ダリアの墓標』にするのだ。
墓標にするダリアの種類は、その都度変化した。
艶やかな赤。可憐なオレンジ。華やいだ黄色。大人びた紫。淡いピンクも眩しい白もあった。色も大きさも多種多彩なダリアは、選び放題だったと言っても過言ではない。太輝の家のすぐそばにダリアの生産農家があり、いつも売り物にならない花がバケツに入れてあったからだ。そこからダリアを持っていくのである。
農家の人は、子どもたちの花泥棒を知っていながら、いつも笑顔で見逃してくれた。「どうせ捨てちまう花だから、いくらでも持ってけ」と。
太輝たちは夢中になって死骸を探した。花の墓標を立てて弔うことが、崇高な儀式であるかのように思っていた。
しかし、あるとき太輝は見てしまった。
弟が小さなトカゲを足で踏みつぶそうとしたのだ。
「そんなことしちゃダメだ!」と、大声で戒めた。
ビクッと肩を動かし、弟が足を止める。薄茶色のトカゲが素早く逃げていく。
「だって、死骸がなかなか見つからないから……」
「だからって殺しちゃダメだよ。小さくたってみんな生きてるんだから」
「それなら、ダリアだって生きてたじゃないか。今は茎を切られて死にかかってる。なんで植物はよくて動物はダメなの? 同じ生き物なのに」
弟の真顔の問いかけに、子どもだった太輝は答えられなかった。大人になったら答えられるのか、と考えたら、それも難しそうだった。
「……とにかく、ダメなもんはダメなんだよ」
結局、なんの説得力もない言葉しか出てこなかった。
「わかったよ」と、泣き出しそうな顔で返した弟の声は、太輝の耳奥にあるレコーダーに録音され、いつでも再生可能になっている。
一体、どう答えればよかったのだろうか。正解は見つからないままでいる。
いたずらっ子だけど可愛い同い年の弟。頼もしい父、やさしい母。ピアノまで家にあったほど、そこそこ豊かだった生活。
そのささやかな幸せは、太輝が八歳のときに突如幕を閉じた。
家族を失って以来、ぽっかりと空いてしまった心の穴は、二十歳になった今でも塞がる気配がない。
いまだに、子どもの頃の夢を頻繁に見る。
かつて、雄大なクジラが泳いでいた神秘の森。
風にそよぐ赤いダリアの花。無邪気にはしゃぐ弟の姿。
もう二度と、あの愛らしい笑顔を見ることはない──。