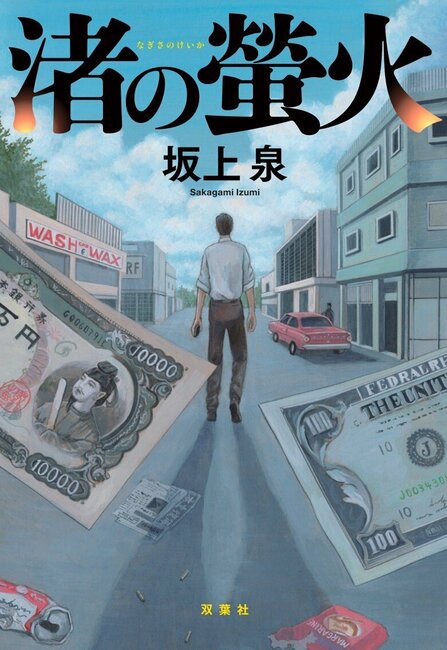第一章 灰色の帰還
四月初旬というのにすでに蒸し暑い風が、開け放たれた窓から会議室のなかに吹いた。机に置かれたガリ版刷りの資料が、パラパラと音を立ててめくれる。出席者の数だけ刷ったが、半分は手に取られることもなく放り出されている。
刑事部長以下、関係する主だった警察幹部が揃うなか、自分には関係ないと決めてかかっている幹部は気だるげに煙草を燻らせる。なかには、鬱陶しげにこちらを睨みつけてくる者もいる。
その視線に気づかぬふりをして、説明を始める。
「対策室捜査班長の真栄田太一警部補であります。お手元の資料にも記載しておりますが、本土では昨年、昭和四十六年(一九七一)の知能犯全体の検挙率は九割であるにもかかわらず、通貨偽造事犯は五割前後と低迷しております。高額紙幣をゼロックスで印刷するような手口は急減した一方で、偽造硬貨を自動販売機に投入し、商品や釣り銭を騙し取る手口が急増しております」
手元のノートには、本土の警察庁がまとめる『犯罪白書』の最新版、昭和四十六年版からの書き写しがある。昭和四十五年(一九七〇)に発見された偽造通貨六三〇枚に対し、被疑者が検挙されて解決されたものは三九〇枚と六割ほど。まだ正式に発表されていないが、四十六年に至っては警察庁の集計では解決数は三割ほどだという。
警備部の総務課長が島の訛りを丸だしにして冗談を放つ。
「相手が機械だから騙さりーさ。ここらの商店には、そんな立派なものはあらんから騙しようもないさあ。『対策室』とやらが、何をそんなに心配する必要あるかー?」
嘲りと茶化しの混ざった笑いが、会議室の四角く囲んだ机の向こう側、警備部の幹部の居座る一帯から上がる。室内の蒸し暑さが増したような気がした。
本土の警察庁が日本全土から集計した数字と、その結果警察庁官僚が抱いている危機感を、ここにいるほとんどの者は理解すらしていない。この「対策室」の設置を主導した刑事部長を正面切って批判せず、最若手のこちらに当てつけようという、みみっちい魂胆だけが明け透けに見えている。鼻で小さく溜息をつく。
「本土の人間はこれまで円の紙幣や硬貨に慣れ親しんでおり、少しの違いにも気づきやすいです。一方で我々――」
言いよどむ。
自分たちは今、己を何者だと名乗るべきなのか。
米軍機の切り裂くような爆音が上空から襲ってきた。轟音は衝撃波のように、開け放った窓ガラスを乱暴に震わせる。鉄筋コンクリート造りの三階建て庁舎は、軍用機の低空飛行でがたつくことはない。ベトナムでの戦争に米軍が出撃するようになって以来、以前にも増して空を覆い尽くすようになった爆音も、この島に生きる者にとっては慣れたものだ。
ある者はうちなーと呼び、ある者は琉球、そして沖縄とも呼ぶ、この島の日常。
轟音が遠ざかるのを待って、言葉を繋いだ。
「――我々沖縄人はこの十四年間米ドルを使い、それ以前のB円も含めると二十年以上、日本円に馴染みがありません。それは我々捜査側、琉球警察も同様かと思われます」
琉球警察――間もなく沖縄県警察へと変わるその名を、あと何度口にするだろうか。
「それが今度の本土復帰に合わせて急に日本円を導入するのですから混乱は必至と見られます。稚拙な技術で作られた日本円の偽札であっても、見慣れていない沖縄人が、いや、我々琉球警察も騙される可能性は大いにあります」
あえて「稚拙」と強い言葉を使ったことで、馬鹿にされた気分になったのか、幹部陣に鼻白んだ空気が漂う。それでも、先ほどよりはまだ話を聞こうという気にはなったはずだ。
「それだけではなく、現在沖縄に流通する数億ドルもの通貨をこれから回収するわけですが、昨年のドル預貯金確認の際にも微量とはいえ一〇〇ドル、二十ドル、五ドル紙幣が各一枚、計一二五ドル分の偽札が確認されております。また、本土でも海外旅行の増加に伴い、米ドルの偽造件数が増加傾向にあります。今回の本土復帰での円ドル交換を好機と見た偽造団が、沖縄に偽札やその製造装置を持ち込む可能性は、大いに警戒すべきかと」
手元のノートに書き記してあった数字を、淡々と幹部陣の鼻先に突きつけ、念を押すように付け加えた。
「万が一、偽の米ドル札をアメリカ側に引き渡せば、ただでさえ円ドル交換レートを巡って琉米の間で軋轢があったばかりです。外交問題につながる恐れもあります。そうなると内地の警察庁はもちろん、米本国からFBIがやってくるような渉外事件になるのは必至かと」
数人の眉間に皺が寄り、面白くないと言わんばかりに煙草を灰皿に押し付ける。
渉外事件――即ち米軍人・軍属の起こした犯罪として、米軍捜査機関との交渉を必要とする共同捜査事件は、広大な基地と数十万の駐留軍人を抱えるこの島では、年間一〇〇〇件近く発生している。そこに日本警察庁と米FBIの双方が介入する事態になれば、どれほどの厄介事になるか。
刑事部長の喜屋武幸勇警視正が、撫でつけたごま塩頭に汗を浮かべながら、咳払いをして恰幅の良い体を震わせた。
「真栄田、警視庁に二年、君を出していたのは、そういう事態にならんようにするためさ。分かっとるか」
「もちろん、この本土復帰でそのような事態を起こさないために我々『対策室』が、刑事部として通貨偽造事犯を監視・捜査いたします。そのためには内偵捜査や偽造鑑定を行える捜査員の数が必要ですが、現在の陣容では私ひとりで動くほかありません」
よく言ったものだ。警視庁への出向が終わって早々に配属された新設の「対策室」は、課長級の対策室長と捜査班長の自分、あとは事務員しか配属されないというのに。