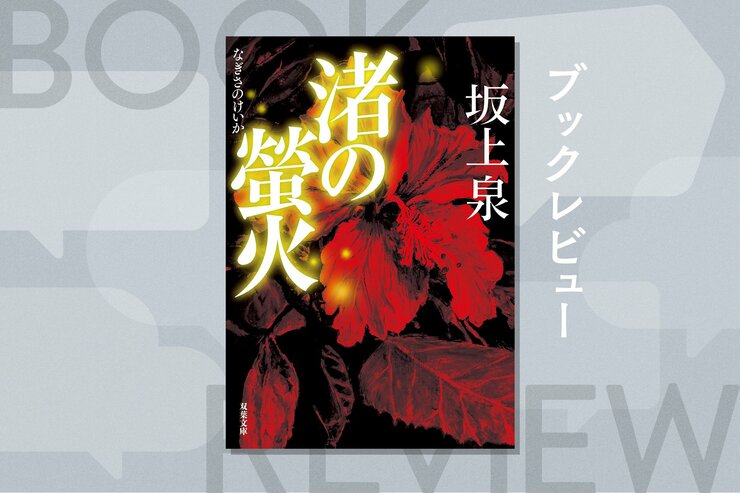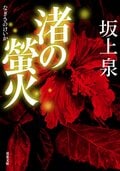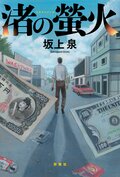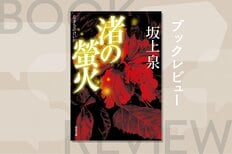沖縄の地に積み重ねられた理不尽、矛盾をサスペンス小説として描く試み──。本土復帰直前の沖縄を舞台にした警察小説『渚の螢火』の著者・坂上泉の歴史小説家としての力量を、先輩作家である谷津矢車さんが語ります。
■『渚の螢火』坂上泉 /谷津矢車 [評]
デビュー前の坂上泉さんに、一度だけお目に掛かったことがある。
歴史小説家は歴史ファンの側面を持っていることが多く、例に漏れずわたしも(不真面目な)歴史ファンなのだが、数年前、そうした縁で呼ばれた飲み会(いわゆるオフ会というやつだ)に参加した際に、ある人から坂上泉さんを紹介されたのである。当時の坂上さんは20代前半、初々しさと如才なさを兼備する好青年で、近現代史、ことに戦後史に通暁した歴史ファンだった。某戦後史重大事件について滔々と語る姿が今も脳裏に焼き付いている。
だからこそ、「坂上さんがプロを目指して小説を書いている」と風の噂に聞いたときには驚いたし、意外の感にも打たれた。あれほど史実に通じた方なら、フィクションではなく、研究やノンフィクションでこそ輝く方なのではないか、と。
……これをお読みの皆様は、さぞ笑いが止まらないことであろう。
そののち坂上さんは2019年に西南戦争の落ちこぼれ兵士たちの活躍を描く痛快時代小説「明治大阪へぼ侍 西南戦役遊撃壮兵実記」で第26回松本清張賞を受賞、同作を『へぼ侍』として改題してデビューする。続いて2020年に発表した第2作『インビジブル』で第16回直木賞ノミネート、第23回大藪春彦賞受賞、第74回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)を受賞と、小説家としてあまりにも赫々たるご活躍ぶりであることは、もはや説明を要さないところだ。
今回、縁あって、坂上さんの第3作『渚の螢火』の解説を担当することになった。まったく世の縁は奇々怪々といったところだが──数年前の不明を羞じつつ、心して書いていくことにしよう。
本作は沖縄を舞台にした警察小説である。
時は沖縄本土復帰直前、沖縄では通貨切り替えのため銀行がドルを集めていた。そんな中、銀行の現金輸送車が襲われ、回収していた百万ドルが何者かに強奪される。琉球警察の一員である真栄田はこの事件の極秘捜査を命じられ、叩き上げ警察官の与那覇らと共に犯人の行方を追うことになる。その捜査を通じ、やがて、沖縄の裏に蠢く、様々な闇に光が当たっていき……。これが本作のストーリーラインである。
本作は、第2作『インビジブル』の正統進化作と位置づけできよう。
道具立ての面での相似点を挙げていけば、過去に存在した警察組織を主体にした警察小説という共通点がある。また、エリート警察官と現地の叩き上げ警官の凸凹コンビによる捜査という枠組みにも、前作との類似点を見て取れる。
だが何よりの共通点は、匂い立つ時代描写だろう。
エンタメ時代劇の香り強い第1作『へぼ侍』とは打って変わり、戦後まもなくの大阪を舞台にした警察小説『インビジブル』は、当時の空気感や臭いまでも浮かび上がらせた時代描写が高く評価された。本作にも、この美点は大いに引き継がれている。
ストーリーに乗せて世相や事件、地域性、すなわち歴史の文脈に言及し、当時の沖縄の実情を浮き彫りにしていく。そうした歴史の文脈が、各登場人物の人物造形を支える背景として利用され、人物像を積み上げていく。かくして、時代考証、時代描写と共に各登場人物の造形が深まり、作品世界を支える屋台骨になっていく。だからこそ、坂上さんの描く登場人物には「まるで当時実際にいたかのような」説得力があるのである。ときに、こうしたやり方は、歴史小説家が歴史上の人物を造形する手つきに近似している。坂上さんは、沖縄返還を歴史として扱っているのである。ちなみにわたしは、捜査中、ハンバーガーチェーンA&Wで買ってきた飲料水、ルートビアを飲んだ時に見せた真栄田たちの反応(204頁)がお気に入りである。
一応当方は歴史小説家であるから、同業者として力説しておきたい。この操作を近現代史で行うのは、控えめに言っても難事である。近現代は史料や証言が多数残っており、全体像の把握だけでも時間が掛かる。それらを取捨選択、吟味し、物語に構築するまでに相当の苦吟があったはずだが、坂上さんはそれをさらりとこなしている(ようにみえる)。実作者の端くれとして、その積み上げに感嘆を覚えるものである。
しかし、時代描写の見事さだけに注視しては、坂上泉という作家の本質を見誤る。
前作『インビジブル』においてもそうだが、坂上作品にとって、優れた時代描写は作品を彩る要素の一つでしかないのである。
結論から申し上げよう。本作最大の魅力は、物語の趣向にこそある。
ずばり、サスペンスの味わいである。
本作のメインモチーフである現金強奪事件は、当時のレートで被害額が3億円を超えると作中で明言されることで、かの3億円事件以上の大事件であると示され、日米両政府に知られてはならない極秘任務であると設定づけられる。沖縄返還までに事件を解決に導かねばならないとタイムリミットを切られ、非正規班である“本土復帰特別対策室”がこの極秘捜査に当たることになるのである。そしてそこに真栄田が尊敬する上司玉城、高校の同級生でありながら真栄田を敵視する与那覇、持ち前の度胸で任意の聴取までこなす女性事務職員の新里、元々不良だったものの気の小さいところもある警察官比嘉といった、キャラの濃い仲間が集う。この道具立てだけでも、サスペンスの味わいを感じ取ってくださる方も多かろうが、本作はこの期待を裏切らない。詳しくはネタバレになるため詳述はしないが、本作にはサスペンスを彩る王道シーンがいくつも配されている。
また、主人公真栄田の人物像にも注目しておきたい。
真栄田は、一貫して帰る場所のない存在として造形されている。詳しくは本編に譲るが、沖縄本島出身ではなく、当時としては珍しく本土の大学を卒業して琉球警察に入ったエリートであり、また琉球警察に入ってからは警視庁に出向していた。一沖縄人としても、一警察官としても、ホームのない存在として位置づけられている。
また、妻の実家との関係についても同様だ。真栄田にとって妻の実家は安住の地ではない。妻の父の存在が真栄田の人生の指針になりはするものの、終盤に登場する義母とのやり取りを見るに、やはり、ホームではない。余談だが、20代から30代の既婚男性は、真栄田の義実家の描かれ方にリアリティを感じるのではないだろうか。
どこにも属さない主人公は、それゆえに、他人の信頼を得られない。作中前半で描かれる与那覇との対立は、真栄田の「どこにも属さない」立ち位置ゆえに生じた軋轢である。一方で、「どこかに属している」がゆえの関係性が用意されていることにも注意したい。アメリカ海兵隊で刑事事件の捜査を担当する犯罪捜査局CIDの憲兵大尉、イケザワとの関係だ。主人公真栄田を中心に「帰属」というキーワードでグラデーションを作ることで、人間関係のもつれを起こし、物語にうねりを生んでいるのである。また、真栄田のそうした複雑さは、作品全体の遠景に鎮座する本土返還直前の、冷戦下の複雑なパワーバランスの上に成り立った戦後の沖縄そのものとも相似形を描いている。
沖縄を象徴する主人公が事件の捜査に当たり、アメリカ占領下、沖縄の地に積み重ねられていった理不尽、矛盾を目の当たりにする。かくして100万ドル強奪事件の(あまりにも大きな敵と、まさかの展開を経た)解決と共に、沖縄の矛盾や真栄田の居場所についても、一定の“解決”を見るに至る。そんな物語の最高潮に沖縄返還その日をぶつけることで、本作は円環の輪を閉じるのだ。実にスマートな終盤戦である。どのように本作が締めくくられるのかを書いては興を削ぐ。読者の皆様のお楽しみに取っておくことにしよう。
坂上作品を形作るもの──それは、小説家としての高度な企みに他ならないのだ。もちろん、坂上作品の魅力に時代描写があることは否定しない。そして、時代描写の業前も作家の実力に支えられるものであると力説するにやぶさかではない。しかし、坂上泉は、若手作家離れした武器を持ちながらもそこにあぐらをかかず、物語の構築に余念のない、まこと恐ろしい小説家なのである。