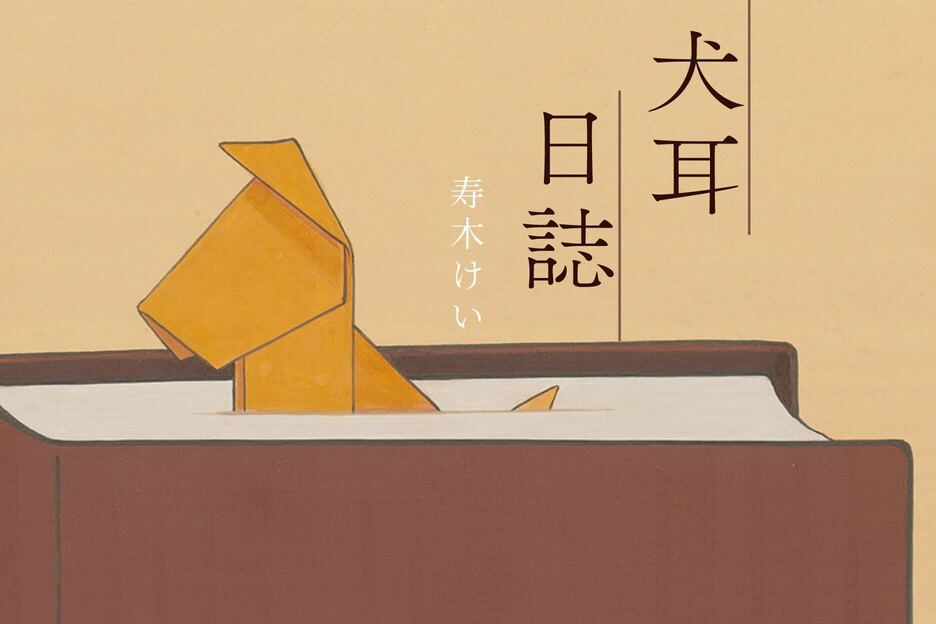誰かの叡智の言葉
年の瀬に仕事を納めたら、子供たちを連れて温泉に行くことにしている。となりの市か、そのまたとなりの市の、1時間あれば着くような近場の宿だ。
一昨年は、部屋にお風呂がついていたが温泉ではなかったし、食事は食堂でいっせいにはじまるスタイルだった。人の多さに興奮した娘が大声を出してしまい、謝りながら肩を小さくして食事をした。
そのことがあったから、昨年は温泉付きの部屋で、食事も運んできてもらえる宿を選んだ。贅沢かなと思ったけれど、払い過ぎた税金も戻ってきたことだし、たまにはいいだろう。
SNSは好きだが、旅に出ていることをリアルタイムで投稿したりはしない。
ひとつは、留守中の用心から。もうひとつは、SNSが怖いと言ったらいいだろうか。シングルペアレントがレジャーや嗜好品に興じていることを、非難めいた好奇心とともに詮索する人がいる。
加えて、私の場合は娘が障害者であることから、ものすごく不幸に暮らしていて然るべきだと思い込まれるというか、押し付けられることさえある。
お茶を出した湯呑みひとつでも、身につけているアクセサリーひとつでも、じいと見て、いい暮らしをしているのね──こういった言葉が喉元まで出そうになっているのが、瞳の奥の揺らぎや、表情筋の連動で分かる。
そうした言葉は、実生活では遠慮や良識によって隠されるが、SNSでは掻き捨てだ。開放されているDM欄には勝手にゴミを捨ててもいいと思っている人がいて、ひどい言い草をポイっと投げてゆく。決して慣れることはない。そういう人も、街ですれ違えば善人の顔をしているだろう。
家事を含む一切の煩わしいことから離れられる旅は、私にとって本当に大切な息抜きの時間である。
あと何日頑張れば──私は仕事、子供は二学期の学校生活──温泉がある。あと10日。あと3日。いよいよ明日! 子供との会話も、温泉のことばかりだ。
川添いの温泉宿の本館を抜け、渡り廊下を歩いた先の新館に、私たちの部屋はあった。
家族三人分の荷物が入ったバッグは係の人にお願いし、貴重品が入ったバッグは息子が持つ。私は娘の肩を支えながら、グズるのを励まし、手を引いて立ち上がらせる。大した距離ではないが、初めての場所での移動は骨が折れる。
部屋に着く頃には、私はすでに疲れていた。こういうとき、まるで充電式の調理家電だなと思う。1分間稼働させたら15分間休ませてくださいと取扱説明書に書いてあるあれだ。家電と違うのは、係の人がこのあとビールを運んできてくれることだ。
無事にビールを受け取り、夕食の時間を相談して、これにて解散と思ったそのとき、係の人が立ち去りがたいような感じで娘を見ているのに気がついた。
その人は、ビールのおかわりはフロントにかけてくださいと電話機を指したあと、
「ママ、がんばって」
こう言って、私ではなく、娘の頭をポンポンしたのだった。
従業員から“お客様”への接客マニュアルがあるとしたら、この態度と言葉は失格だろう。
でも、私はとてもうれしかった。皮肉や照れがない、真正面から投げかけられるようなこうした言葉の強さに打たれ、自分でも驚くほど威勢よく「はいっ!」と返事をした。
ときに名前も知らない人の叡智の言葉を頼りに、私は歩いてきたように思う。
何年か前、近所の子供同士のちょっとした喧嘩があった。ふたを開けてみれば大したことではなかった。誰の子供時代にもひとつやふたつ、あったようなことだ。
その日、仕事で遠方にいた私は、連絡を受けて車で急いで駆けつけた。それぞれの家に鍵をかけて仕舞われた子どもたちの代わりに、大人たちが集まっていた。
ある親は、仕事を口実に、子供のことは祖父母に任せていた(だから自分はあずかり知らない)という保身を口にした。またある親は、ひたすら頭を下げていた。
私は、子供たちの誰かが、たとえそれがどの子であっても、どんなにか傷ついただろう、無事にしているのだろうかと考えていた。みんな、うんと小さいのだ。
そんなとき、ただひとり、ある子供のおばあちゃんが
「運転、疲れたでしょう」
と声をかけてくれた。
そう、私はへとへとだった。現状が把握できない中で急いで帰ってきたから、おばあちゃんに声をかけられて初めて、足が震えていることに気がついたほどだった。
全身から発せられた疲れが、彼女には分かったのだろう。会話のできる人がいたことで、私は落ち着きを取り戻した。大きな事故にならなくてよかった。本当によかった。
この連載は「犬耳日誌」という題で、折に触れて見つけた言葉、心が動いた言葉について書いてきた。宇宙の出来事も、古典に出てくる台詞も、すべて、人間のすることであるかぎり、この里山と地続きである。
ある言葉に反応するということは、自分の中にその言葉がすでにあったということ。もしくは、まだ言葉にできない想いの芽のようなものが、もぞもぞと動いていて、それを言葉がひょいと掬い上げたということだ。言葉に耳を傾けることは、自分を見つめることでもあるのだ。
そうした掬い上げるような言葉を、私は誰かにかけたことがあっただろうか。そう考えていて、遠矢山房のあるお客様のことが思い浮かんだ。
最初は、当たり障りのない世間話をしていた。仕事はどうとか、週末の天気のこととか、なんとかかんとか。
何かの拍子に「(穏やかそうに見える)あなたでも怒ることがあるんですね」と笑った私に、その人は、いいえ、もっと怒ったことがあります、話してもいいですかと言った。言いながら、もう泣いていた。
容易に相槌を打てる話ではなかった。家族には決して話せないというその悲しみの出来事の、耳を塞ぎたくなるような箇所も、私はただ聞いた。
お客様を駅まで送って別れるとき、私が言えたのは、「体を大切に」だった。私よりうんと若いその人に、はんこを捺すように、目を見て伝えた。
そしてそれは、母が私に何度となくかけてくれた言葉だった。若くて健康だった私は、はいはーいと受け流していたけれど。
辛い出来事を私に話すことで、あの人が胸の奥の悔しさや怒りに言葉を与えることができたなら、それは、ともに歩んでいく力をひとつ得たことになる。そう信じているし、願っている。
「犬耳日誌」の連載をお読みくださった皆さま、1年間ありがとうございました。
加筆・再構成のうえ、2026年に単行本として刊行予定です。