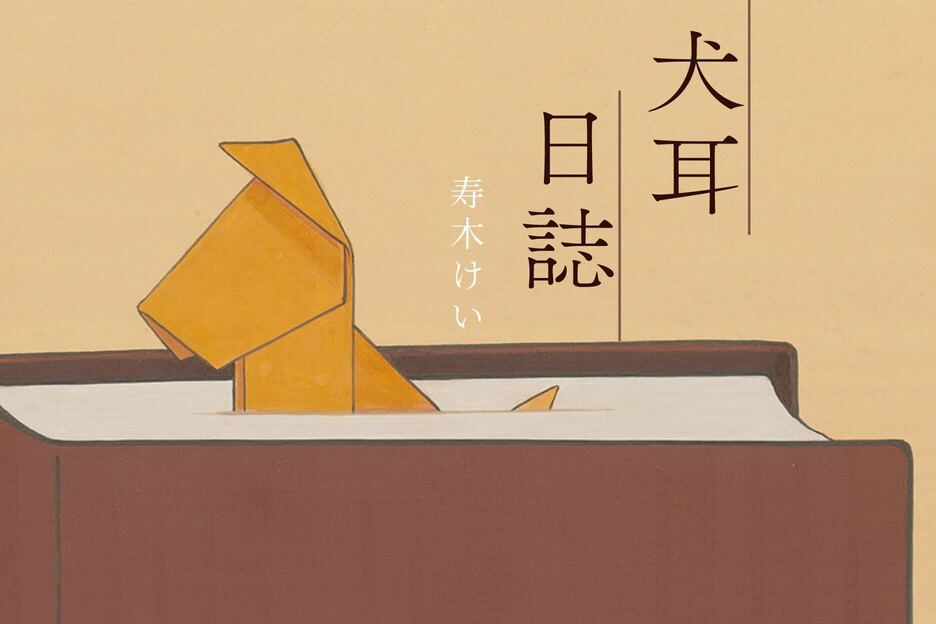日本の優しいヘンタイ
先月、富山県の新田八朗知事と北九州市の武内和久市長による寿司会談が行われた。世界初の寿司会談という触れ込みだ。
天然の生簀と呼ばれる水深1200mの富山湾に面した富山県と、かたや響灘、周防灘、関門海峡を擁する北九州市。ともに寿司は重要な観光資源であり、8月には共同でイベントも企画しているという。
お互いの寿司を持ち寄って意見交換するシーンでテレビに映し出されたのは、きときとのにぎり。おぼろ昆布を巻いて白エビをのせた軍艦に、あぁ、これぞ富山とうれしくなった。
富山で生まれ育ち、東京ではグルメ誌の編集に携わっていたこともある私なりに書くと、富山の寿司文化は鮮度がいい魚介類が手に入るがゆえに、江戸前寿司のようなさまざまな工夫を必要とせず、グルメな層からは刺身寿司などと揶揄されてきた。それでも、港から舌までの距離が短いのは強力なアドバンテージで、江戸前寿司とは違う魅力がある。
実家の近くに好きな寿司店があり、富山に帰省する際はまず予約をしてから新幹線のチケットを手配する。さまざまな地魚のにぎりと地酒をいただくのが楽しい。
北九州市ではないけれど、おとなりの佐賀・唐津への出張を打診された時には、「つく田の鮨を食べたい」と興奮し、ふたつ返事でOKしたものだ。魅力的な飲食店は人に行動を起こさせる。食は力なり。
私が山梨で紹介制の宿「遠矢山房」を始めてもうすぐ2年になる。宿とは別に、どなたでもお入りいただける季節の会を不定期で開催している。
はたしてこの里山まで来てくれる人がいるだろうかと不安な気持ちで始めた。と同時に、ひとりでも来てくださる人がいるならば、まずそこから始めるんだと腹をくくってもいた。ありがたいことに、北は岩手から南は石垣島まで、これまで多くの方が足を運んでくださっている。
しかし、夜7時を過ぎれば駅前のタクシーは仕事じまいをし、市営バスは利用者減少を理由に廃線になったこの土地で、5年後も、10年後も、この仕事を続けていけるだろうか。
そもそもが身の丈に合わない幸運の連続だった。本を出していることによる多少の知名度に加え、東京から山梨に移り住み、古民家をリノベーションして起業している物珍しさが追い風になって人を呼んでくれた。経営者としては最初の一歩を踏み出しただけ。本番はこれからだ。
明らかなのは、ひとりでは続けられないということ。縁もゆかりもない土地に移住した私には、仲間が少ない。もちろん、助けてくれる心強いスタッフはいる。家に招いて食事をする友人もできた。でも圧倒的に人手が足りない。誰とどう手をつないでいったらいいのか──生産者や食品メーカー、社員の採用、執筆とのバランスをどうするのか等々──課題がたくさんある。
と同時にそれは、しがらみとは無縁とも言い換えられる。いちからここで積み上げていったらいい。創業2年目の自分をそう励ましている。
そんな不安な気持ちをMetaのアルゴリズムが察したのか、ある講演の告知がSNSに流れてきた。
テーマは「食を主役に考えるこれからのローカリズムとツーリズム」。主催は株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ。大阪万博の食のパビリオン「EARTH MART」を手がけるコンサルティング会社だ。後援には一般財団法人地域活性化センターと、公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構が名を連ねる。
地方創生をテーマにしたプレゼンテーションで驚いたのは、「ヘンタイ」とスライドに大きく書かれていたことだった。
曰く、たったひとりの天才料理人、つまりヘンタイの料理を食べるために、遠方まで足を運ぶ人がいる。ローカリズムとツーリズムのかぎを握るのはヘンタイの集客力である、と。偉才でも逸材でもなく、変態。漢字で書けばアブノーマルだが、カタカタにすれば音だけが残り、印象が変わる。
少なくとも飲食の世界では使われてきた言葉なのかもしれない。なぜなら、既知のシェフが同業者のことを敬意をこめて「ヘンタイさん」と呼ぶのをSNSでよく目にしてきたからだ。
ヘンタイさんはたとえばこんな人たちだ。自ら銃や罠を持ち山へ入り、イノシシや鹿の命をいただく。野草を摘み、きのこを見分け、美しいひと皿に仕上げる。お店で使うお茶や発酵調味料はすべて手作り。古典を紐解き、アートへの造詣が深く、地球を守る使命に貫かれている。
シェフやレストランが発信するSNSを通して、ひと皿の裏側まで見られるようになって久しい。膨大な準備が可視化され、そこまでするのかと驚かされる。ひと昔前なら謎めいたカリスマと呼ばれたはずだが、今は手の内が明らかな「ヘンタイ」がしっくりくる。
草分けは山形「アル・ケッチァーノ」の奥田政行氏。地産地消という言葉はこの店が広めた。今ならたとえば富山「レヴォ」の谷口英司氏。余談だが、私の姉が数年前にガンで亡くなった時、どうしても行きたいという彼女の希望を叶えて家族で最後に出かけたのがこのレヴォだった。スタッフの皆様にはとてもよくしていただいた。
地方創生が抱える問題は、ヘンタイの一馬力頼みであるという点だろう。ヘンタイ未満の人々に支援金を薄く浅く注ぎ込むより、ひとりのヘンタイにドンと投入したほうが実になるという流れは考えなくてはならないが、さしあたって私にできることは、ヘンタイから吸収できるもの全てを学ぶことだ。
私は出版社勤務時代、少なくないヘンタイに取材やインタビューをした。アスリート、農家、ファッションデザイナー、医師──職業の数だけヘンタイは存在する。
この世界には銀のスプーンならぬ、大きなエンジンを搭載して生まれてきたような人たちがいる。スーパーカーでオフロードを走り続けるような人たちが。
そしてそれは、自分自身を維持して乗りこなすために、十分なメンテナンスが必要な人生でもあると思う。となりを見ても同志が誰もいないことがあるだろう。御輿に担ぎあげられ、はしごが用意されていない時だってあるのではないか。
こう書いてみたものの、ヘンタイは競争や過重労働に結びつくマッチョな響きとは一線を画している。料理の世界のヘンタイにかぎって言うなら、風土を知り、ローカルの食材を深く理解している。足元をよく見て、生産者や食品メーカーと協力関係を築き、話題を作り、その土地の文化までも耕していく。
それはまさに微生物と発酵が歩む道と同じではないか──そう閃いたのは、『発酵文化人類学』(小倉ヒラク著)を読んでいる時だった。
小倉氏は言う。無数に存在する微生物の中で、ごく稀に「人間によくなつき、良いことをしてくれる微生物」がいる。それらを発酵菌と呼び、味噌や漬けもの、ワインなどを生み出す。もちろん、そのためには人の手による工夫が不可欠だ。風土をよく理解して土と海の力を引き出す知恵が、世界中の豊かな発酵食を支えてきたし、発酵食によってローカルの魅力が再発見されてもきた。
再発見。掘り起こし。見過ごされてきた領域にイノベーションを起こしてきたのはいつもひとりのヘンタイだ。しかし、イノベーションが経済的な成長と結びつくとしたら、ヘンタイはそれを目指しているわけではないだろう。
ヘンタイが熱中する事柄は、ときに役に立たないと思われるものだ。「そこまでするのか」は「そこまでしなくても」と表裏一体。コスパタイパを重視すれば遠回りでも、彼らは手と足を動かす。それは、単に「好きだから」ではないはずだ。そうしたほうが美しいからだろう。そっちのほうが善いからだろう。その普遍性が人を惹きつける。
自分だけが有利であればいいという考えは、すぐに見透かされてしまう。彼ら彼女らが通ったあとにはぺんぺん草がちゃんと生えている。現代のヘンタイは、仲間にも地球にもとびきり優しくなければ、憧れも共感も得られないのである。