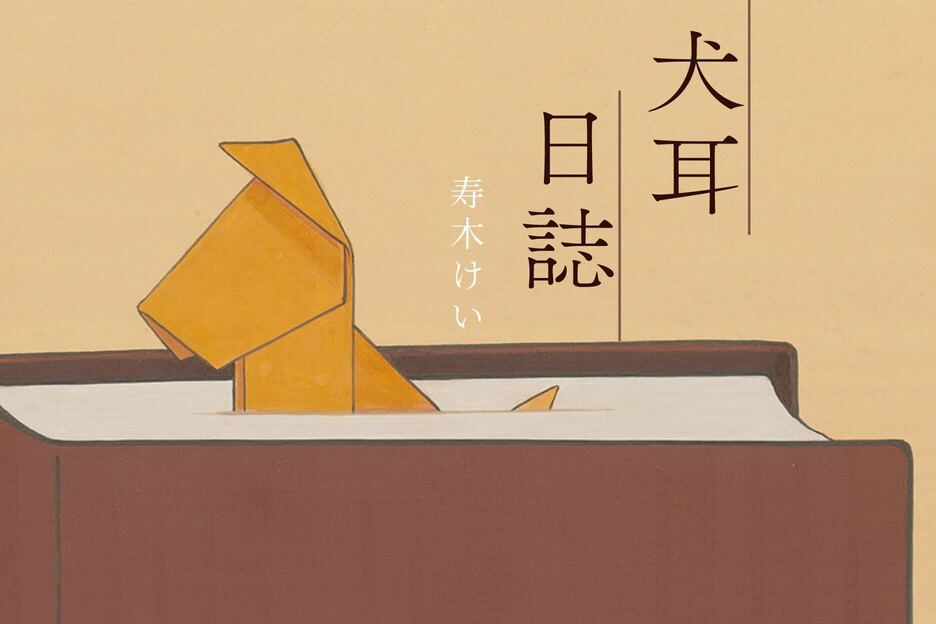専業子供のとなりの国から
私が営む遠矢山房も、人手不足である。
素直で口の堅いMさんは産休に入ったし、性格も人当たりもいいTさんには本業があって、なかなか日程が合わない。知り合いに紹介を頼んだりもしているが、見つからないまま半年近く経つ。
とは言うものの、すごく困っているわけでもない。それは、ある格言が心の支えになっているからだ。
「間違った人を雇うくらいなら、ひとりで働く」
この言葉をインスタグラムで見つけたときは、そう思っていいのだと励まされた。
しかし、こうして原稿に書こうとして、誰の言葉だったか思い出せない。カーネギー、ハイデッガー、ドラッガー──カタカナの濁音という記憶を頼りに探しても見つけられない。となると格言の信憑性も怪しくなってくるけれど、間違いなく私の生活の支えになってきたのだから、信じ込む力というのは大したものである。
人の手を借りるとき、仕事が大変だからというよりは、彩りとして居てほしい気持ちのほうが強い。ゲストに窮屈な思いをさせるのが嫌なのだ。
たとえば、私が調理をしているときは話しかけにくいだろうから、そこにスタッフがにこやかに居てくれたら、ちょっとした頼みごとだって気軽にできる。
資格や専門知識は二の次で、気立ての良さが一番大切だと私は思う。しかし、経営者仲間と話していると、きまって、そういう人こそ出会うのが難しいという結論に辿り着く。仕事は教えられても、心の性質は、指導でなんとかなるようなものではないからだ。
遠矢山房をはじめた2年前、ウェブサイトとSNSを通じてスタッフを募った。
応募者のなかには、志望動機を「簡単そうで、正直、自分にもできそう」と語った人もいたし、未経験の職種にもかかわらず一部上場企業と同水準の給料を求める人もいた。
いっぽうで、部屋と三度の食事があれば、給料はそれほど求めないという人も少なくなかった。ある人はデンマークの農園で、またある人は東北の山小屋で、住み込みで働きながら、オフシーズンは山梨に行きたいと連絡をくれた。彼ら彼女らに共通するのは、土と共に生きたいという強い思いだった。
多くの人とやりとりするうちに、思いがけず人生を覗かせてもらうような形になった。世の中には想像していたよりもずっと、多様な働き方がある。視野が狭いのは私のほうで、募集をかけておきながら、私のサポートをしてくれるアシスタントといった漠然とした人物像しか持っていなかった。
人手不足の状況が劇的に改善されることはない。そうしたなかで、住まい、食事、土の3点は、人が安心して働ける礎になるだろう。
住み込みで人を迎える──移住と子育ての渦中で、考えることすらなかったこの働き方について、最近思いを巡らせることが増えた。それは、子供たちがあと数年で成人するという現実に、ある日、はたと気がついたからだ。
もし子供が家を出れば、部屋をほかの人に使ってもらってもいい。母親として次の段階に入ったとき、私はどんな風に言葉を育てて本を書き、遠矢山房という場を温め続けていくだろうか。
そんな折、ラジオから流れてきたのが「専業子供」という言葉だった。
中国の流行語で、大学を卒業したあとに就職をせず、家事をすることで親から収入を得ている子供を指すそうだ。それにしても、うまく言い表したものだ。
同じ頃、日本では、国勢調査で「ここ1週間で少しも仕事をしなかった人」の選択肢に「家事」が入っていた。日本では愛情の延長として要求される家事に、中国では労働としての値段がついている。どちらが幸せかは、すぐに答えが出せるものではない。
家事といっても、勤め人の家庭と、商売を営む家庭では状況がまったく違う。
私の暮らしは、家事と仕事の境界がない。玄関をきれいに掃き清めることは、他の人にとっては家事でも、ここではお客様へのおもてなしに直結している。
色づいた柿の葉は、やかましく枯れ落ちる目障りなものではない。秋鮭の寿司を包めば、風情のある柿の葉寿司になり、都会からやってきた人の五感を癒やす。家の仕事を磨くことが、自分たちだけではなく、お客様の喜びへと通じているという手応えがある。
もし子供が将来遠矢山房で働きたいと言ったら、すごくうれしい。しかしその前に、子供には別の世界を見てほしいとも思う。「これしかない」と思うことと、いくつかの選択肢から親と同じ職業を選ぶのは違う。
こう書いていて、綺麗ごとを並べているとも思う。自分で決められるということは、極上の自由であり、それができない子供たちの現実の苦しさが思いやられるのである。
中国人ジャーナリストの黄 文葦によれば、中国には「神獣」「小皇帝」「巨嬰(巨大な赤子)」など、子供を指す流行語が多くある。
それが大切なものであるほど、呼び名は増えていく。
私も、子供がうんと小さかった頃は、目を離したすきに何をするか分からない大変さと、それを上回る可愛らしさから、親しみを込めて「怪獣ちゃん」などと呼んでいたことがあるが、こと中国の呼称に関しては、複雑な背景がある。
黄さんによるとそれは、無気力感と誇りと溺愛がない混ぜになった、子供へのやるせない気持ちを含んでいるという。長く続いたひとりっ子政策が落としていった影だろう。
中国では現在10才から46才の人はひとりっ子で、両親と祖父母を入れれば、最大で6人の介護がひとりの肩に乗ってくる。加えて、就職難、結婚難、低いままの出生率。こうした現実が「専業子供」を生んでいるのだから、報酬が発生するからよしとするわけにはいかない。
しかし私がもっとハッとしたのは、中国には人生赢家(人生勝者)という流行語はあっても、「その反対の負け組のような言葉は、中国語には存在しないようだ」という一文だった。勝者がいれば、相対的に敗者も存在するはずだが──。
「負け組」という流行語がないことを理由に、おとなりを見習おうと言っているのではない。
そうではなくて、土と共に生きたいと語った応募者たちの言葉が、ここで重く響いてくるような気がするのだ。
自然に囲まれて生活をしていると、この世界は人間のためだけに作られているわけではないことがよく分かる。生きることに勝負も比較もなく、土に場所を分けてもらって、ただ命を続けていくほかない。土の上で決着がつくのは相撲だけなのだ。
私にはこの場所でやりたいことがまだまだある。今はひとりで小さく遠矢山房を守っているけれど、より遠くへ、長く歩き続けようとすれば、ときにやり方を変え、チームを組んで働くこともあるだろう。
家族構成や暮らしが変わるたびに、何度でも計画を練り直して、生きることを続けていかなくてはならない。そのとき自分を支えるのは、どうなるか分からない未来にだって耐えられると信じ込む力ではないだろうか。
20年ほど前に旅をした上海で、双子の男の子に会った。坊主頭でおそろいの服を着て、人懐っこくて。それが本当に可愛くて、ご両親に頼んで一緒に写真を撮ってもらった。
彼らがひときわ目を引いたのは、珍しかったからでもある。
光の玉のような姿を見て、ああ、ふたりで生まれてきちゃったんだねと思った。それがめでたく、うれしくてたまらなかった。
アラサーになったふたりが、流行語なんて鼻で笑って、元気にしていてくれたらと願う。
参考文献
『新中国語から中国の「真実」を見る!』
黃文葦/風人社