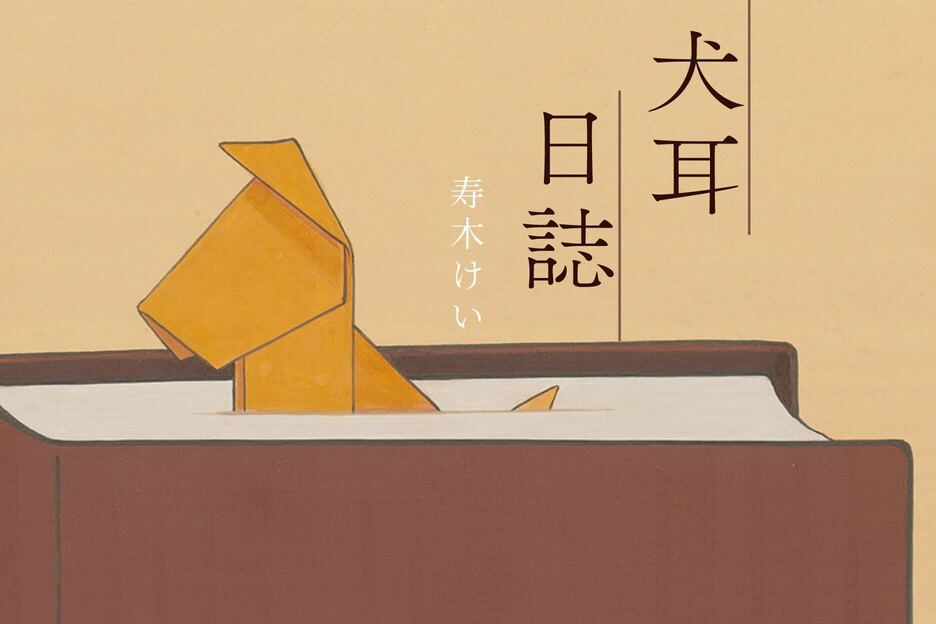No pasa nada (ノ・パサ・ナダ)
水泳選手の富田宇宙さんが朝のラジオ番組に出演されていた。2024年パリ・パラリンピック、400メートル自由形(視覚障害の部)で銅メダルを獲得したトップアスリートである。
大切な人に贈りたい言葉は? という問いかけに対して答えたのが、タイトルに挙げたNo pasa nada (ノ・パサ・ナダ)というスペイン語だ。
直訳すると「何も起きていない」といった意味で、人が失敗をした時などにかけてあげる言葉だという。最初から何も起きてないし、何のことかしら? という態度になり、富田さんの表現を借りれば、励ましであり切り替えの声がけでもある。
日本語だと「気にしないで」が近いだろうか。でもこれだと、いちどは気、つまり意識に上がっているわけで、なかったことにするのは難しい……とまあ、こんな風にいちいち考えて会話しているわけではないけれど、スペイン語の軽やかさに比べると、気という一文字が持つ奥深さを思わずにはいられない。
以前、保育園の父母会のミーティングに出席した時のことだ。
プリントアウトされた書類に誤字があった。原因も間違えた経緯も、すぐに明らかになり、私はてっきり修正して再度印刷しましょうという流れで進むのかと思ったが、事態はむしろ後退していった。
A「前任者のBさんからアドバイスをもらっていたのに、私が悪いんです、本当にすみません」
B「いえ、Aさんに任せっぱなしにしていたのは私ですから、ごめんなさい」
C「私も下書きを読んでいたのだから、気が付くべきでした」
いつまで謝罪の応酬が続くのだろうかと、私は時計を気にしながら聞き、いっぽうで、みんななんて優しいんだろうとも思った。傘をハの字に傾けて道を譲り合うような気遣いを感じたのである。
しかし、その優しさはけっして心地良いだけのものではなかった。物腰は柔らかいものの、人とミスを結びつける算盤を、それぞれの頭の中で瞬時にはじいているのだから。
ではなんのために自分の非を見せ合うのかといえば、輪を大切にしているからだろう。誰しも仲間はずれになりたくないし、仲間はずれを作りたくもないのだ。
当時働いていたベンチャー企業が謝らない社風だったことも、父母会での出来事に驚いた理由のひとつだった。大事なのは謝罪でも庇い合いでもなかった。人間は必ずミスを犯すという前提に立って、次は間違えないように仕組みのほうを変える。それをチームのメンバーにシェアし、徹底して実践させる。そこまでが仕事であり、給与査定で評価されるポイントでもあった。
必ず間違える──人間の本質に寄り添っているようでいて、それで職場の雰囲気が良かったかというとそうでもなかったのが、社会の面白さであり難しさ。ごめんなさい。いえ、こちらこそ。こうした態度が軽視される社内文化が別の部分に皺を寄せ、離職率も高かった。
では自分がミスをした際に、謝罪よりも改善策に重きを置いて乗り切れる人間かというと、まったくそんなことはない。
何年か前、ある女性から指名で依頼された仕事で不義理をしてしまった。渦中にも謝罪をしたし、落ち着いてからあらためて手紙を書いたりもした。
その方が新しくビジネスを始めたと聞けば、さすがだと思ういっぽうで、私がちゃんと協力できてさえいればストレスを与えることもなかっただろうとウジウジしている時期も長かった。
そんなこんなで1年ほど経っただろうか、久しぶりにやりとりをする機会に恵まれた時のこと。「その節はすみませんでした」と切り出した私に、彼女はこうきっぱりと言ったのだった。
「記憶を上書きしてください。切り替えましょう」
冷たい水を浴びせられるというのはこのことだ。
謝り続けるというのは、結局、自分がかわいいのである。安心して座る場所欲しさに、言い訳の座布団を手放さない。相手はとっくに水に流してくれているというのに、後ろめたさの片棒を相手に担がせるような子供じみた態度を取ったことが、いま思い出しても恥ずかしい。
気にしてしまう性分は仕方がないとしても、上書きしたり切り替えたりすることなら、作法として努力できるかもしれない。努力したい。彼女の態度はそれを教えてくれたのである。
切り替えて。この言葉をまさか私が使うことになろうとは、思ってもみなかった。
若いスタッフのひとりが、調理中にミスをした。その人もやはり、保育園での出来事と同じように紐付け作業を瞬時に済ませ、いかに自分のせいであるか説明した。ひどく落ち込んでいるその様子を、可哀想にも思った。
私は私で、時間をかけて準備してきたものが壊れた形になり、ひいてはそれが遠矢山房のお客様に迷惑をかけることに少なからずショックを受けた。
しかし、誰が悪いのかなんてどうでも良かった。考えるんだ、考えるんだ、と自分に言い聞かせ、
「間違いにしなきゃいいじゃん」
野菜を刻みながら、この台詞がポンっと出た。
結果、機転を利かせてその場を乗り切ることができた。アイディアがひらめくまでの時間は、ほんの数分だったように思う。そして、軽く手を打って「切り替えよう」と宣言したのだった。場の雰囲気を変えたい時や、自分に気合いを入れたい時、私はこうしてよく手を鳴らす。スタッフも、何かにパチンと弾かれたように目の輝きが変わった。
しかし翌日、スタッフはまだ申し訳なさそうにしていて、開口一番、昨日の話を始めた。でなければ身の置きどころがないと感じたのだろう。
しかし私は振り返りのムードには乗らなかった。協力して挽回できたし、お客様の満足にもつながった。だからそもそもミスじゃないという風に話を持っていった。
何のことだっけ? まさにノ・パサ・ナダの精神が私の中にも芽生えていたのである。
気にすらしなくていいよと人に声をかけるいっぽうで、絶対に気にし続けて欲しいと願うこともある。
Xでこんな投稿がふと目に留まった。
「気をつけてね」と言って送り出すと、交通事故に遭う確率が7%減るというものだ。この原稿を書くためにソースを探したが見つけられなかったので、作り話かもしれない。そもそも事故にあった人が出発前にどんな言葉をかけられたか(かけられていないか)を追跡することは不可能だから、この手の話の真偽は推して知るべし。
しかし私は、きっと事故に遭わないと信じて「気をつけてね」と子供たちに声をかけてきた。言い忘れたら、遠くなる背中に向かって声を張り上げてきた。だからこそ、その祈りを汲み取ってくれたような投稿に惹かれたのだ。
お客様に対しては、さらに火打石が加わる。遠方から山梨まで長い旅をしてきてくださる方もいるから、言葉だけでは足りない気がする。言霊と火がその人を包む結界となり、無事に家まで送り届けてくれるよう託すのだ。
こうして日々立ち働くキッチンに、ホワイトボードがある。10年以上続けている習慣で、裏がマグネットになったものを冷蔵庫に貼り、思いついたことや買い物リストなどをメモしてきた。
その隅っこに、いまもノ・パサ・ナダを残してある。ラジオで聞いてすぐに書いておいたのだ。書くことで、まず手でなぞり、目で見て、脳に電気刺激が伝わる。そして、通りかかるたびに視界に入り、何度も意識する。
こうして心身に刻み込まれた言葉が、思いがけない時に背中を押してくれる。誰かと暮らしたり働いたりしているかぎり、自分にも、相手にも、声をかけ続けることに横着してはならない。ストックした言葉の中から、ふさわしいものを違わずに取り出し、互いの内面を見せ合わなくてはならないのである。