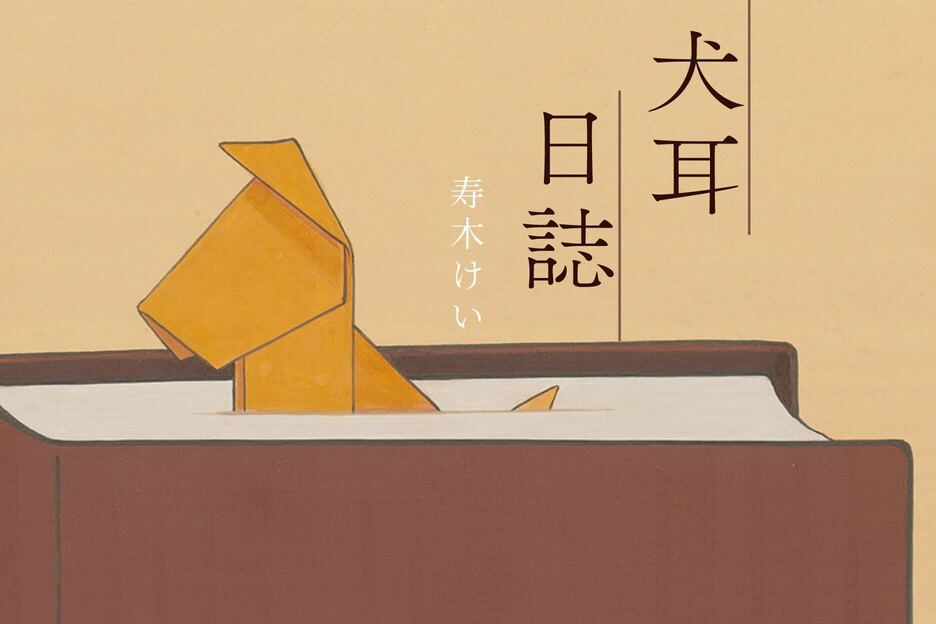幸せな人
正月に帰省した富山で「辻占」という懐かしい文字を見た。スーパーの入口に並べられた、辻占の菓子。切手大のおみくじを米粉の皮に隠して突羽根型にととのえた、北陸の縁起物である。フォーチュンクッキーのようなものと書いたほうが分かりやすいかもしれない。
子供と三人で好きな色を選び、せーのでおみくじを見せ合う。
「渡る世間におにはない」「思いがとどく」「出世が早い」
三つをつなげると文章になり、ケラケラ笑った。出世なんて字を子供が引くのもおもしろい。
友人のぶんもお土産に買って帰った。友人は夫婦で商売をしている。運だめしに引いてみたところ、
「おまえとならば」「今年は豊年万作」
これ以上ない組み合わせが出たと喜んで、わざわざ写真に撮って送ってくれた。
読んで遊ぶ占いだが、元々は聞く占いだった。
古代、辻は神霊が通る場所とされ、夕刻に辻を行き交う人々の言葉に吉凶を託す辻占が盛んに行われた。今よりうんと暗い夕暮れに、風に運ばれて偶然耳にする言葉にはどれほど霊力があっただろう。現代に残ったのは辻占という名前だけだが、由来も含めて子供に伝えていきたい遊びである。
辻。四つ角、もしくは十字路。
調子がよくない時、急いでも急いでもまた同じ四つ角に戻ってきてしまう夢を見る。夢の中では高校生で、受験会場に向かっている。よく知っているはずの景色が、未知の場所に見えるおそろしさ。どこにも辿り着けない焦り。目覚めてもしばらくは胸の奥が重い。
一本道であれば、迷うことも、思いがけず誰かと出くわすこともない。もしあの時あの角を反対に曲がっていたら──ifから始まる物語は、古今東西の色褪せないテーマである。
その富山では実家には泊まらず近くのホテルを取った。病気の家族がいるし、冬のウイルスも流行っている。同じ空間で過ごすリスクを少しでも減らしたのだ。
子供が眠ってしまい、持ってきた文庫本を手に取ろうとして、ふと、ホテルの社長の自叙伝がサイドテーブルに置かれているのに気がついた。
地方都市で生まれた女の子が、不動産業を営む夫と結婚し、やがてホテルチェーンの社長になる。さまざまな試練を乗り越えてきた姿に引き込まれた。
夏の麦茶のようにごくごく読み進めていたその時、ある一文で視線が止まってしまった。
「念のため男の子をふたり生んでほしい」
商売をしているからという理由で、彼女は夫からこう告げられたのだった。思わず奥付にある出版年月を見る。2017年。ひと昔前。
言い付け通り、彼女は男の子をふたり生んだ。今では彼らも結婚し、一族は同じ屋根の下で暮らして、家業の発展に一丸となって突き進んでいる、ああ、なんという幸せよ、この世の春よ──幸せを振りまく一代記とともに新年が始まった。
私が編集者だったら、先の一文は削除することを提案しただろう。書かなくとも仕事への情熱は十分伝わる。何より、息子さんが読んだらどんな気持ちになるだろうと不安になったのだ。
イギリス・チャールズ国王の次男ヘンリー王子の回顧録『スペア』(2023年)を、私は思い出していた。兄であるウイリアム王子の“もしものとき用”だという彼の苦しみは、異国の庶民にはとうてい想像できるものではない。
日本でも昭和天皇と初代宮内庁長官・田島道治の会話を記した『昭和天皇拝謁記』の中にこんなシーンがある。田島が天皇に向かって、(あなたは惣領であるが)二男、三男は「ひやめし」だと軽口を叩くのだ。生まれ順にまつわる発言はこれ以外にもたくさん出てくる。
イギリスからは2020年に、日本からは2021年に、パートナーとともに国外に移住する例が続いたのは偶然だろうか。
隣りで眠る子供を見る。決して念のために生んだわけではない。否定してみたものの、本当にそうだろうかとも思う。ホテル経営者の夫妻には男の子がふたりいて、私には女の子と男の子がひとりずつ。それだけのことだ。それが大きな違いなのか、あるとしたらどんな違いなのか、うまく説明できない。
私は11年前に長女を、その翌年に長男を生んだ。長男が生まれたとき、「でかした!」という義父の歓声とともに金一封を渡された。娘に先天性の障害があったこともあり、長女へのよそよそしい態度と、長男への肩入れの差は堪えた。
また別のある日、親族の女性が息子を見てこう涙ぐんだ。
「福祉の道へ進むもんね。お姉ちゃんの面倒を看てね」
まだ3歳にもなっていなかった息子の肩を抱き、私はその人から離れた。生き方を押し付けられることから息子を守らなければならないと感じた初めての出来事だった。
かく言う私は五人姉妹の五女である。家を継ぐ重みとは縁がなく、スペアのそのまたスペアのスペアだという意識もなければ、生まれてきた意味を問うこともないまま来た。
しかし、娘はなぜ障害を持って生まれたのかと考えたことなら何度もある。答えらしいものを求めて、遺伝や染色体にまつわる本ばかり読んでいた時期もある。もし私が働き過ぎないで体を大切にしていたら。もしもっと若い頃に生んでいたら──考えたところで答えなどない。生まれたからには、ただ生きることを続けるのだ。生物は揺らいでいる。天と地の間を。そして、生と死の間を。あの夫婦と自分に大差はないかもしれないと書いたのはそういうことだ。
山梨に戻ってきてから訪れた図書館で、瀬戸内晴美の『幸福』という随筆集を見つけた。幸せとされるものに背を向けてきた人だと思っていたから、こんな題の本があることが意外だった。
幸福と題された一編は、読みはじめてすぐに出てきた。
ある女性が晴美に会いにくる。有名な財界人の妻で、愛人に妻の座を譲り、自分は出家をしたいと考えている。つきましては先に出家したあなたに色々聞きたいことがある、と。
そう言っておきながらちっとも話さずただ微笑んでいる女性に、晴美はいい印象を持たず、一刻も早くこの時間が終わってくれることを祈るのだが、ふと、ご家族は出家についてどう考えているのか興味を持つ。
女性は答える。夫も娘も出家を喜んでくれている、すべてがうまく行って、完璧で、幸せで──何重もの幸せの押し付けを、晴美は蜘蛛の巣のようにうっとおしいと思うのだった。
後日、女性の得度式が済んだことを新聞で知る。そこには剃髪した姿とともに、記者に語った出家の動機が書かれていた。
彼女の話はこうだ。京都の寺で高名な僧侶に会った。何やらブツブツ言いながら庭を掃く姿を見て、お経を唱えているのだろうと思ったが、近づいてみると違った。
「幸福だ……幸福だ……」
僧侶はこう繰り返していた。その言葉に打たれ、女性は出家を決める。
この記事を読んで初めて、晴美は自分と彼女の間にある深い溝の正体が分かったのである。
私が社長の自叙伝の一文に違和感を持ったのは、出生と性という神の領域にまで踏み込んで、強運を歌いあげていたからだった。ああ、幸せ、ああ、強運と唱えることで、一族とその事業は宗教色を帯び、彼女を神格化しているように思える。
実は日本の辻占菓子がフォーチュンクッキーの起源になっていることはあまり知られていない。そのクッキーに、AKB48が「占ってよ」と呼びかけて大ヒットしたのは12年前のこと。
彼女たちはこうも歌っている。ツキを呼ぶには笑顔を見せることだ、と。辻占のおみくじも、笑うことで運気を引き寄せる。幸せは先払いなのだ。
しかし、つるんとして前を向いていられる日ばかりではない。
たとえば明石の君のように。光源氏との間にもうけた娘を手放し、失意の底に沈むも、その娘は東宮の后となって男の子を生む。明石の一族の繁栄は決定的なものとなり、明石の君も陽の当たる老後を迎える。
不本意な道を選ばざるをえなかった境遇に、人々は自分の身を重ね合わせた。だからこそ、最後に辻褄が合った締めくくりの見事さを「幸い人」と呼んで慕ったのである。
参考資料
『辻占の文化史』中町泰子 ミネルヴァ書房
『昭和天皇拝謁記』(1) 田島道治著、古川隆久、茶谷誠一、冨永望、瀬畑源、河西秀哉、舟橋正真編/協力 NHK 岩波書店