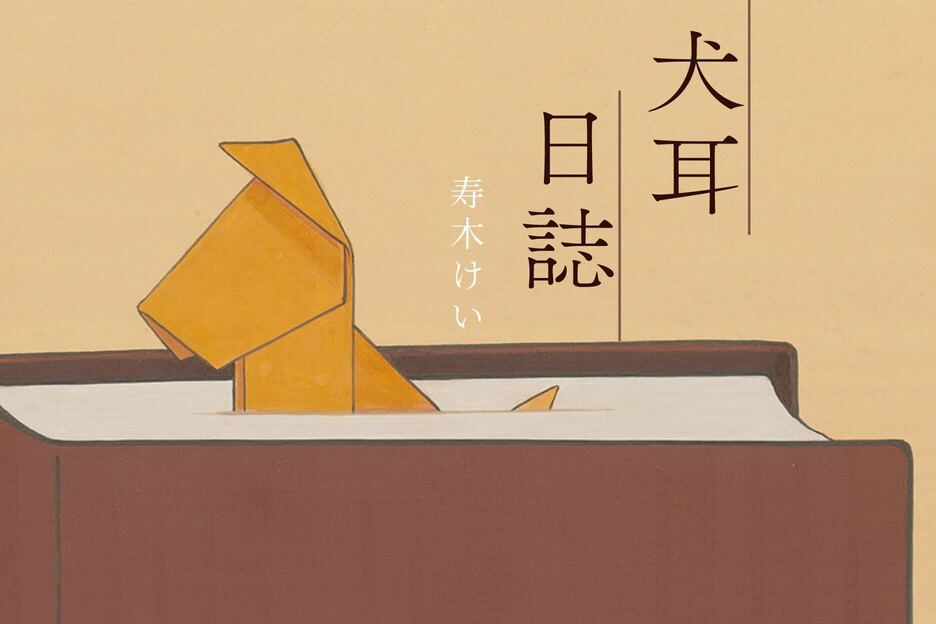犬が教えてくれること
この家が竣工してから2年になる。18か月にわたる改修工事を終えた引き渡しの日、南アルプスにある犬舎から甲斐犬の赤ちゃんが生まれたと連絡が入った。それから56日後、8月生まれの男の子、ブンが家族に加わった。
一緒に暮らしてしばらく経った頃、久しぶりに会った友人が、こんな風に言った。
「シングルマザーでただでさえ大変だろうに、犬、それも甲斐犬を飼うなんて、大丈夫かなって、心配してたよ」
そして、元気そうでなにより、と付け加えた。
気にかけてくれていたことがうれしく、そして、それは逆なんだよと思った。
大変だからこそ、犬と暮らすのだ。先回りしてドアを閉めるのではなく、人生の喜びのために、なんとか場所をあけるような生き方がいい。犬という存在にはそれだけの力があるのだから。
私は幼い頃にチャッピーという犬を飼っていた。柴犬と他の犬種との間に生まれた茶色の女の子で、叔父の家からもらってきたのだった。
あとから母に聞いたことだが、年の離れた姉たちが成長して家を出て、母も働き詰めだったから、鍵っ子でも寂しくないようにと、友達として迎えられたのがチャッピーだった。
放課後も休日も、しょっちゅう一緒にいた。稲刈りが終わったあとの田んぼで、新雪の上で、裏庭の鉄棒の前で、チャッピーと遊んでいる写真がたくさんある。私が大学進学のために上京した2年目の夏まで、チャッピーは13年間生きた。
最期は待っていてはくれなかった。大学の夏休みで帰省する2日前に荼毘に付されていたことを、火葬費用の領収書を見て知った。
以来、犬と暮らすことは考えなかった。
それでも、ドッグランを通りかかれば、よその犬の元気な姿をお裾分けしてもらっていたし、近所のマンションのベランダから柴犬が顔を出すのを知っていて、遠回りして通勤していた。善い顔をしている子で、こっそり撮ってスマホの待受にしていたこともある。いずれにしても、犬は遠くから眺める存在だった。
それが、山梨に古民家を買ってリノベーションの計画が始まったあたりから、犬が恋しくなった。広い庭のある家と、のどかな里山の環境が後押しした。しっかり散歩に連れて行ける脚力を考えると、決断は早ければ早いほどいい。
山梨で暮らすのだから、甲斐犬を飼ってみたい。古来からこの地で暮らしてきた彼らはどんな性質を持っているのか、近くで触れてみたいと思った。
ネットで見つけた犬舎に電話をしてみると、「いちどお子さんを連れてどうぞ。顔を見るだけでも」と声をかけてくださり、ならばと、すぐに遊びに行ってみた。
第一印象は、シュッとしてかっこいい。警戒心が強く、見知らぬ人間に吠える以外は、物静か。のちにブンの両親となる甲斐犬たちに会うこともできたし、何より、子供たちが怖がらなかったのがうれしかった。
甲斐犬には分かりやすい愛嬌はないが、甲斐主──甲斐犬の飼い主はこう自称するのが好きだ──である私には全身全霊で甘えてくる。朝起きて土間に向かうと、もうお腹を見せて、撫でられるのを待っている。外出先から帰宅した時には、私の顔を舐めてから、体を私にギュッと押し付けてくる。しかし表情はスンっとして、静かなものである。凶暴なイメージとは程遠く、むしろ臆病で心優しくさえある。
しかし、冒頭の友人をはじめ、よく知らない人にとっては運動量も多く飼うのが大変だというイメージがあるようだ。それはオオカミの面影を残す風貌と、狩猟に連れて行かれる犬だという認識から来ているのだろう。
ブンを連れて歩くと、怖い怖いと言って笑いながら避ける仕草をするおじいちゃんもいれば、「わたし、甲斐犬嫌いなのよ、ほら、また吠えた!」と言いながらズンズン近づいてくるおばあちゃんもいる。
かわいい、初めて見たと言って撫でてくれるのは、たいてい中学生くらいまでの子供たち。ブンは微動だにせずされるがままになっているが、尻尾が嬉しそうである。
たまに何人かで集まった時に、どんな犬が好きか、これまでどんな犬を飼ったことがあるかという話題になる。そういう時、私は賢さを競うのは苦手だ。犬界で一番賢いのは⚪︎⚪︎だとか、いや、⚪︎⚪︎のほうが賢いとか。
賢くなくたっていい。犬と暮らすということは、ただ、喜びと一緒に暮らすということである。子供たちに対しても、私はそう思う。
犬は1万5000年前から人間の近くで暮らしてきた。犬が愛されてきた理由はその視線にあるという、動物行動学の研究者・永澤美保さんの言葉を、ある日の朝刊に見つけた。
犬が飼い主を見つめ、飼い主がリアクションすることで、互いに愛情や信頼関係に影響するホルモン「オキシトシン」の濃度が上がるそうだ。子供の頃に遠足で行った動物園の猿山では、視線を合わせないように注意されたものだが、犬は違う。
犬の祖先はオオカミで、本来とても怖がりで人間社会には近づかなかった。以下、永澤さんの考察と表現を借りれば、その中に好奇心旺盛な変わった犬がいて、奇跡的に人の集団に辿り着き、殺されずに済んだ。人に伝わるシグナルを獲得した犬が生き残り、さらに、狩猟や番犬としての役割など、互いにメリットがあり、共生するようになった──と。
ブンがうんと小さかった頃のこと。日中外で過ごすための小屋を作ってやろうと思い立ち、たまたま手に入ったワインの樽のてっぺんをくり抜いて、寝かせて設置してやった。洞穴のようできっと落ち着くだろうと思ったが、結局一度しか入ってくれなかった。
同じくワイン樽を住まいにして、私利私欲を断ち、自由で自足的な生活を目指した哲学者ディオゲネスは犬儒学派と呼ばれるが、本物の犬は樽に入ることをよしとしないのである。
甲斐の犬はやっぱり土の上で寝そべっているのが好きだ。器用に自分の体の大きさに合わせた凹みを掘り、丸く収まって過ごしている。夏は涼しく、冬は暖かく、気持ちよさそうにしている。
ワインの樽は今、土間玄関で小物置きになっている。
玄関つながりで言えば、私の家にはインターフォンがない。家で仕事をすることが多いから、集中力を邪魔してくるあの電子音が苦手で、設置しなかった。
その代わりに、骨董店で見つけた鐘に黒檀の支木を添えて、カンカンと鳴らせるようにしてある。決して大きな音ではないが、澄んだ金属の音色がよく響く。
しかし、ブンが来てからはこの鐘すら必要なくなった。声色や吠え方で人間のタイプを教えてくれるからである。
朝刊の配達の方にはもう吠えなくなったのに、同じく毎日来てくれる郵便配達の人には変わらずに吠える。バイクの音に続いて、ウォンウォンウォンとけたたましく吠えるので、すぐにそれと分かる。
威嚇するように低く唸るのは、近所の猫が目の前を横切っている時。息子が帰ってくれば、鼻をくぅんくぅんと鳴らして遊びに誘う。そのほかの知らない人には、短く何度か吠える。「おい待て、誰だ」である。そして、必ず私にちらちらと視線を送って、異変を知らせようとしてくる。
裏の家でも犬を飼っている。アメリカから連れて帰ってきた子で、小さい体でブンより吠える。そのたびに、
「Shut up!」
聞いているこちらまで縮みあがる迫力で、飼い主の声が飛んでくる。
人の振り見てなんとやらで、私はブンをそんな風に叱りはしない。
「分かったよ、教えてくれてありがとう、もう吠えなくていいよ」
こう言って、お座りを命じて静かにさせる。
犬は吠えるのには理由がある。これは子育てにも通じること。子供が大人に対してすることには全部内情がある。大切なことを、こうして犬にも教わっているのである。