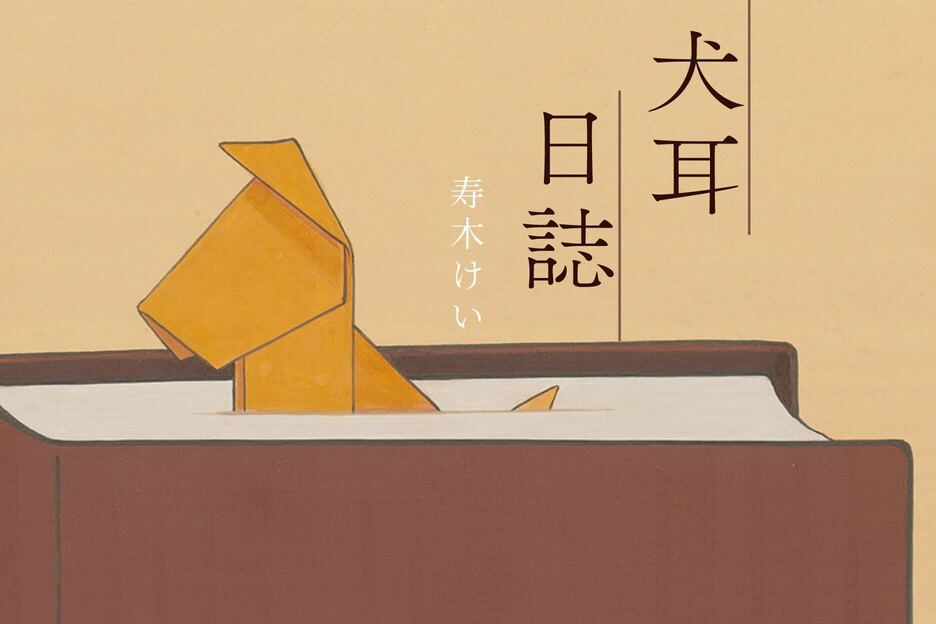大きな朝食
そのラジオパーソナリティが「とうとい」と言うのは、おそらく二度めだった。
一度めはうまく聞き取れず、今なんて言ったのと思っているうちに番組が終わってしまったが、次は違った。
「ご飯派もパン派も、どっちの選択も、とうといものですよね」
朝食に関する話題の中で、こう言ってコーナーを締めくくったのだった。
尊い。ずいぶんカジュアルな使い方だと思ったけれど、考えてみれば別におかしなことではない。尊重と書くくらいだから、否定せずに受け入れる場面で用いるのは正しい。それに、「推しが尊い」という、とっくに市民権を得た表現もあるではないか。ナイスで最高で、大事で愛しい。そうした好ましいもの対して「尊い」は使われ、その濃淡は前後の文脈や語り手のキャラクターから感じ取ればいいのだろう。
そもそも私が集中してラジオを聞いていたのは、ちょうどその頃、宿で出す朝食のメニューに悩んでいたからだった。さまざまな投稿が読み上げられるのを聞き、ご飯もしくはパンの選択ひとつにそれほどまで確固たる理由や嗜好があるのかと笑い、唸った。
私は山梨で紹介制の小さな宿を営んでいる。
チェックインの際には、季節の菓子を作り薄茶を点てる。夜は十皿ほどのコースに山梨のワインを合わせてお出しする。お帰りの際には、庭にあるもの(春の山椒やよもぎに始まり、夏の梅やみょうが、秋の柿、冬の柚子など)を収穫して持ち帰っていただく。小さな宿と言ったのは部屋数を指してのことで、食べることを楽しむ心意気は大きくあれと願い、建物を飛び出して庭にまで及ぶ。
この原稿を書いている4月下旬に収穫するものといえば、まず竹の子。掘ってすぐ茹でてから昆布締めにしたものを、コースの一品目にお出しする。
次に、どこを見ても野草がある。今年は初めて薬草茶を作ってみた。タンポポ、よもぎ、スギナ、ぺんぺん草(春の七草のなずな)、カラスノエンドウを干して水から煮出せば、草の持つ複雑な味わいに驚かされる。
料理にも野草を使う。ぺんぺん草と昆布で取った出汁に塩で味をつけ、グリーンピースを浸した翡翠豆を、この春は何度も作った。
主菜は土鍋で作るすき焼きだ。温まった鍋肌に牛肉を広げ、砂糖と醤油をふり入れて焼く。そこへ、摘んできたばかりの花山椒をじゃんじゃん散らす。甘辛く柔らかい肉と、山椒の涼しい香味。数日間だけ味わうことができるごちそうだ。
鍋肌に残った旨味を逃さぬよう、締めの食事には土鍋にたっぷり湯を沸かし、手打ちのほうとうを茹でる。竹の子とこごみのかき揚げを添えた、天ぷらほうとうである。
ここまで書いて、定番の竹の子ご飯が出てこないぞと思われたのではないだろうか。
竹の子を掘ってすぐに調理できる環境にいるのだから、竹の子ご飯は翌日の朝食のために取ってある。センターのご飯が決まれば、おかずも自ずと定まってくる。庭で採れたふきで作っておいたふき味噌や、ふきと油揚げの煮物、よもぎのきんぴら。子供と一緒に育てた椎茸は味噌汁に。花わさびやごぼうなど、直売所で目が合った食材もふんだんに並べて──こんな風に挙げていくと、迷いなく献立を組み立てきたように思われるかもしれないが、開業以来、こと朝食に関しては試行錯誤を繰り返してきた。
2023年の冬に開業したばかりの頃は、パンと洋食を出していた。和食の夕食とはあえて違ったものにしようと考えてのことだった。
パンに取り合わせたのは、ひとりぶんサイズの蒸篭。さまざまな野菜やきのこ、ハム、ときに手作りのツナなんかもぎゅうぎゅうに詰めて蒸し、作りたてのマヨネーズを添えて出していた。生クリームが入ったオムレツも欠かさない。朝の調理場が湯気で満たされる光景は、自分自身のウォーミングアップのようで、働く楽しさを実感できるひとときだった。
しかし、季節が進み、気温も湿度も上昇するにつれて、蒸篭が暑苦しい気がしてきた。
その頃、自分のために作る朝食と言えば、麦茶で炊く茶粥だった。ふと、これをゲストにもお出ししてみようと思い、器によそって氷を浮かべたら、思いのほか喜ばれた。夏の野菜の揚げ浸しや、私が漬けた梅干しなんかとも相性がいい。
それでも往生際悪く蒸篭を捨てきれない私は、朝食を2つ準備するようになる。夕飯の終盤で「明日の朝はパンとご飯、どちらになさいますか」とゲストに選んでもらうようにして、それが心尽くしとさえ思った。
ちなみに、何組かのゲストに聞いてみてはっきりしたことには、全員が迷わずご飯、つまり和食を選んだ。選ばれなかったパンやハムは、その日の賄いもしくは家族の夕食になった。
選べるということは、本当に贅沢なことなのだろうか。
昔働いていた会社で、期間限定のカフェをプロデュースした時のことだ。某有名店のナポリタンと、某有名店のカレーが並ぶのが売りのひとつで、私は両方を食べたい人のために、ナポリタン半分とカレー半分のセットメニューを作ろうと提案した。人気メニューがいちどに割安で味見できる名案と思ったが、先輩からは反対された。
曰く、一人前の量を食べきることでしか得られない満足感がある。量が半端なら、味わいも半端。
「結局、満足も中途半端になっちゃう」
先輩は迷わず言った。
今はなるほどそうだなと分かる。AもBも尊いという態度では、しっかり届かない。
宿の話に戻そう。現在、朝食はひとつである。それも、パンかご飯かと話を狭くするのではなく、旬の食材が生きる献立を私が決めて、提案する。
わざわざこの宿を選んで来てくださるということは、私が薦めるものを受け入れる用意があるということ。肝が据わっているのはむしろお客様で、宿主のほうが及び腰で二択に逃げこんでいたのだ。
朝食はチェックアウトの直前に食べるものゆえ記憶に残りやすい。だからこそ最後まで神経が行き届いた、わくわくするものをお出ししたいと思う。
それにはやはり、自然に聞くのが一番である。どんな食材が手に入り、それを生かすにはどう手を動かしたらいいかを考える。いや、頭で考えちゃいけない。こねくり回さずに、食材に触れれば、何を作るかが自ずと見えてくる。
思えば、ゲストに朝食を選んでもらっていた頃、ご飯、つまり和食の献立を説明する時の私は、食材や調理法について熱心に説明していた。その熱に引っ張られ、みなさんがご飯を選択したのは当然のこと。答えは私の中にすでにあったのだ。そんなことも分からないまま、手探りで宿を始めた。
ここ山梨の里山の恵みを生かそうと思う時、それはやはり、食べ慣れた、そして作り慣れた和食ということに落ち着く。
最も尊いのは自然そのもので、人間の手も、舌も、旬に付き従って恵みを分けてもらうのみ。それこそが、日常を抜け出して旅をすることの醍醐味である。