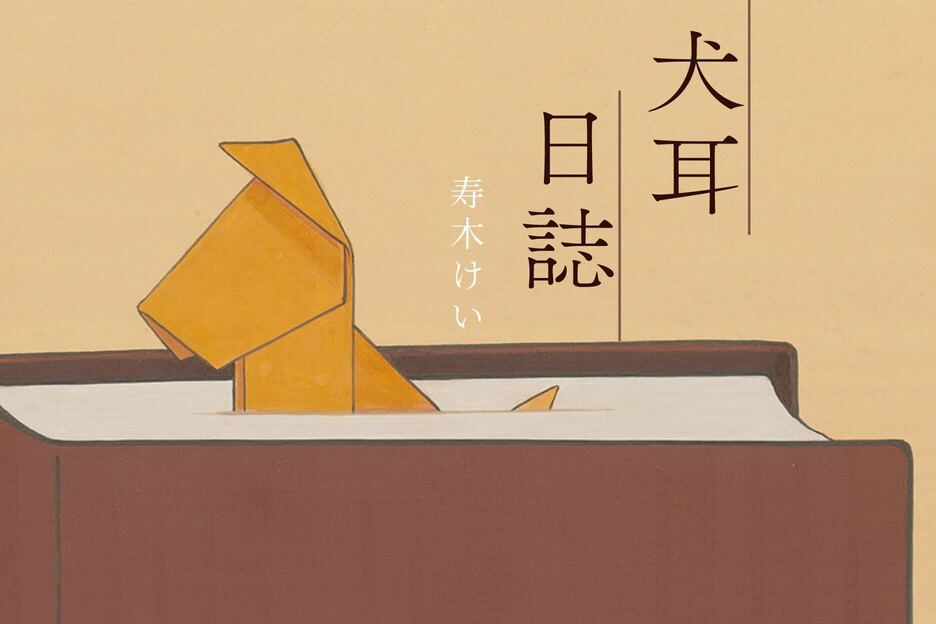私たちの好きな味
東京にいることを実感するのは、相席で食事をしているときである。
師走の蕎麦屋となればなおさらで、疲れた顔や、それでいて充実したような、味のある顔が並び、そうした場に紛れ込んでいると、かえって気持ちが穏やかに澄んでいく。
人間より果樹が圧倒的に多いこの里山で、知らない人と同じテーブルにつく機会はほとんどない。一期一会の精神を学ぶ場といえば、茶道の稽古くらいである。
その日は、子供たちを送り出したあと、9時台の特急で東京へ向かった。荏原畠山美術館で展示中だった杉本博司氏のコレクションを見るためである。
一級の美術品を見続けるには体力がいる。気が付けばおやつの時間に近くなり、足がずしんと重くなって空腹を思い出した。
行く店なら決めてあった。美術館から徒歩15分。白金にある蕎麦屋で、編集者として働いていた頃によく通った店である。
入店待ちの列に並ぶことすら懐かしい。暖簾をくぐって出てくる人がいて、それと同じか、やや少ない人数が暖簾をくぐって入る。この繰り返しだ。
そんなに長く待たずに、前に並んでいた男女と同時に入るよう案内された。
「一番奥、相席でお願いしまーす」
4人がけのテーブルにふたりが並んで座り、私は男性の向かいに座る形になった。
双方がお品書きを手に取ったそのとき、男性が「おトイレ」と言った。消えそうな声だ。
女性は、どうして今言うのよ、座る前にしてよと唇を歪め、不機嫌を隠そうともしなかった。男性には障害があり、立ち上がるのも段差を越えるのも、彼女のサポートが必要なのだ。
人にはその人にしか言い出せないタイミングがあることを、私は子供を育てるなかで知った。楽しみが中断されたり、計画が変更になることなど当たり前。それが生理現象のせいなら、叱っても仕方がない。
目の前の男女をいつでも助けられるように、私は軽く腰を浮かすような心持ちでいた。たとえばそれは、男性がテーブルに手をついて移動しやすいようにスマホをどかしておくとか、もし足に男性の杖がぶつかってしまっても、いいんですよ全然気にしませんというジェスチャーをすぐに示せるようにといったことだ。
しかし、険悪なムードは長くは続かなかった。
無事に席に戻ってきてすぐ、だし巻き玉子が運ばれてきた。
女性が小皿に器用に取り分け、ふたりして無言で食べていたかと思うと、
「私たちの好きな味」
彼女がふふふと内緒話をするような感じで言った。
うん、うん、と首だけで返事をして熱々を頬張っている男性の耳元にぐっと近いて、さらにこう続けた。
「ね、ちょっと甘くてね」
私たち──臆せず発せられたこの主語の甘さ。
なんだ、優しい声もちゃんと持っている人なんだ。
数年前なら、分かち合うパートナーがいていいなあと心の底から思ったかもしれない。しかし今はひとりがいい。主語が複数というのは、重ったるくて仕方ない。好きなときに蕎麦を手繰って、さっさと山梨に戻れる身軽さは、なにものにも代えがたい。
ともあれ、玉子焼きさまさま、一件落着。人の気持ちをこれだけ動かす玉子焼きとはどういうものか、相席をいいことに、ちらちらと見た。火にかけられたことがないような白さに、水分をたっぷり抱え込んで震え、いつまでも湯気が立ち昇っていた。
これに比べると、私が遠矢山房で作る玉子焼きは、かなり甘い。
まず、だしを使わない。代わりに、3種類の砂糖(ザラメ、黒糖、上白糖)に醤油と水少々を加え、煮立てて溶かし、よく冷ましたものを溶き卵に加える。
舌にのせてすぐに感じる鋭角的な甘みと、噛むほどに染み出してくる、重心の低い深い甘み。それぞれの砂糖の特性を生かし、そこに、くすぐったい“卵くささ”がよく合い、口の中に甘く丸い花が咲くような玉子焼きである。
卵はMサイズを5個。銅製の玉子焼き鍋をよく熱して、卵液を5回に分けて流す。流し入れるたびに、きっちり巻き、しっかり焼き固める。どちらかというとレンガを想像させるような、みっしり詰まった重そうな姿をしている。
焼きたてよりも、半日寝かせたほうが味がなじんでおいしい。だし巻きに比べて日持ちもするし、なによりワインに合う。白飯でもほうじ茶でもなく、シャンパーニュと一緒に出すために私はこの玉子焼きを設計している。
レシピを教えてくれたのは、離婚してからできた恋人だった。
母上が玉子焼きの職人で、多くの飲食店に卸していたそうだ。
「いろんな玉子焼きを食べたてきたけど、母のが一番おいしい」
こう何度も回想してくれたその味を、私がどうしても食べたいとお願いし、彼が記憶を頼りに再現した。母上は高齢のため引退し、文字にも書き起こされていなかったのだ。
結局この恋人とは別れてしまったが、もし返せと言われてもレシピだけは返却できない。
何度も練習して、焼きに焼いて、両足のバランスの取り方も、手首の返し方も、体がすっかり覚えてしまった。春夏秋冬で砂糖の配合も変えてきた。だからもう、私のものである。
短くない月日をともに過ごしたが、これがふたりの味だと笑い合うことはできなかった。もう一度誰かと深い信頼関係を結ぶ情熱が自分にはないことが、はっきり分かったのだった。
ちょっとした不注意で、手元は狂う。
この原稿を書こうとして、朝食の目玉焼きを作りながらぼんやり構想を練っていたそのとき、うっかり殻を落としてしまった。
しまったと思ったときにはすでに遅し。白身にどんどん火が入り、小さな欠片は見えなくなった。
「今日は殻が入っています。食べた人が当たりです」
クリスマスイブの朝、失敗を宝探しに変えてテーブルに並べた。
当たりを引いたのは息子。ご褒美に、朝から大好きなコーラを飲んでいいことにした。
何もかもが高くなってしまったこの国で、卵も例外ではなく、10個入りが税込みで300円する。ひとつ30円。これを高いと思うか、安いと思うか。
工夫次第でいくらでもおいしいものを生み出せるのだから、卵はやはり優等生だと私は思う。卵に触れない日はない。ひとりで割り、ひとりで作り、それを子供たちやゲストと分かち合ってきた。
彼の母上は、指が変形するまで卵を焼き続けたという。私も、自分の味を求めて、手を動かし続ける。