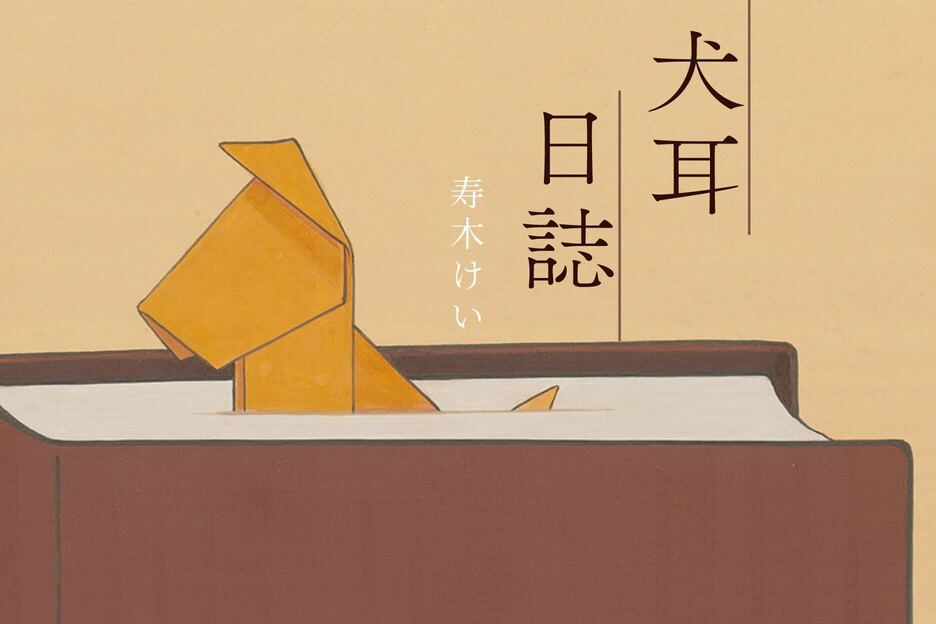親密な離婚
私のもとには、日々さまざまな訴えが届く。
高額医療費の限度額引き上げを撤回してください。飲酒運転で母の命を奪ったドライバーに厳罰を求めます。メガソーラーの建設を中止し、芦別の自然を守りたい──。
一年ほど前に、ソーシャルプラットフォームの署名活動に参加して以来、世界の誰かが新しい訴えを立ち上げるたびに、こうしたお知らせがメールで送られてくる。本名で呼びかけられることもあり、システムの設定で表示されていると知りながらも、切実さに胸がズキンとする。
その日も、いつものように何気なく受信ボックスをチェックしていた。
「9歳の娘が誘拐されました。助けてください」
息子と同じ年齢だ。思わずメールの本文を開く。
勘のいい方はお分かりと思うが、日本で誘拐という言葉が出てくる時、それは片方の親による子供の連れ去りを指すことがほとんどだ。
発信者は東京都内に住む男性。配偶者によってDV加害者に仕立て上げられ、実家に連れて行かれたお子さんとは、180日以上会えていないという。
男性は離婚の円満調停と面会交流調停を求めている。しかし、日本の法律ではそれが叶うまでに長い時間を要すると知り、絶望する前にこの署名サイトを頼ったのだ。
私の長年の友人も、同じように悩んでいた。
配偶者が弁護士を雇って、先の男性と同じくDVの加害者にされ、用意周到に連れ去りが行われた。どうしても子供に会いたくて、変装して保育園の近くまで行き、木陰に隠れて泣きながら見たという。
子供に会えない辛さ。自分の存在をないものにされる怒りと悲しみ。風貌が変わるほど心が壊されてしまった姿に、自分の命を消すことだけはしないでほしいと頼んだ。先の見えない道を歩む苦しさは、理解しているつもりだ。
「理解している」とはっきり書くことができないのは、私も離婚を経験しているとはいえ、元夫と協力して子供たちを育てているからだ。揉めることなく短期間で離婚が成立し、かかった費用は公正証書作成のための数万円だけだった。
ならば、私たちがそのようにできている理由を明らかにすれば、これから親になる人にも、今まさに離婚の渦中にいる人にも、役立ててもらえるかもしれない。
「離婚できたのは、経済的に自立しているからでしょう」と言われることがあるが、それは心を置いてけぼりにした言葉である。
離婚の前に別居していた頃は、なんとか婚姻関係を続けられないか、もがいた。体重は7キロ減った。しかし、とことん考えて、泣いて、大騒ぎして、もうだめだと悟った時、荒れた海がすうっと凪いだ。
それからは速かった。離婚後に子供と過ごす時間について定めた公正証書を作ると決め、打ち合わせの日程や内容について率先して元夫と連絡を取った。証書のたたき台の原稿も自分で書き、公証人にアドバイスをもらいながら元夫と作り上げた。
それはまるで、元夫を大切なクライアントに見立てた、仕事のような取り組み方だった。
私の目は子供たちだけを向いていた。夫は別の道を行く人なのだから、今さら追いかけて石を投げたり、懲らしめて優位に立とうと躍起になったりする必要などなかった。
そんなことより、もっと大事なことがあった。それは“恐れ”である。
親は温かい豊かな雨を子供に注ぐべきで、それは、おいしい食事だったり、片付けの習慣を教えることだったり、話をただ聞いてやることだったりする。とにかく、自分という資源のすべてを与え切る心づもりで生きたいし、元夫にもそう生きてほしい。
私は父親のいない家庭で育った。母は明るく辛抱強く私たち5人の姉妹を育ててくれたが、それでも、資源が出てくる蛇口はひとつだった。
離婚後、もし父親との交流がなくなってしまえば、父親(場合によってはその両親も)が持っている知恵や無形の財産も、仕事や友人関係を通して築いていきた社会的な基盤も、子供たちは失ってしまうことになる。母親と子供だけの閉じた暮らしが生み出す、こうした“貧しさ”こそ、私が恐れたものだった。
協力して子供を育てていると書いたが、たとえばこんな風だ。
子供と話しあうべき問題が起きた時、私の意見を伝えるのはもちろんだが、「今度会った時にパパの意見も聞いてみたら」とうながす。元夫の意見が私と違っていても構わない。そのほうが、子供の知恵も経験も倍になる。
元夫が子供たちと旅行をしたいと言えば、必要なものを買い揃え、荷造りをして送り出す。そのぶん生まれた時間と体力を、私は自分のために使える。それが余裕を生み、家を明るくする。子供というのはいつだって、おもしろいお母さんが好きだ。
子供たちと引き離される苦しみを、私は友人の辛い経験から学んだ。元夫には苦しんでほしくない。それは、長年ともに生きたひとりの男の人への、温情である。
もちろん、離婚の渦中からこんな風に落ち着いていたわけではなかった。収入を安定させ、新しい生活を作っていくなかで、けじめを付け、情緒を耕してきた。離婚という事実に、親密さをまぶすようにして歩んできたのである。
離婚は幸福なものではないけれど、不幸をこれ以上大きくしない方法を考えることはできるはずだ。綺麗事だと思われるかもしれない。でも、どうか、子供のために努力してほしい。
2024年5月24日に公布された改正民法に、共同親権が盛り込まれた(※)。離婚後も父と母が一緒に子供を育てていくことを法で定めたのである。ただし、単独親権または共同親権か選択可能とするという内容にとどまり、これでは、冒頭に紹介した男性のような人は救われない。
署名を通じて男性が望んでいたことは、ひとつは法改正。もうひとつは、子供の心のケアである。前者は法律に則って連れ去りに対処し、国が子供を保護できるよう法改正を求めている。そこに、共同親権の原則化と、それが守られなかった時の罰則化も加わる。そして後者は、連れ去られた子の多くが「片親疎外症候群」に悩まされることを、広く知って欲しいと願っている。
法はつねに生活の後ろを付いてくる。
生活には複雑なグラデーションがある。今回の誘拐の訴えのように、起きてしまったことを法で解決するのは本当に大変なことだ。予防のほうが楽なことは明らかで、その点で、立法機関ではなく、自治体や民間にできることも多いのではないだろうか。この小さなエッセイも、誰かの予防の一助となることを願う。
最後に、私の両親の話をする。
先月半ばに、母が亡くなった。緩和ケアに入ってからは、私も母の個室に寝泊まりし、いろんな話をすることができた。
その中で、父に対してずっと思い違いをしていたことが分かった。
私は、三十年以上の長きにわたり、父は夜逃げ同然で出奔したと思っていた。しかし、そうではなかった。父は私たちと暮らしたがったのだ。そして、それを母が拒んだことは、長い年月を経た今、英断だったと思う。
私たち姉妹が育っていくことは、母の犠牲とともにあった。私たちの家が暗い時代に入った頃、母は4日連続で海へ行き、浜辺で泣き続けたそうだ。
「あの時代は、そうするしかなかった」
同じセリフが、母の口から何度も出てきた。
海で泣いていた母は、今の私より少し若い。母と私が並んで泣いている姿を想像する。そっくりな女性に向かって、きっと私はこう言う。いつまでも泣いてちゃだめだよ、そろそろ子供たちのところに戻ろう──。
父も、母も、もういない。
父と母を、ひとりの人間として、一番近い他人として見る。そこには、私が“育てられる”季節はとうに過ぎたという、懐かしい事実があるのみである。
※2024年の民法改正で「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める」と記されるまで、日本では126年間、離婚後は単独親権のみ認められてきた。明治民法では、婚姻中も離婚後も、家制度のもとで原則として父親にしか親権がなかった。戦後の現行民法で、離婚後はどちらか一方が親権を持つと定められ、婚姻中は共同親権、離婚後は母親も親権を持てるようになった。
参考文献
「子どもは誰のものか? 離婚後『共同親権』が日本を救う」
嘉田由紀子著/文春文庫