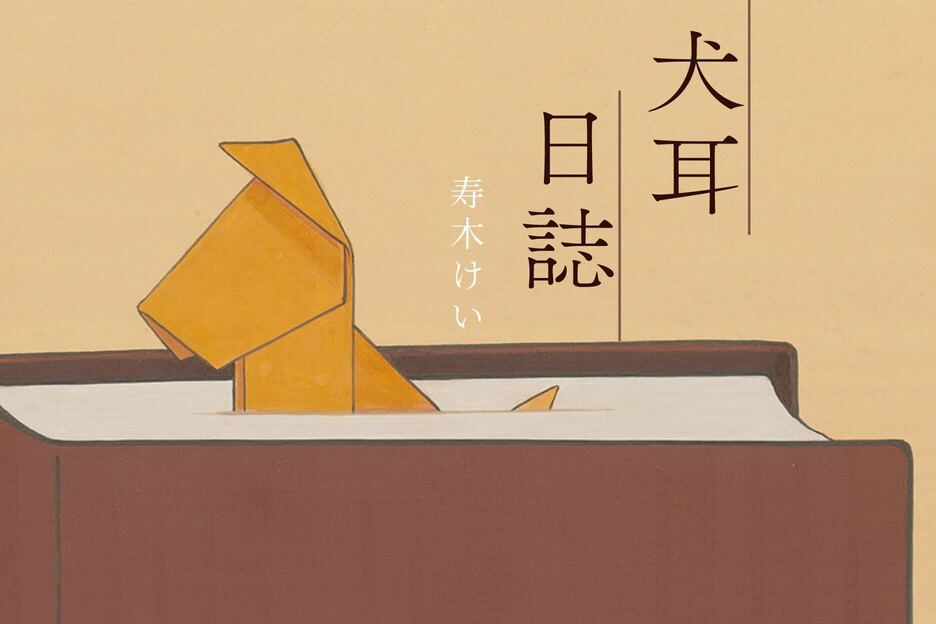10年後の『ハウスワイフ2.0』
NHKラジオに〈小学生の基礎英語〉という番組がある。子供と一緒になってラップを口ずさんだりクイズに答えたりするうちに、私のほうが放送を楽しみにするようになった。
なかでも好きなのが電話相談のコーナーだ。英語にまつわることなら何でも出演者に質問することができ、お父さんの仕事仲間の外国人に、その国の名産品を尋ねたいといった微笑ましい相談もあれば、ゴーストとファントムはどう使い分けるのかという、はてと考えさせる質問もある。電話口に向かってドキドキしている子供たちの姿を想像すると、とても可愛らしい。
その日の相談者は女の子だった。「我慢しなさい」を英語で教えてほしいと言い、穏やかな番組の雰囲気が少し変わった。司会者がさらに深く聞くと、弟が言うことを聞かないから注意したいのだと、しっかりした口調で答えた。
回答者はしばらく考え、英語には我慢しなさいという表現はないと前置きしたうえで、「ノー」とだけ言えば伝わること、そして、ほかの候補として「あとでね」を使ってみてはどうかと提案した。
日本で暮らす小学生にとって、「ノー」で成立するコミュニケーションを理解するのは難しいかもしれない。女の子はなんとなくすっきりしない声でお礼を言い、電話を切った。
おそらく、周囲の人が日ごろから「我慢」を使うのを聞いて育ったのだろう。子供は大人の口癖はもちろん、思考のくせまでも吸収する。「我慢しなさい」と声をかけ、仮に子供が我慢できたとしても、意に反して引っ込めた子供の柔らかい部分は誰がさすってやれるのだろう。
私も軽い気持ちで使っていないだろうか。あの電話をきっかけに、「我慢」をどんな風に伝えているか気になるようになった。少なくとも「我慢しなさい」をしきりに使っている自覚はないけれど──
ラジオを聴いた翌日、二泊三日で大阪万博に出かけた。その初日の午前中のうちに、私は我慢を2回も使っていた。ひとつは移動中に。新幹線に乗り遅れそうなときにかぎってトイレに行きたいと言い出す子供に、「10分我慢して!」と叫んで東京駅を走った。
ふたつめは万博の会場に着いてから。ドイツ館の屋外ステージで、ビールが振る舞われているのが見えた。こちらは炎天下の行列に並んでいる。ビールまであと20分。
「ママ、飲んだら? 今日運転しなくていいし」
親友みたいな口を利いた子供に、
「いま我慢して、夜にゆっくり飲む一杯が最高なんだよ」
こう言ってからハッとした。本当は飲みたくてたまらなかったが、熱中症が怖かった。でもそんなことをいちいち子供には言わない。何かが怖いから好きなものを諦めるという伝え方は、世界を小さくしてしまう。この先に素晴らしい展開があるのだと、おもしろがる方向に持っていくところが私にはあって、シングルペアレントになってからは特にそう心がけてきた。大部分は強がりだが、振る舞いが思考を作っていくこともある。
ふと思う。ラジオの女の子は、親を笑顔にしたかったのかもしれない。自分が小さなお母さんになって弟を躾けることで、親の負担を減らしたかったのだとすればそれは、親が苦しそうに見えるからではないか。我慢しなさいと言う時、人は決して笑顔ではないはずだから。
先日『ハウスワイフ2.0』(エミリー・マッチャー著/森嶋マリ訳/文藝春秋刊)を10年ぶりに再読し、発売当時とはまったく違う印象を抱いた。
10年前、私は第一子の育休を終えて職場に復帰したばかりだった。さあ、これからどんどん働いてみせる。子供がいるから仕事の手を抜いているとは思われたくなかった。
そんな時に「高学歴女子こそ主婦になろう」「キャリア女性の時代は終わった」という謳い文句で話題となったこの本を、複雑な気持ちで開いた。本に登場する才能も努力も持ちあわせた女性たち。こんなに頑張ってきたのに、どうして諦めるの? 後進の道を閉ざすのか、と。
それが今はまったく違うことを考えている。
子供の隣に、自らもまた育っていこうとする大人、言い換えるなら、何者かになろうとしてもがく親がいてはならない。少なくとも私はそう感じている。私は娘がうんと小さな頃に初めての著書を出し、会社員として仕事を持ちながら、子育てと物書きとしてのキャリアが同時にスタートした。その経験を反省して思うのである。
人ひとり育てるのは大変な力が要る。赤ん坊から3,4歳までは手も目も離せず、やがて大きくなると今度は心を離してはならない。人生の大部分を子供に費やす生活が十数年は続く。この時、親だって自分に手間暇かけたいのだと強く願えば、人生を我慢させられていると感じる。子供の存在が邪魔になってしまう。
だから主婦を目指そうと言いたいわけではない。大志を抱くのも良いだろう。子供以外に大事なことがある人生を突き進むのは素晴らしいが、片手間には子育てはできない。我慢だと親自身が感じていることを、子供にも強いることが問題なのだ。親の庇護なしに生きていけない子供には、どうすることもできないのだから。行き過ぎた自分探しや自己実現という言葉に囚われるのをやめ、まず自分の足で立つこと。そうして初めて、子供の人生も大事に抱えることができる。
私の場合は、働く姿を見せながら子供と生きていく道を探して、家でもできる職業に徐々にシフトチェンジし、今の暮らしを作ってきた。娘に重度の障害があり、フルタイムの正社員を続けることはしんどいと早い段階で悟った。そのおかげで、生き方を変えるチャンスが与えられた。辛い辛いと言いながら雇用され続けることから抜け出せた。
障害のある子供がいるから我慢するのが当然だという姿勢を息子に見せてしまったら、彼もまた、障害のある家族がいるから仕方ない、我慢しなくてはと考えるようになるだろう。だから、我慢とは違う努力の方法を本気で探さなくてはならなかった。そういう意味で、運転席のハンドルを他人に預けるなと説いた『ハウスワイフ2.0』は、本質的なところを突いていたのだと思う。
地下鉄で通勤していた会社員時代、ある親子と何度か同じ車両に乗り合わせた。お母さんが小学生の息子さんをしょっちゅう叱っていた。
「ママはあなたが恥ずかしい」
頭から何度もこう浴びせられ、そのたびに小さく縮んでいった坊やのシルエットが忘れられない。見ず知らずの人に申し訳ないけれど、ああはなりたくないと思ったものだ。と同時に、ほんの少しのハンドルの逸れ方で、私もあのお母さんのようになったかもしれない。彼女と地続きの要素が私にもあって、だからこそ胸がざわざわと波立つ。
子供は生まれた時からすでに大きい光の玉ようなものだ。私が小さな脳みそで考え出した「よかれと思って」な理屈は、たいていが思い上がり。ガミガミ、ちまちま、ぐちぐち。すべて余計なこと。
そんな小ささ、つまらなさから自由になりたい。そのためには、親が夢中で今を精一杯生きること。自分ではない誰かを目指そうとしないで、自分を生き切ること。そして、エッセイストの人生観など話半分に聞いておくことだ。