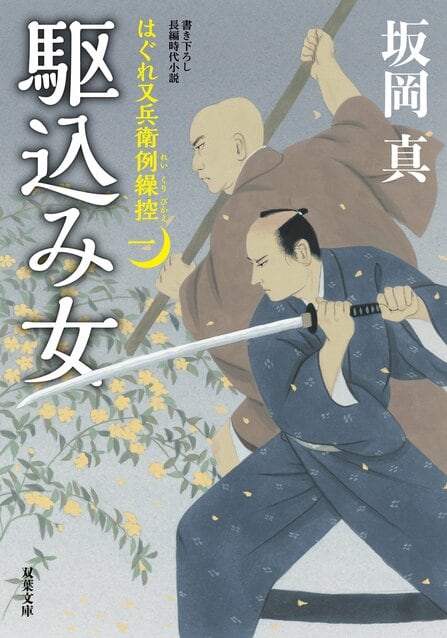四
白塗りの女郎が道端にしゃがみ、尻を出して威勢よく小便を弾いている。
近づいた長元坊にぎくっとしつつも、立ちあがって下から睨みつけてきた。
「あんた、覗き代をいただくよ」
小便で濡れた手を差しだすので、長元坊は溜息を吐く。
「姐さん、山吹を知らねえか」
「ふん、知るかってんだ」
よくみれば、薹が立った女郎だ。暗がりに控えた又兵衛をみつけ、算盤を弾くまねをする。
「二朱でどうだい。ふたりでもかまわないよ」
長元坊は渋い顔をつくった。
「べらぼうだぜ。瘡っ気のある女郎を抱くなら、鼻を失う覚悟がいる。鼻代をさっ引けば、一銭も残らねえってはなしさ」
「遊ぶ気はあんのかい」
「ねえよ。山吹のことを教えてくれたら、こいつをやってもいいぜ」
長元坊は口を開け、長い舌をぺろっと出した。
途端に、女郎は眸子を輝かせる。
舌のうえには、一分金が載っていた。
「ねえ、海坊主の旦那、あさのことが知りたいのかい」
「海坊主とは恐れいったな。おれさまはな、長元坊というんだぜ」
「長元坊、ふん、おかしな名だね」
「まあいい。あさってのは、山吹のことだな」
「そうさ。素直で健気な、いい娘だったよ」
隠売所へ流れてきたのは、八年ほどまえだったという。それより二年前に品川宿の岡場所へ売られてきたが、病がちのせいで金離れのよい常連がつかなかったらしい。
「こんな吹きだまりに落ちて、よくぞ八年も耐えたものさ。とどのつまりは、こっぴどく折檻され、足抜けしちまったけどね」
「どうして折檻されたんだ」
「それこそ、瘡に罹って鼻を無くしちまったのさ。秘め事の最中に糝粉細工の付け鼻が取れて、びっくりした客が玉代も払わずに逃げたんだよ」
「たったそれだけで、焼き鏝を押しつけられたのか」
女郎は目を逸らし、独り言のようにつぶやいた。
「何もなくたって、焼き鏝は押しつけられる。ほかの悪党に取られないためさ」
「何だと」
「家畜と同じなんだよ。焼き鏝には『車』って字が彫ってある。ここの女郎だっていう証しなのさ」
「抱え主は、剃刀の左銀次か」
「そうだよ」
「何処にいる」
「あそこさ」
女郎が顎をしゃくったさきは、細かく区割りのされた長屋の角部屋だ。
「ふうん、あそこか」
長元坊は眸子を細めた。
女郎が慌てて、袖を掴もうとする。
「あんた、悪いことは言わない、やめときな」
「そいつは、おれが決めることだ」
長元坊は一分金を指で弾き、大股で歩きだす。
この際、正面からぶつかってみてもよかろう。
又兵衛は胸の裡でつぶやき、磐のような長元坊の背中にしたがった。
区割りされた女郎の部屋は間口半間に奥行二帖と狭く、蚤の住む蒲団と小さな行燈しかない。抱え主の部屋はそれよりも広いが、三和土も入れて四帖半の板の間にすぎず、南京虫の好みそうな饐えた臭いを漂わせていた。
「ちょいと邪魔するぜ」
長元坊は気軽な調子で戸を開け、三和土に一歩踏みこむ。
部屋にはふたりおり、ひとりは月代の伸びた悪相の浪人だった。用心棒に雇われた野良犬であろう。火鉢を挟んで酒を呑む猪首の四十男が、剃刀の異名を持つ左銀次にちがいない。
なるほど、三白眼に睨めつける目つきが尋常ではなかった。
「誰でえ、おめえは」
「ご挨拶だな。客ならどうする」
「買った女郎に何かあったのか」
「秘め事の最中に糝粉細工の鼻が取れちまったと言ったら、玉代に迷惑料をつけて払ってくれんのか」
「払わねえよ」
左銀次が目配せすると、用心棒がすっと立ちあがった。
「おっと、そうくるか」
長元坊は身構え、だっと三和土を蹴りつける。
「うおっ」
ふいを衝かれた用心棒は刀を抜くこともできず、巨漢の突進をまともに受けた。
──どすん。
部屋が大揺れに揺れ、白壁に背中を叩きつけられた用心棒は白目を剥いた。
振りかえった長元坊は手を伸ばし、仰け反った左銀次の喉首を鷲掴みにする。
「ぬぐっ……ぐ、苦しい」
「苦しいだろうさ。でもな、山吹の苦しみにくらべたら、屁みてえなもんだ」
手を放してやると、左銀次はげほげほ咳きこんだ。
そこへ、又兵衛がぬっと顔を出す。
「げっ、もうひとりいやがった……て、てめえら、何者だ」
「何者でもいい。問いにだけこたえろ」
又兵衛は雪駄のまま板の間にあがり、火鉢の脇に屈んで声を落とす。
落ち着き払って静かなだけに、かえって凄味があった。
「あさに山吹という源氏名を付けたのは、おぬしか」
「いいや、おれじゃねえ。品川の岡場所にいたころからの源氏名だ。名付け親は、太刀魚の元締めさ」
「茂平か」
「ああ、そうだよ。茂平の元締めが言ってた。十年前、あさが十五で連れてこられたとき、商家の娘が着るような山吹模様の振袖を着ていたってな」
何故か、又兵衛は黙りこむ。
ごくっと、長元坊は唾を呑みこんだ。
左銀次は襟を直し、ひらきなおってみせる。
「あさがどうしたってんだ。あいつは駆込みをやって、死んじまったんだぜ」
「ほう、よく知ってんな」
長元坊が睨むと、左銀次は首を引っこめた。
「蛇の道はへびってことさ。あんたら、死んだ女郎のことなぞ調べて、どうする気だ」
「どうもせぬさ」
又兵衛は声を一段と落とす。
「もうひとつだけ聞いておこう。十年前、茂平のもとへあさを連れてきたのは誰だ」
「女衒の親爺さ。もう、死んじまったがな。でも、親爺は言ってたぜ。あさはとんでもねえ悪党どもに拐かされた娘だってな」
「とんでもねえ悪党とは」
「鯔の伝五郎さ」
押しこみに殺しに拐かし、一時は関八州に名を轟かせた悪党一味の頭目だが、近頃はとんと名を聞かなくなった。
「知ってのとおり、鯔は出世魚だ。ひょっとしたら、ぼらかとどにでもなっちまったかもな。へへ、太刀魚の元締めなら、何か知っていなさるかもしれねえ。何しろ、悪党のことで知らねえことはねえからな」
もはや、この男に聞くことはない。
又兵衛はすっと立ちあがり、代わって長元坊が身を寄せる。
「おもしれえもんをみつけたぜ」
握っているのは、先端に鏝のついた細長い鉄の棒だ。
長元坊は鏝を火鉢に突っこみ、にやりと笑ってみせる。
「げっ、何しやがる」
狼狽えた左銀次の裾を踏み、長元坊はどんと腹に蹴りを入れた。
小悪党が蹲るあいだも鏝を焼きつづけ、頃合いをみはからって火鉢から取りだす。
鏝は真っ赤になり、じじと音を起てた。
「……た、たのむ、勘弁してくれ」
「いいや、勘弁ならねえ」
言ったそばから、長元坊は焼き鏝を持ちあげる。
左銀次を仰向けにさせ、額にぐいっと押し当てた。
「ぎゃああ」
断末魔のごとき悲鳴が露地裏じゅうに響きわたる。
気を失った小悪党の額は爛れ、左右の目玉が半分出かかっていた。