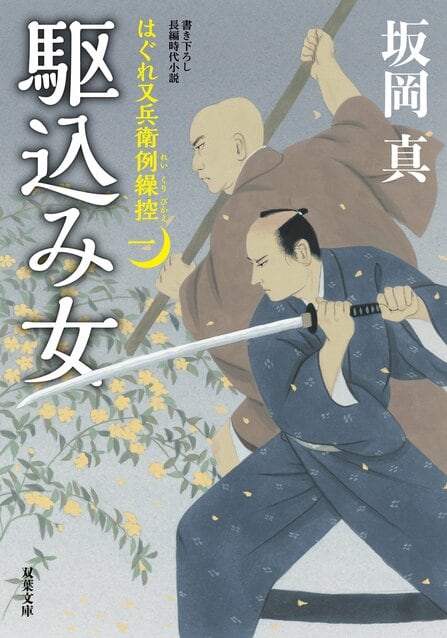一
文政四(一八二一)年如月の終わり、亀戸や大森の梅も咲きそろったころから、性質の悪い風邪が流行りはじめた。流行り歌にちなんで「ダンボ」と名付けられた風邪は江戸市中を席捲し、裏長屋では年寄りたちがばたばた倒れ、小石川の養生所は貧乏人たちで足の踏み場もないほどに埋めつくされた。
第十一代将軍家斉の在位三十四年目のことである。
数寄屋橋御門内の南町奉行所では、与力や同心たちが布切れで鼻と口を覆い、たがいの間合いを遠く取りながら喋っていた。どう眺めても奇妙な光景だが、布切れを持たずに出仕してきた者はことごとく、みなから白い目でみられた。
例繰方与力の平手又兵衛だけは、白い目など気にするふうでもなく、どこにでもあるような面を晒している。
「はぐれゆえ、あやつには何を言うても暖簾に腕押しよ」
と、上役たちも匙を投げた。
はぐれとは仲間をつくらぬというほどの意味で、与えられた例繰方の役目はそつなくこなす。むしろ、何千にもおよぶ類例をすべて記憶しているので頼りにされているのだが、上役に追従する器用さもなければ、同輩や下役の同心たちと一献酌みかわす親しみやすさも持ちあわせておらず、周囲からは「くそおもしろうもない堅物」と目されていた。
齢三十八で独り身、肌の色が浅黒くてひょろ長いことを除けば、これといって特徴はない。たしかに、仏頂面が板に付いた「堅物」にしかみえぬものの、小者の甚太郎だけは敬意を込めて「鷭の旦那」と呼んだ。
鷭は夏の水面に浮かぶ鳥、驚いたおなごのように「きゃっ」と鳴き、身を覆う羽毛は黒くて頭だけが赤い。
「お怒りになると、月代が真っ赤に染まりなさるのさ」
と、甚太郎は三月前に偶さか修羅場を見掛けたことを自慢する。
何でも、油屋の娘を手込めにしようとした暴漢ども五、六人が、芝居町の露地裏で又兵衛らしき者からこっぴどく痛めつけられたらしい。夜目に遠目だったことも重なり、人違いであろうと、はなしをまともに信じる者はいなかった。「くそおもしろうもない堅物」が市中で人助けなどするはずもないし、五、六人相手に大立ちまわりを演じられるほど強くもなかろうと、誰もが口を揃えたのだ。
甚太郎は地団駄を踏んで口惜しがった。悪漢どもから江戸を守る門番ゆえ、せっかく門番の「番」と「鷭」を掛けたのに、誰も聞く耳を持とうとしない。「鷭の旦那」と呼ぶのは今は自分ひとりだが、いずれは奉行所じゅうにわかってもらえるだろうと、甚太郎は大いに期待しているようなのである。
当の又兵衛は意に介さない。「鷭の旦那」と呼ばれようが呼ばれまいが、どうでもよかった。
かといって、心を動かされるものがまったくないわけではない。つきあいが悪いため、今のところは誰も知らぬだけだ。それに、みなから「はぐれ」と目されているほうが気楽だとわかっている。だいいち、面倒な縁談を持ちこまれずに済む。それひとつだけ取ってみても「はぐれ」でいることには、充分な利点があるとおもっていた。
「昨晩遅くに、駆込みがあってな」
布切れ越しにむにゃむにゃ喋っているのは、年番方与力の「山忠」こと山田忠左衛門であろうか。染め残した鬢の白さから推せば、まちがいあるまい。
「駆込みでござるか」
こちらも布切れ越しに空惚けてみせるのは、吟味方与力の「鬼左近」こと永倉左近であろう。四角い顔が大きすぎるので、布切れから鰓がはみだしている。
ふたりは玄関左脇の廊下で立ち話をしており、又兵衛が例繰方の御用部屋から顔だけ出して覗いても、知らぬふりをして顔を引っこめても、気にも掛けずにはなしをつづけていた。
「訴えたのはみすぼらしい身なりのおなごでな、名はあさと申す。名だけを漏らし、門前で力尽きてしもうたとか」
「ほう、死んだと」
「さよう。右手に文を握りしめておってな、文には『さぎんじにころされる』と拙い字で綴られておったらしい」
「それはまた、物騒な文面にござりますな。あさと申すおなごは傷を負っていたのでしょうか」
「刃物傷はなかった。その代わり、焼き鏝で焼いた痕は随所に見受けられたそうじゃ。酷い責め苦を受けたすえの衰弱死に相違ない。骨と皮ばかりで、ものもろくに食べておらぬ様子であったという。おおかた、さぎんじなる者に囲われておったのであろう。哀れなものよ」
「さりとて、哀れなおなごは江戸にいくらでもおります。死んだおなごの訴えを取りあげてやるほど、奉行所は暇ではござりませぬぞ」
「わかっておる。常であれば、おなごの訴えはなかったことにいたすが、そうもできぬ雲行きでな」
「何故にでござりますか」
「決まっておろう、御奉行じゃ。筒井伊賀守さまが運悪く駆込みのことを小耳に挟まれてな、今朝一番でわしを御用部屋へ呼びつけ、この一件どうにかせよとお命じになったのじゃ」
「ふふ、新任早々、はりきっておいでのご様子」
鬼左近は苦笑し、皮肉めいた口調でつづける。
「伊賀守さまは何せ、昌平黌きっての秀才と評されるほどのお方、しかも、長崎奉行の任にあったときでも賄賂をいっさい受けとらなんだと聞きました。清廉潔白ぶりは折紙付きという噂がまことなら、勝手を任されておられる山田さまもさぞかし気苦労が絶えぬことかと、ご同情申しあげまする」
山忠は布切れの内で、ふうっと溜息を漏らす。
「どうにか、恰好だけでもつけてもらえぬだろうか」
「致し方ござりますまい。山田さまに頭を下げられたら、嫌とは申せませぬ。ここはひとつ貸しということで、お引き受けいたしましょう。つぎの吟味方筆頭与力は、何卒それがしに」
「ふむ、考えておこう」
おおかた、鬼左近から廻り方の同心へ命が下され、鼻の利く岡っ引きや小者どもが町じゅうを走りまわることになるのだろう。
又兵衛は聞きながそうとしたが、哀れなおなごの名だけは記憶に留めてしまった。
「あさ……」