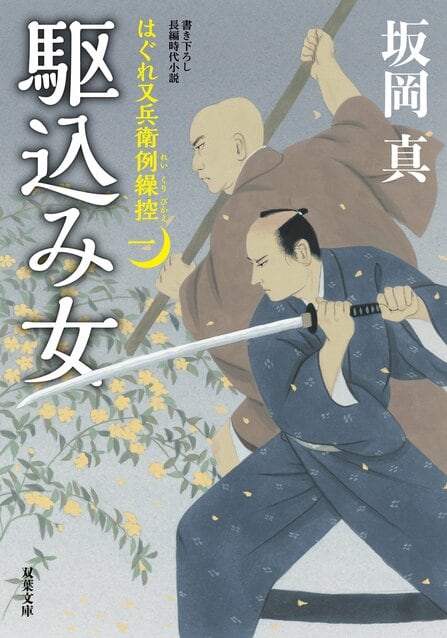小机のうえに山と積まれているのは、吟味方によって公事の経緯や罪状が記された御調帳である。捕らわれた者の口書も添えてあり、これらを類例に照らし合わせ、適用される刑罰を導きださねばならない。
遠島になるのか、死罪になるのか、死罪より一等重い獄門になるのか、罪人の命運を握っていると言っても過言ではないと、意気込んではみても、たいていは吟味の段階で刑罰はほぼ定まっている。駄目押しで刑罰の確定をおこなったり、御沙汰の下書きを推敲してかたちを整えたり、老中への上申書にわかりやすく類例を添えたり、例繰方に課されているのは他からみれば地味な役目にほかならなかった。
それでも、三つ年上で先任与力の中村角馬はいつもはりきっている。
「よいか、われら例繰方はお裁きにおいて最後の砦とならねばならぬ。お裁きが滞りなく進むか否かは、例繰方の力量ひとつに掛かっておるゆえ、心してお役目に勤しむように」
毎朝、下役の同心たちに向かって性懲りも無く訓示を垂れ、眠気覚ましに冷めた茶を大量に呑むせいか、厠に立つ回数は多いし、冬でも鼻の頭に汗を掻いていた。
例繰方は奉行や内与力に呼びつけられる機会も多い。ことに、赴任したばかりの筒井伊賀守のようにきっちりした性格の町奉行は類例を事細かに吟味するので、第八代将軍吉宗のもとで編纂された公事方御定書百箇条と明和のころから約五十年にわたって作成されている御仕置例類集くらいは諳んじられるほどになっていなければならなかった。
もっとも、御定書百箇条と例類集は評定所で評議をおこなう町奉行、寺社奉行、勘定奉行の三奉行と京都所司代ならびに大坂城代にたいしてのみ在職中に交付され、それ以外の者は閲覧を禁じられている。本来ならば、例繰方の与力といえども閲覧さえできぬ代物であった。
とはいうものの、物事には本音と建前があり、南北町奉行所の例繰方詰所にはかならず、ぼろぼろになった写しが置かれている。新入りは何代にもわたって引き継がれてきた写しを頭に入れることからはじめねばならぬのだが、又兵衛はその作業を三日も掛からずに終えてしまった。
おそらく、類例の数は七千を優に超えていよう。それらを順不同で問われても、間髪を容れず、一言一句違わずに述べてみせられる。帳面に綴られた文字を記憶する力だけは生まれつき抜きんでており、中村もその点だけは一目置かざるを得ないようだった。
ただし、同心たちから気軽に「此の儀についての刑罰は」と問われても、又兵衛はいっさい耳を貸さない。底意地が悪いのか、はたまた、応じぬことが指南だとでもおもっているのか、黙りを決めこむので、次第に問う者もいなくなった。
御用部屋にあっても、又兵衛は「はぐれ」なのである。
みずからに課された仕事はすみやかにこなし、部屋の連中がどれだけ忙しかろうが、定刻になったらさっさと片付けをしはじめる。小机のうえにはいっさい物を残さず、文筥や帳面はみずからの定めたところへ、きっちり納めないと気が済まない。
「おさきに失礼つかまつる」
と、言い残して部屋を後にしたところで、舌打ちする者さえいなくなった。
今の季節、日没はあっという間にやってくる。
檜の香りが漂う玄関から雪駄を履いて式台を降りれば、長屋門までまっすぐ延びる六尺幅の青板には夕陽が斜めに射しこんでいた。
又兵衛は眩しげに眸子を細めて足早に歩き、左手の小門のほうへ向かった。
町奉行所の正門は暮れ六つ(午後六時頃)まで開いているのだが、与力といえども捕物出役の助っ人以外で正門を通り抜けてはならない。
狭い小門を潜って小砂利を踏みしめたところへ、小者がひとりすっ飛んできた。
「鷭の旦那」
通りを隔てた対面には、訴人の待合にも使う葦簀張りの茶屋が五軒ほど建っている。そのうちの一軒から飛びだした小者は、縞木綿に小倉の角帯を締めた甚太郎にほかならなかった。
「鷭の旦那、お疲れさまでござんす。じんじん端折りの甚太郎をお忘れですかい」
胡座を掻いた鼻の穴をおっぴろげ、亀のように首を伸ばしてくる。
いつもなら無視を決めこみ、門前で待つ中間ともども帰路をたどるところだが、甚太郎は腰に差した真鍮金具の木刀を撫でながら、胸を反りかえらせてみせた。
「旦那もお聞きおよびかと存じますけど、あさっていう駆込み女の素姓がわかりやしたぜ」
それがどうした、例繰方には関わりあるまいと、胸の裡に囁きつつも、又兵衛は横に歩きかけた足を止め、得意げな甚太郎が導くに任せて往来を横切ると、萌葱色の幟がはためく茶屋の奥へと消えていった。