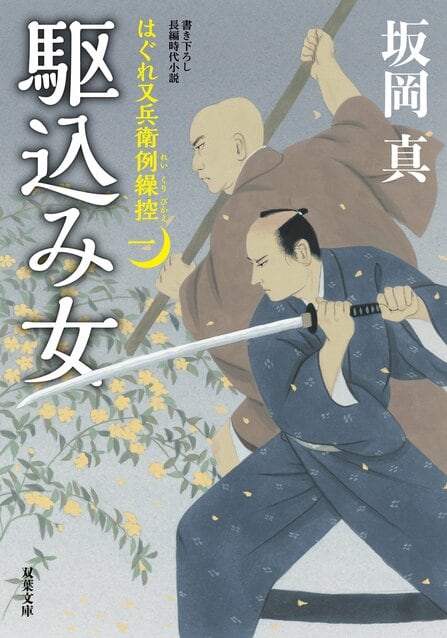湯屋から戻ってくると、冠木門のまえに臼のような巨漢が立っていた。
「ふん、湯屋帰りか。朝っぱらから、こざっぱりしやがって」
憎まれ口を叩くのは、長元坊にほかならない。
又兵衛は嬉しさを隠しきれず、声を弾ませた。
「来てくれたのか」
「暇だからな。それに、おめえは不器用なやつだから、おれがいっしょのほうが好都合だろう。行き先は高輪だったな。ほら、早く着替えてきやがれってんだ」
彼岸を過ぎれば、底冷えのするような寒さも次第に和らいでくる。
八丁堀を南北に突っ切る大路の西には、松平越中守の上屋敷がでんと構えていた。
こちらは伊勢国桑名藩を治める殿様だが、陸奥国白河藩を領した松平越中守定信のほうは今から三十四年前、周囲の期待を一身に背負って幕閣の中心に躍りでるや、賄賂にまみれた田沼意次派を一掃し、六年間にわたって寛政の改革を推進した。
そののち、定信の意志を継いだ松平伊豆守信明は二十一年の長きにわたって政事の舵取りを担ったが、信明亡きあとの老中首座に抜擢されたのは、公方家斉の側近として頭角をあらわした水野出羽守忠成であった。
誰もが節約や自粛を推奨する暮らしに飽き飽きしており、範となるべき公方が率先して浪費に走った。財源とされたのは、元文小判から品位を格段に落とした文政小判である。幕府は小判の改鋳によって莫大な差益を得、世の中には湯水のごとく金が注ぎこまれることとなった。
米価や諸色の値上がりを尻目に、水野忠成は家斉の放埒ぶりを容認し、賄賂と依怙贔屓の横行する悪夢のような失政をおこなっている。これを表立って諫める取りまきもおらず、市井では「水野出て、元の田沼となりにけり」と皮肉る川柳も詠まれていた。
もちろん、驕り高ぶる者たちの行く末が透けてみえたとしても、天下の政事は身分の高いお歴々が司ること、一介の不浄役人には関わりようのないはなしだ。
ふたりは海鼠塀に沿ってのんびり歩き、楓川に架かる弾正橋と京橋川に架かる白魚橋を渡った。楓川は京橋川へと合流し、真福寺川を越えたさきは三十間堀と名を変える。堀川は大きく鉤の手に曲がり、そこからさきは芝口の汐留橋にいたる八町(約九百メートル)さきまでまっすぐに延びていた。
三十間とは川幅のことだが、十間(約十八メートル)ほど狭くする川普請がちょうどおこなわれている最中で、畚や鍬を担いだ人足たちが忙しなく行き来している。
「河岸を広げるんだとよ。対岸の木挽町にゃ、大名屋敷がずらりと並んでいる。べらぼうな普請金の九割方は武家の負担で、恩恵に与る町人の負担は一割だってはなしだ。そんでも、大名家からは文句ひとつ出てこねえ。裏のからくりはよくわからねえが、川普請ってなやり方次第でいくらでも甘い汁が吸えるらしい」
蛇籠に詰める石を積んだ荷船には幟が立てられ、普請を請けおった各藩の家紋が風に揺れている。なかでもめだつのは唐団扇、豊前国中津藩を治める奥平家十万石の家紋であった。拝領屋敷は汐留橋の手前にあり、木挽町側に上屋敷を構える藩のなかではもっとも石高が大きい。石高にともなって分担金も増えるので、世の中に少しでも藩の威勢をしめしたいのだろう。
「さきは長え。猪牙でも使うか」
長元坊に誘われ、紀伊國橋のたもとへ降りていく。
猪牙舟の船頭が煙管を燻らし、人待ち顔でうなずいてみせた。
荷船に紛れるように三十間堀を進み、浜御殿の北西を流れる汐留川へ向かう。
堀川から湾へ飛びだすと、猪牙は波に乗っていっそう速力を増していった。
汗ばむほどの晴天ゆえか、袖をはためかせるほどの向かい風も気持ちよい。
芝浜の岸辺近くを滑るように進み、高輪大木戸のさきで猪牙は舳先を桟橋へかたむけた。
なるほど、舟を使えば早い。
又兵衛と長元坊は陸にあがり、さっそく高輪の車町へ踏みこんでいった。
街道沿いに抹香臭い仏具屋がめだつのは、周辺に寺が集まっているからだろう。脇道から少し坂をのぼれば、赤穂浪士の墓所として知られる泉岳寺などもあった。
「左銀次の上客は、寺の住職どもだったな。たしかに、これだけ寺があれば、獲物にゃ事欠かねえ。ふん、罰当たりな連中だぜ。住職の女犯は晒し首なんだろう」
長元坊に顔を寄せられ、又兵衛は首を左右に振る。
「いいや、寺持僧の女犯は遠島と定められている。博打を開帳した者や、あやまって人を殺めた者と同じだ」
「おいおい、ちと甘すぎやしねえか」
御定書百箇条が編まれたのは、第八代将軍吉宗の治世下である。鋸挽きなどの極刑もあたりまえのようにおこなわれていた幕初にくらべれば、刑罰はずいぶん甘くなった。甘くなったことを悟られれば凶悪な罪も増えることが予想されるため、御定書はおおやけにできないのだ。
「せめて、いっち遠い八丈島に流されてほしいもんだぜ」
そんな会話を交わしながら、淫靡な雰囲気の漂う露地裏までやってくる。
「へへ、この辺りだな」
長元坊は鼻を利かせ、真っ黒な溝沿いの道を奥へ奥へと進んでいった。